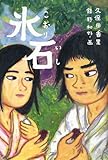そんな時代、人々の衣食住はどんな風であったのか、1日の流れに沿って追ってみる、というのが本書のねらいである。著者のすごいところは、文献などで得られた知識を羅列するだけでなく、自身もヴィクトリア朝時代の服を着たり、身だしなみ法を試してみたり、当時の道具で農作業などの労働をやってみたりしていることだ。実体験に基づいた話は説得力が違う。
上下巻に分かれているが、上巻は起床から昼食前まで。朝の身づくろい、着替え、用足し、運動、朝食、外での仕事、家事に触れる。一応、時間軸に沿ってはいるが、適宜、各事項の背景知識などが織り込まれる。
庶民の暮らしから、貴族の暮らしまで、ざっくり広く触れられているところも楽しい。
いざ、ヴィクトリア朝にタイムスリップ!
朝の目覚めと共に寒さが身に染みる。この時代、寝室の暖炉に火が入ることはめったにない贅沢だった。
朝のシャワーなどはもちろんなく、浴槽につかることもあまり一般的ではなかった。たいていの人は、目覚めの後、寝室で立ち洗いにより身を清めた。水が入った水差し1つで全身きれいになる。浴用布を水に浸し、石鹸を使って体を拭いていく。部位ごとに拭くため、全身裸になる必要はない。寒い時でも大丈夫、部屋にほかの人がいても恥ずかしくはない。ゆったりしたガウンを着ていれば、まったく脱がずに体をきれいにすることができた。
髪を洗うこともそう頻繁ではなかったが、著者によれば、個人差はあるものの、よくブラッシングすると、週に1度程度水ですすぎ、たまにシャンプーを使うくらいでも臭わないという。ヴィクトリア朝の髪型にして、油をつければ、シャンプーなしの生活でも問題はないそうだ。
ヴィクトリア朝の服装といえば、コルセットにクリノリン(服の下にはくフープ状のスカート)だろう。胸郭を締め付けるコルセットは見るからに苦しそうだが、ヴィクトリア朝ではつけていないと「まともな」人間には見られなかったらしい。細いウェストが流行したときには、締め付けすぎて体に悪影響が出ることも多かった。寄宿学校などで1か月に1インチ細くする習わしがあるところもあり、15歳でウェスト23インチ(約58センチ)の時に入学し、17歳で卒業する際には13インチ(約33センチ!)だったという女性もいる。徐々に締めていくわけですねぇ・・・。怖い怖い。
これだけ締めるともちろん、困ったことが起こる。失神したり頭痛に苦しんだり、消化や生殖に影響が出たりする。だがこれらは「締め付けすぎ」の場合の問題で、コルセット自体が悪いという方向にはいかなかったようである。
但し、コルセット着用も試した著者によると、草刈をする際には、コルセットが支えとなり、背中の筋肉に力が入らずに済む利点があった。意外に肉体労働の際には理にかなった面もあったようだ。
ヴィクトリア朝は、多くの庶民にとっては「飢え」の時代でもあった。この時代、じゃがいもの疫病が流行し、収穫量が激減した。1845年はひどい不作の年で、アイルランドでは100万人以上が餓死したといわれる。窮状の中でもイギリスへの農作物の輸出は続き、それが被害をひどくした。この結果、アイルランドからは多くの移民がアメリカ等に渡っていくことになる。
イギリス本土でも飢えは一般的で、食品価格は高騰し、動物性タンパク質をほとんど口にできない者も少なくなかった。
産業革命でさまざまな仕事が生まれたが、労働環境が劣っていたのもこの時代の特徴である。「職場での死や負傷は概して仕方のないことだと思われていた」というのだからすさまじい。鉄道現場での連結作業、紡績工場や織布工場の粉塵、半日以上続く暗がりでの縫製作業。死亡、肺病、視力低下、聴覚障害。田園地帯ではどんな天候でも屋外作業を行うため、肺炎、気管支炎、関節炎に苦しむ者が多かった。水や蒸気で動く機械、馬力に頼る機械で怪我をしたり死亡したりする者もいた。
育児法は現代と違うことが多く、興味深い。特に食べ物と薬だ。母乳から固形物に移行する際、果物や野菜は推奨されず、肉や魚もほんのわずかしか認められない。子供が二歳を過ぎるまで、ほぼ炭水化物のみの食事が推奨された。母乳の出が悪いなどで早くからでんぷん食を与えられた子供は、後々、体調不良に悩まされることが多かったという。
こんな食事では子供は不満だろう。機嫌の悪い子供を落ち着かせるために与えられたのが薬で、何と、子供にアヘン剤を投与することが珍しくなかったというのだ。薬を飲めば子供はよく眠る。アヘン剤には食欲を抑制する効果もあったため、ただでさえあまり栄養状態がよくないのに、薬で静かにさせられて、食欲もなくなり、栄養不良で死んでしまった子供たちは相当な数いたことだろう・・・。
下巻は昼食から就寝まで。




分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント
- ぽんきち2017-11-09 15:22
サカナ男爵さん
そうですね、優雅な階級は優雅だったけれども、庶民はかなり厳しかったようです。
飢饉の時代でもあったようで、食糧事情はあまりよくなかったようですね。
労働環境なんかも、こういう厳しい時代を経て、いろんな保障がされるようになっていったのかなーという感じです。
著者さんは映画や美術館のアドバイザーなんかも務めていて、BBCの教育番組にも出演しているそうです。
邦訳はありませんが、チューダー朝バージョンもあるみたいです。
現代から見ると非合理なようでも、その時代の生活様式には合っていることもあるというのがおもしろいです。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - ぽんきち2017-11-09 21:32
日月さん
をを。NHKで放送していたのですか。それは見たかったな。
人さまのブログの記事なのですが、もしかして、こちらでしょうかね・・・?
http://d.hatena.ne.jp/spqr/20101216/p1
英語版You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=4apIM4l0laY
こちらの番組には、本書の著者さんも出演していたようです。
違う番組の話だったらすみません(><)。
文献を調べるだけでなく、実際に体験してみると、一段深い気づきがありそうで、おもしろいところですね。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - ぽんきち2017-11-09 22:07
日月さん
なるほど、いろんな番組があるのでしょうね。ありがとうございます。
上巻ではとりあえず朝食のみでした。飢餓の時代でもあったので、特に労働者階級は、パンだけだったり、あんまり大したものは食べてないな、という感じでした。この部分は再現はなかったと思います(すみません、図書館本だったので今手元になく(^^;))。
下巻では昼食、夕食も出てくるはずなので、もう少し詳しい料理内容が出てくるかも(近日中に読む予定です)。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
- 出版社:原書房
- ページ数:298
- ISBN:9784562054244
- 発売日:2017年07月11日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。