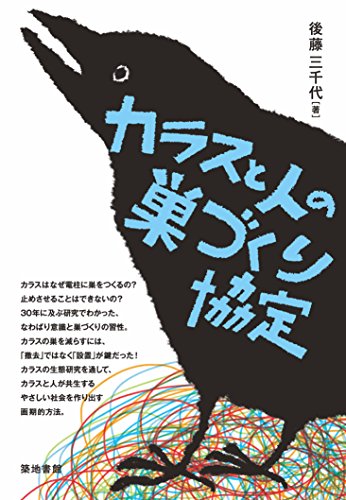▼
「イタチごっこ」から抜け出すために
カラスというと何を思い浮かべるだろうか。
うるさい。ズル賢い。しぶとい。迷惑。
どちらかというとマイナスイメージの強い鳥だが、それは果たしてカラスばかりが悪いのだろうか?
本書の著者はカラスの生態学を専門とし、約30年、カラス問題に取り組んできた。
著者は冒頭で、童謡「七つの子」を挙げる。「烏なぜ啼くの」と始まるおなじみの歌は、カラスの繁殖期が歌われたものである。大正10年に野口雨情作詞で発表された。カラスの幼子に対する優しい思いが綴られる詞は、人がわが子に寄せる愛情とも重ね合わされる。そこに「迷惑」な「困った」鳥という意識は見られない。
100年近くが経つうち、カラスの印象がこうも変わってしまったのはなぜなのか?
そこに文明の発展による人間の侵出と、カラスの生態とのせめぎ合いがあったのではないか?
カラスを排除するばかりでなく、その生態を理解することで、「カラス問題」には解決できる部分があるのではないか?
そんな疑問が著者の研究の背後にある。
カラス問題にはいくつかあるが、本書で取り上げているのは「営巣問題」である。春の繁殖期、カラスが電柱に巣を作ることで、停電などのトラブルが起こることを指す。こうしたトラブルは日本全国で見られる。ひとたび広範囲の停電が起こると影響が大きいため、各電力会社では繁殖期に電柱を見守り、必要に応じて撤去を行う。それでも完全に被害を抑えることは出来ないし、一度撤去しても、カラスはしばしば、また同じ場所か近くの電柱に営巣する。
毎年、延々と人とカラスの「イタチごっこ」が続いているわけである。
ここから抜け出すことはできないのだろうか?
著者らは、カラスの生態を調べることで、こうした問題を解決する糸口を探った。
営巣しているカラスの種類、カラスのなわばりの性質、巣の構造、大きさ、巣材、それらの地域差。
詳細に調べていくことで、日本で電柱に営巣するカラスはハシボソガラスであり、巣材には農業廃棄物や金属が使われていることがわかった。なわばりの数(≒つがいの数)は比較的固定されていた。
これらのことから、初回の営巣を、トラブルが起こりにくい場所へと誘導することで、かなりの問題が解決されることが示唆されてきた。最初の巣に満足出来れば、カラスだって闇雲にあちこちに巣を作らない。人が撤去する手間も格段に減るはずである。
そこで、カラスが巣を作る土台となる人工巣を設置し、その成果の調査が行われた。実地に設置するとなると、電力会社との連携が重要になる。研究結果を踏まえて、人工巣の形状や設置場所を検討しつつ、かなり手応えのある成果が得られたようである。
一方で、巣材が豊富にあることもカラスが何度も巣を作る要因になる。農業廃棄物に関しては、なるべく放置せず、可能であれば有効利用の方法を探ることも必要になってきそうだ。このあたりは農家などとの連携を必要とするところだろう。
駆除や排除だけでなく、「共存」していく可能性を探る。
研究結果を学界で発表するだけでなく、地域に還元し、手を取り合って問題解決を探る。
カラスの営巣問題についてはもちろんだが、野生動物との間のさまざまな問題を考える上でも非常に示唆に富む、おもしろい例として読んだ。
うるさい。ズル賢い。しぶとい。迷惑。
どちらかというとマイナスイメージの強い鳥だが、それは果たしてカラスばかりが悪いのだろうか?
本書の著者はカラスの生態学を専門とし、約30年、カラス問題に取り組んできた。
著者は冒頭で、童謡「七つの子」を挙げる。「烏なぜ啼くの」と始まるおなじみの歌は、カラスの繁殖期が歌われたものである。大正10年に野口雨情作詞で発表された。カラスの幼子に対する優しい思いが綴られる詞は、人がわが子に寄せる愛情とも重ね合わされる。そこに「迷惑」な「困った」鳥という意識は見られない。
100年近くが経つうち、カラスの印象がこうも変わってしまったのはなぜなのか?
そこに文明の発展による人間の侵出と、カラスの生態とのせめぎ合いがあったのではないか?
カラスを排除するばかりでなく、その生態を理解することで、「カラス問題」には解決できる部分があるのではないか?
そんな疑問が著者の研究の背後にある。
カラス問題にはいくつかあるが、本書で取り上げているのは「営巣問題」である。春の繁殖期、カラスが電柱に巣を作ることで、停電などのトラブルが起こることを指す。こうしたトラブルは日本全国で見られる。ひとたび広範囲の停電が起こると影響が大きいため、各電力会社では繁殖期に電柱を見守り、必要に応じて撤去を行う。それでも完全に被害を抑えることは出来ないし、一度撤去しても、カラスはしばしば、また同じ場所か近くの電柱に営巣する。
毎年、延々と人とカラスの「イタチごっこ」が続いているわけである。
ここから抜け出すことはできないのだろうか?
著者らは、カラスの生態を調べることで、こうした問題を解決する糸口を探った。
営巣しているカラスの種類、カラスのなわばりの性質、巣の構造、大きさ、巣材、それらの地域差。
詳細に調べていくことで、日本で電柱に営巣するカラスはハシボソガラスであり、巣材には農業廃棄物や金属が使われていることがわかった。なわばりの数(≒つがいの数)は比較的固定されていた。
これらのことから、初回の営巣を、トラブルが起こりにくい場所へと誘導することで、かなりの問題が解決されることが示唆されてきた。最初の巣に満足出来れば、カラスだって闇雲にあちこちに巣を作らない。人が撤去する手間も格段に減るはずである。
そこで、カラスが巣を作る土台となる人工巣を設置し、その成果の調査が行われた。実地に設置するとなると、電力会社との連携が重要になる。研究結果を踏まえて、人工巣の形状や設置場所を検討しつつ、かなり手応えのある成果が得られたようである。
一方で、巣材が豊富にあることもカラスが何度も巣を作る要因になる。農業廃棄物に関しては、なるべく放置せず、可能であれば有効利用の方法を探ることも必要になってきそうだ。このあたりは農家などとの連携を必要とするところだろう。
駆除や排除だけでなく、「共存」していく可能性を探る。
研究結果を学界で発表するだけでなく、地域に還元し、手を取り合って問題解決を探る。
カラスの営巣問題についてはもちろんだが、野生動物との間のさまざまな問題を考える上でも非常に示唆に富む、おもしろい例として読んだ。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:築地書館
- ページ数:128
- ISBN:9784806715405
- 発売日:2017年06月16日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。