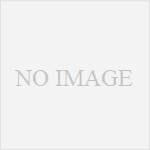darklyさん
レビュアー:
▼
避けられない愛しい人との別れに対して生きている人が持つべき心のありようについて一石を投じた作品。なんとなく読んでしまえばすっと終わってしまうがこの物語の凄さは後でジワジワとやって来る。

小山内堅は東京駅にあるホテルのカフェで奇妙な親子、縁坂ゆいとその娘るりと会うべく待ち合わせをしていた。生意気な少女るりは小山内とその家族しか知らないことを次々と言い当てる。るりは小山内の高校生の時に事故死した娘の瑠璃の生まれ変わりだという。
小山内は娘瑠璃がまだ小さい頃妻から娘の様子がおかしい、奇妙だという話をさんざん聞かされてきたが当時は聞く耳を持っていなかった。この会合には三角という大手ゼネコンの部長も参加する予定だった。三角は大学時代正木瑠璃という人妻と恋に落ちた。しかし正木瑠璃は地下鉄で事故に遭いこの世を去る。小山内瑠璃は正木瑠璃の生まれ変わりではないのかと疑う事実も判明する。
一方正木瑠璃の夫である正木竜之介は妻の死後、紆余曲折を経て工務店で働いていた。瑠璃との関係は破綻しその結婚生活は妻の事故死でピリオドを打つ。その工務店の社長の娘希美は正木に母親が夢で希美ではなく名前をルリにしてほしいと希美からお願いされたという話をする。そしてある時を境にしてそれまで正木に懐いていた希美は正木を避けるようになる。
そのある時とは一定期間原因不明の高熱に見舞われた後、何事もなかったかのように快癒する時である。生まれ変わりだと思われる現象はすべてこの高熱を境にして前人格が現れていた。
果たしてこの現象を小山内はどう整理するのか。そして物語の結末は地味に驚くものになる。
子供の頃から不思議な話が好きだった私は昔から生まれ変わりの話を沢山読んできました。生まれ変わりというテーマは宗教にも使われ、また文学においてもロマンティックな扱われ方をするものは結構あるような気がします。どのような扱われ方をするにしろ、結局は生まれ変わりがあるという設定にした場合はSFやファンタジーのようにするしかないのが大体の相場だろうと思います。
この物語は話が進んでも一向に地を離れファンタジーの空へ飛翔する気配がありません。もし現実の話とするならば生まれ変わりは本当にあるという設定なのか、しかしそれはハードルが高いぞ、どう理屈つける、あやふやな結末は逃げに等しいぞ、お手並み拝見と思いながら読み進めて行きました。
しかし、私はこの時点で作者の狡猾な罠にかかっていることが最後に判明します。この物語の肝は生まれ変わりの有無にあるのではありません。あるのかないのかに意識が集中した私は読み終わった後のファーストインプレッションは少し残念な感じがしたのですが、そこからジワジワと作者の意図が浮かび上がってくるのです。
物語の中で妻を失った老人が庭に飛んできたオウムを妻の生まれ変わりだと大事にする場面が出てきます。かけがえのない人を失った者は、厳しい現実と向き合わなければならない中で、頭では分かった上でそのように思い込むことで自分の気持ちを整理する時間を得ようとするのでしょう。
オウムとは本当の意味でコミュニケーションはできませんが、この物語のように人間によって生まれ変わりが現実だと思わせるような事態が起こったら人はどう反応するのか?全く持って信じない人もいるでしょう。逆に完全に生まれ変わりだと信じるのも破滅を招くと作者は正木竜之介の事件を挙げて主張します。なぜ破滅を招くのか、それは自分よりもはるかに年下で場合によっては幼女を本当に自分の妻だと思い込み行動に出ることは社会的には犯罪としか見えないからです。
ではどのように考えることが良いのか?それは生まれ変わりと考えることも一理あると考えることです。つまりあるかないか、1か0か、ではなく、量子の重ね合わせの状態のように曖昧な状態にしておくということです。そうすることで現実の世界に折り合いをつけながらも自分の大切な人の生まれ変わりということも否定しないことで得られる幸福感、これが人間として最も正しい姿勢ではないかということです。
確かにこの作品は全くのフィクションですが、前述のオウムの例のように、私たちの生活の中でなんらかの現象を今はもう逢えない大切な人からのサインだと思うことは決して後ろ向きな考え方ではないと思うのです。人間にとっては立証のしようがない生まれ変わりがあるのかないのかを気にするよりもサインを糧にして自分の人生を前向きに生きていく方がよっぽど大事なのではないでしょうか。現実を忘れそれにのめり込んでしまうのでなければ。
これは正に宗教のあり方にも通じるところがあるように思います。神や教えが絶対正しいあるいは絶対に間違っているという考えが原理主義を生み出すのだろうと思います。この教えも一理あるよねと人々に思わせそれを元にそれぞれが自分の人生を前向きに考えることができるように導くことが本来の宗教の役割ではないかと思うのです。
この物語は誰が主人公なのかよく分からないまま進んでいきます。最後でようやくというかやはり小山内が主人公だと判明するのですが、それは瑠璃という名前の女性の生まれ変わりの物語は壮大な伏線であるということが判明するからです。つまり小山内が気付き、辿り着く結論に至るためにハードカバー300ページあまりの大半が伏線だとも言えるのです。もちろん物語の最初の方の何気ない記述にもそのヒントは隠されています。
それほど派手な展開がある物語ではないですが、物語の面白みを十二分に味わえるという点においては近年読んだ中では最高の部類に入ると思います。根拠はないですが、平野啓一郎さんの文体によく似ている気がしました。
小山内は娘瑠璃がまだ小さい頃妻から娘の様子がおかしい、奇妙だという話をさんざん聞かされてきたが当時は聞く耳を持っていなかった。この会合には三角という大手ゼネコンの部長も参加する予定だった。三角は大学時代正木瑠璃という人妻と恋に落ちた。しかし正木瑠璃は地下鉄で事故に遭いこの世を去る。小山内瑠璃は正木瑠璃の生まれ変わりではないのかと疑う事実も判明する。
一方正木瑠璃の夫である正木竜之介は妻の死後、紆余曲折を経て工務店で働いていた。瑠璃との関係は破綻しその結婚生活は妻の事故死でピリオドを打つ。その工務店の社長の娘希美は正木に母親が夢で希美ではなく名前をルリにしてほしいと希美からお願いされたという話をする。そしてある時を境にしてそれまで正木に懐いていた希美は正木を避けるようになる。
そのある時とは一定期間原因不明の高熱に見舞われた後、何事もなかったかのように快癒する時である。生まれ変わりだと思われる現象はすべてこの高熱を境にして前人格が現れていた。
果たしてこの現象を小山内はどう整理するのか。そして物語の結末は地味に驚くものになる。
子供の頃から不思議な話が好きだった私は昔から生まれ変わりの話を沢山読んできました。生まれ変わりというテーマは宗教にも使われ、また文学においてもロマンティックな扱われ方をするものは結構あるような気がします。どのような扱われ方をするにしろ、結局は生まれ変わりがあるという設定にした場合はSFやファンタジーのようにするしかないのが大体の相場だろうと思います。
この物語は話が進んでも一向に地を離れファンタジーの空へ飛翔する気配がありません。もし現実の話とするならば生まれ変わりは本当にあるという設定なのか、しかしそれはハードルが高いぞ、どう理屈つける、あやふやな結末は逃げに等しいぞ、お手並み拝見と思いながら読み進めて行きました。
しかし、私はこの時点で作者の狡猾な罠にかかっていることが最後に判明します。この物語の肝は生まれ変わりの有無にあるのではありません。あるのかないのかに意識が集中した私は読み終わった後のファーストインプレッションは少し残念な感じがしたのですが、そこからジワジワと作者の意図が浮かび上がってくるのです。
物語の中で妻を失った老人が庭に飛んできたオウムを妻の生まれ変わりだと大事にする場面が出てきます。かけがえのない人を失った者は、厳しい現実と向き合わなければならない中で、頭では分かった上でそのように思い込むことで自分の気持ちを整理する時間を得ようとするのでしょう。
オウムとは本当の意味でコミュニケーションはできませんが、この物語のように人間によって生まれ変わりが現実だと思わせるような事態が起こったら人はどう反応するのか?全く持って信じない人もいるでしょう。逆に完全に生まれ変わりだと信じるのも破滅を招くと作者は正木竜之介の事件を挙げて主張します。なぜ破滅を招くのか、それは自分よりもはるかに年下で場合によっては幼女を本当に自分の妻だと思い込み行動に出ることは社会的には犯罪としか見えないからです。
ではどのように考えることが良いのか?それは生まれ変わりと考えることも一理あると考えることです。つまりあるかないか、1か0か、ではなく、量子の重ね合わせの状態のように曖昧な状態にしておくということです。そうすることで現実の世界に折り合いをつけながらも自分の大切な人の生まれ変わりということも否定しないことで得られる幸福感、これが人間として最も正しい姿勢ではないかということです。
確かにこの作品は全くのフィクションですが、前述のオウムの例のように、私たちの生活の中でなんらかの現象を今はもう逢えない大切な人からのサインだと思うことは決して後ろ向きな考え方ではないと思うのです。人間にとっては立証のしようがない生まれ変わりがあるのかないのかを気にするよりもサインを糧にして自分の人生を前向きに生きていく方がよっぽど大事なのではないでしょうか。現実を忘れそれにのめり込んでしまうのでなければ。
これは正に宗教のあり方にも通じるところがあるように思います。神や教えが絶対正しいあるいは絶対に間違っているという考えが原理主義を生み出すのだろうと思います。この教えも一理あるよねと人々に思わせそれを元にそれぞれが自分の人生を前向きに考えることができるように導くことが本来の宗教の役割ではないかと思うのです。
この物語は誰が主人公なのかよく分からないまま進んでいきます。最後でようやくというかやはり小山内が主人公だと判明するのですが、それは瑠璃という名前の女性の生まれ変わりの物語は壮大な伏線であるということが判明するからです。つまり小山内が気付き、辿り着く結論に至るためにハードカバー300ページあまりの大半が伏線だとも言えるのです。もちろん物語の最初の方の何気ない記述にもそのヒントは隠されています。
それほど派手な展開がある物語ではないですが、物語の面白みを十二分に味わえるという点においては近年読んだ中では最高の部類に入ると思います。根拠はないですが、平野啓一郎さんの文体によく似ている気がしました。
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
昔からずっと本は読み続けてます。フィクション・ノンフィクション問わず、あまりこだわりなく読んでます。フィクションはSF・ホラー・ファンタジーが比較的多いです。あと科学・数学・思想的な本を好みます。
- この書評の得票合計:
- 46票
| 読んで楽しい: | 7票 |
|
|---|---|---|
| 素晴らしい洞察: | 2票 | |
| 参考になる: | 36票 | |
| 共感した: | 1票 |
|
あなたの感想は?
投票するには、ログインしてください。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:岩波書店
- ページ数:336
- ISBN:9784000014083
- 発売日:2017年04月06日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。