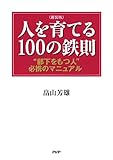紅い芥子粒さん
レビュアー:
▼
織田信長にはアフリカ系黒人の小姓がいた。その名は弥助。彼は宣教師の奴隷だった。信長に見出されるまで、どのような人生をいきていたのか。本能寺を生き延びたあとは……。弥助の謎を追った歴史ノンフィクション。
信長に黒人の小姓がいたことは、広く知られている。その名も弥助。
ネット時代のいま、その知名度は、蘭丸に劣らないかもしれない。
元は宣教師の奴隷であったという弥助。
信長の小姓以前と以後には、彼の人生には、どんなドラマがあったのか。
著者のロックリー・トーマスは、2009年に弥助を知ってから魅了され続け、2016年に歴史ノンフィクションとしてこの本を書き上げた。
弥助のことは、「信長公記」や「松平家忠日記」にその記述がある。
どちらも信頼のおける史料であり、弥助という名の黒人小姓が実在したことはまちがいない。
弥助は、どんな人物だったのか。
太田牛一が「信長公記」に次のように記している。天正九年2月23日のことだ。
「その男は、きりしたん国からやってきた。年齢は、26,7歳。全身、牛のように黒い。健康そうで、見目も良い。しかも十人力。伴天連が連れてきた。」
珍しがった信長と、少しの問答があったのだろう。
彼は、信長の気に入り、召し抱えられた。
弥助という名と、屋敷まで与えられたという。
その後、天正十年六月二日、本能寺で信長が倒れるまで小姓として側近くに仕えた。
本能寺の変では信長を守って戦っていたが、信忠のもとへ行けと命じられ、二条城へ走った。
奮戦したが、明智にとらえられ、その後、イエズス会に戻されたという。
そのとき、明智は「黒んぼうは人間ではない。殺す値打ちもない」といったと伝えられている。
信長の小姓というのは、かなり難度の高い仕事と思われる。
命令通りに動くことができ、気配りもできなければ、いつ首が飛ぶかわからない。
弥助は、日本語を理解し、信長に求められれば異国の珍しい話を語れるほどの日本語力はあったにちがいない。
他の小姓は、家柄が良く、高い教育を受けた美少年ばかり。みな、信長の寵愛を受けている。
弥助も小姓であるからには、信長の「愛人」でもあったのだろうと、著者は推測する。
では、その弥助は、どこから来たのか?
宣教師ヴァリヤーノが連れてきた奴隷だということはわかっている。
それ以前の手掛かりはまったくない。
体格や容姿の記述から、アフリカのどこかだろう。
ヤスケという名の音を頼りにそのルーツを探ってみる。
著者の試みは、16世紀から17世紀にかけて、ヨーロッパ・アジアを移動したアフリカ系黒人の歴史を振り返る壮大な作業になった。
16世紀、世界では奴隷貿易がさかんに行われていた。
アフリカ系黒人だけではなくアジア人も、貧しさから、あるいは戦争の捕虜となって、奴隷船に載せられ世界中で売買されていた。
ガレー船の漕ぎ手や港湾労働者として。傭兵やハーレムの護衛兵として。女性は家事労働者や子守、あるいは性奴隷として。
日本人も例外ではない。傭兵として海外の戦場で戦ったサムライは、大勢いたという。
奴隷は、所有者が死ねば自由民になれた。その地に定住し、子孫を残したものもいるだろう。
本能寺の後、イエズス会に戻された弥助がどうなったかはわからない。
信長の小姓でなくなれば、一介の黒人奴隷にすぎないのだから。
奴隷の行状に注目し、書き留めるものなどいないのだ。
ずいぶん前だが、伊藤潤の「王になろうとした男」という小説を読んだ。
この小説の中で弥助は信長から、「いつかおまえをアフリカのふるさとの王にしてやる」と約束されていた。
もしも、信長が世界を征服したら、の話だ。
弥助は、その日がくるのを信じて夢見ていたのかもしれない。
本能寺を生き延び、奴隷に戻った弥助は、宣教師の船から海に飛び込み、アフリカ大陸に向かって泳ぎだしたのだった。
本能寺の変から四百年以上も経っているのに、弥助の物語は人々を魅了し、想像力を駆り立ててやまない。
著者は、あとがきで書いている。
「弥助は歴史に忘れられ無視されてきた人々に声を与える存在なのだ」、と。
ネット時代のいま、その知名度は、蘭丸に劣らないかもしれない。
元は宣教師の奴隷であったという弥助。
信長の小姓以前と以後には、彼の人生には、どんなドラマがあったのか。
著者のロックリー・トーマスは、2009年に弥助を知ってから魅了され続け、2016年に歴史ノンフィクションとしてこの本を書き上げた。
弥助のことは、「信長公記」や「松平家忠日記」にその記述がある。
どちらも信頼のおける史料であり、弥助という名の黒人小姓が実在したことはまちがいない。
弥助は、どんな人物だったのか。
太田牛一が「信長公記」に次のように記している。天正九年2月23日のことだ。
「その男は、きりしたん国からやってきた。年齢は、26,7歳。全身、牛のように黒い。健康そうで、見目も良い。しかも十人力。伴天連が連れてきた。」
珍しがった信長と、少しの問答があったのだろう。
彼は、信長の気に入り、召し抱えられた。
弥助という名と、屋敷まで与えられたという。
その後、天正十年六月二日、本能寺で信長が倒れるまで小姓として側近くに仕えた。
本能寺の変では信長を守って戦っていたが、信忠のもとへ行けと命じられ、二条城へ走った。
奮戦したが、明智にとらえられ、その後、イエズス会に戻されたという。
そのとき、明智は「黒んぼうは人間ではない。殺す値打ちもない」といったと伝えられている。
信長の小姓というのは、かなり難度の高い仕事と思われる。
命令通りに動くことができ、気配りもできなければ、いつ首が飛ぶかわからない。
弥助は、日本語を理解し、信長に求められれば異国の珍しい話を語れるほどの日本語力はあったにちがいない。
他の小姓は、家柄が良く、高い教育を受けた美少年ばかり。みな、信長の寵愛を受けている。
弥助も小姓であるからには、信長の「愛人」でもあったのだろうと、著者は推測する。
では、その弥助は、どこから来たのか?
宣教師ヴァリヤーノが連れてきた奴隷だということはわかっている。
それ以前の手掛かりはまったくない。
体格や容姿の記述から、アフリカのどこかだろう。
ヤスケという名の音を頼りにそのルーツを探ってみる。
著者の試みは、16世紀から17世紀にかけて、ヨーロッパ・アジアを移動したアフリカ系黒人の歴史を振り返る壮大な作業になった。
16世紀、世界では奴隷貿易がさかんに行われていた。
アフリカ系黒人だけではなくアジア人も、貧しさから、あるいは戦争の捕虜となって、奴隷船に載せられ世界中で売買されていた。
ガレー船の漕ぎ手や港湾労働者として。傭兵やハーレムの護衛兵として。女性は家事労働者や子守、あるいは性奴隷として。
日本人も例外ではない。傭兵として海外の戦場で戦ったサムライは、大勢いたという。
奴隷は、所有者が死ねば自由民になれた。その地に定住し、子孫を残したものもいるだろう。
本能寺の後、イエズス会に戻された弥助がどうなったかはわからない。
信長の小姓でなくなれば、一介の黒人奴隷にすぎないのだから。
奴隷の行状に注目し、書き留めるものなどいないのだ。
ずいぶん前だが、伊藤潤の「王になろうとした男」という小説を読んだ。
この小説の中で弥助は信長から、「いつかおまえをアフリカのふるさとの王にしてやる」と約束されていた。
もしも、信長が世界を征服したら、の話だ。
弥助は、その日がくるのを信じて夢見ていたのかもしれない。
本能寺を生き延び、奴隷に戻った弥助は、宣教師の船から海に飛び込み、アフリカ大陸に向かって泳ぎだしたのだった。
本能寺の変から四百年以上も経っているのに、弥助の物語は人々を魅了し、想像力を駆り立ててやまない。
著者は、あとがきで書いている。
「弥助は歴史に忘れられ無視されてきた人々に声を与える存在なのだ」、と。
投票する
投票するには、ログインしてください。
読書は、登山のようなものだと思っています。読み終わるまでが上り、考えて感想や書評を書き終えるまでが下り。頂上からどんな景色が見られるか、ワクワクしながら読書という登山を楽しんでいます。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:太田出版
- ページ数:280
- ISBN:9784778315566
- 発売日:2017年01月25日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。