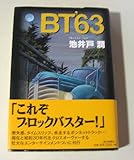ホセさん
レビュアー:
▼
ケン・リュウの本邦2冊目の短編集。長めも含めて16編も読める♪
304 ケン・リュウ 「母の記憶に」
ケン・リュウの本邦2冊目の短編集。長めも含めて16編も読める♪
彼が持ってくる世界は「エッ?」と少し驚くものはあれど、「ウヒャー、凄ぇ!」というものは余りない。
それでも次が出たらまた読む!、と我々を強く引っ張ってくる力がある。
その引力とはいったいどのようなものなのか、それが今回少し分かったかもしれない。
「ループの中で」が一番印象に残った。
仕事がない戦争中にカイラが得たのは、兵器ドローンに代わるロボットの遠隔操縦の仕事だった。
カイラは淡々と仕事をこなしていくが、仕事が終わってからのカイラの生活ぶりからPTSDなり鬱が進行していることがよく分かる。
たとえ自分のその手にかけないとしても、人を殺める事が左程にダメージを残す事を我々は少しだけ感じる事ができる。
暴力も何もしていなくても、言葉で人を傷つけた事をあなたが覚えているなら、あの後味の悪さもその後のフラッシュバックも知っているよね。
いったいカイラが受けたものはその何倍も強く、どんな嫌悪感がどれほどあって、何度その後思い出させられるのだろう?
と我々は問いかけざるを得ない。そしてカイラの日々がその答えを少しだけ教えてくれているのだ。
ある時「(敵の)子供が犠牲になったあの殺戮は、間違っている」とカイラは味方世間から叩かれて職を追われる。
その子を殺さなかったら、味方の人間が随分沢山その子に殺されていたのだが・・・
このお話は、そのものが近い将来起こるだろうと確信させるだけではない。
カイラがこうなら、例えば自分がこんな事をしたなら、ああなってしまうだろう、しちゃいけないな。
という「我々自身への応用例題」として大変効いている。
ケン・リュウの魅力は、作る世界が面白い、作る切り口が興味深い、といったところはもちろんあるのだが、
一番は恐らく「お話の中から、自分の中に普遍的なものやルールを作り、固める事を後押ししている」ことだろう。
我々は殺戮兵器の操縦者になるチャンスは極めて低いが、カイラは幾つもの事を我々に示し思い出させ、考えさせている。
表題の「母の記憶に」は、とても穏やかな余韻だ。
切り口は使い古されたものなのだが、SFの手法を使って、
例えこのように会う事が少なくても「母というものは慈愛に満ちている」と、ケン・リュウが言っている。
これは前作「紙の動物園」と一緒だ♪♪
「訴訟士と猿の王」も面白かった。
1645年に満州軍が行った揚州大虐殺を記した「揚州十日記」は、清によって禁書にされたが、
その本は1808年に昌平坂学問所(御近所湯島だ♪)に納入されている。
その史実はこんなふうにして起こったのではないか、という一つの仮説のお話だ。
(こうした書物の存在は、なぜ我々国民に知らされる機会が少ないのだろう?)
長めの「レギュラー」は、ケン・リュウ版ブレード・ランナーというところだろうか。
こんなアクションストーリーも書けるんだと驚いた。
特に「調整者」というマザーコンピューターに、いざというときに身体能力を上げてもらう、
その為にルースが自分の体にお金をかけて改造する、というところや、
人々が自分の一番大切なものを、あそこにああいう形で隠す、といったことに興奮しながら読んだ。
ケン・リュウが大変醒めた眼を持っていることが、こんなセリフから分かる。
耳を傾けるに値する人かどうかを、私が判断する根拠の一つは、
「いかに醒めた、時に冷酷な捉え方をできる(強い)人かどうか」というところだ。
「ひとり殺すことであらゆる虐待者を止めることは無理だというのなら
-ー文化の方向性を逆転させ、死のからくりを廃止させ、歴史の流れを蛙には足りないというのならーー
もっと大勢を殺さなくては。」
「権力を握った連中はいつだって、過去を消して黙らせたい」
「鳥蘇里罷」には1907(明治40)年の満州では、意思に従って蒸気で動く義手をつけた日本人親子が出てきたり、
「万味調和」では、三国志の関羽と開拓者時代のアメリカが交互に現れる。
「状態変化」には劇作家のTSエリオットが登場すれば、
「「輸送年鑑」より」では、1962年のツェッペリン(飛行船)が舞台だ。
ケン・リュウの興味や想像力の底知れなさを感じるだけでなく、
読んだ後には、「自分のルール」が少し増えている事に気付くかもしれないよ。
(2017/11/9)
ケン・リュウの本邦2冊目の短編集。長めも含めて16編も読める♪
彼が持ってくる世界は「エッ?」と少し驚くものはあれど、「ウヒャー、凄ぇ!」というものは余りない。
それでも次が出たらまた読む!、と我々を強く引っ張ってくる力がある。
その引力とはいったいどのようなものなのか、それが今回少し分かったかもしれない。
「ループの中で」が一番印象に残った。
仕事がない戦争中にカイラが得たのは、兵器ドローンに代わるロボットの遠隔操縦の仕事だった。
カイラは淡々と仕事をこなしていくが、仕事が終わってからのカイラの生活ぶりからPTSDなり鬱が進行していることがよく分かる。
たとえ自分のその手にかけないとしても、人を殺める事が左程にダメージを残す事を我々は少しだけ感じる事ができる。
暴力も何もしていなくても、言葉で人を傷つけた事をあなたが覚えているなら、あの後味の悪さもその後のフラッシュバックも知っているよね。
いったいカイラが受けたものはその何倍も強く、どんな嫌悪感がどれほどあって、何度その後思い出させられるのだろう?
と我々は問いかけざるを得ない。そしてカイラの日々がその答えを少しだけ教えてくれているのだ。
ある時「(敵の)子供が犠牲になったあの殺戮は、間違っている」とカイラは味方世間から叩かれて職を追われる。
その子を殺さなかったら、味方の人間が随分沢山その子に殺されていたのだが・・・
このお話は、そのものが近い将来起こるだろうと確信させるだけではない。
カイラがこうなら、例えば自分がこんな事をしたなら、ああなってしまうだろう、しちゃいけないな。
という「我々自身への応用例題」として大変効いている。
ケン・リュウの魅力は、作る世界が面白い、作る切り口が興味深い、といったところはもちろんあるのだが、
一番は恐らく「お話の中から、自分の中に普遍的なものやルールを作り、固める事を後押ししている」ことだろう。
我々は殺戮兵器の操縦者になるチャンスは極めて低いが、カイラは幾つもの事を我々に示し思い出させ、考えさせている。
表題の「母の記憶に」は、とても穏やかな余韻だ。
切り口は使い古されたものなのだが、SFの手法を使って、
例えこのように会う事が少なくても「母というものは慈愛に満ちている」と、ケン・リュウが言っている。
これは前作「紙の動物園」と一緒だ♪♪
「訴訟士と猿の王」も面白かった。
1645年に満州軍が行った揚州大虐殺を記した「揚州十日記」は、清によって禁書にされたが、
その本は1808年に昌平坂学問所(御近所湯島だ♪)に納入されている。
その史実はこんなふうにして起こったのではないか、という一つの仮説のお話だ。
(こうした書物の存在は、なぜ我々国民に知らされる機会が少ないのだろう?)
長めの「レギュラー」は、ケン・リュウ版ブレード・ランナーというところだろうか。
こんなアクションストーリーも書けるんだと驚いた。
特に「調整者」というマザーコンピューターに、いざというときに身体能力を上げてもらう、
その為にルースが自分の体にお金をかけて改造する、というところや、
人々が自分の一番大切なものを、あそこにああいう形で隠す、といったことに興奮しながら読んだ。
ケン・リュウが大変醒めた眼を持っていることが、こんなセリフから分かる。
耳を傾けるに値する人かどうかを、私が判断する根拠の一つは、
「いかに醒めた、時に冷酷な捉え方をできる(強い)人かどうか」というところだ。
「ひとり殺すことであらゆる虐待者を止めることは無理だというのなら
-ー文化の方向性を逆転させ、死のからくりを廃止させ、歴史の流れを蛙には足りないというのならーー
もっと大勢を殺さなくては。」
「権力を握った連中はいつだって、過去を消して黙らせたい」
「鳥蘇里罷」には1907(明治40)年の満州では、意思に従って蒸気で動く義手をつけた日本人親子が出てきたり、
「万味調和」では、三国志の関羽と開拓者時代のアメリカが交互に現れる。
「状態変化」には劇作家のTSエリオットが登場すれば、
「「輸送年鑑」より」では、1962年のツェッペリン(飛行船)が舞台だ。
ケン・リュウの興味や想像力の底知れなさを感じるだけでなく、
読んだ後には、「自分のルール」が少し増えている事に気付くかもしれないよ。
(2017/11/9)
掲載日:
投票する
投票するには、ログインしてください。
語りかける書評ブログ「人生は短く、読むべき本は多い」からの転記になります。
殆どが小説で、児童書、マンガ、新書が少々です。
評点やジャンルはつけないこととします。
ブログは「今はなかなか会う機会がとれない、本読みの友人たちへ語る」調子を心がけています。
従い、私の記憶や思い出が入り込み、エッセイ調にもなっています。
主要六紙の書評や好きな作家へのインタビュー、注目している文学賞の受賞や出版各社PR誌の書きっぷりなどから、自分なりの法則を作って、新しい作家を積極的に選んでいます(好きな作家へのインタビュー、から広げる手法は確度がとても高く、お勧めします)。
また、著作で前向きに感じられるところを、取り上げていくように心がけています。
「推し」の度合いは、幾つか本文を読んで頂ければわかるように、仕組んでいる積りです。
PS 1965年生まれ。働いています。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:早川書房
- ページ数:526
- ISBN:9784153350328
- 発売日:2017年04月20日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。