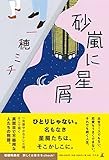三太郎さん
レビュアー:
▼
生前に上梓された三冊の小品集をまとめて読みました。
カフカが生前に自ら選んで出版した三つの小品集がまとめて読める本です。訳は吉田仙太郎氏でみすず書房から出ていましたが、残念ながら現在は絶版のようで古書店の価格も新刊並みです。
三つの小品集から各々1篇を選んで感想を述べてみたいと思います。
第一小品集「観察」からは「国道の子供たち」について。子供が主人公で自宅で一人夕食を摂っていると暗闇のなかから子供たち(友達?)が迎えに来ます。彼らと外に出て道路を橋のところまでふざけ合いながら走っていきます。遠くに汽車が走っていくので皆で歌を唄います。わたしはそばにいる男の子にキスをし戻り路を南の町の方を目指して駆けだしましたが、うちの村ではその町の住人を眠らない連中だと噂していました。眠らないのは疲れないから。疲れないのは馬鹿だから。
唐突にその町の連中は眠らないと書いてありますが、作者は何を言いたかったのかな。カフカ自身は夜中に眠らずにひたすら小説を書いていたというのですが。ところで、主人公を誘いに来た少年たちはひょっとしたら幽霊なのかも。「不幸であるということ」には実際に子供の幽霊がでてきます。
第二小品集「田舎医者」からは作品集のタイトルになった「田舎医者」について。吹雪の中、10マイル離れた村で重傷患者がでたという知らせを受けた医師は、早速馬車で出発しようとしますが肝心の馬は昨日過労死しています。女中が村中を探し回っているが代わりの馬が見つかりません。すると空のはずの豚小屋から一人の見知らぬ馬丁と二頭の馬が突然現れ、馬丁が馬を繋ぐと医師を乗せた馬車はあっという間に患者の家に着いていました。患者は「僕を死なせて」といいますが、医師は直ぐにでも家へ帰りたい。例の馬丁が若い女中のローザを襲おうとしていたからです。
患者を診ると脇腹に大きな傷があって蛆がわいています。患者は「助けてくれるの?」と問いますが、医師は救えないと思います。すると家族と村の長老たちが医者の着物を剥いで裸にし、医者は患者の隣に寝かされます。突然子供の合唱隊が歌います。「直せなければ殺してしまえよ。たかが医者だよ。」医師は言葉たくみに大した傷ではないと患者を言いくるめ、裸で馬車に飛び乗り家を目指しました。
長老たちは医師を裸にして患者の隣に寝かせたのですが、医者が逃げ帰れなかったらどうなったのか、ちょっと怖いですね。
第三小品集「断食芸人」ではタイトルの断食芸人についてはこちらで書いてしまったので、「歌姫ヨゼフィーネ、または二十日鼠の一族」を紹介します。語り手の「わたし」もヨゼフィーネも鼠なのですが、その鼠の歌姫(ディーバ)のお話です。歌姫の「歌」は鼠の一族の中で圧倒的な支持を集めていますが、私はヨゼフィーネには批判的な立場で、彼女の歌は特に優れたところもなく、ただの鼠のピューピュー鳴きなのではないかと言います。しかし彼女は取り巻き連中の絶対的支持を得ていて、彼女が鳴きたいといえば支持者たちが多くの聴衆を動員してコンサートが開催されます。でもそのうちヨゼフィーネは聴衆たちに不満を覚え、だんだん鳴き方がおざなりになり遂には鳴くことを止めてしまう、というお話です。
翻訳者によればこのお話を何かの教訓話と受け取ることは違っているというのですが、現在のSNS全盛時代には様々な「ヨゼフィーネ現象」が見られる気がします。一見批判的にみえる「わたし」の言い分も一方的なものではなくて結構揺れています。
カフカの作品は時間をおいて再読したら、また違った印象を受けるかもしれませんね。
三つの小品集から各々1篇を選んで感想を述べてみたいと思います。
第一小品集「観察」からは「国道の子供たち」について。子供が主人公で自宅で一人夕食を摂っていると暗闇のなかから子供たち(友達?)が迎えに来ます。彼らと外に出て道路を橋のところまでふざけ合いながら走っていきます。遠くに汽車が走っていくので皆で歌を唄います。わたしはそばにいる男の子にキスをし戻り路を南の町の方を目指して駆けだしましたが、うちの村ではその町の住人を眠らない連中だと噂していました。眠らないのは疲れないから。疲れないのは馬鹿だから。
唐突にその町の連中は眠らないと書いてありますが、作者は何を言いたかったのかな。カフカ自身は夜中に眠らずにひたすら小説を書いていたというのですが。ところで、主人公を誘いに来た少年たちはひょっとしたら幽霊なのかも。「不幸であるということ」には実際に子供の幽霊がでてきます。
第二小品集「田舎医者」からは作品集のタイトルになった「田舎医者」について。吹雪の中、10マイル離れた村で重傷患者がでたという知らせを受けた医師は、早速馬車で出発しようとしますが肝心の馬は昨日過労死しています。女中が村中を探し回っているが代わりの馬が見つかりません。すると空のはずの豚小屋から一人の見知らぬ馬丁と二頭の馬が突然現れ、馬丁が馬を繋ぐと医師を乗せた馬車はあっという間に患者の家に着いていました。患者は「僕を死なせて」といいますが、医師は直ぐにでも家へ帰りたい。例の馬丁が若い女中のローザを襲おうとしていたからです。
患者を診ると脇腹に大きな傷があって蛆がわいています。患者は「助けてくれるの?」と問いますが、医師は救えないと思います。すると家族と村の長老たちが医者の着物を剥いで裸にし、医者は患者の隣に寝かされます。突然子供の合唱隊が歌います。「直せなければ殺してしまえよ。たかが医者だよ。」医師は言葉たくみに大した傷ではないと患者を言いくるめ、裸で馬車に飛び乗り家を目指しました。
長老たちは医師を裸にして患者の隣に寝かせたのですが、医者が逃げ帰れなかったらどうなったのか、ちょっと怖いですね。
第三小品集「断食芸人」ではタイトルの断食芸人についてはこちらで書いてしまったので、「歌姫ヨゼフィーネ、または二十日鼠の一族」を紹介します。語り手の「わたし」もヨゼフィーネも鼠なのですが、その鼠の歌姫(ディーバ)のお話です。歌姫の「歌」は鼠の一族の中で圧倒的な支持を集めていますが、私はヨゼフィーネには批判的な立場で、彼女の歌は特に優れたところもなく、ただの鼠のピューピュー鳴きなのではないかと言います。しかし彼女は取り巻き連中の絶対的支持を得ていて、彼女が鳴きたいといえば支持者たちが多くの聴衆を動員してコンサートが開催されます。でもそのうちヨゼフィーネは聴衆たちに不満を覚え、だんだん鳴き方がおざなりになり遂には鳴くことを止めてしまう、というお話です。
翻訳者によればこのお話を何かの教訓話と受け取ることは違っているというのですが、現在のSNS全盛時代には様々な「ヨゼフィーネ現象」が見られる気がします。一見批判的にみえる「わたし」の言い分も一方的なものではなくて結構揺れています。
カフカの作品は時間をおいて再読したら、また違った印象を受けるかもしれませんね。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
1957年、仙台に生まれ、結婚後10年間世田谷に住み、その後20余年横浜に住み、現在は仙台在住。本を読んで、思ったことあれこれを書いていきます。
長年、化学メーカーの研究者でした。2019年から滋賀県で大学の教員になりましたが、2023年3月に退職し、10月からは故郷の仙台に戻りました。プロフィールの写真は還暦前に米国ピッツバーグの岡の上で撮ったものです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:みすず書房
- ページ数:232
- ISBN:9784622080800
- 発売日:2010年05月15日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。