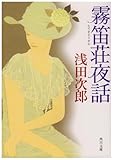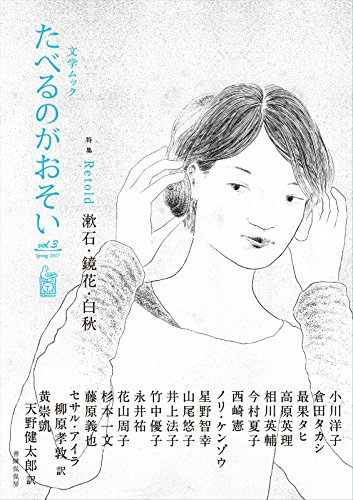たべるのがおそい vol.3
小川洋子、倉田タカシ、最果タヒ、高原英理、今村夏子、西崎憲、星野智幸、山尾悠子、井上法子、竹中優子、永井祐、花山周子、杉本一文、藤原義也、セサル・アイラ、黄崇凱、相川英輔、ノリ・ケンゾウ
▼
作り手の柔らかな物腰と有志で編んだ文学冊子を開くような懐かしさを感じさせてくれる、気心にあふれた一冊。「どうぞ、こちらへ」と読者の手をとり、軽やかに作品世界へ誘ってくれるような間口の広さが魅力だ。
小説、翻訳、短歌の3つのジャンルで構成される「たべるのがおそい」は、ページの随所からどこか懐かしさが匂い立ってくる一冊である。ほどよく手に馴染む心地よい表紙の質感、ところどころに挟まれる温かみのある挿絵、フォント・行間など各作品によって異なる書式を反映させる点など、その懐かしさは文学好きの有志で編む冊子のような手ざわりを思い起こさせてくれる。
もちろんそこは、西崎憲編集長を筆頭に良質な本を世へ送りだす出版社のプロの人たちが仕立てた文学ムックであり、アマチュアの手によるものと比べるべくもないのだが、読者は随所に既成の雑誌とは異なる、作り手のやわらかな物腰を感じることになるのではないだろうか。
気やすさ、とわたしは書いたが、寄稿する書き手の顔ぶれは小川洋子、星野智幸、山尾悠子といったメジャーな小説家をはじめ、「Retold=再話」という今号の特集には詩人の最果タヒが参加するなど、一流の執筆者が揃う。また翻訳小説、短歌といったふだん馴染みのない作者の作品を読めることも嬉しい。以下に、私が気になった作品をいくつかピックアップして記してみる。
Vol.1に掲載された「あひる」が第5回河合隼雄物語賞を受賞した今村夏子の「白いセーター」から。クリスマスイブに、夫とお好み焼き屋へ行く約束を取り付けた“わたし”。その矢先に義姉から、イブの当日に教会で開かれるイベントに子どもたちを連れて行ってほしいと頼まれる。子守り役として教会へ行ったわたしが、彼らのふるまいや言動により、周囲の関係にゆるやかな波紋が生じる一日の出来事を切りとる。”わたし”が日常のエアポケットに不意に落ち込むこの小品は、あたかも白地のセーターに不吉な斑紋が次第に広がっていくような雰囲気を醸す。次第に転調するその変化に注目されたし。
「すごい!」と感嘆したのは、台湾が中国へ宣戦布告するという設定のもとに、台湾国内に住む若者4人の行動とその日々を描く、黄崇凱「カピパラを盗む」である。戦争という非常時にありながらも、市場とネットにはふだんと変わりなくモノと情報が溢れかえる。そのアンバランスな異様なる空間が、サファリパークから盗んだ「カピパラ」の可愛らしい姿を介して描かれる。戦争と日常とを対置させるこのような手法は、「機動警察パトレイバー 2 the Movie」で押井守が描いた世界観を連想させるが、社会がここまで発展・拡大すると、実際の戦時下においてさえも、モノと情報と不断に供給される作中のような光景が展開されるのではないか、と思えるほど。脳裏に「終わりなき日常」という言葉がよぎった。
その他にも、作者と同姓同名となる“星野智幸”という作中人物が過去の一点から分岐したもうひとりの自分との対話を試みる、いわば自戒小説および自己拡充小説とも云うべき、星野智幸「乗り換え」、生存の道が限りなく断たれたディストピア国家において、体制転覆をねらう人物にこと寄せ、語り手が記憶と意識と言葉についての反問を繰り返す、高原英理「ほぼすべての人に題名をつけるとするなら」。またアメリカの農場で酷使される研修生の若者が脱走を試みた末に思わぬ相手からメッセージを授かる、相川英輔「エスケイプ」など、書き手の問題意識やその心象はもとより、現在の国内外の情勢がページの向こうからほの見えてくるところも興味深い。
掌編でありながらも読みごたえ充分となるこのムックは、自然体で飾ったところがなく、一部の読者のみに充てた閉塞性を感じさせることもない。「どうぞ、こちらへ」と読者の手をとり、軽やかに作品世界へ誘ってくれるような間口の広さが魅力だ。出版社のHPには西崎憲編集長のことば、もろもろの重力からの軽減をうたった「読んでいるあいだ、少し動きやすく、歩きやす」くとの、ムックのコンセプトが紹介されているが、その試みは充分に成果を挙げているように思われる。惜しむらくは、特集の押し出しがやや弱い点にあるだろうか。
福岡の出版社・書肆侃侃房が刊行する本書を筆頭に、熊本に拠点を置く伽鹿舎の「片隅」と、九州から既存の文学世界へ新たな風を吹き込もうとする試みがなされている。出版不況が叫ばれる時代にあって、あまたの文学者を輩出してきた九州の文学熱は今も昔も変わりない。”地産地消”ならぬ”地産地読”を念頭に、これからも九州から狼煙をあげる各出版社の動向を見守っていきたい。
もちろんそこは、西崎憲編集長を筆頭に良質な本を世へ送りだす出版社のプロの人たちが仕立てた文学ムックであり、アマチュアの手によるものと比べるべくもないのだが、読者は随所に既成の雑誌とは異なる、作り手のやわらかな物腰を感じることになるのではないだろうか。
気やすさ、とわたしは書いたが、寄稿する書き手の顔ぶれは小川洋子、星野智幸、山尾悠子といったメジャーな小説家をはじめ、「Retold=再話」という今号の特集には詩人の最果タヒが参加するなど、一流の執筆者が揃う。また翻訳小説、短歌といったふだん馴染みのない作者の作品を読めることも嬉しい。以下に、私が気になった作品をいくつかピックアップして記してみる。
Vol.1に掲載された「あひる」が第5回河合隼雄物語賞を受賞した今村夏子の「白いセーター」から。クリスマスイブに、夫とお好み焼き屋へ行く約束を取り付けた“わたし”。その矢先に義姉から、イブの当日に教会で開かれるイベントに子どもたちを連れて行ってほしいと頼まれる。子守り役として教会へ行ったわたしが、彼らのふるまいや言動により、周囲の関係にゆるやかな波紋が生じる一日の出来事を切りとる。”わたし”が日常のエアポケットに不意に落ち込むこの小品は、あたかも白地のセーターに不吉な斑紋が次第に広がっていくような雰囲気を醸す。次第に転調するその変化に注目されたし。
「すごい!」と感嘆したのは、台湾が中国へ宣戦布告するという設定のもとに、台湾国内に住む若者4人の行動とその日々を描く、黄崇凱「カピパラを盗む」である。戦争という非常時にありながらも、市場とネットにはふだんと変わりなくモノと情報が溢れかえる。そのアンバランスな異様なる空間が、サファリパークから盗んだ「カピパラ」の可愛らしい姿を介して描かれる。戦争と日常とを対置させるこのような手法は、「機動警察パトレイバー 2 the Movie」で押井守が描いた世界観を連想させるが、社会がここまで発展・拡大すると、実際の戦時下においてさえも、モノと情報と不断に供給される作中のような光景が展開されるのではないか、と思えるほど。脳裏に「終わりなき日常」という言葉がよぎった。
その他にも、作者と同姓同名となる“星野智幸”という作中人物が過去の一点から分岐したもうひとりの自分との対話を試みる、いわば自戒小説および自己拡充小説とも云うべき、星野智幸「乗り換え」、生存の道が限りなく断たれたディストピア国家において、体制転覆をねらう人物にこと寄せ、語り手が記憶と意識と言葉についての反問を繰り返す、高原英理「ほぼすべての人に題名をつけるとするなら」。またアメリカの農場で酷使される研修生の若者が脱走を試みた末に思わぬ相手からメッセージを授かる、相川英輔「エスケイプ」など、書き手の問題意識やその心象はもとより、現在の国内外の情勢がページの向こうからほの見えてくるところも興味深い。
掌編でありながらも読みごたえ充分となるこのムックは、自然体で飾ったところがなく、一部の読者のみに充てた閉塞性を感じさせることもない。「どうぞ、こちらへ」と読者の手をとり、軽やかに作品世界へ誘ってくれるような間口の広さが魅力だ。出版社のHPには西崎憲編集長のことば、もろもろの重力からの軽減をうたった「読んでいるあいだ、少し動きやすく、歩きやす」くとの、ムックのコンセプトが紹介されているが、その試みは充分に成果を挙げているように思われる。惜しむらくは、特集の押し出しがやや弱い点にあるだろうか。
福岡の出版社・書肆侃侃房が刊行する本書を筆頭に、熊本に拠点を置く伽鹿舎の「片隅」と、九州から既存の文学世界へ新たな風を吹き込もうとする試みがなされている。出版不況が叫ばれる時代にあって、あまたの文学者を輩出してきた九州の文学熱は今も昔も変わりない。”地産地消”ならぬ”地産地読”を念頭に、これからも九州から狼煙をあげる各出版社の動向を見守っていきたい。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
サイトへの出没回数がメタキン並みにレアなので、
皆さまの書評は、投票してくださった方のものを読むようにしています。
ごめんちゃい。
(2019/11/16)
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:書肆侃侃房
- ページ数:176
- ISBN:9784863852570
- 発売日:2017年04月21日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。