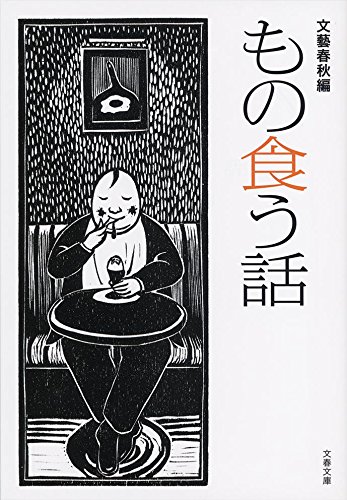えっ?お腹が減っているときに食べる話の本なんか読んだらますますお腹が減ってしまうって?いいじゃないですか、そのあとのご飯が美味しくなって。それよりも、この本はお腹がいっぱいの時に読んでも何となく口が寂しくなってくるんですよ。
で、そこらへんにある醤油煎餅かなんかつまみながら読むじゃないですか。
飲み物も欲しくなるから麦茶もしくは牛乳あたりをそのときの気分で選んで冷蔵庫から出してコップに注ぐわけじゃないですか。
するとますます煎餅が進んで、そしたら口が飽きてくるからじゃあ甘いものでもってことでアルフォートかなんかのチョコ菓子も開けますよね。
太ります。間違いなく太ります。
……なんて話をするためにこの書評を書き始めたわけではないのだが、とにかく色々な意味で読んで美味しい本だった。
この本は去年くらいにレビュアーさんに教えていただいて、宿題になっていたのでした。その時にオススメいただいた該当の部分は早々に読んだのですが、他の作品がとにかく読むとお腹が空くので読むタイミングが限定され、結果カバンに入れっぱなしにして昼休みに長居できるお店でご飯を食べる時に読むことに。
消化するのに数ヵ月かかったという訳であります。
この本は、タイトルから分かる通り食に関する本のアンソロジーなのだが、収録されている作品が豪華すぎる。
短編が収められている作家をざっと挙げてみると
大岡昇平、內田百閒、邱永漢、澁澤龍彥、椎名麟三、武田泰淳、武田百合子、色川武大、赤瀬川原平、吉行淳之介、森鷗外、岡本かの子、筒井康隆、吉田健一、永井龍男、小泉八雲、古川緑波、森田たま、森茉莉、近藤紘一、水木しげる、向田邦子、直木三十五、中島敦、福田恆存。この順番で掲載されている。(この他にも多数の作品からの短い引用が短編と短編の間に挿入されており、豪華かつ手の込んだつくりになっている。)
本好きが愛する近代作家をくまなく網羅したようなこのラインナップ。順番にも唸らされる。普通に本を読んでいたら、まず水木しげるを読んでから向田邦子にはなかなか食指が動かない。
それぞれの作家についての短い解説で、その作家の食に纏わるエピソードにも軽く触れられているのも楽しい。森鷗外の好物は饅頭の茶漬け(…なんて食べ方があることにもビックリ!)、その娘の森茉莉の得意料理はふわふわオムレット、なんて豆知識も仕入れられる。
これだけの作家が一堂に会すると、中には知らない作家や食わず嫌いで未読の作家もいる。
私は森茉莉を勝手に苦手に感じていたのだが、ここに収録されているものは美味しく読ませていただいた。また、吉田健一という作家の存在を知らなかったのだが、この本収録の「饗宴」は、ありとあらゆるご馳走をメチャクチャに大食いする空想を描いた楽しい作品で、これだけで白飯三杯食べられそうな快作だった。未読の作家をちょっとだけつまみ食いするきっかけとしてもこの本の存在はありがたい。
「食」といっても様々な切り口があり、美食から日常の食卓、戦時中の飢え、食人や、マンガのワンシーンで魂を食うところなんてものまでが集められている。「美味しそう」だけで終わらないのがこのアンソロジーの憎いところだ。
食べることに関わることは、楽しいこと、満たされることばかりではない。肉を食べるための殺生、飢餓や拒食・過食、偏食などネガティブな要素も併せ持つ。美味しそうなだけの食のアンソロジーはよくあるが、食の価値観を逆転させた赤瀬川原平の「食い地獄」や、食人する部族を描いた筒井康隆の「人喰人種」は、食という行為の業の深さを感じさせる。
食べ物の物語ならば、誰もが読んで楽しいと感じるはずだ、と、私はかつては単純に思っていた。
が、ある時、あれは確か雑誌ビックイシューで雨宮処凛さんの連載に書かれていたのだったと思うのだが(何分古い記憶なのではっきりしない。違っていたらすみません)、いじめで無理矢理大便を食べさせられた被害者の話を読んだ。食は万人に喜びを与えるわけではないと知ったのはその時だ。
そこまで深刻な例でなくとも、単に食事にそれほど重きを置いておらず空腹を満たせればそれでいいという人、病気で食事が摂れない人、少食で多くは食べられない人もいる。
それでも生命を繋ぐためには、食べなければならない。
そうである以上、誰しもに、食に纏わる記憶がある。美味しい記憶も不味い記憶も、楽しい思い出も苦い思い出も、誰かと囲んだ食卓も、ひとりの食卓も。
逃れられない生き物の業として、あるいは人の世で生きる上での行事として、食というものを捉えた編集がされたこの本こそ、誰もが味わうことのできる本に仕上がっている。
さて、件の宿題である。
いきさつについてはこちらの書評のコメント欄をご参照ください。
要約すると「武田百合子のエッセイ「枇杷」を、百合子をモデルに描いたとされる夫・泰淳の『もの食う女』という小説と比較してみてください。」ということである。
……これを文章にまとめるというのが相当な難題であることは皆様もお察しくださることだろう。
そもそもこのご夫妻の個々の作品単体の書評を書くのだって相当に難しいのだ(作品が難解だというわけではなくて、作品を読んで感じる良さを表現するのが難しい)。
うぉぉハードル高い!!!が、高いハードルほどよっしゃよじ登ってやろうとも思うもの。
なんとかやってみましょう。
泰淳の「もの食う女」は、神経質で繊細な恋人に振り回される男が、その恋人とは真逆の性格の女に惹かれて食事を共にするという内容だ。一方、百合子のエッセイは、晩年の泰淳が百合子が薄く切った枇杷を歯のない口でゆっくりゆっくり咀嚼して旨そうに食べる様子を、泰淳の没後に思い出して描いている。
この作品に共通するのが、「相手を食べてしまったのではないか」という感覚。そこにある官能。
どちらの作品の中でも、この夫妻はそろってお互いにお互いを食べてしまったのではないかと思っている。まぁ仲の良いことで御馳走様、とこちらは思うわけだが、この「食べてしまった」感覚に、微妙な違いがある。
泰淳のその感覚には、罪悪感や畏れが伴う。自分に他に恋人がいるなんて思いもしないような様子で、自分の言動を無条件に温かく受け入れてくれる女。その好意、心を
まるで平気で食べてしまったような気がする……
と、重苦しさを感じ、ひとり泣く真似をする。
なぜ自分のふるまいを女は素直に受け入れてくれるのか。どうしてそこまでしてくれるのか。「幸せすぎて怖い」という月並みなドラマの台詞が脳裏に浮かんだ。泰淳の心の動きは、恋愛の渦中にある不安定さと、「受け入れられること、まっすぐに愛されること」という未知の領域への恐れが感じられる。無条件のおおらかな好意の前に立ち尽くすような、無垢な愛情に打たれたような、複雑で激しい心の動きが感じられる。
百合子の感覚は、一見、複雑さや激しさはないようにみえる。淡々として、日常の延長にあるようだ。
夫がこの世からいなくなってしまったことが、彼女には未だ不思議でならない。それは死を受けとめきれないとか受け入れきれないとかいうのとは、似ているようでちょっと違う。当たり前にそばにいた人がそこにいないこと。理屈では分かっていてもその不在に慣れない。悲しみを通り越して不思議に思えてしまうのではないか。
あのひとがいないのは、あのひとの腕や指がいまここにないのは、私があのとき食べてしまったからではないかしら。
どこかあっけらかんとしたようにも感じられるそのような表現に、私はしみじみとした寂しさを感じた。「喪失」のその時からずっと時間が経って、それでも続く「不在」を、日々感じ続けている。
大人になって歳を経て、親戚や知人のお葬式に行く機会にも遭遇するようになって分かったことがある。葬式が済めばすぐに残された者たちの身には普通の日常が続いていき、そしてそれでもその後ずっと、失われた人の不在による違和感は埋まらないということだ。
その違和感の大きさを、百合子はやわらかな言葉で綴る。
激しい言葉でないことが、かえって私にはその悲しみの深さを感じさせられた。私もまた泰淳のように、そのまっすぐで無垢な悲しみに打たれるような思いがしたのだ。
……と、私にはそのように読めたのだが、このご夫妻の文章はもっと様々な解釈ができるだろう。私自身、時間を置いて読んだらまた違う答えに気づけるように思う。
ずっと飽きずに咀嚼し続けることができるような素晴らしい作品に出会うことができた。
これからも折々に(特に空腹時に)取り出して反芻したい。





かなりふざけたレビューとまあまあ真面目なレビューを気分によって半々くらいで書いています。
性別はめす。ウーパールーパー飼い。雑貨屋店員。
アイコンは、掲示板の昔のリレー小説(2012年)のときのコンビ・ザリちゃんウパちゃんです。
最近の悩みは、なんか色々やりすぎて忙しいこと。
こちらで全然書けなくなってしまいましたが、掲示板などは時々のぞかせて頂いています。
- この書評の得票合計:
- 32票
| 読んで楽しい: | 15票 | |
|---|---|---|
| 素晴らしい洞察: | 1票 | |
| 参考になる: | 16票 |
この書評へのコメント
- mono sashi2017-03-30 13:41
宿題を出した張本人です。生意気言って、すみませんでした(T_T)
わたしは、最愛の夫を亡くした悲哀や喪失感を、あっけらかんとした筆致で、
日常のさりげない一コマに落とし込んだところに、
彼女の底知れない才覚を嗅ぎとったのでした。暗いところがまったくない。
いや~、それにしてもスゴイ!
可能ならば、すべての投票ボタンを押したくなりました。
ちょわさん、ありがとう~! (この本、おもしろいですよね)クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - ちょわ2017-03-30 15:31
>mono sashiさん
楽しい宿題でしたよ~!自分の手の届く範囲のものだけ読んでいたら出会えなかった本でした。ものすごい豪華で凝っていて、何よりとてもおもしろかったです(>_<)
>暗いところがまったくない。
本当にそうなんですよね。亡くなった夫の話だと湿っぽくなりそうなところ、それがなくて。
「食べたかったものを食べている」という時にその時の泰淳を思い出す、という、その感覚を描くところ、そこに目をつける視点というのも凄いと思います。そして、きっと武田夫妻はそういう日常の中のささやかな感覚を共有できるようなふたりだったんだろうなぁ、と思って、切なくなりました。
こんな素敵な本に出会えてよかったです!
mono sashiさんありがとうございました(^o^)/クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
- 出版社:文藝春秋
- ページ数:302
- ISBN:9784167902919
- 発売日:2015年02月06日
- 価格:605円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。