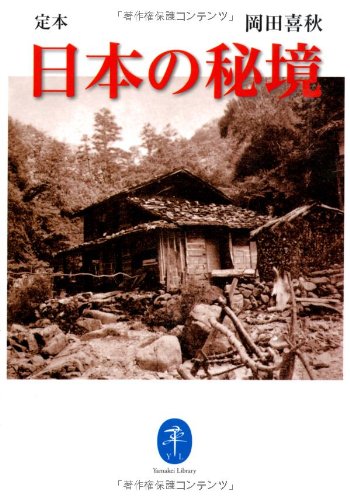レビュアー:
▼
失われた風景に身を置き、自然美を愛でつつ日本の激変を思う。
本書の紀行文は、すべて昭和30年代に書かれた。著者は当時、日本交通公社の雑誌『旅』の編集者であり、これらの文章は「旅は有名な景勝地に行くものだ」という日本人の旅行感覚を大きく変えたと解説に記されていた。誰も見たことがない景色を求めて歩く旅。手つかずの自然と秘湯を求めて歩く旅。人里離れた場所で生きる人間に会う旅。誰も足を運ばない場所を選んで、著者は旅に出る。
昭和30年代の初め、経済白書は結びの言葉に「もはや戦後ではない」と記した。日本は経済発展とともに変貌してゆき、暮らしも風景も変わっていった。しかし、この頃にはまだ多くの「秘境」が日本には残されていた。山、谷、湯、岬、海、湖、それぞれ3つずつの短編が収められている。
60年を経た今では、同じ土地へ行っても著者が感じた旅情を味わうことは叶わない。本書は貴重な記録であると共に、日本人が捨ててきた物事を強く意識させる。
その風土に生きる厳しさも伝わる。ダムを作れば観光客が来る、だから収入が増えると考えても、客足はすぐに途絶え周辺の村は電力の恩恵を受けることもない。目的も定かでない埋め立てにより、美しい海の眺めが消える。「文明到来の悲劇」と著者は言う。けれども、冬場にはバスも通らなくなる土地に生きる過酷さは想像を絶する。木曽の山奥にはダム補償金を投じて作られた通学列車が走り、僻地教育の向上に大きな役目を果たした。風土と住人を理解し、手を差し伸べるべきところを的確に把握した地方行政も存在していた。「便利さ」や「豊かさ」について、本書には様々な問いかけがある。
「アスパラガスを生む羊蹄山麓」(昭和30年)には、しみじみと時の流れを感じた。アスパラガスが新奇な野菜で、すべて輸出用だったとは。考えてみたら子どもの頃に食べていたのは缶詰の白いヤツばっかりで、緑色のアスパラガスは食べたことがなかった。「いくら日本が文化国家になろうと、アスパラガスが庶民の日常の食卓に登場することはまずあるまい。」とあるのに、ちょっと笑った。流麗な名文で歴史や文化に鋭い指摘を連発する著者も、日本人の味覚の急激な変化は予想を超えていたようだ。
「大自然を改造できるのは人間だが、人間はありのままの自然より美しいものを作り出すことはできない。」
この言葉は、著者の旅のテーマのようにも思える。自然の美に身を置く贅沢をゆっくりと味わった。
昭和30年代の初め、経済白書は結びの言葉に「もはや戦後ではない」と記した。日本は経済発展とともに変貌してゆき、暮らしも風景も変わっていった。しかし、この頃にはまだ多くの「秘境」が日本には残されていた。山、谷、湯、岬、海、湖、それぞれ3つずつの短編が収められている。
60年を経た今では、同じ土地へ行っても著者が感じた旅情を味わうことは叶わない。本書は貴重な記録であると共に、日本人が捨ててきた物事を強く意識させる。
その風土に生きる厳しさも伝わる。ダムを作れば観光客が来る、だから収入が増えると考えても、客足はすぐに途絶え周辺の村は電力の恩恵を受けることもない。目的も定かでない埋め立てにより、美しい海の眺めが消える。「文明到来の悲劇」と著者は言う。けれども、冬場にはバスも通らなくなる土地に生きる過酷さは想像を絶する。木曽の山奥にはダム補償金を投じて作られた通学列車が走り、僻地教育の向上に大きな役目を果たした。風土と住人を理解し、手を差し伸べるべきところを的確に把握した地方行政も存在していた。「便利さ」や「豊かさ」について、本書には様々な問いかけがある。
「アスパラガスを生む羊蹄山麓」(昭和30年)には、しみじみと時の流れを感じた。アスパラガスが新奇な野菜で、すべて輸出用だったとは。考えてみたら子どもの頃に食べていたのは缶詰の白いヤツばっかりで、緑色のアスパラガスは食べたことがなかった。「いくら日本が文化国家になろうと、アスパラガスが庶民の日常の食卓に登場することはまずあるまい。」とあるのに、ちょっと笑った。流麗な名文で歴史や文化に鋭い指摘を連発する著者も、日本人の味覚の急激な変化は予想を超えていたようだ。
「大自然を改造できるのは人間だが、人間はありのままの自然より美しいものを作り出すことはできない。」
この言葉は、著者の旅のテーマのようにも思える。自然の美に身を置く贅沢をゆっくりと味わった。
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「本が好き!」に参加してから、色々な本を紹介していただき読書の幅が広がりました。
- この書評の得票合計:
- 44票
| 読んで楽しい: | 17票 | |
|---|---|---|
| 素晴らしい洞察: | 2票 | |
| 参考になる: | 21票 | |
| 共感した: | 4票 |
|
あなたの感想は?
投票するには、ログインしてください。
この書評へのコメント
- Wings to fly2017-09-23 21:27
風竜胆さん
そうなんですか…。ちょっと驚いています。私は「ふるさと納税」にはあんまり賛成できないのですが、そうした状況を少しでも変える役に立つならば、意義のある制度なんじゃないかと思いました。なんだか時代が逆行しているような感慨を覚えますね。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - Wings to fly2017-09-23 21:31
ikuttiさん
これ、ただの紀行文じゃない感じですよねー。地理歴史と人間の文化への考察が素晴らしいと思います。ゆったり楽しんで下さい!書評、ゆっくりお待ちします^ ^クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - Wings to fly2017-09-24 06:40
ランピアンさん
あの白いの、私はマヨネーズつけて食べるの好きでした。いつ頃から緑のアスパラを普通に食べるようになったのかな。北海道のアスパラガス、お値段も高いけど味は格別ですよね。アスパラガスを作り始めた人々は元奥州伊達藩の末裔だそうで、開拓民の歴史物語としても面白かったです。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - Wings to fly2017-09-24 11:43
ランピアンさん
アスパラお好きなんですね(^^) 羊蹄山の麓の開拓地にいた人々が伊達藩の末裔なんですって。アスパラ作り始めたのは昭和20年代頃のようですが、土地に合う作物を考え、海外への販路確保のため、すぐに缶詰工場まで建てちゃった先見の明とバイタリティーに「開拓民魂」を感じましたよー!クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:山と渓谷社
- ページ数:384
- ISBN:9784635047661
- 発売日:2014年01月17日
- 価格:1026円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。
『定本 日本の秘境』のカテゴリ
- ・文学・小説 > ノンフィクション
- ・文学・小説 > エッセー・随筆
- ・歴史 > 日本史
- ・政治・経済・社会・ビジネス > 社会
- ・政治・経済・社会・ビジネス > 地域・都市