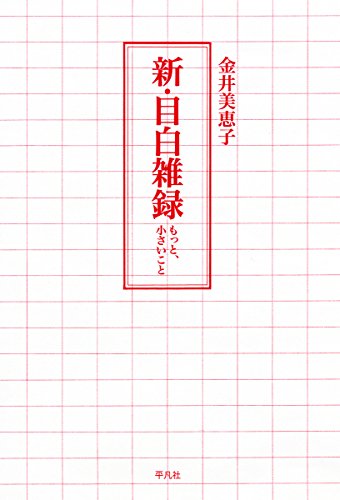三太郎さん
レビュアー:
▼
金井美恵子さんが2013年〜2015年に書いたエッセイ集を読みました。一昔前の事件を振り返りましょう。
金井美恵子のエッセイ「本を書く人読まぬ人とかくこの世はままならぬ part 1,2」は1993年までのエッセイが収められていたが、この本は2013年〜2015年に雑誌に連載されたもの。時事的な話題が多く取り上げられている。例えば2013年秋の渋谷に現れた通称DJポリスと「お巡りさん」と「警職法」の話題や、猪瀬元都知事の不正献金問題と「裸の王様」の意味が原作から変化してきたことや、自称・作曲家の佐村河内守の詐欺事件など。
ここでは僕がよく覚えている佐村河内守の事件について本書を元に振り返ってみようと思う。
事件はまずNHKの番組で、聴覚障害があるクラシックの作曲家の佐村河内守のドキュメンタリーが放送され、彼の作曲したとされる交響曲第一番「HIROSHIMA」が「現代のベートーベン」の曲として商業的に成功するかに見えたが、週刊文春などの大衆ジャーナリズムが佐村河内のうさん臭さを暴いた。
実は佐村河内は自分で作曲はできず、プロの作曲家に「指示書」を渡して作曲させていただけだった。佐村河内はプロモーションをしたので作曲家は別にいたということだった。(ゴーストライターがいたということが詐欺とは言えないかも知れないが、耳が聞こえない作曲家が作ったという嘘でプロモーションし商品の価値を上げようとしたのは詐欺かもしれないな。)
ところで佐村河内の嘘が暴かれた後でも彼の「作品」を評価する声があった。作家の高橋源一郎はこの交響曲を、マーラーのようでもショスタコビッチやペンデレツキのようでもあるといい、エモい音楽だったと評価したとか。
(実は僕も佐村河内の「作品」を一度は聴いたのだが、交響曲はもやもやとした雲のような音の間から微かに旋律が聞こえてくる所はブルックナーの交響曲の出だしみたいだと思ったし、全体の暗さはブラームスを連想させた。またバイオリンのための曲はバッハもどきだと思った。佐村河内の「作品」はいろんな時代の様式を幅広くミックスしたクラシック風の音楽だった。それなら本物のマーラーの曲を聴く方が良くはないか。)
(高橋がマーラーを連想したのは曲の中で鐘の音がしたからだったかも知れないし、20世紀の作曲家のペンデレツキを出してきたのは彼の作品に「広島の犠牲者に捧げる哀歌 」という名前の曲があったからかも。)
一方、プロモーターが作曲家に「指示書」を出して作曲させるシステムを積極的に評価する声もあったのだが。
(でも具体的にはどんな指示だったのでしょうね。もしも出だしはブルックナー風で、途中はブラームス風で、クライマックスはマーラー風で、といった指示なら変なキメラみたいな音楽ができてもしかたかなかったかも。一度聞けば十分でしょう。)
ここでは僕がよく覚えている佐村河内守の事件について本書を元に振り返ってみようと思う。
事件はまずNHKの番組で、聴覚障害があるクラシックの作曲家の佐村河内守のドキュメンタリーが放送され、彼の作曲したとされる交響曲第一番「HIROSHIMA」が「現代のベートーベン」の曲として商業的に成功するかに見えたが、週刊文春などの大衆ジャーナリズムが佐村河内のうさん臭さを暴いた。
実は佐村河内は自分で作曲はできず、プロの作曲家に「指示書」を渡して作曲させていただけだった。佐村河内はプロモーションをしたので作曲家は別にいたということだった。(ゴーストライターがいたということが詐欺とは言えないかも知れないが、耳が聞こえない作曲家が作ったという嘘でプロモーションし商品の価値を上げようとしたのは詐欺かもしれないな。)
ところで佐村河内の嘘が暴かれた後でも彼の「作品」を評価する声があった。作家の高橋源一郎はこの交響曲を、マーラーのようでもショスタコビッチやペンデレツキのようでもあるといい、エモい音楽だったと評価したとか。
(実は僕も佐村河内の「作品」を一度は聴いたのだが、交響曲はもやもやとした雲のような音の間から微かに旋律が聞こえてくる所はブルックナーの交響曲の出だしみたいだと思ったし、全体の暗さはブラームスを連想させた。またバイオリンのための曲はバッハもどきだと思った。佐村河内の「作品」はいろんな時代の様式を幅広くミックスしたクラシック風の音楽だった。それなら本物のマーラーの曲を聴く方が良くはないか。)
(高橋がマーラーを連想したのは曲の中で鐘の音がしたからだったかも知れないし、20世紀の作曲家のペンデレツキを出してきたのは彼の作品に「広島の犠牲者に捧げる哀歌 」という名前の曲があったからかも。)
一方、プロモーターが作曲家に「指示書」を出して作曲させるシステムを積極的に評価する声もあったのだが。
(でも具体的にはどんな指示だったのでしょうね。もしも出だしはブルックナー風で、途中はブラームス風で、クライマックスはマーラー風で、といった指示なら変なキメラみたいな音楽ができてもしかたかなかったかも。一度聞けば十分でしょう。)
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
1957年、仙台に生まれ、結婚後10年間世田谷に住み、その後20余年横浜に住み、現在は仙台在住。本を読んで、思ったことあれこれを書いていきます。
長年、化学メーカーの研究者でした。2019年から滋賀県で大学の教員になりましたが、2023年3月に退職し、10月からは故郷の仙台に戻りました。プロフィールの写真は還暦前に米国ピッツバーグの岡の上で撮ったものです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:平凡社
- ページ数:264
- ISBN:9784582837254
- 発売日:2016年04月18日
- 価格:2052円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。