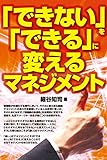ぴょんはまさん
レビュアー:
▼
実験的な小説。
読むに値するし、予想外に大変面白く読んだ。
夫(となるべき男性)の結婚観を知るリトマス試験紙としても推奨。
平成の世になっても、男性にとってはこのハードル、意外と高いかも。
新聞連載小説というのは今でもあるけれど、むしろ今ならNHKの朝の連続テレビ小説、いわゆる朝ドラを日々楽しみにしている感覚に近かったのではないか。
1クール半年の平成インスタント時代より、辛抱強くつきあってくれる読者は多かったかもしれない。
文章は、意外と古くない。
むしろ、読みやすい。
ショック、とか、貰い立てのほやほや、とか、論理にロジックとルビを振ったり、こんな昔から使われてたんだ、という語彙もあれば、江戸の名残を感じる今では使われない言葉も出てくる。
事実に戒飭(カイチョク)される、というキーワードが出てくるのだが、初めて見る漢字だった。
漱石独特の当て字なども含め、注がついているから読むに支障はない。(青空文庫等は未確認)
漱石と言えば、気難し気な年配のオッサン(いかにも文豪。野口英世の前の千円札)を想像するが、満50年生きずに病没しており、彼の小説は高齢者の作ではなく30代の終わりから40代の作品なのである。
主人公の津田由雄(30)はお延(23)と結婚して半年ほどになるが、医者から痔の手術を勧められている。(50近い漱石が書いているからか、現代の感覚で行くと40くらいの夫婦の感じがあり、昔の人って大人だったのねと驚く。)
勤めを休まなければならないし(有給休暇はない)、京都にいる実父からの毎月の仕送りを当てにしていたのが、打ち切られてしまい、金策が必要になる。
親代わりの叔父藤井(漱石本人に近い気がする)は、あまり余裕がない。
お延に、実家同然の叔父岡本から借りてきてもらうのか、夫が裕福な実妹のお秀に頼むのか。
お延は相思相愛で結ばれたと信じ、自分が愛すれば報いられると信じていたが、実は津田には隠し事がある。津田の上司で仲人役の吉川夫人も、津田の妹も、友人で貧乏なため朝鮮に渡ろうとしている小林(このキャラが刺激的)もそれを知っている。・・・
未完でも十分長い(ちくま文庫で633ページ)のだが、そこに書かれているのはわずか15日ほどの出来事に過ぎない。
医者に手術を勧められて5日後には入院、手術して翌週の同じ曜日には退院、翌日小林に会って、翌々日湯治に出かけて、次の日の途中で中断している。
短時間の心象風景を顕微鏡で子細に観察し分析レポートにしたような作品で、考えたことすべてを長台詞で表出してしまうか、そうでなくても自分と会話しつつああ思ったこう思ったと綴っていく。
漱石も女は書けない作家だと思いこんできたのは、まだ何もわかっていない若い頃に読んだせいだけではあるまい。長いうえに絶筆、すなわち未完ということで「明暗」を敬遠し、文豪の最終的な到達点まで読まずじまいだったからなのだと思えた。
他の全作品を読んだわけでもないから印象に過ぎないところをあえて言うと、漱石の若いころの作品には男性しか登場しない。美禰子だろうが藤尾だろうが、描かれている女性は結局のところ男性から見た客体としての女性でしかなかった。
思うに、今でも、多くの男性作家は生きた女性を描けない。
誰とは言わないが、世間で持て囃されている人気作家といえども、かなりお粗末なのが実態だ。(あくまでも私見)
その点、漱石は違う。
150年前に生まれ100年前に亡くなっているのに、21世紀になっても気づいていないそこいらの誰彼と違って、女性も一個の人間なのだとはっきり気づいていたようだ。
漱石の方が先を行っている。
大正初期というのは、21世紀よりも先進的な時代だったのか。
読んでみれば、聖女でも娼婦でもない普通の生身の女の感覚、内面描写へのこだわりは、時には、書いたの女子ですか?と感じるほどで、ある意味、鏡子夫人との合作なのではあるまいかと思えたほどだ。
煮え切らない自己省察が延々と続いたり、夫婦や兄妹の間でも普通なら思っても口に出さないだろうことを一々言葉にして渡り合ったりするのは、おそらく意図的な実験だ。
ほんの数日間の日常の出来事に何百頁も費やしていて、色恋や金銭や人間関係について本音全開の(すべて相手にぶつけるわけではなく自己分析も含む)個人がぶつかり合っている。
それゆえ、ちょっと勘弁してくれ、という感想を持たれる向きも多いのではないかと思う。
特に男性にとってはきついのではないかと思われるが、ひとつ、自分が明治から大正にかけての日本で、女性として生を受けていたら、という想像力を働かせて読んでみてほしい。
書かれた時代背景を考えるに、とてつもなく革新的な作品なのではあるまいか。
新しい女、お延。
そして古風に思えた清子もまた・・・
人間の生き方について、男女の関係について、我を通すことと役割に徹することの間に、自分を確立しようとする近代の日本人について、実に示唆に富む作品だ。
ジェンダー論に関心を持つ大学生の息子にも、勧めてやろうかと思う。
た、た、た、と畳みかける語尾のリズムも偶然ではない。
さすが文豪で、漢文学と英文学の深い教養を背景に、主観的な言語である日本語の限界に挑戦し格闘しているように思われる。
1クール半年の平成インスタント時代より、辛抱強くつきあってくれる読者は多かったかもしれない。
文章は、意外と古くない。
むしろ、読みやすい。
ショック、とか、貰い立てのほやほや、とか、論理にロジックとルビを振ったり、こんな昔から使われてたんだ、という語彙もあれば、江戸の名残を感じる今では使われない言葉も出てくる。
事実に戒飭(カイチョク)される、というキーワードが出てくるのだが、初めて見る漢字だった。
漱石独特の当て字なども含め、注がついているから読むに支障はない。(青空文庫等は未確認)
漱石と言えば、気難し気な年配のオッサン(いかにも文豪。野口英世の前の千円札)を想像するが、満50年生きずに病没しており、彼の小説は高齢者の作ではなく30代の終わりから40代の作品なのである。
主人公の津田由雄(30)はお延(23)と結婚して半年ほどになるが、医者から痔の手術を勧められている。(50近い漱石が書いているからか、現代の感覚で行くと40くらいの夫婦の感じがあり、昔の人って大人だったのねと驚く。)
勤めを休まなければならないし(有給休暇はない)、京都にいる実父からの毎月の仕送りを当てにしていたのが、打ち切られてしまい、金策が必要になる。
親代わりの叔父藤井(漱石本人に近い気がする)は、あまり余裕がない。
お延に、実家同然の叔父岡本から借りてきてもらうのか、夫が裕福な実妹のお秀に頼むのか。
お延は相思相愛で結ばれたと信じ、自分が愛すれば報いられると信じていたが、実は津田には隠し事がある。津田の上司で仲人役の吉川夫人も、津田の妹も、友人で貧乏なため朝鮮に渡ろうとしている小林(このキャラが刺激的)もそれを知っている。・・・
未完でも十分長い(ちくま文庫で633ページ)のだが、そこに書かれているのはわずか15日ほどの出来事に過ぎない。
医者に手術を勧められて5日後には入院、手術して翌週の同じ曜日には退院、翌日小林に会って、翌々日湯治に出かけて、次の日の途中で中断している。
短時間の心象風景を顕微鏡で子細に観察し分析レポートにしたような作品で、考えたことすべてを長台詞で表出してしまうか、そうでなくても自分と会話しつつああ思ったこう思ったと綴っていく。
漱石も女は書けない作家だと思いこんできたのは、まだ何もわかっていない若い頃に読んだせいだけではあるまい。長いうえに絶筆、すなわち未完ということで「明暗」を敬遠し、文豪の最終的な到達点まで読まずじまいだったからなのだと思えた。
他の全作品を読んだわけでもないから印象に過ぎないところをあえて言うと、漱石の若いころの作品には男性しか登場しない。美禰子だろうが藤尾だろうが、描かれている女性は結局のところ男性から見た客体としての女性でしかなかった。
思うに、今でも、多くの男性作家は生きた女性を描けない。
誰とは言わないが、世間で持て囃されている人気作家といえども、かなりお粗末なのが実態だ。(あくまでも私見)
その点、漱石は違う。
150年前に生まれ100年前に亡くなっているのに、21世紀になっても気づいていないそこいらの誰彼と違って、女性も一個の人間なのだとはっきり気づいていたようだ。
漱石の方が先を行っている。
大正初期というのは、21世紀よりも先進的な時代だったのか。
読んでみれば、聖女でも娼婦でもない普通の生身の女の感覚、内面描写へのこだわりは、時には、書いたの女子ですか?と感じるほどで、ある意味、鏡子夫人との合作なのではあるまいかと思えたほどだ。
煮え切らない自己省察が延々と続いたり、夫婦や兄妹の間でも普通なら思っても口に出さないだろうことを一々言葉にして渡り合ったりするのは、おそらく意図的な実験だ。
ほんの数日間の日常の出来事に何百頁も費やしていて、色恋や金銭や人間関係について本音全開の(すべて相手にぶつけるわけではなく自己分析も含む)個人がぶつかり合っている。
それゆえ、ちょっと勘弁してくれ、という感想を持たれる向きも多いのではないかと思う。
特に男性にとってはきついのではないかと思われるが、ひとつ、自分が明治から大正にかけての日本で、女性として生を受けていたら、という想像力を働かせて読んでみてほしい。
書かれた時代背景を考えるに、とてつもなく革新的な作品なのではあるまいか。
新しい女、お延。
そして古風に思えた清子もまた・・・
人間の生き方について、男女の関係について、我を通すことと役割に徹することの間に、自分を確立しようとする近代の日本人について、実に示唆に富む作品だ。
ジェンダー論に関心を持つ大学生の息子にも、勧めてやろうかと思う。
た、た、た、と畳みかける語尾のリズムも偶然ではない。
さすが文豪で、漢文学と英文学の深い教養を背景に、主観的な言語である日本語の限界に挑戦し格闘しているように思われる。
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
小学校時代は図書室に入り浸って子供向け全集を読破したり、本の続きが気になってランドセルを背負ったまま読みながら歩く子どもでした。小遣いでポプラ社のルパンを全巻揃えていたので、本屋の店頭で280円が380円になっていたときは大ショックでした。
中高時代は親に貰った昼食代で文庫を買ってしまい、昼食を摂らずに読んでいたことも・・・当時の愛読書はG・K・チェスタトンと「銀の匙」。
大学進学後は生身の人間の方が面白くなり読書量は減りましたが、30すぎてからまたぼちぼち読むようになりました。
出産を機に哲学の古典をソクラテス以前から読んでみたり(途中であえなく挫折)、シェイクスピア全集を読破したりしました(もちろん日本語)。
長距離電車に乗るのに本を持っていないと耐えられない体質でしたが、最近は年をとったのか、パズルでも大丈夫になってしまいました。
息子たちも本を語れる年になってきました。
息子らはアクションが好きなのですが、私は結局のところ、北村薫やら宮部みゆきの方が落ち着きます。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:筑摩書房
- ページ数:633
- ISBN:9784480426161
- 発売日:2009年06月10日
- 価格:972円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。