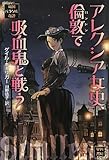著者は昆虫微生物の研究者。「細胞内共生微生物による昆虫宿主の生殖操作」が主な研究内容である。
・・・え? 漢字ばかりで意味不明・・・?
要するに、病気に罹って、いつの間にか男が女化してしまうという話だ。SFみたいだが、実際、そういう例があるのだ。
人ではなく昆虫だけど。
現役研究者らしく、科学的説明からきっちりされるが、わかりやすくかみ砕かれていて読みやすい。基礎を押さえた上で、興味深い事例があれこれ紹介される。
性決定を入口として、生物間のめくるめくせめぎ合いが描き出される。
ヒトの場合は、性は性染色体で決定される。染色体は通常、2本で一対となっているが、性染色体はXとYの二種類があり、XXだと女性、XYだと男性になるというのは、生物の授業で聞いたことがある人もいるだろう。
この性決定システムは意外と多様で、オスの方が2本同じもので、メスの方が1本ずつ違うものを持つ生物もいる(この場合、慣例としてメスをZW、オスをZZと書く)。
そればかりか、ミツバチのように、オスだと性染色体ばかりか他の染色体(常染色体)も1本ずつしか持たず、メスは2本ずつ(一対)持つ例もある。ショウジョウバエのように、性染色体と常染色体の比が大切というものもいる。
少なくとも昆虫の場合は、性決定に直接関与する遺伝子は共通しているようだが、その遺伝子の調節メンバーも方法もまちまちであるようだ。
さて、ところで、性別、オス・メスってなんだろうか?
有性生殖の場合、卵子と精子が結びつくことで次世代の子が生まれる。卵子は通常、大きく、精子は通常、小さくて、ほぼ遺伝情報しか含まない。つまり卵子(大きな配偶子)を持つものがメス、精子(小さな配偶子)を持つものがオスである。
どうしてこうなったかに関してはいくつか仮説がある。大きく栄養も載せて生き残らせようとする戦略と、小さくともとにかく数を作れとする戦略に二分化されたとする説。一方が小さくなることで微生物感染の機会を減らしたとする説。ミトコンドリアなどの細胞内小器官が混ざるのを防ごうとしているとする説。どれもありうる話で、どれも部分的に理由となっているのかもしれない。
さて、微生物と性決定である。
昆虫の世界では、細菌感染によって性が変わる例がいくつか見られている。
タイトルにもある「消えるオス」。この例としてよく知られるのがボルバキアと呼ばれる細菌である。テントウムシやガなどに感染し、オスを胚や若齢幼虫期に殺すことが知られる。資源分配上のメリットがある等の説があるが、ボルバキアが母→子への垂直感染を起こすことから、ぱっと見ると要するに「役立たずが殺されている」印象を受ける。感染しているオスと感染していないメスの子が生まれない仕組みもある。ボルバキアから見ると自身を残すのに都合のよい個体だけを残していることになる。このあたりも興味深いところだ。
ボルバキアを含む感染細菌は宿主にとって悪いことをしているばかりではない。
長い間、宿主に住み続けることで、宿主を助けたり、あるいは宿主にとってなくてはならない存在になっているものもいる。
アブラムシの共生微生物であるブフネラはアブラムシの成長に大きな役割を果たす。ブフネラを駆除するとアブラムシは子孫を残せなくなるし、アブラムシの外ではブフネラは生きられない。
ミミイカと呼ばれるイカは発光によって敵から身を守るが、この光は共生する発光細菌が作り出すものである。
こうした共生の究極の形が、細胞内共生を果たした葉緑体やミトコンドリアなどの細胞内小器官と言えるかもしれない。これらはDNA解析により、元々は細菌だったと見なされている。光合成によってエネルギーを産生する葉緑体。細胞内で使うエネルギーを供給するミトコンドリア。もはやなくてはならない存在である。
とはいえ、共生・寄生、万々歳かといえば、もちろんそんなことはない。
ハリガネムシやトキソプラズマの例を出すまでもなく、宿主を操り、破滅に追い込むものもいる。
生物同士は、せめぎ合い、争い、時に勝ち、時に敗れて、何とか生き残りを図っていく。
著者は、「赤の女王」仮説に触れる。ルイス・キャロルの「鏡の国のアリス」に登場するチェスの女王様だ。彼女はアリスに「その場に留まるためには、全力で走り続けなければならない」という。
生物たちもまさにその通り。止まったら他のものたちに飲み込まれてしまう。日々、しのぎを削って、その場に留まり続けているのだ。
機構を知ることで、病気の治療や予防(本書の事例に近いものとしては、ボルバキアによる蚊の制御)に宛てるという実際的な活用は、もちろんある。
だが、自然を知るということはそれだけに留まらない。不思議さに打たれ、複雑さにうなる。
丁々発止を繰り返している生き物の戦略は、ときに、鬼気迫るものすらある。
その中で、私たちはヒトとしてどのように生きていくのだろう?
少し、立ち止まって考える気にもさせられる。
<関連>
・ボルバキアの利用可能性?
『日経サイエンス2015年09号』
『顧みられない熱帯病: グローバルヘルスへの挑戦』
・アブラムシとブフネラ
『アブラムシの生物学』
・もしかしたらヒトもトキソプラズマに操られる!?
『日経サイエンス2015年07号』
・ヒトとマイクロバイオーム
『失われてゆく、我々の内なる細菌』





分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント
- ぽんきち2015-09-17 11:21
*ご存じない方のために。
ハリガネムシは文字通り、針金のような形で、類線形動物と分類される動物の仲間です。カマキリやカマドウマに寄生します。何が有名かというと、このハリガネムシは水生動物なのですが、カマキリなどに寄生して、腹部で増え、ぱんぱんにします。そして本来ならば水辺には寄らないはずの宿主を川などに飛び込ませるんですね。自分はまんまと脱出して川でまた交配相手を探すというわけです。
カマドウマとハリガネムシの研究者を紹介するナショジオの記事を付けておきます。ある意味、閲覧注意です(^^;)。もっと直接的な映像をお望みの場合は「ハリガネムシ カマキリ」で検索すると動画などがでてきます(^^;)b
http://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/20141030/422341/?P=1クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - ぽんきち2015-09-18 08:01
efさん
うしゃしゃw。
・・や、好きなわけではないです(^^;A)。あまり抵抗がないだけ(同じか(^^;))。
カマドウマはこの場合、むしろ被害者なのですが、そもそもカマドウマが気持ち悪いっていう人は多いみたいですね(^^;)。
*私、何となく、ずっとカマ・ドウマだと思ってたんですけど、カマド・ウマ(竈馬)なんですねー。
私も自然にいるハリガネムシは見たことないです。
平地より山間地の方が寄生率が高いようです。
ナショジオの記事にもありましたが、ハリガネムシ→カマドウマ(やカマキリ?)→ヤマメなどの渓流魚という連鎖もあるようですし、渓流の近くとかってことですかね。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
- 出版社:化学同人
- ページ数:208
- ISBN:9784759816662
- 発売日:2015年07月03日
- 価格:1728円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。