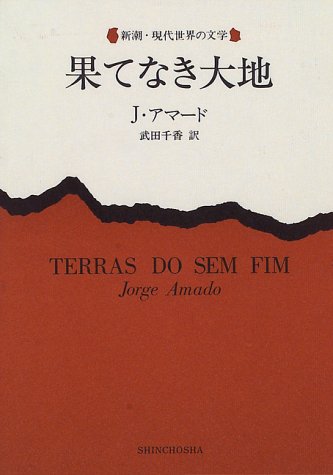hackerさん
レビュアー:
▼
「世界一のカカオの大地、それは血で肥えた大地だったのだ」(本書の最後の一行)
ジョルジェ・アマード(1912-2001)は20世紀ブラジルを代表する作家の一人と言われています。青年時代から共産党員だったそうですが、スターリン批判が行われる前に、中国等の社会主義国訪問をきっかけとして「自主転向」したと Wikipedia には書かれています。ただ、その後も左派として執筆活動を続けたそうです。
1943年刊の本書は、リオデジャネイロの北に位置するバイーア州とその港町イリェウスを舞台に、20世紀初頭に実際に行われていた、カカオを栽培する土地をめぐる、大地主間の血で血を洗う争いを描いたものです。訳者あとがきでは、本書で語られる様々な事件について、実際にイリェウスで生まれ育った作者は、次のように書いています。
「語られる多くの事件がアマードの経験したものである。父親は土地をめぐって二度、女性を巡って一度銃で撃たれ負傷している。そのうちの一度は、テラスでろばにやるための砂糖黍を削っているところを(中略)殺し屋(ジャグンソ)によって狙われたもので、父親は40発もの散弾を浴びながらジョルジュを抱えて家の中に逃げ込むのがやっとだったという」
まず、この時期、ブラジルではカカオ長者が珍しくなかったようです。最初にバイーア州の未開の地に入りこんでカカオ栽培に成功した者は大地主となったのですが、自分の土地と富を増やすために、さらに貪欲となり、自分に土地を売らない者は、配下の殺し屋を使って平気で始末する様になります。その殺し屋たちも、元はと言えば、普通の農民でカカオ栽培で一儲けすることを夢見てバイーア州にやってきた貧民だったのです。しかし働き出してみると、薄給で毎日暗いうちから日没まで働かせられ、残る金もないという生活を強いられ、故郷に錦を飾るなど夢者物語だということが分かってきます。このままでは、かろうじて生きていける環境下で、死ぬまで働くしかないと思い出した者の中から、「根性のある」者を拾い上げて、大地主が殺し屋として使うという構図が、大カカオ農園を動かしていたようです。そして、金をかせぐには、大地主に命じられるがままに殺傷を行うしかないということも、殺し屋たちは分かっていました。そして、作者の父親もまた、紆余曲折はあったものの、バイーア州で大地主として成功した一人でした。実際に、殺人を命じられる立場だったのかは分かりませんが、周囲にこういう人物や殺傷事件が珍しくない環境下で、作者は育ったのは間違いなさそうです。この地の荒っぽさと無法ぶりは、作中でも次のように語られています。
「(イリェウスには)武器の携帯を禁止する条例もあった。しかし、その存在を知る者はごく僅かで、たとえそれを知る僅かな者であっても、守ろうなどとは思いもしなかった。町を往来する男たちは、長靴か厚手の革のブーツを履き、カーキ色のズボンにリネンの上着を身につけて、その下に必ず拳銃を潜ませているのが普通だった。町の中を、連発銃を肩からかけた男が通っても、住民は全く気にかけることはなかった。イリェウスは豪邸が建ち、道路も舗装され、石炭を塗った石の家も建つなどしっかりと根をはやした設備もある一方で、いまだに野営地としての雰囲気も残していた」
まるで西部劇のような本書は、一種の群集劇で、様々な人物が登場します。争う二人の地主には、それぞれが別の政党の後ろ楯があり、その政党を支持する新聞が味方についているという構図は、「あらゆる戦争は経済的理由によるものである」というマルクスの言葉を思い起こさせます。ただ、いささか登場人物が多すぎて、やや類型的であるのは、ちょっと気になるところです。
その中で印象的なのは、一人の人間を仕留めるのに一発の弾丸しか使ったことのない腕を誇るダミアンという男が、雇い主の大地主が別の人物に「お前は人を殺すことがいいとおもっているのか?何も感じないのか?心が痛まないのか?」と言うのを聞いてからおかしくなってしまう姿です。ダミアンは、片手を使ってでしか数えることができず、何人殺したのかもう覚えていないのですが、無学な貧農が善悪の区別もなく、金のために殺し屋となる姿を象徴している人物です。あと、美人三姉妹が外見の衰えと共に夫に逃げられたり、夫と死別したりして、同じ売春宿で生活するようになる姿も印象的です。
作者は共産主義から「自主転向」するまでは、リアリズムを重視するプロレタリア作家として知られていたそうですが、本書に関しては、私がイメージするプロレタリア文学というよりは、むしろリアルな冒険小説です。ただ、前述したように、社会の中で訳も分からないまま搾取されて人生を送る人々の描写には、左翼作家としての立場が感じられます。本書の最後の一行には、そういう立場がよく表れています。
「世界一のカカオの大地、それは血で肥えた大地だったのだ」
別の見方をすると、20世紀のブラジルは、自然を破壊することによって富を蓄えていったことを、教えてくれる本でした。
1943年刊の本書は、リオデジャネイロの北に位置するバイーア州とその港町イリェウスを舞台に、20世紀初頭に実際に行われていた、カカオを栽培する土地をめぐる、大地主間の血で血を洗う争いを描いたものです。訳者あとがきでは、本書で語られる様々な事件について、実際にイリェウスで生まれ育った作者は、次のように書いています。
「語られる多くの事件がアマードの経験したものである。父親は土地をめぐって二度、女性を巡って一度銃で撃たれ負傷している。そのうちの一度は、テラスでろばにやるための砂糖黍を削っているところを(中略)殺し屋(ジャグンソ)によって狙われたもので、父親は40発もの散弾を浴びながらジョルジュを抱えて家の中に逃げ込むのがやっとだったという」
まず、この時期、ブラジルではカカオ長者が珍しくなかったようです。最初にバイーア州の未開の地に入りこんでカカオ栽培に成功した者は大地主となったのですが、自分の土地と富を増やすために、さらに貪欲となり、自分に土地を売らない者は、配下の殺し屋を使って平気で始末する様になります。その殺し屋たちも、元はと言えば、普通の農民でカカオ栽培で一儲けすることを夢見てバイーア州にやってきた貧民だったのです。しかし働き出してみると、薄給で毎日暗いうちから日没まで働かせられ、残る金もないという生活を強いられ、故郷に錦を飾るなど夢者物語だということが分かってきます。このままでは、かろうじて生きていける環境下で、死ぬまで働くしかないと思い出した者の中から、「根性のある」者を拾い上げて、大地主が殺し屋として使うという構図が、大カカオ農園を動かしていたようです。そして、金をかせぐには、大地主に命じられるがままに殺傷を行うしかないということも、殺し屋たちは分かっていました。そして、作者の父親もまた、紆余曲折はあったものの、バイーア州で大地主として成功した一人でした。実際に、殺人を命じられる立場だったのかは分かりませんが、周囲にこういう人物や殺傷事件が珍しくない環境下で、作者は育ったのは間違いなさそうです。この地の荒っぽさと無法ぶりは、作中でも次のように語られています。
「(イリェウスには)武器の携帯を禁止する条例もあった。しかし、その存在を知る者はごく僅かで、たとえそれを知る僅かな者であっても、守ろうなどとは思いもしなかった。町を往来する男たちは、長靴か厚手の革のブーツを履き、カーキ色のズボンにリネンの上着を身につけて、その下に必ず拳銃を潜ませているのが普通だった。町の中を、連発銃を肩からかけた男が通っても、住民は全く気にかけることはなかった。イリェウスは豪邸が建ち、道路も舗装され、石炭を塗った石の家も建つなどしっかりと根をはやした設備もある一方で、いまだに野営地としての雰囲気も残していた」
まるで西部劇のような本書は、一種の群集劇で、様々な人物が登場します。争う二人の地主には、それぞれが別の政党の後ろ楯があり、その政党を支持する新聞が味方についているという構図は、「あらゆる戦争は経済的理由によるものである」というマルクスの言葉を思い起こさせます。ただ、いささか登場人物が多すぎて、やや類型的であるのは、ちょっと気になるところです。
その中で印象的なのは、一人の人間を仕留めるのに一発の弾丸しか使ったことのない腕を誇るダミアンという男が、雇い主の大地主が別の人物に「お前は人を殺すことがいいとおもっているのか?何も感じないのか?心が痛まないのか?」と言うのを聞いてからおかしくなってしまう姿です。ダミアンは、片手を使ってでしか数えることができず、何人殺したのかもう覚えていないのですが、無学な貧農が善悪の区別もなく、金のために殺し屋となる姿を象徴している人物です。あと、美人三姉妹が外見の衰えと共に夫に逃げられたり、夫と死別したりして、同じ売春宿で生活するようになる姿も印象的です。
作者は共産主義から「自主転向」するまでは、リアリズムを重視するプロレタリア作家として知られていたそうですが、本書に関しては、私がイメージするプロレタリア文学というよりは、むしろリアルな冒険小説です。ただ、前述したように、社会の中で訳も分からないまま搾取されて人生を送る人々の描写には、左翼作家としての立場が感じられます。本書の最後の一行には、そういう立場がよく表れています。
「世界一のカカオの大地、それは血で肥えた大地だったのだ」
別の見方をすると、20世紀のブラジルは、自然を破壊することによって富を蓄えていったことを、教えてくれる本でした。
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:新潮社
- ページ数:339
- ISBN:9784105165024
- 発売日:1996年10月01日
- 価格:2097円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。