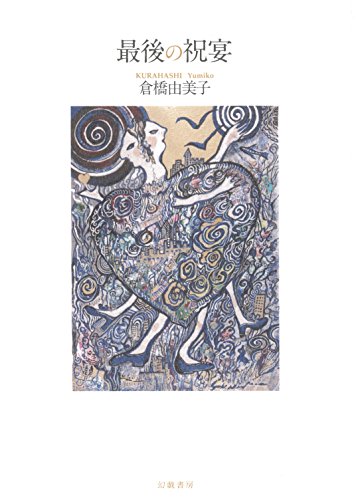かもめ通信さん
レビュアー:
▼
事前に想像していたのとはちょっと違った面白さ。
実を言うと私は倉橋ファンというわけではない。
というより、好き嫌いを判断できるほど、著者の作品を読んだことがないといった方がいいかもしれない。
これまで読んだことがあるのは、小説が2冊に翻訳絵本が2冊のみ。
にもかかわらず、このかなりボリュームのある“没後10年未収録エッセイ集”を手にしたわけは、日頃から(この人の日本語は読んでいて気持ちがいいなあ)とおもっている翻訳家の古屋美登里さんが編者をしていたからだった。
そういえば、倉橋由美子さんの書かれたものも、文字や言葉の選び方など相当なこだわりがあるように思われたから、その辺にもなにかつながりがあるのかもしれないなどと思ったのだった。
60年代からの“単行本未収録”作品を集成したというこの本には、自らの著作についての「作品ノート」や、他の作家の著作に寄せたコメントなどがつまっていて、私のような初心者には、倉橋作品をもっと読み込んでいたならば、もっと味わい深かったかもしれないと思わせられる一方で、作家がそんな風に考えて書いた作品とはどんなものなのだろうか?という興味をもたせるものにもなっている。
それにしても、この人の書くものは本当に不思議だ。
きっとものすごく頭のいい人だったのだろうと思うのだが、強く共感するわけでも感銘を受けるわけでもなく、書かれているあれこれを理解するのが難しいことさえ多いのに、なぜだか魅せられてしまうなにかがあるのだ。
わからないなりにも惹かれつつ読み進めながら、川端康成論には思わず笑ってしまい、安部公房びいきなのにもなんとなく納得してしまったりする。
なんといってもとりわけ興味深かったのは、「外国文学模倣論争」に発展したという江藤淳の“批評”に対する一連の反論だ。
この「論争」の発端となった江藤淳の書いたものはもちろん、やり玉に挙げられた倉橋の『暗い旅』も元ネタとされたビュトールの『心変わり』さえも読んだことがないのだが、倉橋が展開したこの一連の「反論」は、一つ一つの文章だけで、それぞれ充実した文学論になっていて、小説とは何か、どうあるべきで、どう味わうべきものなのか、あるいは作家とは、批評家とは、文壇とは……と、いろんなことを考えさせられ、ここだけでもこの分厚い本を手にしたかいがあったと思えるものだった。
ちなみに江藤淳がどのような“批評”をしたのかについては、編者である古屋さんのこれまたかなり充実した解説の中に長文を引用する形で紹介されているので、気になる方は本文と一緒に読み比べてみるのもいいかもしれない。
それにしても、なかなかのボリュームのこの本を閉じたとき、読み切った充実感よりも、あれやこれやの倉橋作品を読んでいないことへの焦りの方が大きかったことには困惑させられた。
いつの日か、そう遠くない時期に倉橋祭りが開催される予感がする……。
<これまでの倉橋由美子作品レビュー>
● 幻想絵画館
● 大人のための残酷童話
というより、好き嫌いを判断できるほど、著者の作品を読んだことがないといった方がいいかもしれない。
これまで読んだことがあるのは、小説が2冊に翻訳絵本が2冊のみ。
にもかかわらず、このかなりボリュームのある“没後10年未収録エッセイ集”を手にしたわけは、日頃から(この人の日本語は読んでいて気持ちがいいなあ)とおもっている翻訳家の古屋美登里さんが編者をしていたからだった。
そういえば、倉橋由美子さんの書かれたものも、文字や言葉の選び方など相当なこだわりがあるように思われたから、その辺にもなにかつながりがあるのかもしれないなどと思ったのだった。
60年代からの“単行本未収録”作品を集成したというこの本には、自らの著作についての「作品ノート」や、他の作家の著作に寄せたコメントなどがつまっていて、私のような初心者には、倉橋作品をもっと読み込んでいたならば、もっと味わい深かったかもしれないと思わせられる一方で、作家がそんな風に考えて書いた作品とはどんなものなのだろうか?という興味をもたせるものにもなっている。
それにしても、この人の書くものは本当に不思議だ。
きっとものすごく頭のいい人だったのだろうと思うのだが、強く共感するわけでも感銘を受けるわけでもなく、書かれているあれこれを理解するのが難しいことさえ多いのに、なぜだか魅せられてしまうなにかがあるのだ。
わからないなりにも惹かれつつ読み進めながら、川端康成論には思わず笑ってしまい、安部公房びいきなのにもなんとなく納得してしまったりする。
なんといってもとりわけ興味深かったのは、「外国文学模倣論争」に発展したという江藤淳の“批評”に対する一連の反論だ。
この「論争」の発端となった江藤淳の書いたものはもちろん、やり玉に挙げられた倉橋の『暗い旅』も元ネタとされたビュトールの『心変わり』さえも読んだことがないのだが、倉橋が展開したこの一連の「反論」は、一つ一つの文章だけで、それぞれ充実した文学論になっていて、小説とは何か、どうあるべきで、どう味わうべきものなのか、あるいは作家とは、批評家とは、文壇とは……と、いろんなことを考えさせられ、ここだけでもこの分厚い本を手にしたかいがあったと思えるものだった。
ちなみに江藤淳がどのような“批評”をしたのかについては、編者である古屋さんのこれまたかなり充実した解説の中に長文を引用する形で紹介されているので、気になる方は本文と一緒に読み比べてみるのもいいかもしれない。
それにしても、なかなかのボリュームのこの本を閉じたとき、読み切った充実感よりも、あれやこれやの倉橋作品を読んでいないことへの焦りの方が大きかったことには困惑させられた。
いつの日か、そう遠くない時期に倉橋祭りが開催される予感がする……。
<これまでの倉橋由美子作品レビュー>
● 幻想絵画館
● 大人のための残酷童話
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
本も食べ物も後味の悪くないものが好きです。気に入ると何度でも同じ本を読みますが、読まず嫌いも多いかも。2020.10.1からサイト献本書評以外は原則★なし(超絶お気に入り本のみ5つ★を表示)で投稿しています。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:幻戯書房
- ページ数:347
- ISBN:9784864880725
- 発売日:2015年05月26日
- 価格:4104円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。