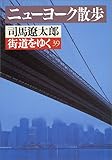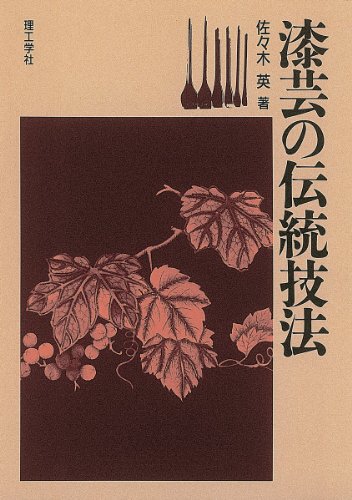ぽんきちさん
レビュアー:
▼
伝統と経験に裏付けられた漆芸技術
日本伝統工芸展(HP)というのがありまして、陶芸や染色といった日本の伝統工芸を保護・育成する目的で、毎年、全国から集まった諸部門の作品の審査が行われ、入選作の展示が各地で行われています。今年は61回目。
NHKの日曜美術館(風と土と技と 第61回 日本伝統工芸展)でも毎年、紹介されているので、ご存じの方もいらっしゃるかもしれません。
数年前、ごく淡い関係の知人の方が入選されたのをきっかけに、見に行くようになりまして、今年も見に行ってきました。
部門は全部で7つ。陶芸、染色、漆芸、金工、木竹工、人形、諸工芸です。
今年は、漆芸が一番印象に残りました。漆ってつやがあって美しいですねぇ。
これって実際、どんな風にして作られているものなのかと探してみたのがこちらの本です。1986年刊、少し古い本です。著者は漆芸作家として活躍された方ですが、発刊時、すでに亡くなっています。
漆の採取法から、漆芸の歴史、素地や塗りの技法あれこれ、漆以外のものを用いた加飾、変わり塗りや、生活の中で生きてきた日本各地の漆芸の紹介など、漆芸についての百科事典のような作りになっています。
自分は素人なので、これを読んだだけで漆芸に手が出せるとは思えませんが、多分、実際にされていて、基本を知っているという人には参考書的にも使える本なのではないかと思います。
塗りと加飾の技法にさかれているページ数が多く、細かいコツや、材料の詳細まで記されています。
木の素地の研ぎに使うのは木賊(とくさ)が一番とか、一度調製した漆は長期間は取っておけないとか、埃を除け適度な湿度や温度を保つため、加工中には「風呂」と呼ばれる小部屋に保存するなど、経験と伝統に裏打ちされた知恵がいろいろです。
下地をきれいに整え、下塗りをし、漆を塗り、乾かし、表面を研ぎ、また塗り、と工程が幾重にも分かれているのも印象的です。手間も時間も掛かり、その上、各工程にはかなりの注意や技量を要するようです。
漆作品、下世話な話ですが、価格もお高い・・・(^^;)。しかし、これだけ手間が掛かるならまぁ高価なのも仕方ないのだろうなという印象です。
NHKの日曜美術館(風と土と技と 第61回 日本伝統工芸展)でも毎年、紹介されているので、ご存じの方もいらっしゃるかもしれません。
数年前、ごく淡い関係の知人の方が入選されたのをきっかけに、見に行くようになりまして、今年も見に行ってきました。
部門は全部で7つ。陶芸、染色、漆芸、金工、木竹工、人形、諸工芸です。
今年は、漆芸が一番印象に残りました。漆ってつやがあって美しいですねぇ。
これって実際、どんな風にして作られているものなのかと探してみたのがこちらの本です。1986年刊、少し古い本です。著者は漆芸作家として活躍された方ですが、発刊時、すでに亡くなっています。
漆の採取法から、漆芸の歴史、素地や塗りの技法あれこれ、漆以外のものを用いた加飾、変わり塗りや、生活の中で生きてきた日本各地の漆芸の紹介など、漆芸についての百科事典のような作りになっています。
自分は素人なので、これを読んだだけで漆芸に手が出せるとは思えませんが、多分、実際にされていて、基本を知っているという人には参考書的にも使える本なのではないかと思います。
塗りと加飾の技法にさかれているページ数が多く、細かいコツや、材料の詳細まで記されています。
木の素地の研ぎに使うのは木賊(とくさ)が一番とか、一度調製した漆は長期間は取っておけないとか、埃を除け適度な湿度や温度を保つため、加工中には「風呂」と呼ばれる小部屋に保存するなど、経験と伝統に裏打ちされた知恵がいろいろです。
下地をきれいに整え、下塗りをし、漆を塗り、乾かし、表面を研ぎ、また塗り、と工程が幾重にも分かれているのも印象的です。手間も時間も掛かり、その上、各工程にはかなりの注意や技量を要するようです。
漆作品、下世話な話ですが、価格もお高い・・・(^^;)。しかし、これだけ手間が掛かるならまぁ高価なのも仕方ないのだろうなという印象です。
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)、ひよこ(ニワトリ化しつつある)4匹を飼っています。
*能はまったくの素人なのですが、「対訳でたのしむ」シリーズ(檜書店)で主な演目について学習してきました。既刊分は終了したので、続巻が出たらまた読もうと思います。それとは別に、もう少し能関連の本も読んでみたいと思っています。
この書評へのコメント
- ぽんきち2014-11-13 21:37
本日、11月13日は「うるしの日」なんだそうでございます。
http://www.nnh.to/11/13.html
http://www.digistyle-kyoto.com/event/nenjugyoji/post_10.htmlクリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - ぽんきち2014-11-25 09:09
漆芸の1つ、存星(存清)をテーマにした展覧会が開催中の模様。
五島美術館・存星-漆芸の彩り
http://www.gotoh-museum.or.jp/exhibition/open.html
存清の技法はこちら↓(香川県漆芸研究所)
http://www.pref.kagawa.lg.jp/USERS/s12730/situgei/technique/zonsei/index.html
基本は唐物で、宋・元時代に作製された伝来物です。
日本の存清は、江戸末期、讃岐の玉楮象谷が尽力して確立されたようです。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:理工学社
- ページ数:240
- ISBN:9784844585329
- 発売日:1986年12月01日
- 価格:3240円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。