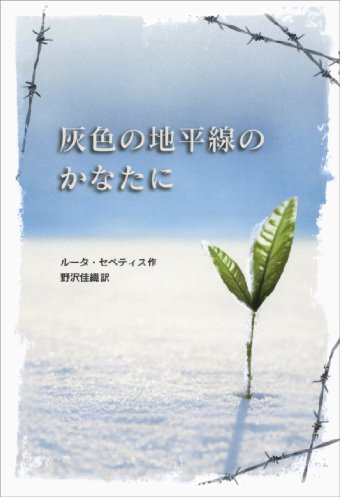ゆうちゃんさん
レビュアー:
▼
リトアニアのカウナスに住む語り手で15歳の少女リナとその両親、弟の運命。彼ら一家は「名簿」に載り、アルタイの草原、そして北極海に臨む荒地で強制労働をさせられる。彼らに希望はあるのか?
本書は、同著者の作品である「モノクロの街の夜明けに」の紹介をしてくださったぱせりさんがコメント欄で紹介してくれた本です。良い本のご紹介ありがとうございました。
冒頭はリトアニアの町カウナス(訳者によれば杉原千畝が住んでいた場所としても知られている)。スターリンが第二次世界大戦のどさくさ紛れにリトアニアを含むバルト三国を占領して1年ほど経った頃だった。1941年6月14日、主人公で語り手、15歳の画家志望の娘リナ・ヴィルカスの家にNKVD(ソ連の秘密警察、後のKGB)が踏み込んできた。大学学部長の父は不在で、ママのエレーナ、弟のヨーナスと共にトラックに詰め込まれる。両親はこのことを予期していたようでママはコートに貴重品や書類を縫い込んでいた。彼らは町の知り合いも乗せられたトラックでカウナス郊外の駅に連れ込まれ、貨車に押し込まれた。同じ車両に乗った勇気のある少年アンドリュスと弟のヨーナスとで貨車を一時的に脱出し、増結された貨車にパパがいるのを見つけた。貨車は出発し6週間も乗せられたままだった。パパも居る青年・壮年の男性を乗せた貨車は途中で切り離された。貨車はアルタイの草原で止まった。主人公らの班はトゥラシャク村の側のテンサイ畑の側の収容所に入れられ強制労働をさせられる。そこでは主人公リナとアンドリュスの不器用な恋もあった。ここで10カ月働かされた後、ここに収容されていたリトアニア人は残る者と移動する者の二手に分けられ、ヴィルカス家の母と子供たちはトラック、貨車、そして船でヤクーツクを経てレナ川の北極海の臨む河口、トロフィモフスクで降ろされた。途中でエストニア人、フィンランド人、ウクライナ人なども合流させられた。監視するNKVDの兵士たちはレンガ造りの宿舎で過ごすが、ここに追放された人たちは、9月、拾った部材で掘っ立て小屋同然の家を建てさせられ、そこに住めという。間もなく、極夜がやって来る。食料は作業の代償としてのパンだけ。吹雪になれば外に出られないし、昼間も闇という過酷な世界に閉じ込められる。赤痢やチフスが流行り、次々と人は死んでいく。
読んでいてあまりに苦しい話である。主人公の少女は直情径行、思慮も浅く想像力もなく、3部構成の2部まではあまり共感できなかったし、リナのママ(エレーナ)が、またあまりに完璧な人間過ぎると思うのだが、最も過酷な第3部まで来るとそんなことは問題なくなる。監視兵の中にも同情的なクレツキーという人物もいれば、追放者の中にも嫌味しか言わないスターラスなどの存在もある。それらのキャラクターが、実は第3部でママの存在を浮き彫りにする効果がある。
苦しいだけの描写では読者に飽きられてしまうのだろう。この話には至る所に謎が散りばめられている。アンドリュスとその母はアルタイの収容所で、監視兵の好意に与るのだが、なぜ好意を受け、また、スターリンに反発していたアンドリュスはそれをどう思っているのか?この話では「名簿」に載ると追放されるということになっているのだが、ヴィルカス家が何故「名簿」に載ったのか?密告したのは誰なのか?密告者は最後まで明かされないが読者はきっとこの人だろうとわかるように書かれている。一家が追放された理由は、時折リナが回想する、カウナスでの生活や、ひと夏をいとこのヨアーナと過ごしたコテージの場面の回想も交え効果的に明かされる。
しかし、こんなことを感想に書くのは著者に失礼かもしれない。本書のエピローグにはこんな文章があった。
本書の「訳者あとがき」には
とあった。自分にはまさにそうで、リトアニアの占領とリトアニア人の追放は自分には全く知らないことだった。
ゴルバチョフがソ連共産党の書記長になり、続いてソ連大統領になった頃、西側諸国は彼の内からの改革と新思考外交に喝采を送ったものだった。そうしたゴルバチョフにソ連「内部」から最初に反旗を翻したのはバルト三国で、最初に平和的独立を果たしたのもこの三国である。その後、ソ連は解体に向かった。自分の読んでいる新聞はソ連の内なる改革を進めるゴルバチョフに好意的で、彼を支援する西欧諸国の首脳の発言を積極的に載せていたものだし、自分もバルト三国がなぜ独立を急ぐのかと思ったものだった。ゴルバチョフ自身、なぜ独立を急ぐのか、とバルト三国人のデモ隊に言っていた記事を読んだ記憶もある。まさか、自分と同様に彼がスターリンのしたことを知らないなどと言うことはあるだろうか?そんな無知から来る考えは、本書を読んで改めた。著者は祖父がリトアニア軍の将校で両親はスターリンの弾圧前にドイツに脱出した。著者自身はアメリカに住む。著者は本書の執筆に当たり、リトアニアを2度訪れ、シベリア追放の生還者やその家族からヒアリングをして本書を書いた。だから本書は完全なフィクションではなく、事実の組み合わせなのだろう。最後に登場するサモデュロフ医師の良心に救われる。スターリン時代にも信念を貫くロシア人がいた。ソ連の大作曲家ショスタコーヴィチの評伝「証言」に登場する、権力の側で唯一ショスタコーヴィチと親しく交際してくれた芸術に理解のある有能で寛大なトゥハチェフスキー将軍を思い出した。彼は粛清されている。サモデュロフ医師のその後が心配だ。
世界史を題材にした小説にはこのような苦しいものが多々あるのが残念であるし、今も世界でそのような材料が作られていること。残念ながら自分は本書を読んで「知った」だけで、行動を起こせていない。
冒頭はリトアニアの町カウナス(訳者によれば杉原千畝が住んでいた場所としても知られている)。スターリンが第二次世界大戦のどさくさ紛れにリトアニアを含むバルト三国を占領して1年ほど経った頃だった。1941年6月14日、主人公で語り手、15歳の画家志望の娘リナ・ヴィルカスの家にNKVD(ソ連の秘密警察、後のKGB)が踏み込んできた。大学学部長の父は不在で、ママのエレーナ、弟のヨーナスと共にトラックに詰め込まれる。両親はこのことを予期していたようでママはコートに貴重品や書類を縫い込んでいた。彼らは町の知り合いも乗せられたトラックでカウナス郊外の駅に連れ込まれ、貨車に押し込まれた。同じ車両に乗った勇気のある少年アンドリュスと弟のヨーナスとで貨車を一時的に脱出し、増結された貨車にパパがいるのを見つけた。貨車は出発し6週間も乗せられたままだった。パパも居る青年・壮年の男性を乗せた貨車は途中で切り離された。貨車はアルタイの草原で止まった。主人公らの班はトゥラシャク村の側のテンサイ畑の側の収容所に入れられ強制労働をさせられる。そこでは主人公リナとアンドリュスの不器用な恋もあった。ここで10カ月働かされた後、ここに収容されていたリトアニア人は残る者と移動する者の二手に分けられ、ヴィルカス家の母と子供たちはトラック、貨車、そして船でヤクーツクを経てレナ川の北極海の臨む河口、トロフィモフスクで降ろされた。途中でエストニア人、フィンランド人、ウクライナ人なども合流させられた。監視するNKVDの兵士たちはレンガ造りの宿舎で過ごすが、ここに追放された人たちは、9月、拾った部材で掘っ立て小屋同然の家を建てさせられ、そこに住めという。間もなく、極夜がやって来る。食料は作業の代償としてのパンだけ。吹雪になれば外に出られないし、昼間も闇という過酷な世界に閉じ込められる。赤痢やチフスが流行り、次々と人は死んでいく。
読んでいてあまりに苦しい話である。主人公の少女は直情径行、思慮も浅く想像力もなく、3部構成の2部まではあまり共感できなかったし、リナのママ(エレーナ)が、またあまりに完璧な人間過ぎると思うのだが、最も過酷な第3部まで来るとそんなことは問題なくなる。監視兵の中にも同情的なクレツキーという人物もいれば、追放者の中にも嫌味しか言わないスターラスなどの存在もある。それらのキャラクターが、実は第3部でママの存在を浮き彫りにする効果がある。
苦しいだけの描写では読者に飽きられてしまうのだろう。この話には至る所に謎が散りばめられている。アンドリュスとその母はアルタイの収容所で、監視兵の好意に与るのだが、なぜ好意を受け、また、スターリンに反発していたアンドリュスはそれをどう思っているのか?この話では「名簿」に載ると追放されるということになっているのだが、ヴィルカス家が何故「名簿」に載ったのか?密告したのは誰なのか?密告者は最後まで明かされないが読者はきっとこの人だろうとわかるように書かれている。一家が追放された理由は、時折リナが回想する、カウナスでの生活や、ひと夏をいとこのヨアーナと過ごしたコテージの場面の回想も交え効果的に明かされる。
しかし、こんなことを感想に書くのは著者に失礼かもしれない。本書のエピローグにはこんな文章があった。
「私の最大の望みは、あなたがこの瓶の中の文章を読んで、心の底から人間らしい共感を呼び起こされ、何らかの行動に出て下さること、誰かにその内容を伝えて下さることです。そのとき初めて、わたしたち人間は、確かめあえるはずです。この種の愚が二度とくりかえされてはならない、ということを」(390~391頁)。
本書の「訳者あとがき」には
歴史には、後々まで多く語られる場面と、あまり語られない場面があるようです(397頁)。
とあった。自分にはまさにそうで、リトアニアの占領とリトアニア人の追放は自分には全く知らないことだった。
ゴルバチョフがソ連共産党の書記長になり、続いてソ連大統領になった頃、西側諸国は彼の内からの改革と新思考外交に喝采を送ったものだった。そうしたゴルバチョフにソ連「内部」から最初に反旗を翻したのはバルト三国で、最初に平和的独立を果たしたのもこの三国である。その後、ソ連は解体に向かった。自分の読んでいる新聞はソ連の内なる改革を進めるゴルバチョフに好意的で、彼を支援する西欧諸国の首脳の発言を積極的に載せていたものだし、自分もバルト三国がなぜ独立を急ぐのかと思ったものだった。ゴルバチョフ自身、なぜ独立を急ぐのか、とバルト三国人のデモ隊に言っていた記事を読んだ記憶もある。まさか、自分と同様に彼がスターリンのしたことを知らないなどと言うことはあるだろうか?そんな無知から来る考えは、本書を読んで改めた。著者は祖父がリトアニア軍の将校で両親はスターリンの弾圧前にドイツに脱出した。著者自身はアメリカに住む。著者は本書の執筆に当たり、リトアニアを2度訪れ、シベリア追放の生還者やその家族からヒアリングをして本書を書いた。だから本書は完全なフィクションではなく、事実の組み合わせなのだろう。最後に登場するサモデュロフ医師の良心に救われる。スターリン時代にも信念を貫くロシア人がいた。ソ連の大作曲家ショスタコーヴィチの評伝「証言」に登場する、権力の側で唯一ショスタコーヴィチと親しく交際してくれた芸術に理解のある有能で寛大なトゥハチェフスキー将軍を思い出した。彼は粛清されている。サモデュロフ医師のその後が心配だ。
世界史を題材にした小説にはこのような苦しいものが多々あるのが残念であるし、今も世界でそのような材料が作られていること。残念ながら自分は本書を読んで「知った」だけで、行動を起こせていない。
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
神奈川県に住むサラリーマン(技術者)でしたが24年2月に会社を退職して今は無職です。
読書歴は大学の頃に遡ります。粗筋や感想をメモするようになりましたのはここ10年程ですので、若い頃に読んだ作品を再読した投稿が多いです。元々海外純文学と推理小説、そして海外の歴史小説が自分の好きな分野でした。しかし、最近は、文明論、科学ノンフィクション、音楽などにも興味が広がってきました。投稿するからには評価出来ない作品もきっちりと読もうと心掛けています。どうかよろしくお願い致します。
この書評へのコメント
- ゆうちゃん2025-11-14 00:15
ぱせりさん、コメントと良い本のご紹介ありがとうございました。
紹介者に共感ボタンを押してもらって、とても嬉しいです。僕もリトアニアのことは何も知らなかったです。第二次世界大戦や戦後・冷戦期のことは沢山勉強してきた積りですが、知らないことはまだまだ沢山ありそうですね。
仰る通り辛い読書ですが、戦争を扱う本は得てしてそうなってしまいます。普通は途中で少し明るい話題が出る筈ですが、本書では最後の数頁に僅かな希望が見られるだけでした。エピローグがなくても小説は成り立つと思いますが、エピローグが僅かの救いですね。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:岩波書店
- ページ数:400
- ISBN:9784001156515
- 発売日:2012年01月26日
- 価格:2268円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。