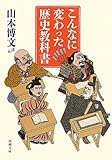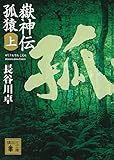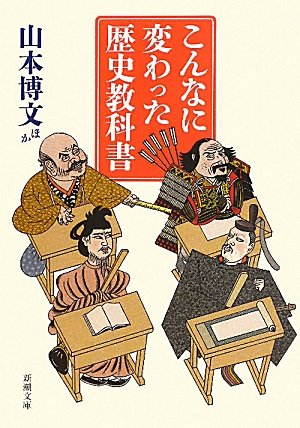はるほんさん
レビュアー:
▼
昭和世代ならカルチャーショック?
歴史・時代小説が好きなので
今でも結構歴史番組やニュース記事は目を通す。
なので書かれていることは8割方知っていたが
改めて自分の時代と今の歴史の教科書が比較出来てよかった。
本書では昭和と平成の歴史教科書で改訂された内容を、
古代・中世・近世・近代ごとに区分し、
中学校教科書の編集員である筆者が解説を加えたものだ。
歴史小説を読む者として、初ねて知った時に
「うえぇぇぇぇっっっ!?」って思ったモノだけあげておく。
①あのオッサンは聖徳太子じゃない。
平成生まれの若い方は知らないだろうが
昔々、五千円札と一万円札は聖徳太子だったんじゃよ…。(遠い目)
まあそんでも冠を載せて袍を着て、笏を持った例の姿は見たことがあるだろう。
昔は「聖徳太子像」とされていたらしいが、現在では
「聖徳太子と伝えられる像」と注釈がつくらしい。
この本には書かれていなかったが、
聖徳太子自身が架空の人物でないかとされる説もある。
じゃあ私達の使っていた五千円札・一万円札のアレは誰…?
広い意味での偽札!?(笑)
②鎌倉幕府はイイクニじゃない。
「イイクニつくろう鎌倉幕府」。
まさに語呂合わせにピッタリの年号だったが、
1192年は「源頼朝が征夷大将軍になった」という節目ではあるが
「幕府成立」とは書かれていないとのこと。
1180年から1192年の間の様々な説の間で揺れており、
いまだ決着はついていないというのが、正しいトコロらしい。
コレも本書ネタではないが、同様に
大化の改新も今は646年が通説なのだそうだ。
学生時代は得意だったんだよと言う人も、
今歴史のテスト受けたら、案外点数悪いかもしれないっすよ。(笑)
③武田騎馬隊はいなかった。
なんかこの時代の馬はポニークラスのサイズだったため
(※正確にはポニーよりはもう少し大きかったとも)
馬は移動にのみつかわれ、戦闘の時はウマから降りたとかいう。(笑)
これは歴史小説の見せ場的にショック。。・゚・(ノД`)・゚・。
小さいお馬さんに乗る武将。畜生かわいいじゃねぇか。
コレも余談だが、日本の馬はそもそも西洋馬と違い
体型がどっしりしている分、馬力があったらしい。
その分非常に気性が荒く、騎馬隊のような整然とした動きを
訓練すると言うのも難しかったんだそうな。
④士農工商はなかった。
もう四文字熟語の域に達するイキオイの完成度だというのに
そんなのもはなかったってアンタ。
実際は武士>>>>>>>武士以下という身分があっただけで
そんなに細かいものではなかったという意。
明治維新後の「四民平等」も、実際平等じゃねーだろってんで今は記載されない。
これとは少しズレるが、「一揆」と言われるものも
教科書で受けたイメージとはちょっと異なるものらしい。
領主はTVドラマみたいに悪人ばっかりじゃなかったらしく
結構話し合いなどで穏便に済むことも多かったんだとか。
でも「農民が一致団結する」=「一揆」なので
全国で話し合いが行われても、「全国で一揆が起こった」ことになるらしい。
内容はこんなカンジ。他にも今の教科書では
「大和朝廷」「仁徳天皇陵」という言葉が使われないことや
「戊申の役」「西南の役」が「戦争」に変わった理由など
昭和世代ならΣ(゚◇゚;)マジデッ!?ってネタがかかれている。
歴史は基本「勝者の歴史」であり
今でも闇に葬られた歴史や曖昧な歴史が存在する。
そこから歴史の扉が新たに開けられたり閉じられたり(笑)する訳だが、
また新たな歴史小説やヒーローが生まれるかも知れない訳で
どちらに転んでも楽しい。
難を言うなら、さっくり読める作りになっている所為か、
もしくは何か問題があるからか
中国や韓国の歴史にはほぼ触れられていない。
教科書問題といえばやはり中国のことがあるので
多少の専門家からの見解はつけて欲しかった気もする。
今でも結構歴史番組やニュース記事は目を通す。
なので書かれていることは8割方知っていたが
改めて自分の時代と今の歴史の教科書が比較出来てよかった。
本書では昭和と平成の歴史教科書で改訂された内容を、
古代・中世・近世・近代ごとに区分し、
中学校教科書の編集員である筆者が解説を加えたものだ。
歴史小説を読む者として、初ねて知った時に
「うえぇぇぇぇっっっ!?」って思ったモノだけあげておく。
①あのオッサンは聖徳太子じゃない。
平成生まれの若い方は知らないだろうが
昔々、五千円札と一万円札は聖徳太子だったんじゃよ…。(遠い目)
まあそんでも冠を載せて袍を着て、笏を持った例の姿は見たことがあるだろう。
昔は「聖徳太子像」とされていたらしいが、現在では
「聖徳太子と伝えられる像」と注釈がつくらしい。
この本には書かれていなかったが、
聖徳太子自身が架空の人物でないかとされる説もある。
じゃあ私達の使っていた五千円札・一万円札のアレは誰…?
広い意味での偽札!?(笑)
②鎌倉幕府はイイクニじゃない。
「イイクニつくろう鎌倉幕府」。
まさに語呂合わせにピッタリの年号だったが、
1192年は「源頼朝が征夷大将軍になった」という節目ではあるが
「幕府成立」とは書かれていないとのこと。
1180年から1192年の間の様々な説の間で揺れており、
いまだ決着はついていないというのが、正しいトコロらしい。
コレも本書ネタではないが、同様に
大化の改新も今は646年が通説なのだそうだ。
学生時代は得意だったんだよと言う人も、
今歴史のテスト受けたら、案外点数悪いかもしれないっすよ。(笑)
③武田騎馬隊はいなかった。
なんかこの時代の馬はポニークラスのサイズだったため
(※正確にはポニーよりはもう少し大きかったとも)
馬は移動にのみつかわれ、戦闘の時はウマから降りたとかいう。(笑)
これは歴史小説の見せ場的にショック。。・゚・(ノД`)・゚・。
小さいお馬さんに乗る武将。畜生かわいいじゃねぇか。
コレも余談だが、日本の馬はそもそも西洋馬と違い
体型がどっしりしている分、馬力があったらしい。
その分非常に気性が荒く、騎馬隊のような整然とした動きを
訓練すると言うのも難しかったんだそうな。
④士農工商はなかった。
もう四文字熟語の域に達するイキオイの完成度だというのに
そんなのもはなかったってアンタ。
実際は武士>>>>>>>武士以下という身分があっただけで
そんなに細かいものではなかったという意。
明治維新後の「四民平等」も、実際平等じゃねーだろってんで今は記載されない。
これとは少しズレるが、「一揆」と言われるものも
教科書で受けたイメージとはちょっと異なるものらしい。
領主はTVドラマみたいに悪人ばっかりじゃなかったらしく
結構話し合いなどで穏便に済むことも多かったんだとか。
でも「農民が一致団結する」=「一揆」なので
全国で話し合いが行われても、「全国で一揆が起こった」ことになるらしい。
内容はこんなカンジ。他にも今の教科書では
「大和朝廷」「仁徳天皇陵」という言葉が使われないことや
「戊申の役」「西南の役」が「戦争」に変わった理由など
昭和世代ならΣ(゚◇゚;)マジデッ!?ってネタがかかれている。
歴史は基本「勝者の歴史」であり
今でも闇に葬られた歴史や曖昧な歴史が存在する。
そこから歴史の扉が新たに開けられたり閉じられたり(笑)する訳だが、
また新たな歴史小説やヒーローが生まれるかも知れない訳で
どちらに転んでも楽しい。
難を言うなら、さっくり読める作りになっている所為か、
もしくは何か問題があるからか
中国や韓国の歴史にはほぼ触れられていない。
教科書問題といえばやはり中国のことがあるので
多少の専門家からの見解はつけて欲しかった気もする。
投票する
投票するには、ログインしてください。
歴史・時代物・文学に傾きがちな読書層。
読んだ本を掘り下げている内に妙な場所に着地する評が多いですが
おおむね本人は真面目に書いてマス。
年中歴史・文豪・宗教ブーム。滋賀偏愛。
現在クマー、谷崎、怨霊、老人もブーム中
徳川家茂・平安時代・暗号・辞書編纂物語・電車旅行記等の本も探し中。
秋口に無職になる予定で、就活中。
なかなかこちらに来る時間が取れないっす…。
2018.8.21
この書評へのコメント
- かもめ通信2015-07-15 06:58
これ気になっていた本でもあるので買ってもいいかな~と思っていたのだけれど、先を越されたかっ!ww>新潮文庫の100冊
http://www.honzuki.jp/bookclub/theme/no224/index.html?latest=20クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - kuori2015-07-15 07:19
>日本の馬はそもそも西洋馬と違い
初めて木曾馬写真を見た時は、あまりの短足さに吹き出した記憶が--;
今、画像検索するとそこまで短足に思わないのは、そういう種類と思って見るからかな?
時速10km位で、大人が走ったほうが早いとかも聞きました..っ
↓ 木曾馬Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%9B%BD%E9%A6%ACクリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:新潮社
- ページ数:279
- ISBN:9784101164465
- 発売日:2011年09月28日
- 価格:529円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。