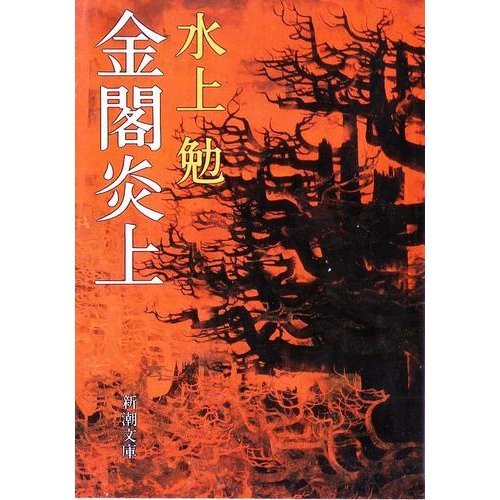ぽんきちさん
レビュアー:
▼
彼はなぜ金閣に火をつけたのか
いわゆる「金閣寺放火事件」は1950年7月2日に起きた。鹿苑寺金閣の国宝・舎利殿に火が放たれ、全焼したのである。寺の徒弟僧、林承賢(俗名:養賢)によるものだった。養賢は、放火後、自殺を図るが未遂に終わった。判決は懲役7年(後、恩赦により5年3月に減刑)。拘束中に精神を病み、満期釈放後に精神科病院に入院。以前から患っていた肺結核で死亡している。
本書はこの事件に取材したもので、著者・水上勉は上梓までに20年もの歳月をかけている。本事件を題材にした作品としては三島由紀夫『金閣寺』がつとに有名である。水上も本作より先に『五番町夕霧楼』を発表している。この2作がフィクション性が高いことに比べ、本作はほぼノンフィクション形式で書かれている(但し、例えば、水上は犯人の養賢に偶然会ったことがあるとしているが、その部分が事実であるかどうかについては議論があるようだ)。
放火犯である養賢の生い立ちから放火に至るまで、そしてその死までを丹念に追う作品である。
養賢は、若狭湾に面した半島の北端で生まれた。田舎の貧寺の子である。父は僧侶だった。母はどうした縁か、遠く大江山麓から嫁いできた。両親には気性の相違があり、仲はあまりよくなかった。養賢は幼少時から吃音であった。父は肺結核を長く患った末、養賢がまだ13歳のころに病没。かねてより、息子を金閣寺で修行させたいとの希望があり、養賢は中学卒業前に金閣寺の徒弟となった。
戦時中は栄養状態の悪さや養賢の肺病発症などもあり、故郷に戻る時期もあったが、戦後、再び金閣に戻り、大学予科に入学。そのころから勉学を怠るようになり、3年目には学年最下位となる。そのため、住職に叱責されることもたびたびだった。また素行も悪く、暴力沙汰を起こすこともあった。一方で、修行の場というより観光で金儲けしている金閣の現状に疑問もあり、上位の僧侶や事務職への反発心も抱いていた。
養賢は金閣寺の後継者となることを夢見ていたが、住職の態度が冷淡であり、このままではそれも見込めないと考え、次第に犯行の決意を固めた、というのが大方の流れである。
著者は自身も(寺ではないが)貧しい家に生まれ、金閣と同系列の寺院で修行した経験がある。そこで仏弟子といいながらも生臭い、僧侶の姿を見聞きもしている。そうした著者の目線がそこここで犯人のものと重なってくる。
もちろん、放火は犯罪であり、重要な文化財の焼失は惜しまれることなのだが、そこに至るまでに何があったのか、深く潜入していくような読み心地である。
著者あとがきには
片や、吃音で肺も病み、出世も見込めないが田舎に帰っても居場所はない、青年僧の鬱屈。片や、本音と建て前が乖離した、虚栄まみれの大寺院。養賢はどうしようもない現実に、それでも爪痕を残そうとしたのか。
養賢の母は、息子の犯行を知り、京都の警察で事情聴取を受けた後、家へ帰る列車から身を投げて自死している。
養賢は、前述のように獄中で精神を病みつつ、住職への詫びの手紙を送り続けている。
金閣は住職の尽力もあり、1955年に再建された。養賢は再建した金閣の写真を見たいか問われた際、
禅には時に、物騒な命題があるが、養賢は、「殺仏殺祖」(仏を殺し、親を殺す)(『臨済録』)について考えていたという話があるという。反抗期の心が、刃のような言葉を咀嚼しきれずに振り回してしまった面もあるのだろうか。
著者は、金閣を始め、系列寺院の内情も縷々綴る。もちろん、取材も重ねたのだろうが、寺で修行の日々を過ごした者でなければ書けない描写だろう。貧村から、いくばくかの夢を抱いて上京し、したたかで一筋縄ではいかぬ現実に幻滅を抱いた、という点では、著者と養賢に通じ合うところがあったのかもしれない。そこで犯罪に走るかどうかはまた別だが。
著者は最後に、探し続けていた養賢とその母の墓にたどり着く。その筆からは、犯罪への糾弾ではなく、鎮魂がにじむ。それは、金閣放火犯ひとりではなく、貧しさに喘ぎ、どん底で果てた、顧みられぬ幾多の人に向けたものであるようにも思える。
本書はこの事件に取材したもので、著者・水上勉は上梓までに20年もの歳月をかけている。本事件を題材にした作品としては三島由紀夫『金閣寺』がつとに有名である。水上も本作より先に『五番町夕霧楼』を発表している。この2作がフィクション性が高いことに比べ、本作はほぼノンフィクション形式で書かれている(但し、例えば、水上は犯人の養賢に偶然会ったことがあるとしているが、その部分が事実であるかどうかについては議論があるようだ)。
放火犯である養賢の生い立ちから放火に至るまで、そしてその死までを丹念に追う作品である。
養賢は、若狭湾に面した半島の北端で生まれた。田舎の貧寺の子である。父は僧侶だった。母はどうした縁か、遠く大江山麓から嫁いできた。両親には気性の相違があり、仲はあまりよくなかった。養賢は幼少時から吃音であった。父は肺結核を長く患った末、養賢がまだ13歳のころに病没。かねてより、息子を金閣寺で修行させたいとの希望があり、養賢は中学卒業前に金閣寺の徒弟となった。
戦時中は栄養状態の悪さや養賢の肺病発症などもあり、故郷に戻る時期もあったが、戦後、再び金閣に戻り、大学予科に入学。そのころから勉学を怠るようになり、3年目には学年最下位となる。そのため、住職に叱責されることもたびたびだった。また素行も悪く、暴力沙汰を起こすこともあった。一方で、修行の場というより観光で金儲けしている金閣の現状に疑問もあり、上位の僧侶や事務職への反発心も抱いていた。
養賢は金閣寺の後継者となることを夢見ていたが、住職の態度が冷淡であり、このままではそれも見込めないと考え、次第に犯行の決意を固めた、というのが大方の流れである。
著者は自身も(寺ではないが)貧しい家に生まれ、金閣と同系列の寺院で修行した経験がある。そこで仏弟子といいながらも生臭い、僧侶の姿を見聞きもしている。そうした著者の目線がそこここで犯人のものと重なってくる。
もちろん、放火は犯罪であり、重要な文化財の焼失は惜しまれることなのだが、そこに至るまでに何があったのか、深く潜入していくような読み心地である。
著者あとがきには
彼がなぜ金閣に放火したか、そのことをつきつめて考えてみたかった。とある。
だが、本当のことはいまもわからないとも。
片や、吃音で肺も病み、出世も見込めないが田舎に帰っても居場所はない、青年僧の鬱屈。片や、本音と建て前が乖離した、虚栄まみれの大寺院。養賢はどうしようもない現実に、それでも爪痕を残そうとしたのか。
養賢の母は、息子の犯行を知り、京都の警察で事情聴取を受けた後、家へ帰る列車から身を投げて自死している。
養賢は、前述のように獄中で精神を病みつつ、住職への詫びの手紙を送り続けている。
金閣は住職の尽力もあり、1955年に再建された。養賢は再建した金閣の写真を見たいか問われた際、
どうでもよい、無意味なことだと答えたという。
禅には時に、物騒な命題があるが、養賢は、「殺仏殺祖」(仏を殺し、親を殺す)(『臨済録』)について考えていたという話があるという。反抗期の心が、刃のような言葉を咀嚼しきれずに振り回してしまった面もあるのだろうか。
著者は、金閣を始め、系列寺院の内情も縷々綴る。もちろん、取材も重ねたのだろうが、寺で修行の日々を過ごした者でなければ書けない描写だろう。貧村から、いくばくかの夢を抱いて上京し、したたかで一筋縄ではいかぬ現実に幻滅を抱いた、という点では、著者と養賢に通じ合うところがあったのかもしれない。そこで犯罪に走るかどうかはまた別だが。
著者は最後に、探し続けていた養賢とその母の墓にたどり着く。その筆からは、犯罪への糾弾ではなく、鎮魂がにじむ。それは、金閣放火犯ひとりではなく、貧しさに喘ぎ、どん底で果てた、顧みられぬ幾多の人に向けたものであるようにも思える。
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:新潮社
- ページ数:347
- ISBN:9784101141190
- 発売日:1986年02月27日
- 価格:540円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。