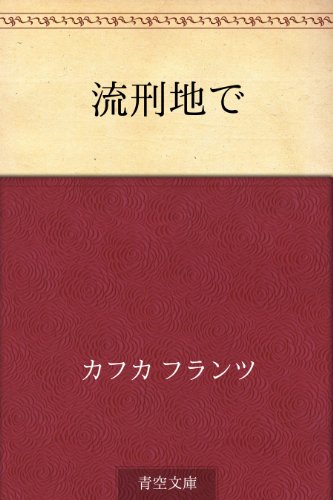ゆうちゃんさん
レビュアー:
▼
人の信念とは何か。流刑地での処刑を通じてカフカが明らかにしたもの。
主な登場人物は、この流刑地(実は島)で死刑を担当する将校とその処刑を見学する旅行者(後で、彼はフランスらしき外国人の法学関係の高名な学者だとわかる)、受刑者と受刑者を監視する兵士である。将校の話の中に新旧司令官が登場するが、将校は彼が今担当している処刑制度を作り上げた旧司令官の心酔者で、新しい考えを持つ新司令官とは反りが合わない。新司令官は、この地で穏健な処刑制度を支持する婦人方を味方にしているように見えるが、将校曰く、この流刑地で旧司令官を支持する人が大多数だったという。
(おそらくドイツの)将校は旅行者にフランス語で旧司令官が編み出した死刑執行装置について説明している。それは受刑者を裸にしてベッドに縛り、12時間かけて上から針で罪名を体に刻む装置だった。滴る血や脱がされた服は脇の穴に流され、捨てられる。受刑者は途中で反転させられ、腹側と背側にそれぞれ罪名を刻まれ、最後は死に至る。旧司令官が編み出したその装置を将校は大変な熱意で旅行者に説明する。
旅行者が目にしている受刑者は、前夜の当番兵で、いざという時に活発に動けるように、1時間おきに中隊長に対して敬礼する義務があるところ、深夜2時に中隊長が覗いてみると寝呆けていたのだと言う。中隊長がそのことを彼に注意すると、逆に中隊長は掴みかかられた。将校は中隊長の申し立てで受刑者を捕らえ、死刑の判決を下した。裁判も尋問も抜き、将校は検事兼裁判官であり、それが当然と言う口ぶりである。将校はこの有力な外国人が、この場所に見学に来たのは新司令官の差し金だと見抜いている。そして判決を下す方法の不当性、刑の残虐性を指摘されると予想していた。だが、旧司令官の心酔者の将校は、この旅行者が自分の説明に納得すると信じて説明をしていた。旧司令官の時代、この装置を使った処刑に人は鈴なりに集まったものだし、今は新司令官の元、鳴りを潜めているが、連中の内心は旧司令官に賛成なのだと言う。
旅行者が自分の意見に賛成しないと思うや、将校は言質をとられない曖昧な答えをして欲しいと懇願する。旅行者は、自分は単なる外国人であり、また、たとえどんな意見を言ったとしても、それは一個人のものに過ぎず、自分の影響力を過大視しているという。だが将校はおさまらない。将校に問い詰められ、とうとう、彼は「賛成できない」と言った。すると将校は、旧司令官の刻んだ文字「正しくあれ」を示し、自ら服を脱ぎ始め・・・。
旅行者は最後に旧司令官の墓があると言う茶屋に行く。僧らによって基地内の埋葬場所への埋葬を拒まれ、旧司令官はその茶屋に葬られたと言う。その墓を見学して彼は、島を去ってゆく。受刑者と監視兵は旅行者についていこうとするが、拒否される。
荒唐無稽な作品だが、人の信念を皮肉ったものだろうか。いかにおかしなことでも、心から信じてしまえば、それはその人にとって真実である。将校は、法学者に自分の信念を否定された時、絶望的な行動をとる。そのくらい強く信じていたことなのである。
昔の作品であるが、これも、他の大作家の幾つかの作品のように、非常に現代的である。時代によっては、カフカが単にカリカチュアを書いただけに思える。だが、この頃は真実や信念をめぐって、かまびすしい。カフカが現代にも読まれるのは、こういう点があるからだろうか。
(おそらくドイツの)将校は旅行者にフランス語で旧司令官が編み出した死刑執行装置について説明している。それは受刑者を裸にしてベッドに縛り、12時間かけて上から針で罪名を体に刻む装置だった。滴る血や脱がされた服は脇の穴に流され、捨てられる。受刑者は途中で反転させられ、腹側と背側にそれぞれ罪名を刻まれ、最後は死に至る。旧司令官が編み出したその装置を将校は大変な熱意で旅行者に説明する。
旅行者が目にしている受刑者は、前夜の当番兵で、いざという時に活発に動けるように、1時間おきに中隊長に対して敬礼する義務があるところ、深夜2時に中隊長が覗いてみると寝呆けていたのだと言う。中隊長がそのことを彼に注意すると、逆に中隊長は掴みかかられた。将校は中隊長の申し立てで受刑者を捕らえ、死刑の判決を下した。裁判も尋問も抜き、将校は検事兼裁判官であり、それが当然と言う口ぶりである。将校はこの有力な外国人が、この場所に見学に来たのは新司令官の差し金だと見抜いている。そして判決を下す方法の不当性、刑の残虐性を指摘されると予想していた。だが、旧司令官の心酔者の将校は、この旅行者が自分の説明に納得すると信じて説明をしていた。旧司令官の時代、この装置を使った処刑に人は鈴なりに集まったものだし、今は新司令官の元、鳴りを潜めているが、連中の内心は旧司令官に賛成なのだと言う。
旅行者が自分の意見に賛成しないと思うや、将校は言質をとられない曖昧な答えをして欲しいと懇願する。旅行者は、自分は単なる外国人であり、また、たとえどんな意見を言ったとしても、それは一個人のものに過ぎず、自分の影響力を過大視しているという。だが将校はおさまらない。将校に問い詰められ、とうとう、彼は「賛成できない」と言った。すると将校は、旧司令官の刻んだ文字「正しくあれ」を示し、自ら服を脱ぎ始め・・・。
旅行者は最後に旧司令官の墓があると言う茶屋に行く。僧らによって基地内の埋葬場所への埋葬を拒まれ、旧司令官はその茶屋に葬られたと言う。その墓を見学して彼は、島を去ってゆく。受刑者と監視兵は旅行者についていこうとするが、拒否される。
荒唐無稽な作品だが、人の信念を皮肉ったものだろうか。いかにおかしなことでも、心から信じてしまえば、それはその人にとって真実である。将校は、法学者に自分の信念を否定された時、絶望的な行動をとる。そのくらい強く信じていたことなのである。
昔の作品であるが、これも、他の大作家の幾つかの作品のように、非常に現代的である。時代によっては、カフカが単にカリカチュアを書いただけに思える。だが、この頃は真実や信念をめぐって、かまびすしい。カフカが現代にも読まれるのは、こういう点があるからだろうか。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
神奈川県に住むサラリーマン(技術者)でしたが24年2月に会社を退職して今は無職です。
読書歴は大学の頃に遡ります。粗筋や感想をメモするようになりましたのはここ10年程ですので、若い頃に読んだ作品を再読した投稿が多いです。元々海外純文学と推理小説、そして海外の歴史小説が自分の好きな分野でした。しかし、最近は、文明論、科学ノンフィクション、音楽などにも興味が広がってきました。投稿するからには評価出来ない作品もきっちりと読もうと心掛けています。どうかよろしくお願い致します。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:
- ページ数:30
- ISBN:B009B1Q576
- 発売日:2012年09月14日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。