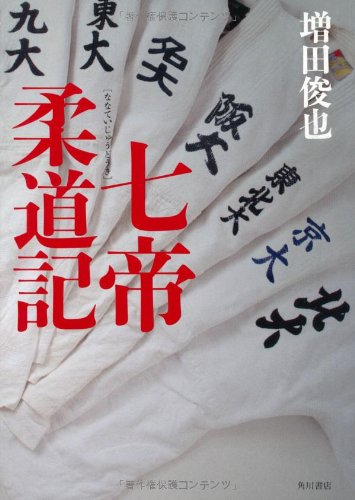過去のレビュアーの方々がおっしゃっている通り、これは好き嫌いがはっきり分かれる作品だと思います。
正直に言って、この作品は僕には全く合わないものでした。
ただ、この作品の持つ熱さに対しては敬意を表します。だからこそ、僕自身も本気でこの作品を批判するつもりです。
物語は主人公である著者が北海道にやってきたところから始まります。彼は晴れて北大に合格したのです。
彼が北大に入学した理由はただ一つ、それは「七帝柔道」をやるためでした。
「七帝柔道」は立ち技を重視する現在一般的な柔道=講道館柔道とは異なり、寝技を重視する柔道なのです。
あらかじめ体重差のような身体能力やセンスによって左右される立ち技と違って、寝技の技術はひたすら練習することでしか養えません。つまり、寝技を主体とした七帝柔道とは、より多く練習したものこそが最も強いものとなる柔道なのです。
北大のほか東大や京大などの旧帝大では、戦前では主流だったこの寝技主体の柔道を今でもかたくなに守っているのでした。
主人公は北大柔道部に入部し、猛練習の日々を重ねてゆくのです。
この作品を読んだ正直な感想として僕が感じたのは、作者は読者を侮っているのではないか、ということでした。
たとえば
「だが、このただひとつの目標のための練習が苦しすぎた。辛すぎた」
「たった一日の休みである日曜日が来るまでがあまりに長かった。あまりに苦しかった。拷問のような時間だった」
このような表現、作者はどうして自分でこのようなことを言うのでしょうか。練習の辛さ、苦しさ、それをわざわざ自分で言うなよ、と。
それを物語として表現したもの、それが「小説」なのだと僕は思うのです。
物語として表現せずに自分の主観を押し付ける、そんなのは居酒屋で上司に聞かされる武勇伝もどきの与太話でしかありません。
彼の先輩が彼に語りかける「頑張れ」「負けるな」「辞めるな」という言葉と同じくらいに空虚なものでしかない。
僕はこの作品に作者のナルシシズムを感じます。
彼がこの物語を通して読者に伝えたいことというのは、「そんなつらい練習を乗り越えてきた俺ってすごいだろ?」ってことなんじゃないかと。
独善的だと思うのです。作者自身が述べているように、別に誰かに強制されたわけではなく、自分で好き好んでこの世界に身を投じたにも関わらず、まるで悲劇のヒーローのように自らの体験を語るというのは。
この作品のタイトルは「七帝柔道記」ですが、「七帝柔道」に関する考察のようなものはどこにも見当たりません。本来ならばこの小説のタイトルは「増田俊也自伝」であるべきでしょう。
にもかかわらず、まるで自分こそが「七帝柔道」の神髄を会得したかのように本書のタイトルに堂々と「七帝柔道記」とつけるその浅ましさ。
なんて傲慢で、なんて厚顔無恥なのだろう。
たとえ本書が「七帝柔道」の素晴らしさを描いていたとしても、実際にはそんな「七帝柔道」に青春をささげた自分の素晴らしさを描いているにすぎません。
それはまるで「日本」という国を称賛することで、その国に生まれただけの自分まで偉くなったと勘違いして外国人を排斥する、ああいう人たちの思考と本質的に同じものだと思うのです。
本当は肥大化した自意識を持て余しているのに、それが体育会系の思考回路なのか、自分ではなく自分が信奉するものを代わりに祀り上げて自己陶酔する、そういう屈折したナルシシズム、はっきり言って大嫌いです。
「峰岸が私になついているのも、本当は筋肉ではないのだ。腕力でも外貌でもないのだ。この一年三カ月で、私も竜澤も自分で知らぬうちに大きく変わっていた。まったく違う人間になっていた。峰岸や看護婦たちが私たちを慕うのは、きっと人に対する私たちの眼差しが変わったからなのだ」
「私は○○の経験を経て、こんなに成長しました」だなんて、就職試験の自己アピールじゃあるまいし、よくもまあ、そんなことを自分の口から言えたものだと思います。
強くなることや他人を認められるようになること、そういうのも確かに「成長」なのかもしれないけれど、それって結局「自分」だけのことでしょう。
誰かに勝つことや、誰かが自分になびくことが「成長」の証なのだとしたら、そんな「成長」なんて、あまりに虚しい。
「汗の蒸気が立ち込めるあの道場で、自分の弱さにも仲間の弱さにも眼を背けることができないのだ。精神的弱さにも肉体的弱さにも眼を背けることができないのだ。しかしなお、それでも、その残酷な場面を私たちは眼を見開いて見続けなければならないのだ。七帝柔道という、逃げ場のない、あまりに残酷な場所で。そしてなんとしてでもこの場所で勝利を目指していくのだ。練習量だけを信じて……。
そう思うと、また泣けてきた」
この引用は作品のかなり後半の部分です。結局、主人公はそうして、最初から最後まで「自分」のことだけが大好きで、ただ「自分」で「自分」を憐れんでいるだけなのでした。一体それのどこが「成長」だというのだろう。
彼の中の「世界」に疑問を投げかける人物は、みな彼から離れてゆきます。「自分」の信じる「世界」と、そしてその厳しい「世界」の中で生き残ってゆくかっこいい「自分」だけを残して。
青春時代は輝かしいけれど、同時に恥ずかしいもの。
そんな青春時代を語ることができるのは、その時代を終えた者、その恥ずかしさが分かる大人のみができること。客観的な視点で「自分」を語ることのできない者は、いくら歳をとっていても、いまだ青春の中に生きている洟垂れ小僧でしかありません。
本書を読みながら僕の心に浮かんだのは、かつて新人賞の講評で山田詠美さんが語った言葉でした。
その言葉こそ、この作品を語るのに最もふさわしい。
それは、こんな言葉なのでした。
「子どもが書いた子どもの物語なんて、小説と呼ぶに値しない。そんなものは作文でしかない」
twitterで自分の個人的な思いを呟いてたら見つかってメッセージが来て気持ち悪いのでもうここからは退散します。きっとそのメッセージをした人はほくそ笑んでいることでしょう。おめでとう。
今までお世話になった方々ありがとうございました。
- この書評の得票合計:
- 54票
| 読んで楽しい: | 16票 | |
|---|---|---|
| 素晴らしい洞察: | 6票 | |
| 参考になる: | 30票 | |
| 共感した: | 2票 |
この書評へのコメント
- タカラ~ム2015-03-02 08:40
素通堂さんのレビューを読んで、「なるほどなぁ〜」と思いました。
私は、この作品を読んで、
「こんな辛いこと、よくやるなぁ〜」
「これは、自分には絶対ムリだわぁ〜」
というのが率直な感想で、自分にできないことをやっているということに対して、率直に感心したといったところです。
素通堂さんの感じたことも、私や他のレビュアーの皆さんが感じたことも、それぞれが本書から得た感動や違和感なのだろうと思います。
そういう人それぞれの感じたことがレビューに書かれて、それを読んだ人が、そこからさらに興味をもっていくこと。それが、「本が好き!」というサイトの持つ良さなんだろうな、と改めて感じました。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - 素通堂2015-03-02 11:34
SETさん☆ そう言って頂けて、書いてよかったなと思います。ありがとうございます!
うん、そうですよね。このサイトも、「課題図書」企画も、レビュアーの皆さんが思ったことを自由に書ける場所であった方がいい! たとえそれが酷評レビューであっても!!
タカラ~ムさん☆
僕のこのレビューを読んで、逆にこの作品に興味を持ってくださる人がもしもいらっしゃったら、それに越したことはないなあ、って思います。
タカラ~ムさんがおっしゃっているように、いろいろな見方があるのがこのサイトの魅力ですよね♪ 僕自身、他の方の酷評レビューだって楽しんで読んでますからw
……でも、僕自身はやっぱりこういうのはこれで終わりにして、またしばらくは絶賛レビューばっかり書いていきたいなあ。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - mothra-flight2015-03-02 12:45
「小説を書くのは、恥ずかしいことなんだ」と藤枝静男だったかがいっていましたが、確かに自分をさらけ出して呆気らかんとしている作品には興ざめですね。
自分をさらけ出しまくってるわりに私小説に収まらず、素晴らしい物語へと昇華してしまう太宰のような怪物もいますがw
この作品、積読で完全放置だったのですが、これを機会に読んでみようと思います。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - タカラ~ム2015-03-02 15:02
ちなみに、最近は格闘技系のノンフィクションか小説ばかり書いている著者の増田俊也氏の作家デビューは、このミステリーがすごい大賞の優秀賞を受賞した「シャトゥーン ヒグマの森」なんですよね。
はるほんさんのレビュー(http://www.honzuki.jp/book/47669/review/120333/)が面白かったです。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - 素通堂2015-03-03 01:19
かもめ通信さん☆
おお、そうだったのですね! 棚に戻しちゃったんですかあ。ここであえてチャレンジしてみるとか…しませんよね、やっぱり。
いつかみんなで太宰を語り合うのも楽しそうですねえ>太宰好き。その時は三島由紀夫ばりに「俺は太宰が嫌いだ!」という人がいてくれると楽しいのだけれど。
タカラ~ムさん☆
はるほんさんの「シャトゥーン ヒグマの森」レビューは面白いですよね♪
実は今回本書を読みながら、ずっと「どうして自伝にしたんだろう」と思っていたんです。そうじゃなかったなら、もっと何も気にせずに楽しんで読めたような、そんな気がしています。「シャトゥーン ヒグマの森」は読んでみたいけれど……、でも、もう苦手意識が付いちゃったしなあ。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - 素通堂2015-03-03 01:38
有坂汀さん、コメントありがとうございます!
自分が好きな作品をけなされるのって、いい気持ちしないですよね。申し訳ありません。
そして有坂さんのレビューも拝読していたのですが投票していなかったこと、無礼をどうかお許しください。
有坂さんはレビューを拝読していても、いろんなものの見方や考え方の中で中立的な立場をとろうとされているように思います。
僕の書いたレビューは僕自身の主観にすぎません。そしてそれがとても偏っていることは自覚しています。
自分でも品のいいレビューだとは思いませんが、こういう感想も含めて、この作品に興味を持ってくれる人がいればいいのかな、と。
ところで、有坂さんも太宰お好きなんですね☆ 有坂さんの太宰論、読んでみたいなあ。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - ぴょんはま2015-03-10 21:11
自分では好意的な書評を書いているくせに「共感した」?とお思いかもしれませんが、素通堂さんの書評を拝見していてわかった気がします。
この本は、小説でもエッセイでもなく、物語的にも未完だし、そもそも完成された独立の作品とは評価しにくい。ご指摘もっともです。
これに対して「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」の方は、長くはありますがノンフィクション作品として完成度が高かったし、著者の熱さがむしろ魅力になっていましたから、どなたにでも広くお勧めできる作品だと思いますよ。
私はその熱さを体験した後で、「七帝柔道記」をいわば仲間内の楽屋話として読んだから、粗削りで作文レベルでもそこは置いておいて、楽しめたと思います。
質的には格段の差がありますので、どちらか一方を読むなら、多少長くても間違いなく「木村政彦」の方がお勧めです。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - 素通堂2015-03-10 22:57
ぴょんはまさん、コメントありがとうございます☆
僕も「シャトゥーン」や「木村政彦」の方はどうなのか、ということに興味がなくはないのですが…。
でもまた「やっぱり駄目だあ」じゃいやだし、今回クソミソに言ってしまった以上、褒めるのも癪だし…… (._+ )☆\(-.-メ) ヲイ!
まあそれは冗談として、正直自分で書いていて嫌だなあと思ったのは、このレビューが著者個人に対する攻撃になってしまってるところなんですよね。
でも、仕方ないんですよ。だって「自伝」なのだから。「作品」として分けて考えるわけにはいかないな、と思って。
僕が批判したことは、結局、この作品が「自伝」であるということに尽きると思います。
だからこそ、好きな人は好きだろうし、そうじゃない人はそうじゃないってはっきり分かれるんじゃないかと。
きっと入口を間違えちゃったんでしょうね。僕もこの作品から入るべきじゃなかったと思います。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - タカラ~ム2015-03-10 23:13
「木村政彦」について、私はレビュー(http://www.honzuki.jp/book/190409/review/123986/)の中で、以下のように書きました。
本書は、著者の木村政彦に対する執着的ともいえる想いが存分に詰まっている。
詰まり過ぎているが故に暑苦しささえ感じるくらいで、格闘技に興味のない人
には受け入れにくい作品かもしれない。特に前半から中盤の木村政彦と彼を
取り巻く日本の柔道界の解説に関する部分は、何故に著者がここまで熱くなって
いるのかと読者が興醒めしてしまう危険性をはらんでいる。
「木村」も「シャトゥーン」も「七帝」も、共通しているのはこの著者の暑苦しさだと思うんですよね。たぶん、この人は自分がリスペクトする対象にトコトン暑くなる人なんでしょう。「七帝」の場合、その対象に自分が含まれちゃったのが欠点になってしまったのかもしれませんね。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - はにぃ2015-03-25 22:37
遅くなりました。
読んでくださったんですね。ありがとうございます。
私は根っからの体育会系なので、この物語にどっぷりハマりました。
その上、好きな男性のタイプは大柄で筋肉質で短髪で・・・(以下自粛)とまさに柔道家のような人なので、登場人物を勝手に好みの姿に想像しながら、イケメン祭り状態で読んでいました。
これほど好きになった本だったので、皆さんにも読んでもらいたい、特に文化系の方はこの世界をどう感じるのか気になって推薦したのですが、ここまで手厳しいとは(^-^;
素通堂さんの書評を読んで、ガツンとやられた気分です。
私が思いもしなかったことばかりで、そう感じる方もいらっしゃるのだととても新鮮でした。
そしてなにより素通堂さんが真剣に向き合って書いてくださったことが伝わる書評で、嬉しく思います。ありがとうございました。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - 素通堂2015-03-26 00:51
はにぃさん、コメントありがとうございます。
そして大好きな作品を悪く言うレビューを書いたこと、本当に申し訳ありません。
言いすぎかとも思いましたが、むしろそうすることがこの作品の熱さに対する礼儀であること、きっと体育系の方々にはわかってもらえるんじゃないかと。
色々暴言を吐きましたが、読んでよかったです。多くの方がこの作品を読んでみて、「俺も嫌いだ」「いや、俺は好きだ」「まあまあ、そう熱くならずに…」なんて盛り上がってくれればいいなあと思っています。
ご推薦いただき、ありがとうございました!
P.S.
回復されてまた戻ってこられること、蔭ながらお祈りしています。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
- 出版社:角川書店(角川グループパブリッシング)
- ページ数:580
- ISBN:9784041103425
- 発売日:2013年03月01日
- 価格:1890円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。