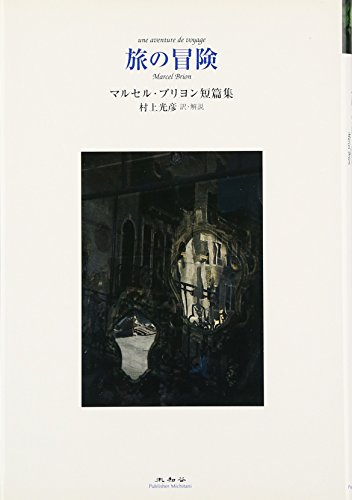hackerさん
レビュアー:
▼
「アイルランド系の父と南仏に先祖を持つ母の間にマルセイユで生まれ、ラテン的知性とゲルマン的感性の対話の中に育つ」と作者略歴で紹介されているマルセル・ブリヨン(1895ー1984)の幻想小説集です。
ぱせりさんの書評で、この本のことを知りました。感謝いたします。
実は、この作家を読むのは初めてですが、仏語版の Wikipedia では「小説家、エッセイスト、文学評論家、仏美術史の評論家」という順番で冒頭で紹介されており、専門はイタリア・ルネッサンスとドイツ・ロマン派ということで、相当の知識人だったことをうかがわせます。本書には中短編集『深更の途中下車地』(1942年)から訳者村上光彦が選んだ五つの幻想小説が収められていますが、これらを読んでも感じることができます。
しかし、なんと幻想小説然とした作品ばかりなのでしょう。村上光彦は、ブリヨンの幻想小説を「無意識の底から噴出してくる心像のあとを追いながら、心の目に映る光景をそのまま写してゆく」と評したそうですが、それゆえ当然ながら、分かりやすい小説ではありません。まぁ、このジャンルにそんなことを求めてはいけないのでしょう。私が読んでいて、連想したのは映画監督タルコフスキーの水と火の世界です。本書収録作品にも、この二つはよく登場し、火はいうまでもなく破壊、水は生でもあり死でもある象徴なのでしょうが、タルコフスキー同様「無意識の底から噴出してくる心像のあと」を追っていると、なにかそれに系統だった答えを探ろうとしても無駄なのかもしれません。
そんな中で、特に印象に残ったのは、やはり『深更の途中下車地』です。
この作品は、「旅の目的地などどうでもよくなって」降り立った「私」が訪れた町の話です。その町の建物は正面しかなく、つまり映画のセットのように正面の後ろはがらんどうであり、泊ろうとしたホテルの部屋は地下にあるので、息苦しくなった「私」は深夜の町に散歩に出て、妙に体を密着してくる足の悪い女の子と、この町に囚われていついてしまった男と出会います。男は「私」に向かって、こんなことを言います。
「正面しかない町は正面なき町なのです」
この町のイメージは、明らかに墓場で、つまり「正面しかない」というのは墓石のことでしょうから、ホテルの部屋が地下にしかないのも当然なのです。
それが同時に「正面なき」であるのは、原文を確認していないので間違えていたらゴメンナサイなのですが、仏語の「正面」 face は、もちろん英語の「顔」なわけで、墓石にそんなものはないのです。
更に、本作の後半部分では水が再生と死のシンボルとして登場し、この作品に関しては、イメージを頭の中で作りやすい作品に仕上がっているのです。
さて、他の四作(『恐怖の元帥』『火のソナタ』『旅の冒険』『なくなった通り』)については、個別に語ることはしませんが、いずれも死と破壊(戦争や火)の匂いが濃厚であることは否定できません。もちろん、生のイメージも登場しますが、どちらかと言えば、死と破壊に負けています。ですから全体の印象としては明るくはありませんが、明るい、暗いというのは、ポジティブ、ネガティブの問題ではなく、スタイルの差ですから、それでどうこう言うつもりはありません。そういう意味では、いかにも、この作家らしい小説を選んだ短編集だと思います。
実は、この作家を読むのは初めてですが、仏語版の Wikipedia では「小説家、エッセイスト、文学評論家、仏美術史の評論家」という順番で冒頭で紹介されており、専門はイタリア・ルネッサンスとドイツ・ロマン派ということで、相当の知識人だったことをうかがわせます。本書には中短編集『深更の途中下車地』(1942年)から訳者村上光彦が選んだ五つの幻想小説が収められていますが、これらを読んでも感じることができます。
しかし、なんと幻想小説然とした作品ばかりなのでしょう。村上光彦は、ブリヨンの幻想小説を「無意識の底から噴出してくる心像のあとを追いながら、心の目に映る光景をそのまま写してゆく」と評したそうですが、それゆえ当然ながら、分かりやすい小説ではありません。まぁ、このジャンルにそんなことを求めてはいけないのでしょう。私が読んでいて、連想したのは映画監督タルコフスキーの水と火の世界です。本書収録作品にも、この二つはよく登場し、火はいうまでもなく破壊、水は生でもあり死でもある象徴なのでしょうが、タルコフスキー同様「無意識の底から噴出してくる心像のあと」を追っていると、なにかそれに系統だった答えを探ろうとしても無駄なのかもしれません。
そんな中で、特に印象に残ったのは、やはり『深更の途中下車地』です。
この作品は、「旅の目的地などどうでもよくなって」降り立った「私」が訪れた町の話です。その町の建物は正面しかなく、つまり映画のセットのように正面の後ろはがらんどうであり、泊ろうとしたホテルの部屋は地下にあるので、息苦しくなった「私」は深夜の町に散歩に出て、妙に体を密着してくる足の悪い女の子と、この町に囚われていついてしまった男と出会います。男は「私」に向かって、こんなことを言います。
「正面しかない町は正面なき町なのです」
この町のイメージは、明らかに墓場で、つまり「正面しかない」というのは墓石のことでしょうから、ホテルの部屋が地下にしかないのも当然なのです。
それが同時に「正面なき」であるのは、原文を確認していないので間違えていたらゴメンナサイなのですが、仏語の「正面」 face は、もちろん英語の「顔」なわけで、墓石にそんなものはないのです。
更に、本作の後半部分では水が再生と死のシンボルとして登場し、この作品に関しては、イメージを頭の中で作りやすい作品に仕上がっているのです。
さて、他の四作(『恐怖の元帥』『火のソナタ』『旅の冒険』『なくなった通り』)については、個別に語ることはしませんが、いずれも死と破壊(戦争や火)の匂いが濃厚であることは否定できません。もちろん、生のイメージも登場しますが、どちらかと言えば、死と破壊に負けています。ですから全体の印象としては明るくはありませんが、明るい、暗いというのは、ポジティブ、ネガティブの問題ではなく、スタイルの差ですから、それでどうこう言うつもりはありません。そういう意味では、いかにも、この作家らしい小説を選んだ短編集だと思います。
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:未知谷
- ページ数:187
- ISBN:9784896423433
- 発売日:2011年05月01日
- 価格:2100円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。