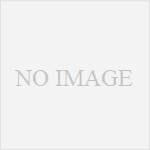というわけでなぎ倒されるバトルドロイドみたいになりたくなかったら←なん(ry、そう闇雲に人のことを悪く思わないように心掛けることだが、いったん出来てしまった湿地帯はそう簡単に干上がるものではない。こうなったらもう胃薬を飲んでも収まらない胃痛・胃もたれと付き合うように、イライラしながら世間と付き合うハメと相成る。人が嫌いということは自分が嫌い、自分が嫌いということは自然自分を守りつつ縛る世間の”宗教”(=常識・慣習)というものから遊離するということになりやすく、そういった人は他のタイプの人より簡単に”どこか”へ行ってしまう。それは無鉄砲とか蛮勇とかではない。ただ世間との絆の淡泊が故である。
さて、物語は「私」と「先生」との出会いに始まる。大学生である「私」は浮世離れした雰囲気を纏わせる「先生」に惹かれ、現代ならば”ちょっとウザいんじゃないの?”と言われかねない接触を重ね、自宅に招かれるほどの知友となる。そんな「先生」とはどのような人か。
ある程度財産があるようで、仕事に就かず悠々自適な生活をしているようだ。静(しづ)という名の細君がいるようだ。かつての学友などごく限られた人間関係しか築いていないようだ。他者にたいして冷淡なわけではないが淡泊であるらしい。そもそも人間というものをあまり好いてはいないし、なにより自分自身を好いていないようだ。月に決まった日、知人の墓に参っているが、未だかつて誰をも同道させたことはないという。
「先生」の漏らす言葉の端々からその人物像を推測する「私」だが、やはりその全体像は掴めない。そうこうしているうちに大学を卒業した。故郷の父が危篤となって帰郷した。だが父の前に「先生」が死んだ。自殺であった。「先生」から遺書が届いた。
「私」が経験する物語は、粗筋としてはそれだけである。物語全体は『上・中・下』の三部に分かれているが、『上』は二人の出会いと親交を深めた顛末、『中』は父危篤の報に帰郷した「私」の人間社会でのしがらみを描き、『下』は自死を遂げた「先生」による遺書が綴られる。
それによれば「先生」は本来資産家の家に生まれたが幼くして両親が相次いで亡くなった。財産の管理を託された叔父は誠実そうな顔の裏で両親の財産を食い物にしていたのが発覚し、以来叔父を始めとする親族とは断絶し、郷里には二度と戻らないと誓ったのだった。そして取り返せる限りの財産を手に東京で下宿を借り、ひとり勉学に励んでいたのだった。彼にとって信頼を裏切った叔父を始めとする”人間”は、いつなにをするかわからない卑しい存在でしかないのだった。
そんな「先生」にも「K」という友人がいた。「K」は寺の次男坊であるが医師の家に養子にやられ、医師になることを期待されていた。しかし高い志と我の強さを持つKは養家に内密で自分が学びたい勉学に打ち込み、やがてそのことを告白してほぼ勘当に近い扱いを受ける。「K」の克己的・禁欲的な姿勢に惹かれる「先生」はこの親友を援助すべく自らと同じ下宿に呼び寄せ、寝食を共にするのだった。
この時の「先生」は「K」に対して「私」を彷彿とさせるようなお節介を焼いている。良く言えば禁欲的、悪く言えば人間味に欠ける頑なさを持つ「K」の心を解きほぐすべく、「先生」は様々の気遣いを以て自分や下宿の主人―軍人の未亡人である「奥さん」と「御嬢さん」―との関係に交わらせようと努める。しかしそれは思わぬ誤算を招く。「先生」が秘かに思いを寄せていた「御嬢さん」に、「K」もまた恋愛感情を抱いてしまったのだ。
このときの「先生」には、「K」の資質への尊敬はありながらもやはりどこかで彼を見くびっていたのではないか。彼は所詮人間味には疎い堅物であり、自分の恋のライバルになどはなり得ない男。無害な男。この時期の「先生」の「K」への配慮には、どこか”後輩の面倒を見てやる先輩”のような驕り、とまで言っては残酷だが、一種の不用意さがあったような気はする。しかしそれは「先生」の「K」への求愛―恋や愛というような一面的な意味ではなく人間として人間を乞うような―の感情があったようにも思える。それは『上』で異様なまでに「先生」に接近を図ろうとする「私」と共通するもののようにも思える。ただ傍から見ればその姿は紛うことなき”俗物”ではないか。
だが「K」の恋愛の自白に及んで急遽「K」は「先生」の利害を脅かす”敵”となった。このときの「先生」の驚愕は”飼い犬に手を噛まれた”などと言ってはまたも残酷だが、意想外の衝撃を受けて只ならぬ焦りに憑りつかれる。このままでは「K」に「御嬢さん」を取られてしまう・・・。思い余った「先生」はもともと自分を良く思っていた「奥さん」に「御嬢さん」との結婚を申し込み、すんなりと許可される。ここに「先生」は「K」から「御嬢さん」を”掠め取る”ことに成功した。
「K」はそんな「先生」を責めもしなければ恨みがましい態度も取らなかった。ただ黙って自殺した。遺書に記された理由は、”意志弱行ゆえ将来を悲観して”だった。「K」の死は「先生」の心のなかに永劫消えない陰となって付き纏うことになった。
さて、「K」は何故死んだのだろう。一般に自死の理由は”絶望”だろうか。では何に対する。恋に破れた絶望?親友に騙された絶望? しかし「先生」はその理由を
たった一人で淋しくって仕方がなくなった結果、急に所決したのではなかろうかと思うに至る。孤独の絶望。まるで自分のように。
「K」の克己的にして禁欲的な日頃の所作は俗世に対する軽蔑から生まれたものではないか。そしてそんな「K」にとって、人間との最後の絆が「御嬢さん」だったのではないか。「K」は「御嬢さん」と共にいるときは、人間としての歓喜を感じることができたのではないか。しかし最愛の「御嬢さん」は同じく親友である「先生」のものとなってしまった。この世と繋がる最後の絆が切れた・・・。ということなのかもしれない。
そこに思い至ったとき、「先生」は自分があれほど軽蔑していた叔父を始めとする人間たちと同類―俗物―でしかなかったということを痛感させられた。
叔父に欺かれた当時の私は、他の頼みにならない事をつくづくと感じたには相違ありませんが、他を悪く取るだけあった、自分はまだ確かな気がしていました。世間はどうあろうともこの己は立派な人間だという信念が何処かにあったのです。それがKのために美事に破壊されてしまって、自分もあの叔父と同じ人間だと意識した時、私は急にふらふらしました。他に愛想を尽かした私は、自分にも愛想を尽かして動けなくなったのです。
自分を信頼する甥から財産を掠め取った叔父と、信頼する「K」から「御嬢さん」を掠め取った自分はどこがどう違うのか。腐臭に塗れた俗物と決めてかかっていた人間たちと、自分も同じ臭いを放っているではないか。「先生」のアイデンティティである”自分は周囲よりはマシな人間である”というささやかな矜持は木端微塵に打ち砕かれる。しかも世間との絆の切れたことを知るや否や死を選び得た「K」と異なり、自らの存在理由を失くしても尚、「先生」は死を選ぶことはなかった。
「死にたくない」というのは人間にとってのあらゆる”宗教”を凌駕する、唯一の宗教以外のモノ、「本能」ではないか。自らを律する宗教を失った「先生」は、本能によって辛うじて生きていた。しかしそれは常に自らの宗教に責め苛まれながらの生ではなかったか。有体に言えば”生きているべき理由もないのに思いきることができなくてズルズルと生きている”のではなかったか。人間を軽蔑し、社会を軽蔑し、なによりも自分自身を軽蔑し、それでも尚生きている。あらゆるものの臭いに顔を顰めながら、誰よりも自分自身が最も酷い臭いを放っている。それでも尚、死ぬ決心がつかない。書物にも酒にも溺れることの出来ない、観念の生き地獄。
そんな折に訪れた明治天皇の崩御、つづく乃木大将の殉死。壮大な”宗教”の物語を目の当たりにさせられて”死”というものと向かい合わせられたのはなにも「先生」ばかりではない。『中』に登場する、人間社会の因習を体現するかのような「私」の父もまた、病床にあってこの物語に心を震わせている。
一般によく言い習わされる「明治の精神の死」。正直言ってこの言葉に明確な実感は湧かないし、どういう意味なの?と質問されても曖昧な苦笑いしかできないであろう。だがこの壮大な死の物語によって改めて「先生」は”死”と向かい合う。しかも乃木大将は西南戦争の際の軍旗喪失の責任に苛まれて以来、合計三十五年もの屈託を抱えた後の死であるという。それが事実であるかどうかは問題ではない。ひとつの巨大なものの死によって引き寄せられる死。目の前で展開したその物語に”呼ばれて”、「先生」もまた引き寄せられたのではないか。「私」の父もまた―本編中ではまだ死は遂げていないが―引き寄せられた一人ではないか。明治天皇の死と乃木大将の殉死という”スペクタクル”は、日本人すべてに「死」というものを見つめさせたのではないか。「先生」も乃木と同じく”死に時”を見出したのではないか。
私が本書を読んでいて引き込まれたのは、どういうわけだか現世を生き続けていた、本来とうの昔に死んでいったはずの男の、危うい彷徨の足取りであった。
【追記】
『下』の「先生と遺書」のことばかり書いたが、『中』に展開する「両親と私」も人間を守りつつ縛る昏い因習が抜けきらない田舎の町で人間関係と世間体の鎖を纏わりつかせる「私」の姿は濃度の差こそあれ今も昔も泥沼の中で足掻かざるを得ない、我々の姿である。
「小供に学問をさせるのも、好し悪しだね。折角修行をさせると、その小供は決して宅(うち)へ帰って来ない。これじゃ手もなく親子を隔離させるために学問させるようなものだ」
”宅”とはすなわち故郷ではないか。学問によって”宗教”から自由になってしまった人間には、”故郷”が是が非でも帰りたい場所かどうかは、確かに疑問である。





読書とスター・ウォーズをこよなく愛するもと本嫌いの本読みが知識もないのに好き放題にくっちゃべります。バルバルス(barbarus)とは野蛮人の意。
周りを見渡すばかりで足踏みばかりの毎日だから、シュミの世界でぐらいは先も見ずに飛びたいの・・・。というわけで個人ブログもやり始めました。
Gar〈ガー〉名義でSW専門ブログもあり。なんだかこっちの方が盛況・・・。ちなみにその名の由来h…(ry
この書評へのコメント
- magamin10292018-04-05 21:02
本当にすばらしい洞察だと思いました。坂口安吾がどこかで、こころの先生が20年もたって自殺して「奇想天外」だと書いていましたが、私もその通りだと確信していたのですが。いくつか夏目漱石論も読んだのですが、どうもピンと来なかった。barbarusさんのこの評論は全く新しいと思うと同時に、感情移入というのは簡単ではないということを再認識しました。
クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - ごみら2021-10-03 15:36
barbarusさん、面白いです!
力作ですね!
丁寧に読まれたのだなぁと思いました。
そしてなるべく正直にお考えやお気持ちを表されたと思います。
面白かったです。
凄いですね。
先生のKに対する気持ちが、侮りや上から目線、しかし求愛であったという点にも共感しました。
何となく感じていたものを言葉にされたと思いました。
人間が嫌い自分が嫌いだと、またさらにドツボにはまっていく、永遠のループですよね。
夏目漱石は自分の気持や世界観をどこまでも正確に表現したと思います。
だからこそ、こんなに暗くて、心理的に気持ち悪くもなるのだと思います。
正直ですよね。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - ごみら2021-10-04 09:09
>noelさん
他の人のコメント欄でこんなやり取りするのも変なものですが(笑)。
barbarusさんの少し漢語調な文体は、やはり読み応えのある本を沢山読んでこられた証なのだろうなと思います。
私淑したいです。
おどけるのも堂に入っていて、仙人レベルだと思います。
でもNoelさんの文章も素晴らしいです。
流れる水のようにスイスイ入ってきます。
「偏屈」だというような事を、どこかで仰っていましたが、全然そんなことないと思います。
まだコメントして無いですが、noelさんの「こころ」のレビューも、面白く拝読いたしました。
何かnoelさんの後ろめたさや自虐を感じてしまいました(笑)。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
- 出版社:岩波書店
- ページ数:300
- ISBN:9784003101117
- 発売日:1989年05月01日
- 価格:483円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。