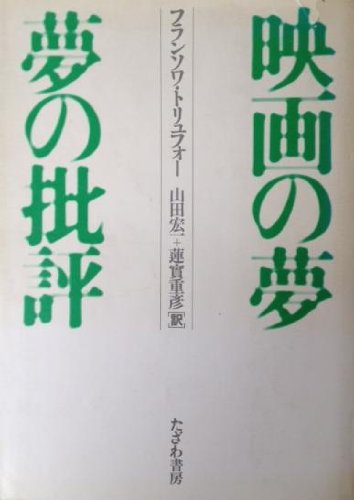hackerさん
レビュアー:
▼
まずお断りしておきますが、この拙文で語るのはチャップリンの偉大な映画『独裁者』(1940年)と、それについてのトリュフォーの感動的な批評だけです。本書収録の他の批評や、他の映画の内容には触れません。
本書は、映画監督フランソワ・トリュフォーの映画評を収録したものです。こういう本は、取り上げられている映画一本一本について書いていくと際限がないので、何度も読んだ本ではありますが、今までこのサイトで紹介したことはありません。しかし、ロシアのウクライナ侵略を受けて、チャップリンの『独裁者』をDVDで再見し、その凄さ、チャップリンの偉大さに、あらためて感じ入りましたので、この映画と、それについてのトリュフォーの感動的な批評に限って語ってみたいと思います。
チャップリンが監督・脚本・主演をした、原題は "The Great Dictator' のこの映画の内容は、ヒトラーを徹底的におちょくった風刺映画と捉えられがちですが、それだけでなく、ヒトラーの恐ろしさもしっかり語った映画でもあります。この映画の製作と公開の背景については、トリュフォーは次のように述べています。
「1938年(チャップリンは)『独裁者』のシナリオを書き、その映画化の準備に入った。しかし、それからずっと、一年間も、チャップリンに対してこの映画を撮ることを阻止するためにあらゆる働きかけがおこなわれた。ドイツの外交官たちや、いくつかのアメリカの組織がチャップリンに圧力をかけた。1940年の春になって、やっと映画が完成したが、上映されたのはそれから半年後のことであった」
この間のナチス・ドイツの動きについてまとめると、以下のようになります。
1938年
3月 オーストリア併合
9月 ミュンヘン会談によりチェコスロバキアのズデーデン地方を併合
11月 ユダヤ人居住地区やシナゴーグが襲われ放火された水晶の夜事件
1939年
3月 チェコスロバキア併合
8月 独ソ不可侵条約締結
9月 ポーランドに侵攻し、英仏両国が宣戦布告して第二次世界大戦勃発
1940年
4月 ノルウェー、デンマークに侵攻
5月 両国を実質支配下に置く
ルクセンブルグ併合、オランダとベルギー降伏
6月 フランスが休戦という名の降伏を選択し、ヴィシー政府樹立
9月 日独伊三国同盟成立
こうやって振り返ると、あらためてナチス・ドイツがなしくずし的に領土を拡張していき、最後に第二次大戦に至ったことが、よく分かります。先日、橋下徹がウクライナ出身の政治学者相手に、ウクライナは一旦引き下がったらどうかという主旨の発言をして口論となりましたが、ヨーロッパのこういう歴史が頭に入っていれば、ヒトラーやプーチンのような独裁者相手に安易な妥協はできないということは理解できるはずです。
さて、トリュフォーは、この映画の公開が遅れた理由は、チャップリンが1940年に非米活動調査委員会に召喚されたことが影響しているのではないかと考えているようです。チャップリンが共産主義者ではないかという疑いが当時は強かったのは事実です。後にチャップリンは1952年にヨーロッパに出かけた際、再入国を拒否され、1972年にアカデミー特別賞受賞のために帰国するまでアメリカの土を踏むことはありませんでした。
物語は、あからさまにヒトラーである独裁者ヒンケルと、ユダヤ人の床屋(名前は与えられていません)が、瓜二つという前提で、抑圧する側と抑圧される側を並行して描きながら、最後には二人の入れ替わりが起こり、大勢の兵隊の前でチャップリンが行う、おそらく映画史上最も有名な演説のシーンで終るというものです。この二つの世界について、トリュフォーはこう述べています。
「ひとつはヒンケル(ヒトラー)の宮殿、もう一つはユダヤ人のゲットーである。自分の生命があぶないときには、とても客観的にはなれないものだが、にもかかわらず、できるかぎりの客観性をもって、チャップリンは、二つの世界を対比させて描いてみせる。どちらの世界も滑稽には描いているが、前者は苛烈に容赦なく、後者はやさしさをこめて、しかも、人種的な真実をしっかりとふまえたうえで描く。ユダヤ人のゲットーのシーンは、まるですべるようにスムーズで、いたずらっぽく、狡猾で逃げ足が早く、ほとんど踊っているような感じだ。それに反して、ヒトラーの宮殿のシーンは、自動装置で動かされているかのように、せかせかしていて、断続的で、滑稽で、ばかばかしいぐらいに狂っている。被害者たちには狂おしいほどすさまじい生への渇望がある。彼らは、卑怯すれすれのぶざまさを見せながらも、機略を奔し、才智の限りをつくして生きのびようとする(たとえば、ケーキのなかに隠されたコインに当たった者が総統暗殺をひきうけることが決められたときに、だれもが難をまぬがれようとしてズルをする地下室のシーン)。加害者たちには愚劣としか言いようのない狂信的興奮があるだけだ」
映画の中で「裏切者!」「言論の自由なんかいらない!」と怒鳴り、約束は平気で反故にするヒンケルの姿は、ヒトラーだけでなく、プーチンを連想させることは言うまでもないでしょう。
そして、映画のラストは、チャップリンの有名な演説となります。全文を紹介します。翻訳は、以下のサイトから引用しました。なお、そちらでは、英語の原文も掲載されていますので、興味のある方はご覧ください。
https://ameblo.jp/sho5g0/entry-12169440550.html
「申し訳ないが、私は皇帝などなりたくない。それは私には関わりのないことだ。誰も支配も征服もしたくない。できることなら皆を助けたい、ユダヤ人も、ユダヤ人以外も、黒人も、白人も。
私たちは皆、助け合いたいのだ。人間とはそういうものなんだ。私たちは皆、他人の不幸ではなく、お互いの幸福と寄り添って生きたいのだ。私たちは憎み合ったり、見下し合ったりなどしたくないのだ。
この世界には、全人類が暮らせるだけの場所があり、大地は豊かで、皆に恵みを与えてくれる。人生の生き方は自由で美しい。しかし、私たちは生き方を見失ってしまった。強欲が人の魂を毒し、憎しみと共に世界を閉鎖し、不幸、惨劇へと私たちを行進させた。
私たちはスピードを開発したが、それによって自分自身を孤立させた。ゆとりを与えてくれる機械により、貧困を作り上げた。
知識は私たちを皮肉にし、知恵は私たちを冷たく、薄情にした。私たちは考え過ぎで、感じなさ過ぎる。機械よりも、私たちには人類愛が必要なのだ。賢さよりも、優しさや思いやりが必要なのだ。そういう感情なしには、世の中は暴力で満ち、全てが失われてしまう。
飛行機やラジオが私たちの距離を縮めてくれた。そんな発明の本質は人間の良心に呼びかけ、世界がひとつになることを呼びかける。
今も、私の声は世界中の何百万人もの人々のもとに、絶望した男性達、女性達、子供達、罪のない人達を拷問し、投獄する組織の犠牲者のもとに届いている。
私の声が聞こえる人達に言う、『絶望してはいけない』。 私たちに覆いかぶさっている不幸は、単に過ぎ去る強欲であり、人間の進歩を恐れる者の嫌悪なのだ。 憎しみは消え去り、独裁者たちは死に絶え、人々から奪いとられた権力は、人々のもとに返されるだろう。 決して人間が永遠には生きることがないように、自由も滅びることもない。
兵士たちよ。 獣たちに身を託してはいけない。君たちを見下し、奴隷にし、人生を操る者たちは、君たちが何をし、何を考え、何を感じるかを指図し、そして、君たちを仕込み、食べ物を制限する者たちは、君たちを家畜として、単なるコマとして扱うのだ。
そんな自然に反する者たち、機械のマインド、機械の心を持った機械人間たちに、身を託してはいけない。君たちは機械じゃない。君たちは家畜じゃない。君たちは人間だ。君たちは心に人類愛を持った人間だ。憎んではいけない。愛されない者だけが憎むのだ。愛されず、自然に反する者だけだ。君たち、人々は、機械を作り上げる力、幸福を作り上げる力があるんだ。君たち、人々は人生を自由に、美しいものに、この人生を素晴らしい冒険にする力を持っているんだ。
兵士よ。奴隷を作るために闘うな。自由のために闘え。『ルカによる福音書』の17章に、「神の国は人間の中にある」と書かれている。一人の人間ではなく、一部の人間でもなく、全ての人間の中なのだ。君たちの中になんだ。
だから、民主国家の名のもとに、その力を使おうではないか。皆でひとつになろう。新しい世界のために、皆が雇用の機会を与えられる、君たちが未来を与えられる、老後に安定を与えてくれる、常識のある世界のために闘おう。
そんな約束をしながら獣たちも権力を伸ばしてきたが、奴らは嘘をつく。約束を果たさない。これからも果たしはしないだろう。独裁者たちは自分たちを自由し、人々を奴隷にする。
今こそ、約束を実現させるために闘おう。世界を自由にするために、国境のバリアを失くすために、憎しみと耐え切れない苦しみと一緒に貪欲を失くすために闘おう。
理性のある世界のために、科学と進歩が全人類の幸福へと導いてくれる世界のために闘おう。兵士たちよ。民主国家の名のもとに、皆でひとつになろう」
この演説について、トリュフォーは次のように書いています。
「(トリュフォーの育ての親である批評家)アンドレ・バザンは、チャップリンの全作品中、最も重要なキー・ポイントが、この『独裁者』のラストの演説のシーンにあることに着目した。というのも、このシーンでは、あのチャーリーの<顔>がしだいに消えていき、そのかわり、メークアップをまったくしていない―すでにびんに白髪のまじった―チャールズ・チャップリンそのひとの顔があらわれてくるからだ。彼は世界に向かって希望のメッセージを投げかけ、福音書と神の言葉を読みあげる―明らかに虐げられた民族が救世主的な夢の実現のなかにこそ幸福を見出そうとしている姿が、そこにある。この映画は彼自身の顔でなく、ポーレット・ゴダード(チャップリンの当時の妻)の顔で終わる。チャップリンはポーレット・ゴダードの役名にハンナ(Hannah)という彼の実の母親の名を付けたのだった。 Hannah には、パランドロミックな(つまり逆から読んでも同じ意味になる)名前であり、まさしく、この名にこの映画の精神が見事に要約されている―というのもヒンケルはさかさまにしたユダヤ人の床屋にほかならぬからだ。チャップリンは、この長い演説の最後に、『ハンナ....』と母親の名に呼びかけるのである。そのとき、スクリーンには、地べたに泣き伏しているポーレット・ゴダードの姿が崇高な美しさに彩られて移される。彼女は面をもたげ、チャップリンの呼びかけに耳を傾ける―『見上げてごらん、ハンナ。空のほうを見てごらん、ハンナ。聞こえるかい?聞いておくれ!』」
ああ、なんという、偉大な映画作家と偉大な映画に対する尊敬が込められた文章なのでしょう。映画を観た後のトリュフォーの受けた感動が、そのまま伝わってきます。優れた芸術作品を称賛する時には、こういう文章を書きたいものです。
なお、トリュフォーがこの批評を書いたのは1957年、『独裁者』がリバイバル上映された時です。また、この批評の冒頭の方には、次のような記述もあります。
「年月とともにチャップリンの映画は<古びた>か否か?ばかげた問いかけだ。そう、もちろん、古びるのが当然だ、としか答えようがないではないか。『独裁者』が古びたのは、たしかである。そして、それは幸福なことだ。新聞の政治欄の論説のように、エミール・ゾラの『私は弾劾する』のように、時事問題をめぐる記者会見のように、この映画は古びたのであって、その結果、『独裁者』はすばらしい記録となり、貴重な資料となり、時代の証言として役立つ物件となると同時に、時代を超えた純粋な芸術作品として、あらためて、その姿を現したのである」
真の傑作に時の試練が関係ないことは、ギリシャ悲劇やシェイクスピアには、トリュフォーが言うように<古びている>にもかかわらず、誰も<古びている>という言葉を使わないことを思えば明らかだと思うのですが、映画の場合、リュミエール兄弟による世界最初の商業映画が公開されたのが1895年ですから、誕生からたかだか120年ちょっとしか経っていないわけで、<古びている>間もまだ与えられていないと個人的には思っています。それは、無声映画時代の傑作群、ムルナウの『吸血鬼ノスフェラトゥ』(1922年)、ラングの『ドクトル・マブゼ』(1922年)と『二―ベルゲン』(1924年)、シュトロハイムの『グリード』(1924年)、エイゼンシュテインの『戦艦ポチョムキン』(1925年)、ドライヤーの『裁かるるジャンヌ』(1928年)を観れば分かることです。
そして、この中には、もちろんチャップリンの『黄金狂時代』(1925年)も入ります。実は、チャップリンの真の傑作は『黄金狂時代』と『街の灯』(1931年)だと私は思っていますが、『独裁者』は、別の意味で、偉大なチャップリンが作った偉大な映画であることには変わりありません。
つい長々と書いてしまいました。最後になりますが、『独裁者』を未見の方、YouTube では、本作のチャップリンの演説だけ見ることができるようですが、それは止めてください。頭から観ても、終わりから観ても、真ん中から観てもいいような映画ではありません。映画に限らず、偉大な芸術作品に接する時は襟を正すべし、というのが私の考えです。<古びて>いても最後まで無声映画の芸にこだわったチャップリンの意地、独裁者の本質を笑いに閉じこめながら語る部分があってこそ、最後の生涯初の長い演説が活きるのですから。『独裁者』を観る時は、どうか最初から観てください。年老いた映画ファンからの、わがままなお願いでした。
チャップリンが監督・脚本・主演をした、原題は "The Great Dictator' のこの映画の内容は、ヒトラーを徹底的におちょくった風刺映画と捉えられがちですが、それだけでなく、ヒトラーの恐ろしさもしっかり語った映画でもあります。この映画の製作と公開の背景については、トリュフォーは次のように述べています。
「1938年(チャップリンは)『独裁者』のシナリオを書き、その映画化の準備に入った。しかし、それからずっと、一年間も、チャップリンに対してこの映画を撮ることを阻止するためにあらゆる働きかけがおこなわれた。ドイツの外交官たちや、いくつかのアメリカの組織がチャップリンに圧力をかけた。1940年の春になって、やっと映画が完成したが、上映されたのはそれから半年後のことであった」
この間のナチス・ドイツの動きについてまとめると、以下のようになります。
1938年
3月 オーストリア併合
9月 ミュンヘン会談によりチェコスロバキアのズデーデン地方を併合
11月 ユダヤ人居住地区やシナゴーグが襲われ放火された水晶の夜事件
1939年
3月 チェコスロバキア併合
8月 独ソ不可侵条約締結
9月 ポーランドに侵攻し、英仏両国が宣戦布告して第二次世界大戦勃発
1940年
4月 ノルウェー、デンマークに侵攻
5月 両国を実質支配下に置く
ルクセンブルグ併合、オランダとベルギー降伏
6月 フランスが休戦という名の降伏を選択し、ヴィシー政府樹立
9月 日独伊三国同盟成立
こうやって振り返ると、あらためてナチス・ドイツがなしくずし的に領土を拡張していき、最後に第二次大戦に至ったことが、よく分かります。先日、橋下徹がウクライナ出身の政治学者相手に、ウクライナは一旦引き下がったらどうかという主旨の発言をして口論となりましたが、ヨーロッパのこういう歴史が頭に入っていれば、ヒトラーやプーチンのような独裁者相手に安易な妥協はできないということは理解できるはずです。
さて、トリュフォーは、この映画の公開が遅れた理由は、チャップリンが1940年に非米活動調査委員会に召喚されたことが影響しているのではないかと考えているようです。チャップリンが共産主義者ではないかという疑いが当時は強かったのは事実です。後にチャップリンは1952年にヨーロッパに出かけた際、再入国を拒否され、1972年にアカデミー特別賞受賞のために帰国するまでアメリカの土を踏むことはありませんでした。
物語は、あからさまにヒトラーである独裁者ヒンケルと、ユダヤ人の床屋(名前は与えられていません)が、瓜二つという前提で、抑圧する側と抑圧される側を並行して描きながら、最後には二人の入れ替わりが起こり、大勢の兵隊の前でチャップリンが行う、おそらく映画史上最も有名な演説のシーンで終るというものです。この二つの世界について、トリュフォーはこう述べています。
「ひとつはヒンケル(ヒトラー)の宮殿、もう一つはユダヤ人のゲットーである。自分の生命があぶないときには、とても客観的にはなれないものだが、にもかかわらず、できるかぎりの客観性をもって、チャップリンは、二つの世界を対比させて描いてみせる。どちらの世界も滑稽には描いているが、前者は苛烈に容赦なく、後者はやさしさをこめて、しかも、人種的な真実をしっかりとふまえたうえで描く。ユダヤ人のゲットーのシーンは、まるですべるようにスムーズで、いたずらっぽく、狡猾で逃げ足が早く、ほとんど踊っているような感じだ。それに反して、ヒトラーの宮殿のシーンは、自動装置で動かされているかのように、せかせかしていて、断続的で、滑稽で、ばかばかしいぐらいに狂っている。被害者たちには狂おしいほどすさまじい生への渇望がある。彼らは、卑怯すれすれのぶざまさを見せながらも、機略を奔し、才智の限りをつくして生きのびようとする(たとえば、ケーキのなかに隠されたコインに当たった者が総統暗殺をひきうけることが決められたときに、だれもが難をまぬがれようとしてズルをする地下室のシーン)。加害者たちには愚劣としか言いようのない狂信的興奮があるだけだ」
映画の中で「裏切者!」「言論の自由なんかいらない!」と怒鳴り、約束は平気で反故にするヒンケルの姿は、ヒトラーだけでなく、プーチンを連想させることは言うまでもないでしょう。
そして、映画のラストは、チャップリンの有名な演説となります。全文を紹介します。翻訳は、以下のサイトから引用しました。なお、そちらでは、英語の原文も掲載されていますので、興味のある方はご覧ください。
https://ameblo.jp/sho5g0/entry-12169440550.html
「申し訳ないが、私は皇帝などなりたくない。それは私には関わりのないことだ。誰も支配も征服もしたくない。できることなら皆を助けたい、ユダヤ人も、ユダヤ人以外も、黒人も、白人も。
私たちは皆、助け合いたいのだ。人間とはそういうものなんだ。私たちは皆、他人の不幸ではなく、お互いの幸福と寄り添って生きたいのだ。私たちは憎み合ったり、見下し合ったりなどしたくないのだ。
この世界には、全人類が暮らせるだけの場所があり、大地は豊かで、皆に恵みを与えてくれる。人生の生き方は自由で美しい。しかし、私たちは生き方を見失ってしまった。強欲が人の魂を毒し、憎しみと共に世界を閉鎖し、不幸、惨劇へと私たちを行進させた。
私たちはスピードを開発したが、それによって自分自身を孤立させた。ゆとりを与えてくれる機械により、貧困を作り上げた。
知識は私たちを皮肉にし、知恵は私たちを冷たく、薄情にした。私たちは考え過ぎで、感じなさ過ぎる。機械よりも、私たちには人類愛が必要なのだ。賢さよりも、優しさや思いやりが必要なのだ。そういう感情なしには、世の中は暴力で満ち、全てが失われてしまう。
飛行機やラジオが私たちの距離を縮めてくれた。そんな発明の本質は人間の良心に呼びかけ、世界がひとつになることを呼びかける。
今も、私の声は世界中の何百万人もの人々のもとに、絶望した男性達、女性達、子供達、罪のない人達を拷問し、投獄する組織の犠牲者のもとに届いている。
私の声が聞こえる人達に言う、『絶望してはいけない』。 私たちに覆いかぶさっている不幸は、単に過ぎ去る強欲であり、人間の進歩を恐れる者の嫌悪なのだ。 憎しみは消え去り、独裁者たちは死に絶え、人々から奪いとられた権力は、人々のもとに返されるだろう。 決して人間が永遠には生きることがないように、自由も滅びることもない。
兵士たちよ。 獣たちに身を託してはいけない。君たちを見下し、奴隷にし、人生を操る者たちは、君たちが何をし、何を考え、何を感じるかを指図し、そして、君たちを仕込み、食べ物を制限する者たちは、君たちを家畜として、単なるコマとして扱うのだ。
そんな自然に反する者たち、機械のマインド、機械の心を持った機械人間たちに、身を託してはいけない。君たちは機械じゃない。君たちは家畜じゃない。君たちは人間だ。君たちは心に人類愛を持った人間だ。憎んではいけない。愛されない者だけが憎むのだ。愛されず、自然に反する者だけだ。君たち、人々は、機械を作り上げる力、幸福を作り上げる力があるんだ。君たち、人々は人生を自由に、美しいものに、この人生を素晴らしい冒険にする力を持っているんだ。
兵士よ。奴隷を作るために闘うな。自由のために闘え。『ルカによる福音書』の17章に、「神の国は人間の中にある」と書かれている。一人の人間ではなく、一部の人間でもなく、全ての人間の中なのだ。君たちの中になんだ。
だから、民主国家の名のもとに、その力を使おうではないか。皆でひとつになろう。新しい世界のために、皆が雇用の機会を与えられる、君たちが未来を与えられる、老後に安定を与えてくれる、常識のある世界のために闘おう。
そんな約束をしながら獣たちも権力を伸ばしてきたが、奴らは嘘をつく。約束を果たさない。これからも果たしはしないだろう。独裁者たちは自分たちを自由し、人々を奴隷にする。
今こそ、約束を実現させるために闘おう。世界を自由にするために、国境のバリアを失くすために、憎しみと耐え切れない苦しみと一緒に貪欲を失くすために闘おう。
理性のある世界のために、科学と進歩が全人類の幸福へと導いてくれる世界のために闘おう。兵士たちよ。民主国家の名のもとに、皆でひとつになろう」
この演説について、トリュフォーは次のように書いています。
「(トリュフォーの育ての親である批評家)アンドレ・バザンは、チャップリンの全作品中、最も重要なキー・ポイントが、この『独裁者』のラストの演説のシーンにあることに着目した。というのも、このシーンでは、あのチャーリーの<顔>がしだいに消えていき、そのかわり、メークアップをまったくしていない―すでにびんに白髪のまじった―チャールズ・チャップリンそのひとの顔があらわれてくるからだ。彼は世界に向かって希望のメッセージを投げかけ、福音書と神の言葉を読みあげる―明らかに虐げられた民族が救世主的な夢の実現のなかにこそ幸福を見出そうとしている姿が、そこにある。この映画は彼自身の顔でなく、ポーレット・ゴダード(チャップリンの当時の妻)の顔で終わる。チャップリンはポーレット・ゴダードの役名にハンナ(Hannah)という彼の実の母親の名を付けたのだった。 Hannah には、パランドロミックな(つまり逆から読んでも同じ意味になる)名前であり、まさしく、この名にこの映画の精神が見事に要約されている―というのもヒンケルはさかさまにしたユダヤ人の床屋にほかならぬからだ。チャップリンは、この長い演説の最後に、『ハンナ....』と母親の名に呼びかけるのである。そのとき、スクリーンには、地べたに泣き伏しているポーレット・ゴダードの姿が崇高な美しさに彩られて移される。彼女は面をもたげ、チャップリンの呼びかけに耳を傾ける―『見上げてごらん、ハンナ。空のほうを見てごらん、ハンナ。聞こえるかい?聞いておくれ!』」
ああ、なんという、偉大な映画作家と偉大な映画に対する尊敬が込められた文章なのでしょう。映画を観た後のトリュフォーの受けた感動が、そのまま伝わってきます。優れた芸術作品を称賛する時には、こういう文章を書きたいものです。
なお、トリュフォーがこの批評を書いたのは1957年、『独裁者』がリバイバル上映された時です。また、この批評の冒頭の方には、次のような記述もあります。
「年月とともにチャップリンの映画は<古びた>か否か?ばかげた問いかけだ。そう、もちろん、古びるのが当然だ、としか答えようがないではないか。『独裁者』が古びたのは、たしかである。そして、それは幸福なことだ。新聞の政治欄の論説のように、エミール・ゾラの『私は弾劾する』のように、時事問題をめぐる記者会見のように、この映画は古びたのであって、その結果、『独裁者』はすばらしい記録となり、貴重な資料となり、時代の証言として役立つ物件となると同時に、時代を超えた純粋な芸術作品として、あらためて、その姿を現したのである」
真の傑作に時の試練が関係ないことは、ギリシャ悲劇やシェイクスピアには、トリュフォーが言うように<古びている>にもかかわらず、誰も<古びている>という言葉を使わないことを思えば明らかだと思うのですが、映画の場合、リュミエール兄弟による世界最初の商業映画が公開されたのが1895年ですから、誕生からたかだか120年ちょっとしか経っていないわけで、<古びている>間もまだ与えられていないと個人的には思っています。それは、無声映画時代の傑作群、ムルナウの『吸血鬼ノスフェラトゥ』(1922年)、ラングの『ドクトル・マブゼ』(1922年)と『二―ベルゲン』(1924年)、シュトロハイムの『グリード』(1924年)、エイゼンシュテインの『戦艦ポチョムキン』(1925年)、ドライヤーの『裁かるるジャンヌ』(1928年)を観れば分かることです。
そして、この中には、もちろんチャップリンの『黄金狂時代』(1925年)も入ります。実は、チャップリンの真の傑作は『黄金狂時代』と『街の灯』(1931年)だと私は思っていますが、『独裁者』は、別の意味で、偉大なチャップリンが作った偉大な映画であることには変わりありません。
つい長々と書いてしまいました。最後になりますが、『独裁者』を未見の方、YouTube では、本作のチャップリンの演説だけ見ることができるようですが、それは止めてください。頭から観ても、終わりから観ても、真ん中から観てもいいような映画ではありません。映画に限らず、偉大な芸術作品に接する時は襟を正すべし、というのが私の考えです。<古びて>いても最後まで無声映画の芸にこだわったチャップリンの意地、独裁者の本質を笑いに閉じこめながら語る部分があってこそ、最後の生涯初の長い演説が活きるのですから。『独裁者』を観る時は、どうか最初から観てください。年老いた映画ファンからの、わがままなお願いでした。
- 髪に白いものが混じったチャップリンのラストの演説。無声映画にこだわった彼の初めての長い台詞でした。
- 映画のラスト・ショット、チャップリンの声に導かれ空を見上げようとするハンナ(ポーレット・ゴダード)
- これも有名な場面、地球儀(=世界)をもてあそぶ独裁者ヒンケル
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:
- ページ数:276
- ISBN:B000J8E4U0
- 発売日:1979年06月01日
- 価格:1680円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。