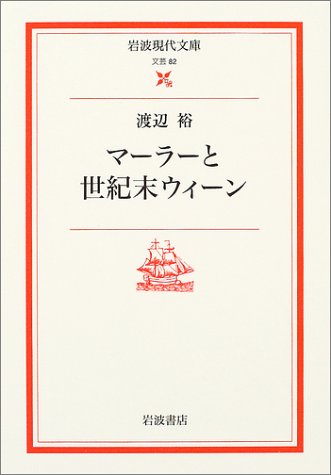三太郎さん
レビュアー:
▼
映画「ベニスに死す」の挿入音楽で広く知られた作曲家マーラーと19世紀末の楽都ウィーンの関係は複雑なものだった。
元は1990年に出された本だというからちょっと古いが、マーラーの音楽が世紀末のウィーンの文化と密接に結びついていることを論証した本です。
マーラーは生前には腕利きの指揮者として有名で、欧州の指揮者としての最高の地位であるウィーン宮廷歌劇場の音楽監督に登りつめた人でした。一方、作曲家としては片手間に訳の分からない音楽を書く人だと思われていたとか。
しかしこの本によると、マーラーは美術界の異端児であるクリムトの提唱する「分離派」の運動に共鳴し、分離派が開催したベートーベン展にウィーン歌劇場の演奏家を連れて行って交響曲9番の一部を演奏したとか。分離派にとってベートーベンは特別な音楽家で、ワグナーの総合芸術(音楽、演劇、舞台芸術が一体となった芸術)の先駆者であり、その実例が合唱を伴った交響曲9番だった訳です。
マーラーは自作の交響曲のなかにしばしば独唱や合唱を組み込んでいますが、これもワグナー流の実践だったと考えられます。
そしてワグナーと並んでマーラーに影響を与えたのがニーチェの著作でした。マーラーの音楽にはニーチェーが唱えたディオニソス的な狂乱があります。交響曲3番ではニーチェの「ツァラトストラ」の中の詩「酔歌」からの引用があります。
「深い夢から私は目覚めた 世界は深い 昼が考えたより深い」
夢といえばこれには「夢判断」を書いたフロイトの影響もあるかもしれません。
交響詩「ツァラトストラはかく語りき」を作曲したリヒャルト・シュトラウスはマーラーに交響曲3番の演奏を申し出たことがあるそうです。それを知るとシュトラウスの交響詩の響きにマーラーの影響を感じてしまいます。
マーラーの交響曲5番のアダージェットはビスコンティ監督の映画「ベニスに死す」の挿入音楽として有名ですが、この映画の原作はトーマス・マンの小説でした。しかしマンの小説の主人公は作家なのに映画では作曲家に変えられ、主演俳優のルックスはマーラーによく似ていました。そこでビスコンティ監督はマーラーをイメージして台本を書いたと思われ、主演男優が監督からモデルはマーラーだと聞いたという記事が出回って騒ぎになります。
しかしビスコンティ自身が自分はそんなことは言っていない、主人公はマーラーとは無関係だと主張しました。ところが後日、マン自身が小説の主人公の造形はマーラーをモデルにしていたと手紙に書いていたことが明らかになります。だからビスコンティ監督が映画の主人公にマーラー似の俳優を使ったのは偶然ではなかったかもしれません。この映画がマーラーの大衆化に一役かったのは間違いないでしょう。
実はマンは晩年のマーラーと交友があり、交響曲8番の初演に立ち会い、マーラーを食事に招いたりしていたとか。当時のウィーンでの交友関係は結構狭かったということでしょうか。
最終章はマーラーの交響曲の演奏の変遷について。交響曲4番を題材に演奏のテンポについて統計学の手法を用いて分析しています。
マーラーの録音は古くは弟子のメンゲルベルクの演奏から始まり、1987年のベルティーニの録音まで、20種類の録音が分析対象です。僕は若い頃はブルーノ・ワルターの1940年代の古い録音をよく聴いたのですが、メンゲルベルクのロマンティック過ぎる演奏からワルターの端正で整った演奏へ演奏スタイルが移っていき、それがマーラーの演奏のスタンダードになります。
しかし、1980年ごろからマーラーの音楽への理解が変わってきたようなのです。それが端的に表れているのが、小節ごとのテンポのばらつきの解析結果でした。
ワルターの演奏はテンポの揺らぎが少なく、曲全体が滑らかに連続していました。いわゆる新即物主義的な演奏スタイルで、著者はこれを「モダン」なスタイルと呼んでいます。カラヤンの演奏もやはり同様の傾向がありました。
ところが1985年録音のインバルの演奏では傾向ががらりと変わって来て、テンポの遅/速と音の強/弱を用いてメリハリのある演奏へと変化しています。たまたま手元にCDがあったので聴いてみたのですが、CDのライナーノーツによれば、インバルの演奏はマーラー自身の楽譜への書き込みを忠実に再現したものだとか。
本来マーラーが目指した音楽は、滑らかにフレーズが接続した、古典派のような端正な音楽ではなくて、異なる性格のフレーズ(テンポと楽器の音色)が重なり合う、マーラーのいうポリフォニックな響きのする音楽で、実は当時の前衛音楽だったのです。著者はこれを「ポストモダン」と呼んでいます。
尖がった前衛的なマーラー本来の音楽を弟子のワルターは滑らかに聴きやすくしたのですが、それがまた本来の形に戻ってきたという訳です。
またマーラーがひどく聴きたくなりました。これから手元のCDを録音年代に注意していろいろ聴き比べてみようと思います。
マーラーは生前には腕利きの指揮者として有名で、欧州の指揮者としての最高の地位であるウィーン宮廷歌劇場の音楽監督に登りつめた人でした。一方、作曲家としては片手間に訳の分からない音楽を書く人だと思われていたとか。
しかしこの本によると、マーラーは美術界の異端児であるクリムトの提唱する「分離派」の運動に共鳴し、分離派が開催したベートーベン展にウィーン歌劇場の演奏家を連れて行って交響曲9番の一部を演奏したとか。分離派にとってベートーベンは特別な音楽家で、ワグナーの総合芸術(音楽、演劇、舞台芸術が一体となった芸術)の先駆者であり、その実例が合唱を伴った交響曲9番だった訳です。
マーラーは自作の交響曲のなかにしばしば独唱や合唱を組み込んでいますが、これもワグナー流の実践だったと考えられます。
そしてワグナーと並んでマーラーに影響を与えたのがニーチェの著作でした。マーラーの音楽にはニーチェーが唱えたディオニソス的な狂乱があります。交響曲3番ではニーチェの「ツァラトストラ」の中の詩「酔歌」からの引用があります。
「深い夢から私は目覚めた 世界は深い 昼が考えたより深い」
夢といえばこれには「夢判断」を書いたフロイトの影響もあるかもしれません。
交響詩「ツァラトストラはかく語りき」を作曲したリヒャルト・シュトラウスはマーラーに交響曲3番の演奏を申し出たことがあるそうです。それを知るとシュトラウスの交響詩の響きにマーラーの影響を感じてしまいます。
マーラーの交響曲5番のアダージェットはビスコンティ監督の映画「ベニスに死す」の挿入音楽として有名ですが、この映画の原作はトーマス・マンの小説でした。しかしマンの小説の主人公は作家なのに映画では作曲家に変えられ、主演俳優のルックスはマーラーによく似ていました。そこでビスコンティ監督はマーラーをイメージして台本を書いたと思われ、主演男優が監督からモデルはマーラーだと聞いたという記事が出回って騒ぎになります。
しかしビスコンティ自身が自分はそんなことは言っていない、主人公はマーラーとは無関係だと主張しました。ところが後日、マン自身が小説の主人公の造形はマーラーをモデルにしていたと手紙に書いていたことが明らかになります。だからビスコンティ監督が映画の主人公にマーラー似の俳優を使ったのは偶然ではなかったかもしれません。この映画がマーラーの大衆化に一役かったのは間違いないでしょう。
実はマンは晩年のマーラーと交友があり、交響曲8番の初演に立ち会い、マーラーを食事に招いたりしていたとか。当時のウィーンでの交友関係は結構狭かったということでしょうか。
最終章はマーラーの交響曲の演奏の変遷について。交響曲4番を題材に演奏のテンポについて統計学の手法を用いて分析しています。
マーラーの録音は古くは弟子のメンゲルベルクの演奏から始まり、1987年のベルティーニの録音まで、20種類の録音が分析対象です。僕は若い頃はブルーノ・ワルターの1940年代の古い録音をよく聴いたのですが、メンゲルベルクのロマンティック過ぎる演奏からワルターの端正で整った演奏へ演奏スタイルが移っていき、それがマーラーの演奏のスタンダードになります。
しかし、1980年ごろからマーラーの音楽への理解が変わってきたようなのです。それが端的に表れているのが、小節ごとのテンポのばらつきの解析結果でした。
ワルターの演奏はテンポの揺らぎが少なく、曲全体が滑らかに連続していました。いわゆる新即物主義的な演奏スタイルで、著者はこれを「モダン」なスタイルと呼んでいます。カラヤンの演奏もやはり同様の傾向がありました。
ところが1985年録音のインバルの演奏では傾向ががらりと変わって来て、テンポの遅/速と音の強/弱を用いてメリハリのある演奏へと変化しています。たまたま手元にCDがあったので聴いてみたのですが、CDのライナーノーツによれば、インバルの演奏はマーラー自身の楽譜への書き込みを忠実に再現したものだとか。
本来マーラーが目指した音楽は、滑らかにフレーズが接続した、古典派のような端正な音楽ではなくて、異なる性格のフレーズ(テンポと楽器の音色)が重なり合う、マーラーのいうポリフォニックな響きのする音楽で、実は当時の前衛音楽だったのです。著者はこれを「ポストモダン」と呼んでいます。
尖がった前衛的なマーラー本来の音楽を弟子のワルターは滑らかに聴きやすくしたのですが、それがまた本来の形に戻ってきたという訳です。
またマーラーがひどく聴きたくなりました。これから手元のCDを録音年代に注意していろいろ聴き比べてみようと思います。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
1957年、仙台に生まれ、結婚後10年間世田谷に住み、その後20余年横浜に住み、現在は仙台在住。本を読んで、思ったことあれこれを書いていきます。
長年、化学メーカーの研究者でした。2019年から滋賀県で大学の教員になりましたが、2023年3月に退職し、10月からは故郷の仙台に戻りました。プロフィールの写真は還暦前に米国ピッツバーグの岡の上で撮ったものです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:岩波書店
- ページ数:255
- ISBN:9784006020828
- 発売日:2004年02月19日
- 価格:1050円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。