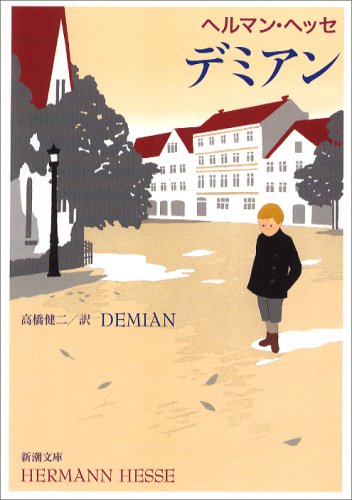かもめ通信さん
レビュアー:
▼
「自分を解き明かすことができるのは、他人ではなくあくまで自分だけだ。」青春の1ページとして忘れがたいこの作品の翻訳読み比べをやってみた。今回はクイズ形式。投票はいらないのでコメント欄にぜひ答えをw
ヘルマン・ヘッセの『デミアン』といえば、やはり
新潮文庫の初版はなんと1951年(昭和26年)、未だ現役で広く読まれている。
古典名作とくれば岩波文庫の手堅さも要チェック。
光文社古典新訳文庫から2017年(平成29年)に出た酒寄進一訳(C)はと言うと
この一節はどの訳を読んでも、この作品を初めて読んだ、卵からもがき出ようと苦しんだ10代の頃の記憶を呼び起こさずにはいられない。
この有名な一節とともに強く印象に残っているのは、この物語の本質をずばり言い表している序文の前に小さなフォントで掲げられた一節だ。
それぞれ、どの訳者のものかわかるだろうか?
問題1
続いては物語の性格を明確に著した序文から
問題2
最後にラストの名場面、いよいとデミアンの正体が!?
問題3
物語のラストでデミアンが何者であったかを知るとき、読者はもう一度冒頭に掲げられた一節を思い起こす。
Das Ich(自我)からSelbst(自己)へ至る道の困難さを思ってため息をつきながら。
鳥は卵の中からぬけ出ようと戦う。卵は世界だ。生まれようと欲するものは、一つの世界を破壊しなければならない。鳥は神に向かって飛ぶ。神の名はアプラクサスというの訳文でお馴染みの高橋健二訳(A)が最も読まれているのではないだろうか。
新潮文庫の初版はなんと1951年(昭和26年)、未だ現役で広く読まれている。
古典名作とくれば岩波文庫の手堅さも要チェック。
鳥は卵からむりに出ようとする。卵は世界だ。生まれようとする者は、ひとつの世界を破かいせねばならぬ。鳥は神のもとへとんでゆく。その神は、名をアプラクサスという。と訳した実吉捷郎版(B)の初版は1959年(昭和34年)、こちらも現役だ。
光文社古典新訳文庫から2017年(平成29年)に出た酒寄進一訳(C)はと言うと
鳥は卵から出ようともがく。卵すなわち世界なり。生まれんと欲する者は世界を破壊するほかなし。鳥は神をめざして飛ぶ。神の名はアプラクサスときた。
この一節はどの訳を読んでも、この作品を初めて読んだ、卵からもがき出ようと苦しんだ10代の頃の記憶を呼び起こさずにはいられない。
この有名な一節とともに強く印象に残っているのは、この物語の本質をずばり言い表している序文の前に小さなフォントで掲げられた一節だ。
それぞれ、どの訳者のものかわかるだろうか?
問題1
(1)迸(ほとばし)り出る自分の思いそのままに生きようとしただけなのに、なんでそれがこうも難しかったんだろう。
(2)ぼくはもとより、自分のなかからひとりでにほとばしり出ようとするものだけを、生きようとしてみたにすぎない。どうしてそれが、こんなにむずかしかったのだろう。
(3)私は、自分の中からひとりで出てこようとしたところのものを生きてみようと欲したにすぎない。なぜそれがそんなに困難だったのか。
続いては物語の性格を明確に著した序文から
問題2
(a)人間とは何かということを、こんにち知っている人はすくない。それを感じている人は多い。だからわりあいらくな気持ちで、死んでゆく--ちょうどぼくが、この物語を書きあげてしまったら、おそらくわりあいらくに死んでゆくのと同様に。
ぼくは、自分のことを、知識ある者とよぶわけには行かない。ぼくは求道者であったし、今でもそうなのだが、しかしもはや、星や書物のなかに求めてはいない。ぼくの血がぼくのなかできかせてくれる教えを、聞きはじめているのだ。
(b)今日では、人間とはなにか、を知っている人はほとんどいない。しかしそれを感じている人はおおぜいいる。それで、その人たちはほかの人よりは安らかに死んでいく。ちょうど私がこの物語を書き終えたら、いくらか安らかに死ねるように。
私はあえて自分を、知っている者とは呼ばない。私はさがし求める者であった。いまでもそうである。しかし私はもはや星の上や書物の中をさがし求めはしない。私の血が胎内を流れつつ語っているところの教えを、私は聞き始める。
(c)人間とはなにか、その答えを知る者はいま少なくなってしまったけれど、それを感じ取っている人は相当の数にのぼるはずだ。それを感じ取れるなら、心安らかに死んでいける。ぼくもこの物語を書き終えたら、きっと心おきなく死んでいけるだろう。
自分のことを、人間とはなにかということを知っている者だなどと言う気はさらさらない。ぼくはただの探求者だった。その点はいまでもおなじだ。いまではもう星や書物に道を求めるのをやめたけれど。いまは、自分の血が説く教えに耳を傾けている。
最後にラストの名場面、いよいとデミアンの正体が!?
問題3
(Ⅰ)シンクレール、よく聞きたまえ!ぼくは去らなければならないだろう。きみはおそらくいつかまたぼくを必要とすることがあるだろう、クローマーに対して、あるいはほかのものに対して。そのとき、きみがぼくを呼んでも、ぼくはもうそうむぞうさに馬や貴社でかけつけはしない。そのときはきみは自分の心の中を聞かなければならない。そしたらぼくがきみの中にいることに気づくよ。わかるかい?
(Ⅱ)ねえ、小さなジンクレエル、しっかりきくんだよ。ぼくはいずれここを出てゆくことになる。きみはたぶん、いつかまた、ぼくを必要とすることがあるだろうね--クロオマアやなんかに対してさ。そうなってぼくを呼んでも、ぼくはもうそんなとき、そう手がるに、馬にのったり、または汽車にのったりして、きはしないよ。そんなときはね、きみ自身の心に耳をかたむけなければいけない。そうすればぼくがきみの心のなかにいるのに、気がつくよ。わかるかい。
(Ⅲ)ちびのシンクレア、よく聞けよ。ぼくはもう行かなくてはいけない。きみはまたぼくを必要とするときがあるだろう。クローマーのような奴を敵にまわしてね。だけど、ぼくを呼んでも、馬や汽車に乗って駆けつけるのはもう無理だ。困ったときは、自分の心の声に耳を傾けろ。そうすれば、ぼくがきみのなかにいることに気がつく。わかったか
物語のラストでデミアンが何者であったかを知るとき、読者はもう一度冒頭に掲げられた一節を思い起こす。
Das Ich(自我)からSelbst(自己)へ至る道の困難さを思ってため息をつきながら。
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
本も食べ物も後味の悪くないものが好きです。気に入ると何度でも同じ本を読みますが、読まず嫌いも多いかも。2020.10.1からサイト献本書評以外は原則★なし(超絶お気に入り本のみ5つ★を表示)で投稿しています。
- この書評の得票合計:
- 39票
| 読んで楽しい: | 9票 | |
|---|---|---|
| 参考になる: | 30票 |
あなたの感想は?
投票するには、ログインしてください。
この書評へのコメント
- かもめ通信2019-01-21 05:57
さて、お約束の月曜日になりましたので、回答を。
正解は
A-3-b-Ⅰ
B-2-a-Ⅱ
C-1-c-Ⅲ
です。
今回は問題がくどすぎたかな。(汗)
一応、簡単に解説(?)しておくと、
最も広く読まれてきたと思われる新潮の高橋訳の主人公&語り手はシンクレール=「私」
ひらがなやカタカナの使い方など一番古風な感じがするのは「ジンクレエル」の岩波の実吉。
光文社古典新訳の酒寄訳は「シンクレア」。新訳にありがちなぶっとび感ははなく、なかなか手堅く読みやすい筆運びなので、いきなり「迸り出る自分」ではじまっても、さほど怖じ気づく心配はないかとw
というわけで、回答を寄せてくださったぴょんはまさん。
長々書いた読み比べに目を通してくださった皆さんありがとうございました。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - かもめ通信2019-01-21 05:57
酒寄訳で中味について(?)のレビューもアップしたので、そちらもどうぞよろしく!
https://www.honzuki.jp/book/254915/review/220343/クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:新潮社
- ページ数:223
- ISBN:9784102001028
- 発売日:1988年03月03日
- 価格:420円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。