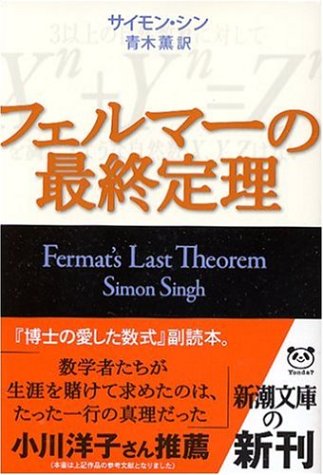はるほんさん
レビュアー:
▼
♪力と技と団結の コレがフェルマーの定理だ! エイエイエイオウ!
暗号解読 上下巻、宇宙創成 上巻、下巻につづいて、サイモン・シンの本。
骨の髄まで文系脳の自分に読めるのだろうか──、
そんな不安に後回しにしていたが、思い切って読み始めることに。
まず最大の難関は
ふぇるまーのさいしゅーてーりってなぁに?ってトコである。(タイトルですよ)
まぁでもこんなズブズブの数学素人でも
きっと親切なサイモン・シンがなんとかしてくれるにちまいない。
思いっきり他力本願で表紙を捲る。
それは1993年の出来事から始まる。
ある数学者がケンブリッジ大学の壇上でこの定理を解く。
「──これで終わりにしたいと思います」
それは証明を解き終えたと同時に、
長い長い数学史の因縁の戦いに終止符を打ったことを意味した。
さて歴史は幾世紀を遡り、「数論」へ移る。
数という概念から、分数や負の数、無理数といった数字が生まれた経緯だ。
あんなワケの分からん数字を計算させられたのが
ピタゴラスの罠だったと今理解して、憤る文系脳。←イマココ
ピタゴラスは1000年以上の時を越え、
フェルマーという数学者の脳内にあるヒラメキを生んだ。
ピタゴラスの定理「a² + b² = c²」というのを、学生時に習っただろう。
三角形の2辺の二乗の和が、他の1辺の二乗と等しいと言うアレだ。
「これが三乗以上になると、解はない」というのが、フェルマーの予想だ。
ここで「定理」という言葉について触れねばなるまい。
1993年を迎えるまで、この謎は正確には「フェルマーの予想」だった。
たとえば「1+1=2だお」と計算上で正解を得ても、それは定理にならない。
証明を経て、がっつり「1+1=2」の証拠を披露してこそ
「定理」は研究や論文で威力を発揮する。
が、このフェルマーと言うオッサンが頭が良過ぎて、
証明をキッチリ書かない定理が多かったんだと。
ページの余白にさらさらっとソレっぽいものをメモし、
「…という発見をしたお!でも余白が足りないから書かないお!」みたいな。
その最後に残ったのが、「フェルマーの最終予想(定理)」だ。
ナイもんはナイでよいではないかと思うのだが、
理系脳たちはこの「解がない」ことを証明しようとするのである。
「ある」ことを証明するより、「ない」ことを証明する方が困難だと言われるが
これはまさにその例かもしれない。
この数学者焦らしプレイは、実に300年続くのである。
幾人もの数学者が最終定理に臨み、倒れていった。
だが幾人かの勇者は、後継者へつなぐアイテムを残す。
前任者のアイテムを引き継ぎ、セーブポイントからボスに挑む。
だが勇者は敢え無く果てる。ささやかなアイテムを残して。
俺の 俺の屍を越えて行けと
一見シンプルにも思えるこの定理は意外にも、
数学の世界を網羅することになる。
冒険の地図を端から端までマッピングし、
アイテムをかき集め、ステージボスを倒し、
勇者たちは何世代にも渡り、じりじりとフェルマーのラスボスに迫っていく。
文系脳にその過程は、ひたすら魔法の呪文にしか聞こえない。
「そうか!M構造のガンマゼロを加えればいいんだ!」と言われても
どんなビームが出てるのか分からない。
分からないのだが、遥か時空を越えて
フェルマー戦隊が力を合わせて戦っている姿にワクワクする。
この定理がなにに繋がるのかもわからない。
だが定理はどこかの定理の一点となり
世界平和とは何ら関係のない秩序を守っていることは、おぼろげながら分かる。
無用な数字がないように、無用な数学もない。
嗚呼、理系脳の友人たちは、あの頃からその真理に気づいていたのだ。
黒板のサインコサインタンジェントの呪文の向こうに
こんなにオモチロイ無限世界をみていたのだ。
──あの頃から数十年、本書を読んで自分の中に残ったものは
「理系様は勝ち組」という人生の最終定理であった。(寂)
骨の髄まで文系脳の自分に読めるのだろうか──、
そんな不安に後回しにしていたが、思い切って読み始めることに。
まず最大の難関は
ふぇるまーのさいしゅーてーりってなぁに?ってトコである。(タイトルですよ)
まぁでもこんなズブズブの数学素人でも
きっと親切なサイモン・シンがなんとかしてくれるにちまいない。
思いっきり他力本願で表紙を捲る。
それは1993年の出来事から始まる。
ある数学者がケンブリッジ大学の壇上でこの定理を解く。
「──これで終わりにしたいと思います」
それは証明を解き終えたと同時に、
長い長い数学史の因縁の戦いに終止符を打ったことを意味した。
さて歴史は幾世紀を遡り、「数論」へ移る。
数という概念から、分数や負の数、無理数といった数字が生まれた経緯だ。
あんなワケの分からん数字を計算させられたのが
ピタゴラスの罠だったと今理解して、憤る文系脳。←イマココ
ピタゴラスは1000年以上の時を越え、
フェルマーという数学者の脳内にあるヒラメキを生んだ。
ピタゴラスの定理「a² + b² = c²」というのを、学生時に習っただろう。
三角形の2辺の二乗の和が、他の1辺の二乗と等しいと言うアレだ。
「これが三乗以上になると、解はない」というのが、フェルマーの予想だ。
ここで「定理」という言葉について触れねばなるまい。
1993年を迎えるまで、この謎は正確には「フェルマーの予想」だった。
たとえば「1+1=2だお」と計算上で正解を得ても、それは定理にならない。
証明を経て、がっつり「1+1=2」の証拠を披露してこそ
「定理」は研究や論文で威力を発揮する。
が、このフェルマーと言うオッサンが頭が良過ぎて、
証明をキッチリ書かない定理が多かったんだと。
ページの余白にさらさらっとソレっぽいものをメモし、
「…という発見をしたお!でも余白が足りないから書かないお!」みたいな。
その最後に残ったのが、「フェルマーの最終予想(定理)」だ。
ナイもんはナイでよいではないかと思うのだが、
理系脳たちはこの「解がない」ことを証明しようとするのである。
「ある」ことを証明するより、「ない」ことを証明する方が困難だと言われるが
これはまさにその例かもしれない。
この数学者焦らしプレイは、実に300年続くのである。
幾人もの数学者が最終定理に臨み、倒れていった。
だが幾人かの勇者は、後継者へつなぐアイテムを残す。
前任者のアイテムを引き継ぎ、セーブポイントからボスに挑む。
だが勇者は敢え無く果てる。ささやかなアイテムを残して。
俺の 俺の屍を越えて行けと
一見シンプルにも思えるこの定理は意外にも、
数学の世界を網羅することになる。
冒険の地図を端から端までマッピングし、
アイテムをかき集め、ステージボスを倒し、
勇者たちは何世代にも渡り、じりじりとフェルマーのラスボスに迫っていく。
文系脳にその過程は、ひたすら魔法の呪文にしか聞こえない。
「そうか!M構造のガンマゼロを加えればいいんだ!」と言われても
どんなビームが出てるのか分からない。
分からないのだが、遥か時空を越えて
フェルマー戦隊が力を合わせて戦っている姿にワクワクする。
この定理がなにに繋がるのかもわからない。
だが定理はどこかの定理の一点となり
世界平和とは何ら関係のない秩序を守っていることは、おぼろげながら分かる。
無用な数字がないように、無用な数学もない。
嗚呼、理系脳の友人たちは、あの頃からその真理に気づいていたのだ。
黒板のサインコサインタンジェントの呪文の向こうに
こんなにオモチロイ無限世界をみていたのだ。
──あの頃から数十年、本書を読んで自分の中に残ったものは
「理系様は勝ち組」という人生の最終定理であった。(寂)
投票する
投票するには、ログインしてください。
歴史・時代物・文学に傾きがちな読書層。
読んだ本を掘り下げている内に妙な場所に着地する評が多いですが
おおむね本人は真面目に書いてマス。
年中歴史・文豪・宗教ブーム。滋賀偏愛。
現在クマー、谷崎、怨霊、老人もブーム中
徳川家茂・平安時代・暗号・辞書編纂物語・電車旅行記等の本も探し中。
秋口に無職になる予定で、就活中。
なかなかこちらに来る時間が取れないっす…。
2018.8.21
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:新潮社
- ページ数:495
- ISBN:9784102159712
- 発売日:2006年05月01日
- 価格:820円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。