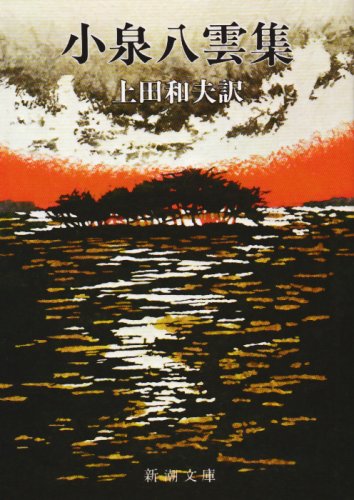たけぞうさん
レビュアー:
▼
もっと早く読んでおけばよかった #こたつ本
ショートカット先「あなたの #こたつ本 教えてください」参加書評です。
ショートカット先「ヘルンとセツ」がとても魅力にあふれていたので、
長らく手元にあったこの本を思い出しました。読み時だと思ったのです
────── 結局、もっと早く読むべきだと気づきましたが。
耳なし芳一。むじな。ろくろ首。雪おんな。牡丹灯籠。
知らない人を探すほうが難しい著名作がずらりと並びます。
それもそのはず、翻訳者は編者としてハーンの多くの作品の中から
選んで編さんしていますから。
果心居士のはなし。幽霊滝の伝説。破られた約束。
読み始めると、あっ、あの話だと思い出す人が多い作品たち。
さらにこの一冊が素晴らしいのは、ラフカディオ・ハーンによる日本評論が
収録されていることです。
日本人の微笑という題ですが、日本の精神性をよく理解していて、
日本人では気づかないようなことが丁寧にまとめられています。
現在の日本人に間違いなく受け継がれていることが分かります。
また、巻末の翻訳者による解説も、研究の成果報告みたいになっていて、
なぜハーンが日本で物語を収集することになったのか、
巻末の年譜とともに理解できるだけの情報が盛り込まれているのです。
文章自体は、前半の怪談パートに対して、後半の評論関係に入ると
趣が異なってきて戸惑う部分があります。しかしそれは些末なことです。
総じてみれば、物語性に富み、百年以上前の作品とは思えない
高揚感を覚えるハイレベルな著作だと断言できます。
ついのめり込んで、睡眠時間を削られたことだけはいただけないのですが。
心中ものや、幽霊ものが多かったですね。印象的でした。
妖怪話は少なく、哀愁漂う作品が多いのですよ。
また、現代の怪談は脚色が進み過ぎているようで、
原典のこちらに戻るとかなり印象が異なる作品がありました。
ろくろ首や雪おんなは典型的です。
自分の直観ですが、ハーンは人を怖がらせようとして物語を収集したのでは
ない気がします。当時の社会の悲哀や憂いが、物語の形となって、
社会の縮図的に民間で伝承されていると考えていたのではないでしょうか。
日本に来る前にも、エジプト・エスキモー・インド・フィンランド・アラブ・
ユダヤの民族伝承をもとに本を一冊書いていることからも分かります。
この分野に強い関心があったのでしょうね。
ハーンは、当時の印刷事情を考慮するとものすごく多作です。
同時に、ハーンは天才的な言語センスの持ち主であると想像できます。
日本で通訳を務めてくれた人がいたのですが、
だからといってここまで琴線に触れる文章を書けるものではありません。
天才ですよ、間違いなく。
冬休みのこたつ本にして正解でした。
きっかけをくれたヘルンとセツも、話題になって欲しいですね。
ショートカット先「ヘルンとセツ」がとても魅力にあふれていたので、
長らく手元にあったこの本を思い出しました。読み時だと思ったのです
────── 結局、もっと早く読むべきだと気づきましたが。
耳なし芳一。むじな。ろくろ首。雪おんな。牡丹灯籠。
知らない人を探すほうが難しい著名作がずらりと並びます。
それもそのはず、翻訳者は編者としてハーンの多くの作品の中から
選んで編さんしていますから。
果心居士のはなし。幽霊滝の伝説。破られた約束。
読み始めると、あっ、あの話だと思い出す人が多い作品たち。
さらにこの一冊が素晴らしいのは、ラフカディオ・ハーンによる日本評論が
収録されていることです。
日本人の微笑という題ですが、日本の精神性をよく理解していて、
日本人では気づかないようなことが丁寧にまとめられています。
現在の日本人に間違いなく受け継がれていることが分かります。
また、巻末の翻訳者による解説も、研究の成果報告みたいになっていて、
なぜハーンが日本で物語を収集することになったのか、
巻末の年譜とともに理解できるだけの情報が盛り込まれているのです。
文章自体は、前半の怪談パートに対して、後半の評論関係に入ると
趣が異なってきて戸惑う部分があります。しかしそれは些末なことです。
総じてみれば、物語性に富み、百年以上前の作品とは思えない
高揚感を覚えるハイレベルな著作だと断言できます。
ついのめり込んで、睡眠時間を削られたことだけはいただけないのですが。
心中ものや、幽霊ものが多かったですね。印象的でした。
妖怪話は少なく、哀愁漂う作品が多いのですよ。
また、現代の怪談は脚色が進み過ぎているようで、
原典のこちらに戻るとかなり印象が異なる作品がありました。
ろくろ首や雪おんなは典型的です。
自分の直観ですが、ハーンは人を怖がらせようとして物語を収集したのでは
ない気がします。当時の社会の悲哀や憂いが、物語の形となって、
社会の縮図的に民間で伝承されていると考えていたのではないでしょうか。
日本に来る前にも、エジプト・エスキモー・インド・フィンランド・アラブ・
ユダヤの民族伝承をもとに本を一冊書いていることからも分かります。
この分野に強い関心があったのでしょうね。
ハーンは、当時の印刷事情を考慮するとものすごく多作です。
同時に、ハーンは天才的な言語センスの持ち主であると想像できます。
日本で通訳を務めてくれた人がいたのですが、
だからといってここまで琴線に触れる文章を書けるものではありません。
天才ですよ、間違いなく。
冬休みのこたつ本にして正解でした。
きっかけをくれたヘルンとセツも、話題になって欲しいですね。
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
ふとしたことで始めた書評書き。読んだ感覚が違うことを知るのは、とても大事だと思うようになりました。本が好き! の場と、参加している皆さんのおかげです。
星の数は自分のお気に入り度で、趣味や主観に基づいています。たとえ自分の趣味に合わなくても、作品の特徴を書評で分かるようにしようと務めています。星が低くても作品がつまらないという意味ではありません。
自己紹介ページの二番目のアドレスは「飲んでみた」の書評です。
三番目のアドレスは「お絵描き書評の部屋」で、皆さんの「描いてみた」が読めます。
四番目のアドレスは「作ってみた」の書評です。
よかったらのぞいてみて下さい。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:新潮社
- ページ数:421
- ISBN:9784101094014
- 発売日:1975年03月01日
- 価格:620円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。