フォビアがいっぱい――多文化共生社会を生きるために





「フォビア」には、特定のモノや場所に対する恐怖心と、特定の人に対する激しい嫌悪や増悪という意味があるということを示し、これらの詳細とその理由について、多方面から分析を試みています。
特定のモノや場所に対する恐怖心には、高所恐怖症、閉所恐怖症、集合体恐怖症などがあり、特定の人に対する…

本が好き! 1級
書評数:778 件
得票数:15468 票
後期高齢者の立場から読んだ本を取り上げます。主な興味は、保健・医療・介護の分野ですが、他の分野も少しは読みます。でも、寄る年波には勝てず、スローペースです。画像は、誕生月の花「紫陽花」で、「七変化」ともいいます。ようやく、700冊を達成しました。





「フォビア」には、特定のモノや場所に対する恐怖心と、特定の人に対する激しい嫌悪や増悪という意味があるということを示し、これらの詳細とその理由について、多方面から分析を試みています。
特定のモノや場所に対する恐怖心には、高所恐怖症、閉所恐怖症、集合体恐怖症などがあり、特定の人に対する…
![]()




『五輪書(ごりんのしょ)』は、380年ほど前、剣豪・宮本武蔵が死の直前に書き上げた書物ですが、医師であり、宮本武蔵の後継である野田派ニ天一流第19代師範の娘でもある筆者が「超訳」したのが、この本です。
宮本武蔵について、書かれた小説は、吉川英治著『宮本武蔵』が有名ですが、筆者は「この小説のかなり部分が…




裁判官が、法廷で述べた言葉の中で、貴重と思われた文言を、10章92件にわたって、その背景とともに記した、まさに「前例のない本」と筆者自身が述べている本です。
ただし、この本の名前は、少しふざけすぎてはいませんかと、まず断ってから、本文に入ります。 とい…




東京の水のない川「暗渠」に続いて、その暗渠にかかっている橋「暗橋」を愉しめる8コースを、紹介している本です。
暗渠になっている川として、『水のない川 暗渠でたどる東京案内』(以下「案内」と略します)の書評で紹介…




東京のまちの変遷を、かつて流れていた川や水路の痕跡(暗渠)からたどり、「江戸から東京」、「戦前・戦後」、「高度経済成長期」の豊富なビジュアル資料を駆使して〈土地の記憶と景観〉をよみがえらせています。
「水の都大阪」と言われていますが、現在の東京を「水の都」とは誰も言いません。しかし、江戸時代には、水…





安部元首相の銃撃による殺害と「国葬」が呼び起こした「政治と宗教」の問題をめぐっての緊急出版。編者は、五名の筆者により、「立体的複眼的」に取り上げていると言っています。
本書の内容とそれぞれの筆者は次の通りです。 序 章 公共空間における宗教の位置・・・・・・・・…





「これまで、人間以外の霊長類の研究を通じて人類の進化の足跡をたどってきた。」著者が、人間文化研究機構の研究所の一つである「総合地球環境学研究所」の所長に就任してから、これまで書いた文章をまとめた本です
朝日、毎日、京都の各新聞や、『公研』(公益産業研究調査会)や『青淵』(渋沢栄一記念財団)などの雑誌に…





牧野富太郎の生涯を描いた小説です。
次の十三章で構成されています。〈〉内は、当時の主人公の年頃とそのありようです。 一 岸屋の坊〈…





「たましん地域文化財団歴史資料室」は、多摩信用金庫国立支店の5階にあり、平成3(1991)年に開設され、現在は「たましん歴史・美術館」として、登録博物館になっているそうですが、その活動記録の一端です。
この施設では、①図書、②雑誌、③地図、④絵葉書、⑤チラシ・リーフレット、⑥ポスター、⑦写真、⑧包装紙…





「国書刊行会」という不思議な名前の出版社の50年の記念誌です。
「国書」というのは、広辞苑によれば「①国の元首が、その国名をもって発する外交文書。②日本で著述された…





東京二三区の中にあって、今なお、農家している家の物語です。
四百年前から今まで続いている、農家の年中行事です。 【年末年始】 ・十二月に入ると、一年分のたく…





千葉県流山市。千葉県の北西部の江戸川のほとりにある、人口20万6千人ほどの都市ですが、この10年で人口が3万8千人ほど増加し、人口増加率全国一といわれているそうです。一体、どんなことが起きているのか?
この町は、利根川と江戸川との間にあり、1890年に二つの川を結ぶ「利根運河」が開通したことで、銚子港…





60年前に出されて、今なお読み継がれている、安部公房の代表作であり、もはや現代世界文学の古典といっていい、というヤマザキマリの「100分de名著」にひかれて、読んでみました。
昆虫採集に出かけて、目指す砂丘にたどりつき、そこで、行方不明となり、七年たち、民法第三十条によって、…




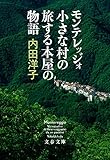
イタリア・トスカーナの山深いある村では、本の行商で生計を立ててきたのだそうです。この村を訪れて書いた、本と本屋の原点を描いた、ノンフィクションです。
筆者は、東京外国語大学イタリア語科を卒業し、現在は、通信社ウーノアソシエイツ代表として、欧州と日本間…





この本は、京都に伝わる「いもぼう」、海川魚料理、うなぎ料理、とり料理、そして洋食の五つの料理を取り上げて、料理(屋)文化の系譜をたどりなおしたという本です。
この本に取り上げている料理の内容は、次のようなものです。 ・いもぼう:東京で食えないものとして…





江戸の古地図を眺めていると、いつしか頭のなかに江戸の風景を思い浮かべて、まるでそこを歩いているような気がする、という筆者が、古地図をもとに江戸の町を想像上の散歩をするという趣向で書いた本です。
徳川家康が、江戸に幕府を開いてから420年、明治維新から155年たった今もなお、東京には江戸の名残り…
![]()




あるロックバンドの、作詞・作曲者であり、ボーカル担当、ギタリストでもある筆者の全作詞(詩)とのことです。未発表のものもあるということですが、それにしても膨大な量に圧倒されました。
これまで歌というものは、曲と詞があることによって成り立っている、と思ってきた者にとって、詞だけを独立…






子供向きの絵本にしては、紙質もよく、装幀もしっかりしていて、書店の棚も「大人の絵本」として並べられていました。開いてみると、淡い水彩画が描かれ、ところどころに文字が書かれている、とても贅沢な絵本です。
物語は、静かなパリの家並みから一日目が始まります。ある家の庭先で、一人の少女がばらばらになりそうにな…




国土の7割ほどが山である日本のなかでも、「勾配克服の見本市」と筆者が呼んでいる、長野県を舞台にして、鉄道や集落をはじめ、その多様性を「地図」をキーワードにして紹介している本です。
かつての信越本線の横川―軽井沢間には、66.7パーミルという急勾配があり、アプト式という歯車上のレー…





神社仏閣から、授与される「お守り」の歴史とエピソードから読み解く、日本人の祈りと願いの文化史。
わが国で最古の「お守り」は、790年の秋から冬にかけて、長岡京で得体のしれない疫病が猛威を振るい、そ…