戦後教育史 貧困・校内暴力・いじめから、不登校・発達障害問題まで (中公新書)【Kindle】



カバーに「なぜ行き詰まったか」とあるが、「本当に行き詰まってるのか?」と疑問を感じた。確かに、校内暴力やいじめ、不登校など数々の問題はあっただろう。それらを振り返ることにも一定の意味はあるだろう。
私も奥さんも育った家庭は経済的には中の下ぐらい。今は中の上の端くれぐらいには引っかるだろうか。まだ教…

本が好き! 1級
書評数:283 件
得票数:2646 票
会社員としての先もそろそろ見えてきたこの頃。書評を通じて社会と繋がりが持てればと思います。ご多分に漏れず、年齢を重ねてからは歴史小説をよく読みます。でも、まだまだ幅広い分野に興味を持っていたいので、おもしろそうな本には何でも挑戦してみます。



カバーに「なぜ行き詰まったか」とあるが、「本当に行き詰まってるのか?」と疑問を感じた。確かに、校内暴力やいじめ、不登校など数々の問題はあっただろう。それらを振り返ることにも一定の意味はあるだろう。
私も奥さんも育った家庭は経済的には中の下ぐらい。今は中の上の端くれぐらいには引っかるだろうか。まだ教…






生きる上で、何を指針にしてよいか迷ったら本書をお勧めする。自らの実践、体験に基づいた講話だけに重みがある。平易な言葉で書かれているので、年代に応じた読み方ができると思う。
私は今年の3月で定年退職を迎える。再雇用を選ばず、再就職の道を選んだ。否応なく、自分はなぜ仕事を続…






畏友正岡子規は若くして結核で亡くなる。ロンドンへの2年間の留学を経て、遂に漱石は職業作家に転身。作品は大反響を受けるが、徐々に体調が悪化。「明暗」が未完のまま漱石49歳にて永眠。漱石は何を残したのか。
漱石はやはり傑出した人物であり、文部省の第1回給費留学生に選ばれイギリスに2年間留学。帰国後は東大…






国民的作家、夏目漱石の生涯を描く。旧名主の六男として生まれた金之助は勉学に秀で、東大に進学し、畏友正岡子規と出会い、英語教師として松山や熊本に赴任する。金之助は生涯の仕事に何を選ぶか。
夏目金之助は旧名主の六男として生まれるが、「恥かきっ子」として養子に出される。金之助は学問に秀でる…
![]()





グーグル発で一躍有名になった「心理的安全性」。単なる仲良しクラブではなく、真にイノベーティブな組織にするにはどうしたら良いのか。経験豊富な著者が解説します。
心理的安全性はアメリカで提唱された概念である。この手の本はなぜ心理的安全性が必要になったのか、その…





現在行われている俗流キャリア教育の問題点を指摘し、キャリア教育はいかにあるべきかを論じている。元々はちくまプリマー新書として刊行されており、中高生向けのメッセージも掲載されている。
本書は2013年にちくまプリマー新書として刊行されており、2018年に電子化にあたり改変を加えられ…





人間が地球環境にあまりに大きな影響を与えてしまった「人新世」においては、資本主義の枠組みでは危機を解決できず、脱成長のコミュニズムが必要であることを説く。
人新世とは、人間が地球環境にあまりに大きな影響を与えてしまったので、それまでの地質学的な年代と区別…



見開き2ページで仏教2500年の歴史の1項目を説明するスタイルを取った仏教の入門書。本書の特色は日本だけでなく、チベットや東南アジアなど仏教が伝播した地域での歴史にも言及していることだ。
仏教2500年の歴史を見開き2ページで1項目で説明するスタイルを取り、ゴータマ・ブッダの生涯、大乗…






壁に囲まれ、外と隔絶した世界で完結している「世界の終り」。現実世界で奇妙な情報戦争に巻き込まれてしまった私の「ハードボイルド・ワンダーランド」。2つの世界が同時並行で進み、最後は?
村上春樹の小説を読んでいるとビールが飲みたくなる。サンドウィッチも食べたくなる。作品を読んでいる間…




浄土宗と日蓮宗。あまり共通点があるとは考えたことはなかったが、言われてみるとよく似た点がある。法然と日蓮を徹底比較。
私はお寺巡りが趣味なので、日蓮宗のお寺にはあまり仏像がなく、何となく疎遠な感じがしていた。また、日…




精進料理という言葉は僧侶の間ではなく、在家が僧侶の食事のことをそう呼んでいたらしい。精進料理を作る心構え、食事作法、話は中国や仏教発祥の地インドまで広がり、多面的に精進料理を考察しています。
新聞か何かの書評を見て本書を注文したような気がします。意外なことに仏教には「精進料理」という言葉はな…




時は奈良の天平時代。唐から伝戒の師を招請するために遣唐使に送られた4人の青年僧と、それに応じた鑑真が渡来するまでの物語。
奈良の天平時代、日本は律令制度の下でようやく国家の体をなしてきたが、まだまだ政治や文化、仏教におい…





アンガーマネジメントとは怒りをコントロールすること。怒りによって人間関係は悪い方向に行ってしまう。それをコントロールすることで豊かな人間関係が築けるのは大事なことだ。
アンガーマネジメントとは怒りをコントロールすることだが、それ以前に「怒り」とは何かを分析しており、こ…




分析哲学の立場から、哲学で何が分かるかを実際の講義録の形で書籍化。哲学的な問題は解決しえないとの主張が行われる。
哲学者の間ではどんなことが哲学的な問題かは共通認識があるが、どうすればその問題を解決できるかに…





昨年12月、東大安田講堂事件から50年ということで何度も報道で取り上げられていましたが、その当事者の記録。
昨年12月、東大安田講堂事件から50年ということで何度も新聞やテレビで取り上げられていましたが、機…



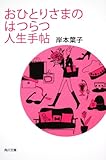
若い時はよいが、40代ともなると女性が一人で生きていると、この先このままでよいのかとふと不安なることもあるでしょう。そんな時にお薦めの本です。
著者の岸本葉子さんの文章は日経の夕刊で毎週愛読している。著作も読んでみようと思って、手に取ったのが…





人はなぜ物語を求めるのか。それは人間が外界を物語形式でしか認識できないからである。物語を人間がいかに理解するかを掘り下げて論じている。
人は自分が何者かを説明する際に時系列で経歴を説明する。人は自己理解においても物語形式になっている。…



「弱いロボット」とは何か。ロボット単体では機能を果たすことができず、他社に助けられることで初めて役割を果たせるロボットのこと。コミュニケーションについて考察する道具となっている。
通常、ロボットはロボット単体で目的を果たすべく製作される。そのために、様々な機能が追加され、高機能…




お坊さんという職業はあまり活動内容を知られていない。お坊さんの日常と、若き僧侶の思いが綴られたエッセイ。
本書は若くして住職になった僧侶の青春の書である。前半は高野山大学の学生時代のことや、住職になりたて…





人生100年時代はもうそこまで到達している。人生100年を生き抜くための戦略はどう考えるべきかを論考。
昨年、「人生100年時代」がキーワードになり、日本政府も最近年金改革の方向性を発表しているが、本書…