東京・築地 五つ星の味、極上の逸品




築地を知り尽くした著者が、旬な素材は何なのかを紹介してくれる
著者は筑地探索のブレーンを従え、徹底して築地を調査研究している「築地王」の異名を持つ築地歩きの第一…

本が好き! 1級
書評数:6242 件
得票数:91965 票
昔から活字中毒症。字さえあれば辞書でも見飽きないです。
年金暮らしになりましたので、毎日読書三昧です。一日2冊までを限度に読んでいます。
お金がないので、文庫、それも中古と情けない状態ですが、書評を掲載させて頂きます。よろしくお願いします。




築地を知り尽くした著者が、旬な素材は何なのかを紹介してくれる
著者は筑地探索のブレーンを従え、徹底して築地を調査研究している「築地王」の異名を持つ築地歩きの第一…




生き生きとして日々を暮らす。それは、多くの人間関係に恵まれ、多趣味で活発に生きること。それ以外はみじめ。少し硬直的な見方ではないか。
60歳でも、65歳でもいいのだが、ほぼ40年間、会社、サラリーマン生活がすべてで暮らしてきた人が定…



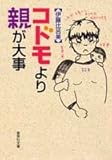
…家族を抱える女性。何々をしたいというのではなく、何々をせねばならないという強い気持ちで、夫、子どもから、納得ずくで、何々をする時間を奪い取らねばならない。
本を読みたい、絵を鑑賞したい、コンサートにも行きたい、とにかく外出して、自分の空間時間を持ちたい、…




男女平等といっても、育児を父親がするのは、どうにも世間からみて似合わない
男女平等社会といわれ、子供の世話や育児も共同で行うべきと巷間言われるが、なかなか男が育児をするとい…




やりたいことをやるためには、やりたくないことをせねばならない。本当にそうだと思う。
町田康の人生相談と、東京を散歩しながらの町田といしいの対談が収録されている。 町田の「やり…




甲子園で活躍した日ハムの斎藤佑樹投手。吉井は彼は一流の投手に変わることを信じて疑わない
近鉄のエースからヤクルトへそれから海を渡り、メッツを皮切りに大リーグのチームを転々、そして日本に復…




プロレスには初めから台本がある。木村と力道山の格闘家日本一を決める試合。台本があったのだが、その台本を力道山が破る
プロレスには真剣勝負というのはなく、すべて台本があり、その台本がいかに素晴らしく、また、その台本通…




至上最強の柔道家といえば木村政彦である。これだけやれば史上最強にもなるだろうと納得する猛練習である
戦争を挟んで15年間不敗記録を持つ、柔道家であった木村政彦七段。「木村の前に木村なく、木村の後ろに…




ギャンブラーと言われる人は、勝ったことしか言わない。それで極意とか必勝法とかをひけらかす
今は個人情報保護の観点から、個人の所得番付けは発表されなくなったが、その番付け発表が行われた最後の…



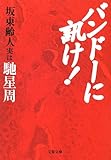
馳が猛烈な読書家になった原点は、祖父母の家にあった
読書狂いの馳星周が、まだ本名坂東齢人の名で書いていた91年から97年までの書評を収録。 我…




…私が住んでいる市にある静岡エコパスタディアムを徹底的にこき下ろす。読んでいる私もそうだよなと思うから情けない
韓国が審判を買収したのではというほど疑惑の試合がたくさんあった2002年の日韓共催ワールドカップの…




バケツは馬穴からきている。これ本当?
明治、大正、昭和そして平成と、四代にわたる事物の起源とその変遷をたくさんのエピソードを交えて描いた…




…相手を受け入れない不寛容は寛容に対して圧倒的に強い。しかし寛容こそ今求められている態度である
大読書家である紀田順一郎は若い時から読書をしていて、これは名言だと思う言葉にであうとノートに書き留…




産後クライシスとは大変なことだとわかった
川上未映子35歳での妊娠、出産から1歳までの育児経験を書いた作品。 産後クライシスの場面が強く印…




最近の農業や一般家庭での料理の簡便さを小泉は堕落だと嘆く
食べ物を入れる口は非常に重要な場所だが、それと同じくらい重要なのが、食べたものを吐き出すお尻も大切…



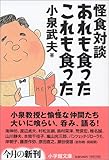
NHKアナウンサー山川静夫さんの新人のころのエピソードが面白い
宮田輝の後を引き継いで「紅白歌合戦」の司会を9年間務めたのが、山川静夫アナウンサー。山川の最初の赴…




は、母親も働き、料理をじっくり作る時間がない。簡単に作れてちょっとした工夫で美味しい料理に変わるこつを指南する
毎日の朝晩にだすおかず。仕込みに何時間もかけて、一流料理など作っている時間は無い。だいたいが30分…




小泉武夫の食事本がおいしく感じるのは、擬音、擬態語の多用にある
小泉の料理、食事のエッセイを読んでいると、ムラムラと食欲がわいてきて腹がすいてこまるという投書が、…




古代お酒はお米を口で噛みくだき、それを壺にはきだすことで作られた。そんな方法で作られる酒が今でもあるそうだ。
今の感覚と昔では大きな差があるからそうなのかもしれないが、縄文後期に編み出された酒の製造方法につい…




今は真冬に亡くなる人が多いが、江戸時代は真夏に亡くなる人が多かった。酷暑の夏をどう乗り切るか、それで発酵食品が発展した
日本ほど、多くの種類の伝統的漬物が存在する国はない。漬物市場は何と6000億円にものぼる。 …