東電福島原発事故 総理大臣として考えたこと

自身の視点で書いているので本人にとっての事実ということだが当時を窺い知ることができる。感傷的あるいは今だから言えることという箇所もあるが、そんな心積もりだったかと改めて知る所もある。

本が好き! 2級
書評数:50 件
得票数:153 票
キャリア、キャリア開発にかかわる本が多いです。また、それに関連するカウンセリングやグループの本も.最近の関心はナラティブ、かなぁ。

自身の視点で書いているので本人にとっての事実ということだが当時を窺い知ることができる。感傷的あるいは今だから言えることという箇所もあるが、そんな心積もりだったかと改めて知る所もある。






さまざまな地域、領域、場面でなぜ紛争、衝突は起こるのか?そしてそれを私たちは乗り越えられるのだろうか?プロセス指向心理学創始者であるミンデルがランクという概念を元にその方向性を解きほぐす。





臨床心理はプライベートな領域に立ち入るので関わる人たちの職業倫理が問われる。それはクライアントを守るだけでなくサイコロジスト自身をも守るものという前提に立ち、その内容と教育の方法について詳述している。
心理臨床家はクライアントの秘密を守ることが前提である。 しかし、例えば ○クライアントが子ど…


タイトルで期待される内容ではなく、人材育成に関わる論述は一般的にいわれていることでやや表層的。IT関連の専門人材については、筆者の会社で展開するスキル標準を使うことが海外で通用することであるとのこと






西洋的(ギリシャ哲学的)文化と東洋的(道家的)文化が、その人のかなり無意識に近いレベルの考え方、行動に影響しているかを多様な実験、観察を元に解説されます。納得度高し!





物語を紡ぎ出す装置として6つのテーマを提示し、実際にストーリーをつくってみる本。講座の名前の通り、実際にやってみることがお勧め。人の考え方の道筋をたどるための枠組み、自分のキャリアをたどる上でも有用





自分のライフヒストリーを書くということは、自分自身を客観的に、つまり第三者として主観的にみるということ。そこには自分では気づかなかった意味があり、見てはいたけれど目を背けていたディテールがある。


ドラッカーのマネジメントにはこんなことが書いてあるという長いたとえ話。たとえ話だから感動とかストーリー性とかは追求してはいけないわけです。女子高生はそんなことしないんじゃないの?とかというのもなし。





キャリア教育とは何か、が平易に書かれている。教師は親は何をすべきかがコンパクトにまとめられている。キャリア教育とは教育改革運動のことであるというスタンスにたっているようなので少し違和感はあるかも






どこを読んでも示唆に富む。対談形式なので、話の筋を見失うこともあるけれど、キャンベルの一文、一文に目から鱗が落ちたり、はたと膝を打ったり。オトナになったら一度は読んでおきたい本。






家族療法家でもある著者がナラティヴによるセラピーをVTRに撮り解説を加えたワークショップを元にした本。臨床実践と標題にある通り他の方法とどう違うのかを分かりやすく解説。夭逝されたことが惜しまれる。





ありそうでなさそうな、となりの席の関くんの授業中の内職。1巻よりもパワーアップした将棋、そして新ネタ福笑い、登山など、絶対無いんだけどありそうで、見ている方もついつい引き込まれるのは横井さんと同じ。




努力して成功したら幸福になるのではなく、幸福と感じる状態である方が成功しやすいという発想。ここでの幸福は本人にとってのものであり、それをどう捉え、実感するかについての7つの実践ルールが記されている。

キャリアを考えるについて事業計画策定に倣ってみる方法は願望や希望に終始しがちな就職転職活動に効果的。ただ、土壌となる思いの部分をどう描くかについての考察があっさりしすぎ?ここがずれている人が多いような




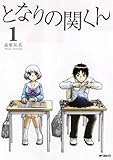
誰にでも経験がありそうでなさそうな、教室の(一部校庭の)風景。現役学生も大人もクスリと笑えます。
なんといいましょうか、素朴におもしろいです。 大笑いということはないですが、1話に1度はクスリと笑…




タイトルに惹かれて購入。人はどのように自尊心を取りもどしていくのかを一人一人の登場人物に寄り添いながら描いています。どれも過酷な状況ですが、程度は違っても自分もそうであることに気づかされ、励まされます





拠点を持たない併走型支援で若者を一人一人サポートする「静岡方式」を実施団体、支援を受けた人、受け入れた企業のコメントも含めて紹介。なぜこの方式がうまくいくのかだけでなく、就労支援の在り方がよく分かる。




「夜回り先生」を読んで早速こちらも。子どもが自分で生きることを徹底的に支援する水谷先生。子どもが生きるためにその親も容赦はしない。親以上に子どもを信じ、支える人。人を支えることの意味が身に染みて分かる




水谷先生の活動と考え方が淡々と語られます。自分は大人だなと思う方は一読を。私たちに同じことはできないでしょう。でも賛同するところは多いでしょう。それを私たちなりに実践していく手がかりとなるでしょう




英国で若年、中年、高年の3階層の人についてインタビューしたものをまとめた本。ビジネススクールで教えている著者の交遊範囲なので限定的とはいえキャリア開発に取り組んでいる人たちの考え方に特徴が現れている。