ヒザの痛みがとれた!―脚が楽になった!






類書ではもっとも図が豊富。解説もわかりやすい。カラダを休めて痛みをとる療法で森林浴がある。頑固なヒザの痛みは森へ持っていく、というのが新鮮。

本が好き! 1級
書評数:248 件
得票数:1719 票
本を読んでも内容をほとんど覚えていません。
読んだはずなのに、気づかずにもう一度読んだことがあります。
最後まで読んでも以前読んだことを思いださなかった。
ということがありまして、ショックを受けました。
そこで、内容を覚える事は無理でも、読んだ記録をつけようと思いました。
(2010年12月22日 登録)






類書ではもっとも図が豊富。解説もわかりやすい。カラダを休めて痛みをとる療法で森林浴がある。頑固なヒザの痛みは森へ持っていく、というのが新鮮。





著者は都会の人の田舎への受け入れを事業化している。田舎暮らしに留まらず、日本の農業が抱える問題に迫っている。
●日本では広すぎる土地だと不便 欧米は畑や放牧が中心なので、広々とした農地や山林を持っていてその…





里山の魅力は自然だけでなく、祠、神社、鎮守の森など民俗学的分野も興味深いものがある。里山の風景では、自然界と精神世界が分ちがたくむすびついている。
◆著者について サブタイトル:カントリーサイド(里山)・ウォーキングのすすめ アメリカ人の著…






NHKテレビで「おかあさんといっしょ」という長寿番組が今も続いている。だいぶ昔に、お姉さんが朗読するコーナーがあった。ある話が妙に心に残った。それがなにかずっとわからなかった。
インターネットで検索するうちに判明した。1972年前後、別役実さんのオリジナル童話を田島令子さんが…




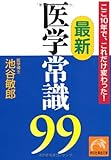
この10年で医学常識は変わった。(例)暗い所で読書しても視力は下がらない/37度は発熱ではなく、37.5度から/体温を上げると免疫力が上がるのはホント/卵を多めに食べてもコレステロール値は上がらない。





長生きされているおじいちゃん、おばあちゃんは特別な健康法をやっている訳ではない。特殊な呼吸法、高価なサプリメント、禁欲的な食事、苦行のような体操などを行っている話は聞かない。
著者の雨宮氏は武道の達人であり、日本呼吸器学会指導医でもある専門家である。 ◆危ない呼吸法 …
![]()





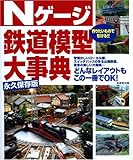
レイアウトを作るために必要な知識を網羅している。永久保存版を謳う内容に偽りなし。眺めているだけで楽しい。
◆レイアウト 「都市と自然のレイアウト」JR九州をテーマにビルが林立する都市部と緑深い山間部が美し…






雑誌の表紙、挿絵。レコードのジャケット。化粧品、デパートのポスターなどで、見たことがあるイラストでうれしくなる。
日本のイラストレーションの歴史を、1950年代から現代まで網羅。歴史を知るうえで欠かせないキーワー…






呼吸をコントロールすることによって、心をコントロールするのが坐禅の基本原理。著者は京都大を卒業後、臨済宗の僧侶となり、管長となる。管長を辞してから46歳で医学部に入学し、禅僧初の医師となった。
◆形を真似る 坐禅は姿勢を正すことから始める。形から入る。学ぶは「まねぶ=真似ぶ」。習うこと…




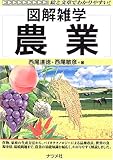
日本の農業は厳しい状態にある。原因は農業がもうからないから。狭い農地では充分な所得を得られない。高齢化し、後継者不足となる。農地を貸すか売却できない場合には耕作放棄となってしまう。
<日本農業の発展> ◆戦後の農地解放 (+)自作農となり意欲が高まり、戦後の食料不足を克服す…




「高級ペンよりも100円ペンをあちこちに置くと、いつでもメモできる」「ノートを縦2分割にすると1行の文字数が少なくて書きやすく、見やすい」…などすぐ使えるアイデアがいろいろ。





著者は29歳の女性である。野宿するのにお金はかからない。休みがなくても。一晩外で寝るだけでいい。体と寝袋があればいい。寝袋がなくてもいい。学生や貧乏旅行者だけがするものではない。野宿が愉しいからする。
<なんだって愉しめる人間になる> 著者は29歳の独身女性である。介護福祉士である。女子高校生…





禅の教えは頭で理解するものではない。知識や思考などを捨ててしまう必要がある。否定を重ねることによって、ことばで説明できない悟りとはなにかを説く。
◆坐禅は仏教よりも古い 坐禅は古代インドでは一般的な修行であった。仏陀は坐禅をして悟りを開いたこ…





坐禅を続けるうちに五官が鋭敏になってくる。自分という存在が透明になっていく感じがする。まわりの空気と一体化して、風、雨の音、鳥、蝉の声などがスーッと身体のなかを通り抜けいくような感覚を覚える。
◆坐禅 坐禅をはじめると、風の音、遠くの物音などそれまで気づいていなかった音が聞こえる。この…





禅の目的は、「無」になること。あらゆるものには永遠不滅の実体がなく、「我」もない。我という幻に翻弄されない不動心をもつ。
◆動機 この頃、気が弱くなってきた。そこで精神を鍛えようと思った。「禅」が思い浮かんだ。本書を選…




秘密の地下室、近親相姦的愛情、アルコール中毒、父殺し、薬物乱用、整形して別人になる、戦時下の虐殺行為、戦争ビジネスのからくり、双子の兄弟、などガジェット(ストーリー上の小道具、仕掛け)が盛りだくさん
◆芥川賞作家によるサスペンス長編 主人公は軍需産業で財を成した一族に生まれた。「邪」の家系。…






良い方に考えるのも、悪い方に考えるのも、自分である。性格は簡単に変えられないが、考え方は変えられる。受けとめ方を変える。今まで思いこんでいたものが変わって見える。
<考え方は変えられる> ◆人生の試練は何度も押し寄せる。 人は周囲の人々と自分との比較…






理趣経:欲望をもち、煩悩に悩まされている凡夫の暮らしのなかに真理に生きる姿を認めようとするもの。5世紀頃からインドではヒンドゥー教が台頭し、仏教も影響を受け、タントラ教的な密教経典が作られた。
<仏教がヒンドゥー教化されていく> ◆阿弥陀経(あみだきょう) 極楽浄土のみごとな姿を端的…






般若心経:あらゆる事物は他のものに条件づけられて、その限りにおいて存在する。固定的な実体を持っていない。「空」である。執着、悩みでもその本体は空である。だからこそ修行によってなくすことができる。
<民衆のあいだから起こった宗教運動> ◆般若心経(はんにゃしんぎょう) あらゆる事物は他の…






ダンマパダ(法句経):相手が失礼なことをしたと思っていたら、わだかまりができる。それは相手に伝わり、仕返しを受け、怨みがやまない。しかし、こちらがそれを忘れてしまえば、わだかまりは消えてしまう。
<人の心は2千年前から進化していない> ◆ダンマパダ(法句経) 人生の指針ともいうべき句を…