星の子






親から受けた洗脳はカビのように脳の中にまで根を張っていて、そう簡単に駆除できない。「家族」というものはそれほどにやっかいなものなのである。
少し前に、女優の渡辺えりさんの新聞紙上での人生相談の回答が評判を呼んだ。相談者は「何か気に入らないこ…

本が好き! 1級
書評数:382 件
得票数:2900 票
村上主義者。






親から受けた洗脳はカビのように脳の中にまで根を張っていて、そう簡単に駆除できない。「家族」というものはそれほどにやっかいなものなのである。
少し前に、女優の渡辺えりさんの新聞紙上での人生相談の回答が評判を呼んだ。相談者は「何か気に入らないこ…






村上春樹は今年69才。今でも毎朝10キロ走っているという。彼は今、自身の「老い」をどう感じているのだろうか。
タイトルの通り、村上春樹が「走る」ことをテーマに書き記したもの。本人の言によればこれは「メモワール」…






チャトウィンといえば紀行文の傑作『パタゴニア』があまりに有名だが、そのレッテルに反抗するかのように書かれた最後の小説。
チャトウィンといえば、紀行文の傑作『パタゴニア』があまりに有名。とはいえ、彼がパタゴニアに赴いたのは…






川上弘美が「ウェブ平凡」でずっと連載している「東京日記」の第五巻。
川上弘美が「ウェブ平凡」でずっと連載している「東京日記」の第五巻。これまで『卵一個ぶんのお祝い。』『…






今年の「新潮文庫の100冊」にもラインナップされています。自由研究となるとついつい肩ひじ張って背伸びしてしまいがちだけれども、いかにもな「結論」よりも「小さな気づき」のほうがずっとずっと大切で面白い。
編者は、静岡県の私立中学の先生。毎週、科学の面白さを伝える「リカちゃん新聞」というプリントを発行して…






誰にも頼ることなくたったひとりで世界と闘うことを決意し、生き続けた女性のたおやかで美しい記録。
メイ・サートンは1912年生まれ。科学史家の父親と芸術家の母親との間にベルギーで誕生し、第一次大戦時…






漱石は『坑夫』の執筆を通して『虞美人草』の「あちら側」にある世界を覗きに行ったのである。
大学の職と地位を捨て、持てる力をすべて注ぎ込んで臨んだ『虞美人草』だったが、その評判はかんばしいもの…





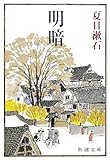
津田の病室で入れ替わり立ち替わりに繰り広げられる「お延」「お秀」「吉川夫人」らの丁々発止のやりあいは、壮絶なバトルといっていい。
『明暗』は「朝日新聞」に大正5年(1916年)5月26日から同年12月14日まで連載された。しかし漱…






清子が流産後の静養のために逗留している温泉場へ津田が赴き、ようやく清子との問答が始まったところで「未完」の文字が躍るのだから、その結末を夢想したくもなる。
漱石の『明暗』は、津田のかつての恋人であり、突然に自分の前から去って行った清子との再会のシーンで途絶…





漱石は欲張り過ぎた。ヒロイン・藤尾を「近代」、主人公小野の許嫁・小夜子を「前近代」とする対立軸まで設定したものだから、全体の結構がいびつになった。
朝日新聞入社の辞で大学を悪しざまに批判した漱石は、自ら退路を断ってこの『虞美人草』の執筆に臨んだ…






「村上柴田翻訳堂」の一作。100年以上の時を経ても、きわめて現代的なテーマがそこにある。まったく古びていない。
タイトルだけ見るとゴシックホラー小説のようだが、著者のハーディは19世紀後半のイギリスの大作家で、本…






「村上柴田翻訳堂」の一作。ラードナーの自由奔放な作風は「小説」というよりも「話芸」といったものに近い。
リング・ラードナーは1885年生まれ。巻末の村上春樹と柴田元幸との対談によれば、十代の頃から新聞にコ…






村上春樹と柴田元幸による絶版書籍の復刊シリーズ「村上柴田翻訳堂」の一冊。『救い出される』で描かれる南部独特の濃密な空気と薄気味の悪さは『闇の奥』のクルツの狂気に通じる。
アメリカ南部の田舎町に暮らす男四人が、ある日、カヌーでの川下りを計画する。彼らはそれぞれに家庭を持ち…






中上健次というひとは、これほどまでに美しい文章を書く作家だったのか。
中上健次というひとは、これほどまでに美しい文章を書く作家だったのか。読了して驚いたのは、まず、このこ…





これは面白かった。第一線で活躍するジャーナリスト10名へのインタビュー集。
これは面白かった。第一線で活躍するジャーナリスト10名へのインタビュー集。聞き手であり、編者を務める…





「iPad」デビューにまつわるエッセイ。タカハシさんは、筋金入りの「親指シフター」だったのだ。
高橋源一郎のTwitterアカウントを見ると「2009年12月に登録」とある。実際に、東日本大震災の…





帯には〈これは“本”ではない〉とある。賞金5千万円をかけたゲームブックだが、ストーリーもなかなかに面白い。
帯には〈これは“本”ではない〉とある。いわゆる「ゲームブック」と呼ばれるもので、位置情報ゲーム「イン…





新潮文庫創刊100年を記念したアンソロジーである。1914年から10年刻みで全10巻まで、毎月刊行されるらしい。
新潮文庫創刊100年を記念したアンソロジーである。編者はドイツ文学者の池内紀、評論家の川本三郎、編集…





中川翔子に「編者」として白羽の矢を立てたのは、出版社の慧眼といえる。
アンソロジーを編むのはなかなかに難しい。なにせ、膨大な書物の中からセレクトするわけである。どのような…






虐待は程度問題ではない。子どもの心に傷を残すような行為は、どんな些細なことであれすべて虐待だ。
新潮文庫の名作新訳コレクション、今月の一冊。『にんじん』といえば、児童文学の名著として名高い。小学校…