決断力 (角川oneテーマ21)




将棋棋士、羽生善治の本。「将棋の本」ではなく、将棋を通じた人生訓的な本。ここ一番の決断や、勝負の姿勢など。テクノロジー他で情報の共有が広まり、勝負が変質したという話は面白い。

本が好き! 1級
書評数:129 件
得票数:193 票
色々あって今は図書館で働いている人です。本は目についたものから読んでいくタチ……だと思ってたんですが、ここに書くようになってから自分がミステリとビジネス書に偏って読んでいることに気がつきました。




将棋棋士、羽生善治の本。「将棋の本」ではなく、将棋を通じた人生訓的な本。ここ一番の決断や、勝負の姿勢など。テクノロジー他で情報の共有が広まり、勝負が変質したという話は面白い。





P149「日本の出版産業が電子書籍で対峙する最大のライバルは、アップル、アマゾン、グーグルといった米国のネット企業です」電子書籍の話をお題に他ネットの話。
電子書籍に関する本です。タイトルに「グーグル」がないのが珍しいかなぁ、と思って手にとって見ました。…




見開き1ページにつき1名言1エピソード。ちょっとした時間の合間にジョブズの成功哲学について学べる本。結構たんたんと書かれている本なので純粋にジョブズについて知りたい人向け、若しくはジョブズファン向けです。





解説が基本の機能のみにしぼってあるのが良い。説明も完結。p80ページあたりの「友達認証」をどれくらいするのかという話は参考になる。facebookを試しに使ってみる前にちょっと読んでおくと良い本
facebook使いこなし術。僕は最近facebookを触り始めたヤツです。まだ友達も少なくて、途方…
![]()





「いまの若人たちが欲しがらないという見方も、彼らの興味対象がお金のかかるものからかからないものに転換されたことに大人が気づいていないだけなのかもしれない」僕もこの本で言うと「ソーシャルネイティブ世代」なんですが、結構あってると思いましたよ
この本の言う「ソーシャルネイティブ世代」とは1990年代前後に生まれた人たちのことで、ネットやゲー…





池上彰さんによる話をわかりやすくするための勉強法および情報の入手法。この本を読むと池上さんの情報へのアンテナのはり方、整理法、視点、切り口。池上さんがいかに超人かわかります。池上さんの域までは達せないですが、でも確実に参考になる本です。
池上彰の講談社現代新書「わかりやすさを考える」シリーズの最終巻。 わかりやすくニュースを伝…





「日本人にリスク回避の傾向があるのは、日本の社会のリスクが大きすぎるから」日本人は冒険心がない、弱腰だなどとバッサリ切られることに不満を持っている人は是非読んでみてください!
「日本人全体を特徴づけているこのリスク回避傾向は実はリスクが大き過ぎることに原因がある」 草…





「集団にはリーダーがいて部下がいる」そういう常識を覆す新しい組織、コミニュケーションの提案。ファシリテーターという新たな存在が集団の中核をなす。面白い視点。今の組織や集団に疑問を思ってるなら目からウロコかも
具体的でわかりやすい本だと思いました。本に出てくる「エコロジカル・コミュニケーション」というのもと…





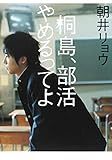
高校生の話です。描写がとっても丁寧でリアルで、自分の高校の時をふと考えてしまいました。学校って閉鎖的な空間なんですよね。こうして本にしてもらって客観的に見ると、なんかおかしい気がしますね。
高校生の話。野球部、バレー部、ブラスバンド部、映画部、ソフトボール部などなど。それぞれの部活に所属…





芸人エレキコミックやついさんの三国志解説本。「合コンに連れて行くならこの武将」「三国志ファン的にはググるのことを司馬るという」などなど、他の三国志解説とは違う視点が面白い。






獣の奏者の外伝。王獣編(2)と探求編(3)の間の話。僕は(2)と(3)の話の間エリンさんは平和に暮らしていたと漠然と思っていたんですが、まさかこんな激しい恋愛をしていたなんて……シリーズを読んだ人は是非






パワーポイントの使い方がスゴク良かったです。パワーポイントが使い慣れない大学生とかは絶対読んで欲しい
タイトル通り、わかりやすく伝えるってことに関する本なわけです。 構成としては前半3章までが池上さ…





データを見るってスゴイ。テレビとか雑誌で言っていることは本当なのか、実際にデータを見ると、本当は違うのかもしれません。
僕は数学がわからないヤツです。高校の時から数えて向こう十年以上数学の公式などからは無縁な生活をおくっ…





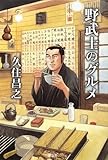
野武士がするような食事に憧れる人のエッセイです。一人で居酒屋に入ってウジウジ悩んでいたりするエッセイなんですが、とても素敵な本です。「一人で外食するのってこんなに楽しそうなんだ」って思います。僕は読んだ後一人で居酒屋に行きました.
「女将は年若くても、男性客のお母さんの役割を押し付けられてる。自分はそれがあまり好きではない。野武士…





読めば読むほど、これを書いた作者さんの伊達政宗と真田幸村への思い入れがヒシヒシと伝わってきます。この本を片手にそれぞれの名所にいけば、いままでとはまた別の見方ができるんじゃないでしょうか。