行動経済学―感情に揺れる経済心理

京都大学という自由度の高さが育んだ著者による経済学の最先端理論を解説した書。他説批判の正しさと自説展開の緻密さが光る良書である。
2010年刊。 著者は京都大学大学院経済学研究科教授(行動健康経済学・情報通信経済学)。 …

本が好き! 1級
書評数:949 件
得票数:2339 票
自己紹介文がまだありません。

京都大学という自由度の高さが育んだ著者による経済学の最先端理論を解説した書。他説批判の正しさと自説展開の緻密さが光る良書である。
2010年刊。 著者は京都大学大学院経済学研究科教授(行動健康経済学・情報通信経済学)。 …

近世英国国内生産と交易の内実を、蘭国等の諸国との比較を踏まえつつ論じ、イギリスにおける資本主義・自由交易国家成立のメカニズムと理由を明らかにしようとする書。少し古いが参考となる思考方法が詰まった良書
1979年刊行(初出1969~79年)。 著者は国際基督教大学客員教授・東京大学名誉教授。 …

本来の議院内閣制は、政府・官僚・与党が結合し巨大権力になる統治システム。ところが過去の経緯からかつてはそうではなく、一方で、現在の趨勢は過去と一線を画している。その様を諸外国と比較しつつ論じる良書。
2011年刊行。 著者は駒沢大学法学部教授(政治制度論・行政法)。 タイトルどおり、戦後日…

会計学の肝たる企業会計原則に言及しない本書は、会計学の基礎たる「会計」概念や財務諸表作成の目的論を解説するものだ。そしてそれは単にアメリカ会計制度礼賛一辺倒の書とは一線を画し、問題意識確立に資するもの
2009年刊。 著者は慶應義塾大学教授(財務会計論)。 その昔、会計学(のうち、会計公準と…

群集の齎す抗議活動への嫌悪感を隠さずに叙述する点は、感情過多でマイナス評価。だが、群衆を分析するための個別要素の解読は説得力十分。著者の感情に左右されないリテラシーを要求する大衆行動論の書。
1993年(底本1952年、原本初版1895年)刊。 著者はフランス社会心理学者。 なかな…

国際経済の観点では鋭い指摘も多々あるが、日本国内に関する分析については途端に稚拙な分析に止まってしまう。長短相俟った国際経済分析書である。
2000年(底本1997年、初出1991~95年)刊行。 著者はプリンストン大学教授(国際経済学)…
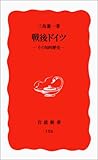
ナチス告発裁判と賠責の継続的な実施は、WWⅡ敗戦国ながら日独の差異は顕著。が、大衆の志向面での戦前との連続性とこれへの反駁・断絶性。これらの相克という複雑なドイツの様相を、戦前との連続性を基軸に解読
1991年刊行。 著者は学習院大学教授(独文学・独思想史)。 東西分割、独立後の再軍備…

インターネット空間の黎明期において、心の交感手段が拡充する実情と、その中で沈殿する無意識に光を当てる書。斬新ではあるが、論の運び方とアイロニーの選択とに疑問が残る。
2002年(底本1993年)刊。著者は大阪府立大学総合科学部教授。 恋人どうしの会話、電話の…

革命というべきケインズ経済学の内容と変遷を解説し、現代に対する影響と意義を解読せんとする。経済学の用語に精通していた方が読み易いが、そうでなくても読み込むことは可能な水準に設定されている。
1991年刊行。著者は京都大学経済学部助教授(現代経済学)。 経済学史において、ケインズが果…

ユーロの瓦解も、ドルに代替する基軸通貨化の何れの言説も誤謬だと指摘し、ユーロには地域統合通貨としての長短が共に伏在するとの分析を丁寧に行う好著。ユーロ圏の財政統合と共にドイツの重要性が浮き彫りに
2010年刊。 著者は中央大学経済学部教授(欧州経済、経済統合論)。なお16年刊の同著者・同テーマ…

18世紀末の書ながら、平和条約への醒めた現状認知の他、国家間連合や民主制の重要性と加え、常備軍の危険性という現在未到の観念にも言及する古典。ただ、永遠平和の前提たる道徳政治の意味把握は難儀かも
改版前1985年(初出1795~1796年、底本1964年)刊行。 (解説者曰く)フランス革…

史料が整う後北条氏を中心に、徴税システムや治安維持機構など、村と国人、あるいは戦国大名との関係性を具体的に提示し、従来は支配構造の断絶論が主流であった戦国と近世大名との比較論に、新風を巻き起こす書
2014年刊。 著者は駿河台大学教授(日本中世史)。 藤木久志氏らが議論を展開してきた中世…






電気自動車や再生可能発電システムに関する世界潮流からみて、その先見性を看取し得る好著。他方で、再生可能Eに関する国際競争において、日本企業の周回遅れと共に、政策対応の遅延も本書からは理解できそう
2009年刊。 著者は立命館大学大学院政策科学研究科教授・京都大学経済研究科特任教授(計量経済学・…

古典派経済学の学説史紹介の上巻に対し、下巻は、刊行時の理論経済学の中核、ケインズとマルクスの理論、これを支える統計経済学を解説。易しくはないが、読応えは十分。現代的問題意識と経済数学を齧った後に再読か
1981年(初定稿版1950年)刊。 著者は旧東京商科大学教授。上下巻中の下巻(予定されていた第三…

北朝鮮の核兵器開発の翻意・是正を目指す国連経済制裁。これを実効化あらしめるのが安保理の制裁委員会専門家パネル。この元職による内実開示本は、強制捜査権なく、非協力的委員が犇く中での苦心の様が赤裸々に
2017年刊。 著者は元国際連合安全保障理事会朝鮮民主主義人民共和国制裁委員会専門家パネル委員。 …

非正規労働や派遣社員の増大。明瞭化しつつある労働者間格差には歴史的淵源がある問題意識の下、格差の構造的問題や固定化懸念を「身分」という語で顕出化。組合の機能不全の害悪と労働時間規制の重要性も看取できる
2015年刊。 著者は元関西大学経済学部教授(企業社会論)。 (忘れられているかな)あ…

通常運転の水野氏に比し、榊原氏に関しては、個人的には意外に見える本書は、経済成長至上主義への懐疑論を展開。読み易く、資本主義のパラダイムシフト期との見立てには納得感がある他、興味深い言及も多い
2015年刊行。著者榊原は青山学院大学教授、同水野は日本大学国際関係学部教授。 アベノミクス…

広範な庶民の生活実像を開陳するのは流石の宮本節。常識が覆るという意味で印象的なのは、農民・山民の移動距離や範囲が広範な点と、庶民の村内社会秩序維持機構が儒教的価値基準とは甚だ乖離していた点
1987年(底本1976年。雑誌掲載1955~60年)刊。 著者は武蔵野美術大学教授。 …

貨幣の信用化体物論。マルクスを批判的に継承した論は、古典派経済学への鋭い匕首に。また、不均衡を原理的に志向する資本主義という解読は、あの「見えざる手」の欺瞞性を暴露し、古典派の問題点を広く開陳
1997年刊(底本1994年、雑誌他初出1987~93年)。 著者は東京大学経済学部教授。 …

戦時下の政府批判や怨嗟の声は、実は特高や内務省警保局などの摘発・取締機関に集積する。本書は、その一次史料や同時代の日記等から、戦時下の日常生活の実を開陳する。全然美しくない銃後の本音が垣間見える好著
2004年(底本1997年)刊。 著者は明治大学情報コミュニケーション学部助教授。 戦時下…