泣き虫弱虫諸葛孔明〈第1部〉






私の身近にも、小さな孔明、曹操、超雲、あともう一人だれかが鎮座しています。川本喜八による人形をもとにした、例のおまけですが。
映画版「レ・ミゼラブル」を見ていて不思議に思ったことがある。全編英語であったことだ。元のモデルにな…

本が好き! 1級
書評数:697 件
得票数:8276 票
学生時代は書評誌に関わってました。今世紀に入り、当初はBK1(現在honto)、その後、TRCブックポータルでレビューを掲載してました。同サイト閉鎖から、こちらに投稿するようになりました。
ニックネームは書評用のものでずっと使ってます。
サイトの高・多機能ぶりに対応できておらず、書き・読み程度ですが、私の文章がきっかけとなって、本そのものを手にとってもらえれば、うれしいという気持ちは変わりません。 特定分野に偏らないよう、できるだけ多様な書を少しずつでも紹介していければと考えています。
プロフィール画像は大昔にバイト先で書いてもらったものです。






私の身近にも、小さな孔明、曹操、超雲、あともう一人だれかが鎮座しています。川本喜八による人形をもとにした、例のおまけですが。
映画版「レ・ミゼラブル」を見ていて不思議に思ったことがある。全編英語であったことだ。元のモデルにな…





海賊(大名)たちから見た中世から近世への変化
「村上海賊の娘」以来、瀬戸内海賊が気になり、読んでみたのが本書。戦国時代における瀬戸内海賊の栄光を…






放送大学の新学期テキストですが、これだけでも十分に読みごたえがあり面白いです。(「日本近世史」に入れていた書評の再録です。お手数おかけしました)
本書は、書名どおり「日本の近世」を扱った放送大学の講義のテキストであるものの、文化を中心とした構成…






「日本近世史」の後継科目「日本の近世」の書評なのですが、検索しても「日本の近世」が出てこなかったので、こちらに投稿してしまいました。まぎわらしくてすみませんが、本書がとても面白かったのでご容赦を。
本書は、書名どおり「日本の近世」を扱った放送大学の講義のテキストであるものの、文化を中心とした構成…






そもそも「総力戦研究所」とは、研究所なのか? 教育機関なのか?
猪瀬氏の数あるノンフィクションの中でも、最も読まれそして最も人気のある1作といってよいだろう。私も…




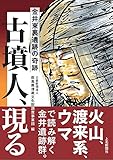
その人は、なぜそこで、甲を着けたまま倒れていたのか?
群馬県の「金井東裏遺跡」と言われても、「どのような遺跡なのか」を答えられる人は多くはないはずだ。ま…





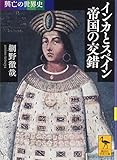
『はるかなる黄金帝国』という小説をおぼえていませんか?
小学校4年生の時に手にした小説『はるかなる黄金帝国』(やなぎやけいこ著)で、インカ帝国の存在とその…






「文明の絶滅」を考えさせられる
「なんとなく知っている」うちだった1冊。この「なんとなく」がくせ者で、そのうち、「読んだ気」になっ…






歴史の盲点を学ぶ力作
つい忘れがちだが、敗戦まで日本には「植民地」があった。もちろん、この程度の事であれば日本史の教科書…






日本の夏は宿題が多い。
昭和史研究家・保阪氏の大著である。文庫版でもそれぞれが600頁をこえる上下2巻構成で、十二分の読み…





戦争と経済の関係をどう考えたらよいのか?
日中戦争、そして日米戦争へと至る経緯についての本をいくつか読んでいくにつれ、その背景にあった「経済…





魅力的なタイトルなのだけれど
あの歴史的人物は、また、あの時代の人は、どのように買い物をしたのだろうか? などという素朴な好奇心…





骨は雄弁です。情報満載です。ついでに著者もよく語ります。
だいぶ前になるが、ある古典研究者の方が、「昔の日本人の身長がどれくらいだったのか知りたくなったのだ…





今は亡き新人物往来社より、歴史への妄想いや愛を込めて
「村上海賊の娘」以来、村上水軍もしくは瀬戸内海の海賊への興味が盛り上がってしまった。 まず、さ…





コンパクトながら元祖シンクタンクを手際よく紹介。考え、のちに何をすべきか?
「満鉄調査部」というものが、「元祖シンクタンク」と呼ばれていることは、何となくは知っていたのだけれ…






お江戸の政治経済史を読み直す
享保・寛政・天保の江戸時代の三大改革は、おそらく小学校の日本史でも習うであろう基本事項である。その…





「中世史」がわかりにくいかどうかは素人の私にはなんともいえませんが、ドラマにはなりにくいでしょう(ウケにくい?)。
本書は、中世史研究者が集まって執筆し15章で構成したオムニバスの新書である。編者2人による概論はあ…





働く女性の物語:江戸時代編は「奥奉公は、花嫁修業か女の一生の職業か。」
「女中」というと、「心ならずも他人の家で働き・・・」などというイメージがないだろうか。これが(江戸…






重い歴史を軽やかに語る。
著者は医史学を専門とする研究者。1930年代生まれだそうなので、この分野においては大先生といってよ…






「ところで渋沢は何を本職にしている大臣かね」(昭和天皇)
佐野真一「旅する巨人」が面白すぎて手にとったのが本書。おそらく、著者自身も書いていて楽しかったので…