さあ、本屋をはじめよう 町の書店の新しい可能性






本屋の専門家による「独立書店の紹介」と「独立書店の始め方」についての本。 20店舗ほどの独立書店のオーナーによる寄稿文に加えて、「本屋をはじめるのに参考になるブックガイド」も兼ねている。

本が好き! 1級
書評数:225 件
得票数:920 票
自己紹介文がまだありません。






本屋の専門家による「独立書店の紹介」と「独立書店の始め方」についての本。 20店舗ほどの独立書店のオーナーによる寄稿文に加えて、「本屋をはじめるのに参考になるブックガイド」も兼ねている。



途中まで面白かったが、結局、間取り関係ない。





冷戦終結後に書かれた「情報/消費社会」についての本。「情報/消費社会」を肯定的に捉えつつ、そのままでは資源、環境、貧困などの「限界問題」が解決されないことから、その「転回」を主張している。
その主張は現代のSDGsに極めて近いことは、以下の引用から分かる。 "転義としての「消費社会」…




猫が著した「人間の飼い慣らし方」のノウハウ本。





森博嗣による工作をキーとした教育・社会・仕事論。





斉藤幸平氏が『人新生の資本論』よりも前の2019年に刊行していた、マイケル・ハート、マルクス・ガブリエル、ポール・メイソンとの対談集。





ゲームクリエイター小島秀夫を作った本、映画、音楽にまつわる書評・エッセイ集。
単行本『僕が愛したMEMEたち~必要なのは、人にエネルギーを与えるMEME』(メディアファクトリー、…






釜ヶ崎(西成、あいりん地区)は広く薄く、日本全体へ溶け出しているのではないか。
釜ヶ崎の三畳のドヤ(日雇い労働者向けの簡易宿泊所)で30年以上暮らしながら、部屋の壁面三方は資料だら…





『スノーグース』『小さな奇蹟』『ルドミーラ』の3作からなる短編集。 「訳者あとがき」にあるように、3作品は主人公の人間と動物の心の交流を描いている点が共通している。
『スノーグース』は1940年に発表され、第二次世界大戦が物語に大きく関わっている。 『小さな奇…




『働きマン』などの安野モヨコによる、夫の庵野秀明氏との夫婦生活を描いたコミック。
時系列としては、『監督不行届』連載時期は2003~2004年。 2004年から『働きマン』の連載が…





『堕落論』『続堕落論』を含む9つのエッセイや小説からなる本。 坂口安吾を読んだのは初めてだが、著者についての感想は「戦前・戦中・戦後を生きたビート(北野)武」。
『堕落論』『続堕落論』を含む9つのエッセイや小説からなる本。 坂口安吾を読んだのは初めてだが、…






本書のテーマは大きく4つ。 ●アナログ商品市場の再形成。 ●ECは世界や各国の数社を除けば赤字。 ●デジタル自体に教育効果は無い。 ●GAFAなどデジタルサービストップ企業ほど業務ではアナログを重視している。
コロナ禍以前の2017年の刊行。 研究書、インタビュー集、エッセイを混ぜた感じ。 ●アナ…






テレビアニメ放送終了から旧劇場版公開までの間に行われた庵野秀明氏へのインタビューと、庵野氏不在での鶴巻和哉、貞本義行、摩砂雪、佐藤裕紀、大月俊倫などの各氏による言いたい座談会。
庵野氏のインタビューは1996年に行われたものながら、2021年放送のNHKのドキュメンタリー・イン…






ワガママお嬢様の夏子は、周囲の男性をつまらなく感じて修道院へ入ることを決める。しかしその道中で毅と出会い、あっさりと修道院入りをやめて毅に付いていく。旅路の果てに夏子が出した結論は?お騒がせ冒険譚。






主人公の血族が抱える病を中心にした、残酷とも美的ともいえる物語。






スプラッターホラーの残虐シーンにトリックを埋め込んだ仕掛け作品。 気づく人はすぐ気づくし、最後にビックリする人もいると思う。




「重いライトノベル」と思っていたけど、中年になって読み直すとライトノベル。





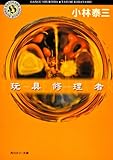
表題作の短編「玩具修理者」は、乙一どころではない、文字だけで語られる「世にも奇妙な物語」、マンガ・アニメ・ドラマ「岸辺露伴は動かない」も余裕でぶち抜くホラーの傑作。






天然パーマ、背が低い、一重、親が金持ちといった10種類のコンプレックスについて、武田砂鉄の論考、当事者インタビュー、インタビュー後の再考という構成で作られた本。 「遅刻」のインタビューが秀逸すぎる。






「逆転」とあるが「正転」だと思う。 またインタビュアーが素晴らしいので、インタビュー本として質が非常に高い。