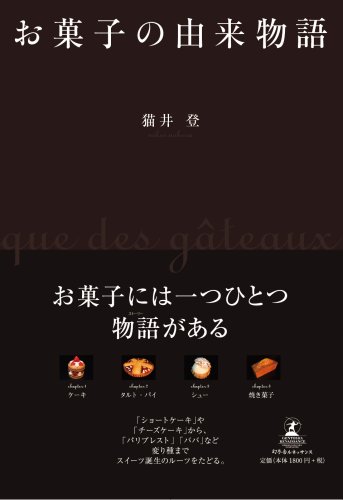▼
「シュークリーム」は立派な和製英語だ。これを英語圏で注文すると「靴クリーム」が出てくるというエピソードの真偽はともかくも、蓋ですくって食べるというのは、私の世代にとっては、常識だろう。
この本は、古今東西の(洋)菓子に関する「起源」、「由来」、そして時には「日本への伝来」が書かれている。
最初に取り上げられているのは「スポンジ」。「カスティーリャ王国のお菓子(カスティーリャ・ボーロ)」と呼ばれたスペインのこのお菓子は、そもそもはパンを日持ちさせる作業の中で生まれた物であり、それが鉄砲と伴もに日本に伝わって「カステラ」と「ボーロ」へと変遷したとある。続く「ショートケーキ」では、「ショート」が「短い」という意味での"short"ではなく、「サクサクしている」という意味としての"short"であるとし、日本で最初の「ショートケーキ」に関する2説を提示してある。
さらに面白い事に、「今日のショートケーキ」と題して、「ショートケーキを置いてないケーキ店が珍しい理由」にも触れている。(この事は、懇意のケーキ店でのマスターから聞いていたのだが、なんとも面白い話だ)
著者・猫井登氏の経歴が面白い。大手銀行に勤務していた著者は、お菓子に関して調べはじめたものの、その由来に関する本の少なさなどに奮起し、会社を辞めて本格的にお菓子の勉強をし、
を目指してこの本を書かれたそうだ。
猫井氏は1才年上なのだが、実は私も(洋)菓子には興味があって、学生の頃には、主に今田美奈子氏の著作を片手に、かなり真剣に作っていたし、そういう進路も考えなかったわけではなかった。が、なにしろ不器用な私は、何度作っても「シュー」が膨らまないことで挫折した(笑)
そういう訳で、この本に書かれている事の大半は(どこでだったかは忘れたが)何かで読んだものだったけれど、それ故に、猫井氏がこの本をまとめた情熱と苦労を充分に感じ取ることができた。
もちろん知らないことも多く書かれている。中でも面白かったのは、イギリスのパン菓子「スコーン」の項。その名前の由来には、ツタンカーメン王の玉座の下にあった「運命の石」が関係してるとの事。面白いのはここからで、そうして神聖な石を由来とするお菓子なので、ナイフで切ることはせず、しかも横方向に、手で割って食べるのがマナーとなっているというのだ。この「スコーン」項では「『運命の石』とは」というコラムが添えられているのだが、この所々に散りばめられたコラム(囲み薀蓄)がまた実に興味深く面白く、そして文章が巧い。
とまあ、こうして「お菓子(スイーツ)に関する薀蓄」の宝庫なので、もちろんお菓子好きの女子には、やや写真が平凡ではあるけれど、楽しい本だとは思う、が、なんといってもお薦めなのは「スイーツが好きな女の子」を好きな男子の熟読だ。
30年前のデートの鬼門「ミルフィユ」を食べることになった時など、
「よく『ミルフィーユ』って言うけど、このお菓子は千枚の木の葉って事だから『ミルフィユ』って発音するのが本当なんだってぇ」
などと言いながら、供されたミルフィユをおもむろに倒し、
「ほら、こうするとパイ生地が葉っぱみたいでしょ?倒してからなら食べやすいしね」
などと言ってあげれば、高得点を得られるかもしれないのだ、、、相手次第だけれどネ。
最初に取り上げられているのは「スポンジ」。「カスティーリャ王国のお菓子(カスティーリャ・ボーロ)」と呼ばれたスペインのこのお菓子は、そもそもはパンを日持ちさせる作業の中で生まれた物であり、それが鉄砲と伴もに日本に伝わって「カステラ」と「ボーロ」へと変遷したとある。続く「ショートケーキ」では、「ショート」が「短い」という意味での"short"ではなく、「サクサクしている」という意味としての"short"であるとし、日本で最初の「ショートケーキ」に関する2説を提示してある。
さらに面白い事に、「今日のショートケーキ」と題して、「ショートケーキを置いてないケーキ店が珍しい理由」にも触れている。(この事は、懇意のケーキ店でのマスターから聞いていたのだが、なんとも面白い話だ)
著者・猫井登氏の経歴が面白い。大手銀行に勤務していた著者は、お菓子に関して調べはじめたものの、その由来に関する本の少なさなどに奮起し、会社を辞めて本格的にお菓子の勉強をし、
ざっと読めば日本のケーキ店で売られているお菓子全般についての概略がわかる本」(「はじめに」より)
を目指してこの本を書かれたそうだ。
猫井氏は1才年上なのだが、実は私も(洋)菓子には興味があって、学生の頃には、主に今田美奈子氏の著作を片手に、かなり真剣に作っていたし、そういう進路も考えなかったわけではなかった。が、なにしろ不器用な私は、何度作っても「シュー」が膨らまないことで挫折した(笑)
そういう訳で、この本に書かれている事の大半は(どこでだったかは忘れたが)何かで読んだものだったけれど、それ故に、猫井氏がこの本をまとめた情熱と苦労を充分に感じ取ることができた。
もちろん知らないことも多く書かれている。中でも面白かったのは、イギリスのパン菓子「スコーン」の項。その名前の由来には、ツタンカーメン王の玉座の下にあった「運命の石」が関係してるとの事。面白いのはここからで、そうして神聖な石を由来とするお菓子なので、ナイフで切ることはせず、しかも横方向に、手で割って食べるのがマナーとなっているというのだ。この「スコーン」項では「『運命の石』とは」というコラムが添えられているのだが、この所々に散りばめられたコラム(囲み薀蓄)がまた実に興味深く面白く、そして文章が巧い。
とまあ、こうして「お菓子(スイーツ)に関する薀蓄」の宝庫なので、もちろんお菓子好きの女子には、やや写真が平凡ではあるけれど、楽しい本だとは思う、が、なんといってもお薦めなのは「スイーツが好きな女の子」を好きな男子の熟読だ。
30年前のデートの鬼門「ミルフィユ」を食べることになった時など、
「よく『ミルフィーユ』って言うけど、このお菓子は千枚の木の葉って事だから『ミルフィユ』って発音するのが本当なんだってぇ」
などと言いながら、供されたミルフィユをおもむろに倒し、
「ほら、こうするとパイ生地が葉っぱみたいでしょ?倒してからなら食べやすいしね」
などと言ってあげれば、高得点を得られるかもしれないのだ、、、相手次第だけれどネ。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分野を問わず、好奇心の赴くまま、同時に数冊を読み進めてしまう、しかしながら、恐ろしく遅読のおぢさん。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:幻冬舎ルネッサンス
- ページ数:192
- ISBN:9784779003165
- 発売日:2008年09月20日
- 価格:1890円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。