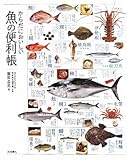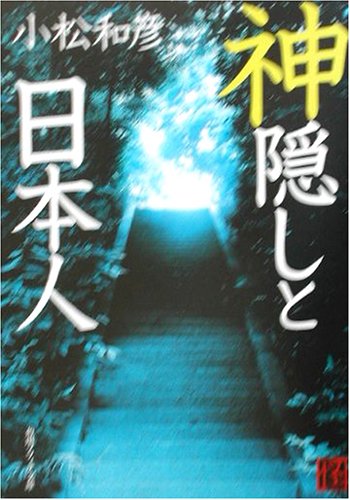風竜胆さん
レビュアー:
▼
「神隠し」、今となっては迷信にしか過ぎないが、かっては、それなりの社会的な役目があったのだ。
人が突然いなくなるという、現代では単に「失踪事件」と呼ばれるような出来事。少し前の時代までは、人ならざる者により異界へ連れて行かれたのだと考えられ、「神隠し」と呼ばれた。もちろん、そのような考え方は、近代合理性とは相容れないものであり、現代ではこの言葉は死語となってしまったかのように思える。この「神隠し」を民俗学的な視点から解き明かそうとしたものが本書、「神隠しと日本人」(小松和彦:角川書店)である。
「神隠し」を行う者は、「隠し神」と呼ばれ、それは天狗だったり、狐だったり、鬼だったりする。面白いことに、それぞれに目的が違うらしい。天狗は特に目的もなく人を連れまわすため、狐は人を化かすため、そして鬼は人を食うためと考えられていたそうだ。しかし、この「神隠し」の主体、今の感覚では、どれをとっても、「神」などではなく、「妖」と言う概念のなかに含まれそうである。一神教の世界なら、間違いなく「悪魔」の方に分類される者たちだろう。このあたりは、「神」と「人」と「妖」の境界があいまいな我が国の民俗文化の特徴のようで、極めて興味深い。
著者は、「神隠し」には4つのパターンがあると述べている。まず失踪者が無事に発見される場合でこれは本人が失踪中のことを覚えている場合と覚えていない場合の2つに分けられる。3つめは、行方不明のまま発見されない場合。そして4つ目は、死体となって発見される場合である。本書は、色々な文献に記されている「神隠し」の物語を取り上げ、その後ろに潜んでいるものについて考察を加えながら、最後に現代的視点から、「神隠し」を覆っているヴェールを引きはがす。
ヴェールをはがして見た「神隠し」は、自発的な失踪だったり、誘拐事件や殺人事件だったり自殺だったりと、人間社会のどろどろとした真相を私たちに見せつける。著者は<神隠しとは、こうした実世界の様々な現実をおおい隠すために作りだされ用いられた言葉であり観念だったように思われる>と述べている。「神隠し」は、失踪事件に対する解釈であり納得であり言い訳であったのだ。それは、現実の過酷さを和らげる緩衝装置の役割を果たしていたのだろう。かっての民俗社会自体が、「神隠し」というものを必要としていたのだ。
近代合理性だけに支配される世の中は味気ない。著者は最後の方で、<現代こそ実は「神隠し」のような社会装置が必要なのではないか>と括っている。しかし、「神隠し」に代るようなものを現代社会に見出すことができるのだろうか。
○小松和彦さんの他の著作に対するレビュー
・神になった人びと
「神隠し」を行う者は、「隠し神」と呼ばれ、それは天狗だったり、狐だったり、鬼だったりする。面白いことに、それぞれに目的が違うらしい。天狗は特に目的もなく人を連れまわすため、狐は人を化かすため、そして鬼は人を食うためと考えられていたそうだ。しかし、この「神隠し」の主体、今の感覚では、どれをとっても、「神」などではなく、「妖」と言う概念のなかに含まれそうである。一神教の世界なら、間違いなく「悪魔」の方に分類される者たちだろう。このあたりは、「神」と「人」と「妖」の境界があいまいな我が国の民俗文化の特徴のようで、極めて興味深い。
著者は、「神隠し」には4つのパターンがあると述べている。まず失踪者が無事に発見される場合でこれは本人が失踪中のことを覚えている場合と覚えていない場合の2つに分けられる。3つめは、行方不明のまま発見されない場合。そして4つ目は、死体となって発見される場合である。本書は、色々な文献に記されている「神隠し」の物語を取り上げ、その後ろに潜んでいるものについて考察を加えながら、最後に現代的視点から、「神隠し」を覆っているヴェールを引きはがす。
ヴェールをはがして見た「神隠し」は、自発的な失踪だったり、誘拐事件や殺人事件だったり自殺だったりと、人間社会のどろどろとした真相を私たちに見せつける。著者は<神隠しとは、こうした実世界の様々な現実をおおい隠すために作りだされ用いられた言葉であり観念だったように思われる>と述べている。「神隠し」は、失踪事件に対する解釈であり納得であり言い訳であったのだ。それは、現実の過酷さを和らげる緩衝装置の役割を果たしていたのだろう。かっての民俗社会自体が、「神隠し」というものを必要としていたのだ。
近代合理性だけに支配される世の中は味気ない。著者は最後の方で、<現代こそ実は「神隠し」のような社会装置が必要なのではないか>と括っている。しかし、「神隠し」に代るようなものを現代社会に見出すことができるのだろうか。
○小松和彦さんの他の著作に対するレビュー
・神になった人びと
投票する
投票するには、ログインしてください。
昨年は2月に腎盂炎、6月に全身発疹と散々な1年でした。幸いどちらも、現在は完治しておりますが、皆様も健康にはお気をつけください。
- この書評の得票合計:
- 82票
| 読んで楽しい: | 8票 | |
|---|---|---|
| 素晴らしい洞察: | 6票 | |
| 参考になる: | 67票 |
|
| 共感した: | 1票 |
|
あなたの感想は?
投票するには、ログインしてください。
この書評へのコメント
- 風竜胆2012-11-17 11:34
最近、この方の書かれた本を2冊買いましたが、読む暇がない・・・orz
1冊めはこれ、「憑霊信仰論 妖怪研究への試み」
以前読んだ、「神になった人々」もこの方の著書と言うことに気が付きましたので、リンクを張りました。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - 風竜胆2012-11-18 11:20
>miol morさん
実は、最近ケルト関係のこんな本も読んでいるのですが、他の分野のいろんな本を何冊も並行して読んでいるので、いつ読み終わることやらw
あそこの文化もいろいろと興味深いものがあります。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - 風竜胆2012-11-19 20:34
そう言えば、先般この方の本を2冊買って、1冊は紹介したけど、もう1冊を忘れていました。著者は、国際日本文化研究センターの所長さんだということです。
この本の参考文献を見ると、京極夏彦さんの著書なんかも入っていたのでちょっとびっくり。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:角川書店
- ページ数:238
- ISBN:9784043657018
- 発売日:2002年07月01日
- 価格:660円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。