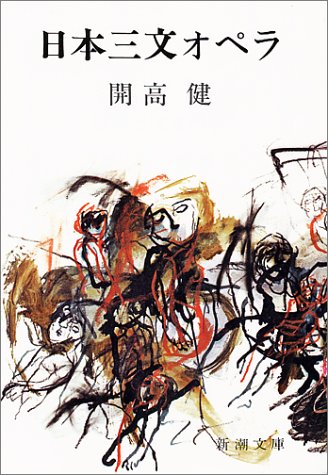三太郎さん
レビュアー:
▼
時は終戦後の昭和30年代前半で、物語の舞台は大阪市のど真ん中にあった大阪陸軍造兵廠跡地だ。そこでは毎夜、警官隊とアパッチ族の攻防戦が行われたという。
時は終戦後の昭和30年代前半で、物語の舞台は大阪市のど真ん中にあった大阪陸軍造兵廠跡地だ。ここは終戦直前の米軍による空爆により廃墟と化し、そのまま約20年間放置されていたという。
今の駅名でいえば大阪環状線の京橋と森ノ宮に挟まった所で、大阪城址の東側に、35万坪の敷地があったという。陸軍造兵廠は戦中は東洋一の軍需工場だったから、廃墟に残された金属資材の量も半端なかったらしい。そこに登場したのがこの物語の主人公たち「アパッチ族」だった。
ウィキペディアによれば『昭和30年から昭和34年にかけて、夜間になると川を越えて敷地内に不法侵入し、鉄くずを回収しては持ち去って売却する在日韓国人、在日朝鮮人らがいた。彼らと警察の攻防を新聞は「アパッチ族」と書き立てた』のだという。つまり新聞が名付け親らしい。アパッチ族が在日韓国人、在日朝鮮人だけでなかったろうことは容易に想像できるが。
著者の開高はアパッチ族が警察により解散させられた昭和34年にこの小説を発表した。34年というと僕はまだ2歳になったばかりだから、無論当時のことはなにも知らないのだけれど、戦後まもなくには日本の各地で似たようなことがあったのではないかな。何しろ当時は職のない人間が五万といて、一方では経済成長が始まり金属くずへの需要は旺盛だったろうから。
この物語の語り手のフクスケは大阪の町で乞食のような生活をしていたところを、アパッチ族の親方のキムに拾われて、衣食住と造兵廠跡地から金属スクラップを回収する仕事を与えられる。
僕の大学時代からの友人に、実家が戦後間もなくから金属の廃品回収業を営んでいる男がいた。彼の父親は戦後に朝鮮半島から渡って来て日本に帰化した。場所は大阪ではなくて東北地方のある県庁所在地の街の事だが、息子は国立大学に進んだのだから彼の実家は事業家として成功していたといえるだろう。だから戦後は似たような状況が各地にあったのだろうとは思うのだ。
小説のなかで親方のキムは造兵廠跡の守衛たちを京橋の串カツ屋で買収するのだが、大阪らしいエピソードかな。僕も会社員時代に一度だけ、ちょっと危なげな町の安ホテルに泊まって、近所の路地に軒を連ねた串カツ屋で飲んだことがあった。大阪には仕事で何度も訪れているが、街のことは案外よくは知らないなあ。
フクスケは親方のキムの家で食事を出して貰うのだが、おかずは牛か豚のモツの焼肉だ。戦後まもなくはモツは庶民の食べ物だったと思う。我が家でもモツの煮込みを子供の頃はよく食べた。主に鳥のモツだったが、肉屋で普通に売っていた。仙台の牛タンは今では名物だけれど、僕の子供の頃は父が飲み屋の帰りにお土産に買ってくるもので、これはたまにしか食べられなかった。
アパッチ族は分業制が徹底していて、造兵廠跡地に侵入してブツの在処を見つける者、ブツを掘り出して運搬する者、守衛や警察の動向を見張る者など体力に応じた職分があり、その他関連業務として渡し船を営業する者、川に落ちたブツを潜水して引き上げる者などなど。
運び出したブツは親方が買い取り、自分の敷地内に保管して買い手に引き渡す。親方は自分ではブツの運び出しには手を染めず、いわば故買商に徹している。これが盗品でなければ立派なリサイクル業者だ。
親方の夫婦はカカア天下でキムは女房に一目置いていた。彼らは済州島の出身で、そこは小石ばかりの不毛の地だったという。それで日本統治時代には多くの島民が日本へ移住したという。アイルランドのアラン島のような所だったろうか。
物語のクライマックスはアパッチ達と警官隊の最後の決戦である。この時初めてアパッチの親分たちは結束して一つの秘密作戦を決行するのだが・・・
このルポタージュ風の開高の小説が彼の代表作とされるのも頷けました。60年安保前夜の騒然とした街の雰囲気も感じられて楽しい読書でした。
今の駅名でいえば大阪環状線の京橋と森ノ宮に挟まった所で、大阪城址の東側に、35万坪の敷地があったという。陸軍造兵廠は戦中は東洋一の軍需工場だったから、廃墟に残された金属資材の量も半端なかったらしい。そこに登場したのがこの物語の主人公たち「アパッチ族」だった。
ウィキペディアによれば『昭和30年から昭和34年にかけて、夜間になると川を越えて敷地内に不法侵入し、鉄くずを回収しては持ち去って売却する在日韓国人、在日朝鮮人らがいた。彼らと警察の攻防を新聞は「アパッチ族」と書き立てた』のだという。つまり新聞が名付け親らしい。アパッチ族が在日韓国人、在日朝鮮人だけでなかったろうことは容易に想像できるが。
著者の開高はアパッチ族が警察により解散させられた昭和34年にこの小説を発表した。34年というと僕はまだ2歳になったばかりだから、無論当時のことはなにも知らないのだけれど、戦後まもなくには日本の各地で似たようなことがあったのではないかな。何しろ当時は職のない人間が五万といて、一方では経済成長が始まり金属くずへの需要は旺盛だったろうから。
この物語の語り手のフクスケは大阪の町で乞食のような生活をしていたところを、アパッチ族の親方のキムに拾われて、衣食住と造兵廠跡地から金属スクラップを回収する仕事を与えられる。
僕の大学時代からの友人に、実家が戦後間もなくから金属の廃品回収業を営んでいる男がいた。彼の父親は戦後に朝鮮半島から渡って来て日本に帰化した。場所は大阪ではなくて東北地方のある県庁所在地の街の事だが、息子は国立大学に進んだのだから彼の実家は事業家として成功していたといえるだろう。だから戦後は似たような状況が各地にあったのだろうとは思うのだ。
小説のなかで親方のキムは造兵廠跡の守衛たちを京橋の串カツ屋で買収するのだが、大阪らしいエピソードかな。僕も会社員時代に一度だけ、ちょっと危なげな町の安ホテルに泊まって、近所の路地に軒を連ねた串カツ屋で飲んだことがあった。大阪には仕事で何度も訪れているが、街のことは案外よくは知らないなあ。
フクスケは親方のキムの家で食事を出して貰うのだが、おかずは牛か豚のモツの焼肉だ。戦後まもなくはモツは庶民の食べ物だったと思う。我が家でもモツの煮込みを子供の頃はよく食べた。主に鳥のモツだったが、肉屋で普通に売っていた。仙台の牛タンは今では名物だけれど、僕の子供の頃は父が飲み屋の帰りにお土産に買ってくるもので、これはたまにしか食べられなかった。
アパッチ族は分業制が徹底していて、造兵廠跡地に侵入してブツの在処を見つける者、ブツを掘り出して運搬する者、守衛や警察の動向を見張る者など体力に応じた職分があり、その他関連業務として渡し船を営業する者、川に落ちたブツを潜水して引き上げる者などなど。
運び出したブツは親方が買い取り、自分の敷地内に保管して買い手に引き渡す。親方は自分ではブツの運び出しには手を染めず、いわば故買商に徹している。これが盗品でなければ立派なリサイクル業者だ。
親方の夫婦はカカア天下でキムは女房に一目置いていた。彼らは済州島の出身で、そこは小石ばかりの不毛の地だったという。それで日本統治時代には多くの島民が日本へ移住したという。アイルランドのアラン島のような所だったろうか。
物語のクライマックスはアパッチ達と警官隊の最後の決戦である。この時初めてアパッチの親分たちは結束して一つの秘密作戦を決行するのだが・・・
このルポタージュ風の開高の小説が彼の代表作とされるのも頷けました。60年安保前夜の騒然とした街の雰囲気も感じられて楽しい読書でした。
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
1957年、仙台に生まれ、結婚後10年間世田谷に住み、その後20余年横浜に住み、現在は仙台在住。本を読んで、思ったことあれこれを書いていきます。
長年、化学メーカーの研究者でした。2019年から滋賀県で大学の教員になりましたが、2023年3月に退職し、10月からは故郷の仙台に戻りました。プロフィールの写真は還暦前に米国ピッツバーグの岡の上で撮ったものです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:新潮社
- ページ数:289
- ISBN:9784101128023
- 発売日:1971年06月01日
- 価格:500円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。