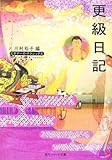休蔵さん
レビュアー:
▼
弥生時代の奴国の王都の可能性が限りなく高い福岡県春日市の須玖遺跡群の調査成果を紹介する1冊。当時の国の実態を垣間見ることができるはず。
「漢委奴国王」と刻まれた金印は、ほとんどの日本人が知っている考古遺物ではないだろうか。
金印にある奴国は『後漢書』倭伝にも出てくる国名で、「建武中元二年(西暦五七)、倭奴国、奉貢朝賀す。使人自ら大夫と称す。倭国の極南界なり。光武、賜うに印綬を以てす」とある。
その具体的な位置は福岡県福岡市から春日市、筑紫野市にかけて広がっていたと考えられているという。
そして、上記の国域の多くを占める福岡平野を見下ろす春日丘陵上に、本書が紹介する須玖遺跡群は位置する。
須玖遺跡群は奴国の王都と評価されている。
弥生時代の国というと邪馬台国を思い浮かべるが、須玖遺跡群では国という機構の様相が具体化しつつある。
王都という評価は、遺跡群が大規模で、遺構・遺物の量が膨大、内容も充実しているというところから得られたもののようだ。
矛や矢じりなどの武器あるいは武器型祭器などの青銅器を生産する、豊富な副葬品を持つ王墓が確認される、国内のみならず朝鮮半島産の遺物も数多く出土するなど、王都の具体を示す資料は他の弥生時代遺跡を圧倒する。
いわゆる農村とは乖離した姿と言え、王都たるゆえんである。
遺跡の発掘調査は、近年でも継続的に実施され続けている。
そのスタートは明治32年、1899年にまでさかのぼる。
長さ3.3m、厚さ0.3m、重量4tの大石が個人宅建設の時に見つかり、それをどかしたところ甕棺墓が見つかったことに始まる。
もっとも甕棺墓が見つかっただけなら大して注目を集めなかったのだろうが、そこから水銀朱や銅鏡、銅矛、銅剣の各破片、ガラス管玉などが見つかったのだ。
銅鏡は重なった状態での厚さが3寸、つまり9㎝程度で、研究の結果、30面以上はあったと評価されている。
しかも、直径20㎝以上の大型鏡が3面は含まれていたとそうだ。
このサイズの銅鏡は中国では王候クラスの墳墓に副葬されていたということで、王墓という評価が真実味を強くさせている。
弥生時代の国と言えば邪馬台国というイメージに拘泥していては、研究は前に進まない。
“おらが村の邪馬台国”をいたずらに主張し続けるより、確実な資料と真摯に向き合い、的確な評価を試みることが何より重要ということを、須玖遺跡群の調査成果は物語っている。
遠い未来のいつの日か、邪馬台国の位置が明確になり、その内容が追求される時が来るかもしれない。
そのためにも、まずは足元の遺跡の評価を進めておく必要がある。
須玖遺跡群は奴国の王都と評価され得る内容を持つ。
弥生時代の国の実態の追求が今後も継続的に進められ、いつの日か邪馬台国と対峙する場合に備えておく必要があろう。
本書は、多くの人たちが弥生時代の国の実態に触れるきっかけとなる1冊と言えよう。
金印にある奴国は『後漢書』倭伝にも出てくる国名で、「建武中元二年(西暦五七)、倭奴国、奉貢朝賀す。使人自ら大夫と称す。倭国の極南界なり。光武、賜うに印綬を以てす」とある。
その具体的な位置は福岡県福岡市から春日市、筑紫野市にかけて広がっていたと考えられているという。
そして、上記の国域の多くを占める福岡平野を見下ろす春日丘陵上に、本書が紹介する須玖遺跡群は位置する。
須玖遺跡群は奴国の王都と評価されている。
弥生時代の国というと邪馬台国を思い浮かべるが、須玖遺跡群では国という機構の様相が具体化しつつある。
王都という評価は、遺跡群が大規模で、遺構・遺物の量が膨大、内容も充実しているというところから得られたもののようだ。
矛や矢じりなどの武器あるいは武器型祭器などの青銅器を生産する、豊富な副葬品を持つ王墓が確認される、国内のみならず朝鮮半島産の遺物も数多く出土するなど、王都の具体を示す資料は他の弥生時代遺跡を圧倒する。
いわゆる農村とは乖離した姿と言え、王都たるゆえんである。
遺跡の発掘調査は、近年でも継続的に実施され続けている。
そのスタートは明治32年、1899年にまでさかのぼる。
長さ3.3m、厚さ0.3m、重量4tの大石が個人宅建設の時に見つかり、それをどかしたところ甕棺墓が見つかったことに始まる。
もっとも甕棺墓が見つかっただけなら大して注目を集めなかったのだろうが、そこから水銀朱や銅鏡、銅矛、銅剣の各破片、ガラス管玉などが見つかったのだ。
銅鏡は重なった状態での厚さが3寸、つまり9㎝程度で、研究の結果、30面以上はあったと評価されている。
しかも、直径20㎝以上の大型鏡が3面は含まれていたとそうだ。
このサイズの銅鏡は中国では王候クラスの墳墓に副葬されていたということで、王墓という評価が真実味を強くさせている。
弥生時代の国と言えば邪馬台国というイメージに拘泥していては、研究は前に進まない。
“おらが村の邪馬台国”をいたずらに主張し続けるより、確実な資料と真摯に向き合い、的確な評価を試みることが何より重要ということを、須玖遺跡群の調査成果は物語っている。
遠い未来のいつの日か、邪馬台国の位置が明確になり、その内容が追求される時が来るかもしれない。
そのためにも、まずは足元の遺跡の評価を進めておく必要がある。
須玖遺跡群は奴国の王都と評価され得る内容を持つ。
弥生時代の国の実態の追求が今後も継続的に進められ、いつの日か邪馬台国と対峙する場合に備えておく必要があろう。
本書は、多くの人たちが弥生時代の国の実態に触れるきっかけとなる1冊と言えよう。
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
ここに参加するようになって、読書の幅が広がったように思います。
それでも、まだ偏り気味。
いろんな人の書評を参考に、もっと幅広い読書を楽しみたい!
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:新泉社
- ページ数:0
- ISBN:9784787723338
- 発売日:2023年12月26日
- 価格:1870円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。