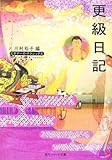DBさん
レビュアー:
▼
ウナギのライフサークルの本
筆者はスウェーデンの日刊紙の文芸記者だったそうで、子供の頃に家の近くの川で父親とウナギ釣りをした想い出が何度も語られます。
スウェーデンに住むヨーロッパウナギは大西洋北西部の四つの海流に囲まれたサルガッソー海で生まれる。
サルガッソー海は大航海時代には「魔の海」や「船の墓場」と呼ばれていたが、海面がサルガッサムという褐色の粘り気のある海藻に覆われていて、この海藻の絨毯が魚やクラゲ、カメ、エビ、微小な無脊椎生物を守り育んでいる。
そして深いところではまた別種の海藻が生い茂り闇の中に生命が満ち溢れた場所だ。
ここで卵から孵ったウナギは、柳の葉に似た透明で平らな身体を持つ数ミリのレプトセファルスとなって海流に乗り、大西洋を漂ってヨーロッパ沿岸にたどり着く。
時間をかけて成長しながら旅するウナギは、ヨーロッパ沿岸につくころには人差し指くらいの長さのシラスウナギになっている。
そこから川をさかのぼって淡水に順応したウナギは成長して黄ウナギとなり、定住して何年も過ごす。
そしてある日繁殖を思い立ったウナギは生まれた海を目指して泳ぎ始め、背中が黒ずみ脇腹に銀の横縞が浮き出した銀ウナギとなってサルガッソー海へと還り子孫を残して死んでいく。
早くて八年、長ければ三十年くらい黄ウナギで過ごすようですが、個々のウナギが故郷へ帰ろうと思うタイミングはわかっていないらしい。
脂肪の蓄積と成長が一定の線を越えたらという科学的な話ではなく、あくまで故郷に呼ばれる日があるという語りになっているのが興味深い。
壮大な生活史を持つウナギですが、その生態は長い間謎だったそうで、銀ウナギになってようやく生殖器が形成されるためアリストテレスの「ウナギは泥から発生する」という説が長いこと信じられていたそうです。
十八世紀後半になってようやくウナギも通常の魚と同じく卵から生まれることが発見され、二十世紀になってようやくデンマーク人のシュミットによってサルガッソー海が繁殖地であることが発見された。
このウナギ研究に心理学者のフロイトが関わっていたこともあるのは初耳でした。
ウナギ研究と歴史の話の間に、筆者と父親のウナギ釣りの体験が挟まれていることでウナギの世界が神秘的に語られていた。
あのレイチェル・カーソン女史もウナギに魅せられた一人で、ウナギのアンギラを主人公にした小説を書いていたそうだ。
日本人にウナギというと鰻重を思い浮かべる人がほとんどだろう。
食用のイメージが強すぎてなかなかウナギで哲学を語る気になれない部分もあるが、塚本教授が二ホンウナギの生まれ故郷がマリアナ諸島の西の海域であることを突き止めたという話も一ページだけだけど出てきます。
ウナギの養殖は本書が上梓された頃はまだ失敗の連続だったようですが、最近近大が成功したというニュースを見ました。
マグロといい近大はいい仕事をしているなと思ったが、天然のウナギは絶滅の危機に瀕している。
日本人が食い尽くしていると言われないためにも、ウナギの生態がもっと詳しくわかって保護してほしいと思う。
ウナギだけでなく海を守ること、地球を守ることが未来につながる話でした。
スウェーデンに住むヨーロッパウナギは大西洋北西部の四つの海流に囲まれたサルガッソー海で生まれる。
サルガッソー海は大航海時代には「魔の海」や「船の墓場」と呼ばれていたが、海面がサルガッサムという褐色の粘り気のある海藻に覆われていて、この海藻の絨毯が魚やクラゲ、カメ、エビ、微小な無脊椎生物を守り育んでいる。
そして深いところではまた別種の海藻が生い茂り闇の中に生命が満ち溢れた場所だ。
ここで卵から孵ったウナギは、柳の葉に似た透明で平らな身体を持つ数ミリのレプトセファルスとなって海流に乗り、大西洋を漂ってヨーロッパ沿岸にたどり着く。
時間をかけて成長しながら旅するウナギは、ヨーロッパ沿岸につくころには人差し指くらいの長さのシラスウナギになっている。
そこから川をさかのぼって淡水に順応したウナギは成長して黄ウナギとなり、定住して何年も過ごす。
そしてある日繁殖を思い立ったウナギは生まれた海を目指して泳ぎ始め、背中が黒ずみ脇腹に銀の横縞が浮き出した銀ウナギとなってサルガッソー海へと還り子孫を残して死んでいく。
早くて八年、長ければ三十年くらい黄ウナギで過ごすようですが、個々のウナギが故郷へ帰ろうと思うタイミングはわかっていないらしい。
脂肪の蓄積と成長が一定の線を越えたらという科学的な話ではなく、あくまで故郷に呼ばれる日があるという語りになっているのが興味深い。
壮大な生活史を持つウナギですが、その生態は長い間謎だったそうで、銀ウナギになってようやく生殖器が形成されるためアリストテレスの「ウナギは泥から発生する」という説が長いこと信じられていたそうです。
十八世紀後半になってようやくウナギも通常の魚と同じく卵から生まれることが発見され、二十世紀になってようやくデンマーク人のシュミットによってサルガッソー海が繁殖地であることが発見された。
このウナギ研究に心理学者のフロイトが関わっていたこともあるのは初耳でした。
ウナギ研究と歴史の話の間に、筆者と父親のウナギ釣りの体験が挟まれていることでウナギの世界が神秘的に語られていた。
あのレイチェル・カーソン女史もウナギに魅せられた一人で、ウナギのアンギラを主人公にした小説を書いていたそうだ。
日本人にウナギというと鰻重を思い浮かべる人がほとんどだろう。
食用のイメージが強すぎてなかなかウナギで哲学を語る気になれない部分もあるが、塚本教授が二ホンウナギの生まれ故郷がマリアナ諸島の西の海域であることを突き止めたという話も一ページだけだけど出てきます。
ウナギの養殖は本書が上梓された頃はまだ失敗の連続だったようですが、最近近大が成功したというニュースを見ました。
マグロといい近大はいい仕事をしているなと思ったが、天然のウナギは絶滅の危機に瀕している。
日本人が食い尽くしていると言われないためにも、ウナギの生態がもっと詳しくわかって保護してほしいと思う。
ウナギだけでなく海を守ること、地球を守ることが未来につながる話でした。
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
好きなジャンルは歴史、幻想、SF、科学です。あまり読まないのは恋愛物と流行り物。興味がないのはハウツー本と経済書。読んだ本を自分の好みというフィルターにかけて紹介していきますので、どうぞよろしくお願いします。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:新潮社
- ページ数:0
- ISBN:9784102201718
- 発売日:2023年07月28日
- 価格:880円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。