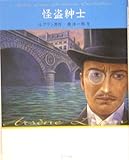休蔵さん
レビュアー:
▼
日本庭園の歴史を知るために最適な1冊。なんとなく眺めていた日本庭園の底流を理解することができる気がする。
国内観光の目的地の1つとして、著名な日本庭園を選択することがある。
日本庭園と言えば、鯉が泳ぐ池があって、松が植えられており、芝生の間を遊歩道が通るイメージがある。
あるいは、水を白い玉砂利で表現し、奇岩で雰囲気を引き立てた枯山水も思い浮かぶ。
しかしながら、日本庭園のイメージを醸造してきた歴史的背景については、恐ろしいほど無知であった。
そこで、本書を手にしてみた。
本書は独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所に在籍し、庭園研究を推進してきた著書が発表してきた論文をまとめたもの。
数多く発表してきたものの中から8編を選定したもので、古代から中世、近世そして近代の主要庭園を取り上げて、流れを分かりやすく示した1冊だ。
古代の庭園は、遺跡で確認されるものが主体である。
そのためか、奈良県が主体となっている。
なかなか触れることが難しい古代庭園であるが、発掘調査成果をもとに復元された事例がいくらか存在する。
奈良市平城京跡の東院庭園はその際たるもので、古代庭園の雰囲気を知るうえで欠かせないものと言える。
平安時代には神泉苑が形成された。
この雰囲気は地方の神社などにかろうじて残る場合があり、在住県内にも類例がありそうなので、旅行という手段をとらなくても楽しめそうだ。
そして、なにより日本庭園の基礎を形成したきっかけは禅宗の導入であろう。
今でも数多くの禅宗寺院に厳かな雰囲気の庭園が存在する。
苔生して、樹々が覆い、薄暗く物静かな雰囲気がある禅宗寺院であるが、築庭当初の雰囲気までは分からない。
案外明るく、通気性の良いものなのかもしれない。
枯山水も時代により異なることを知った。
桃山時代には華やかな色彩の花により彩られていたというのだ。
“枯”という響きとは異なる雰囲気を桃山時代の枯山水庭園は持っていたようだが、江戸時代には枯れてしまったようだ。
この桃山時代は、日本庭園を語るうえで重要な時代らしい。
幾何学的な刈込みも行われたとのことで、それも日本独自で発生した可能性もあるというのだ。
植樹も行われてようだが、
そして、庭園を観光資源とすることも行われていたようだ。
ただし、寺院庭園の場合、見学が許されるのはその宗派の帰依者のみ。
あくまで、訪問する帰依者に快適な非日常性を感じさせる接遇の装置として捉えていたそうだ。
日本庭園の歴史をざっと追及できるとともに、観光資源たる庭園の出現状況についても知ることができた。
日本庭園そのものというよりその歴史展開を手っ取り早く理解するためには最適な1冊と感じた。
日本庭園と言えば、鯉が泳ぐ池があって、松が植えられており、芝生の間を遊歩道が通るイメージがある。
あるいは、水を白い玉砂利で表現し、奇岩で雰囲気を引き立てた枯山水も思い浮かぶ。
しかしながら、日本庭園のイメージを醸造してきた歴史的背景については、恐ろしいほど無知であった。
そこで、本書を手にしてみた。
本書は独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所に在籍し、庭園研究を推進してきた著書が発表してきた論文をまとめたもの。
数多く発表してきたものの中から8編を選定したもので、古代から中世、近世そして近代の主要庭園を取り上げて、流れを分かりやすく示した1冊だ。
古代の庭園は、遺跡で確認されるものが主体である。
そのためか、奈良県が主体となっている。
なかなか触れることが難しい古代庭園であるが、発掘調査成果をもとに復元された事例がいくらか存在する。
奈良市平城京跡の東院庭園はその際たるもので、古代庭園の雰囲気を知るうえで欠かせないものと言える。
平安時代には神泉苑が形成された。
この雰囲気は地方の神社などにかろうじて残る場合があり、在住県内にも類例がありそうなので、旅行という手段をとらなくても楽しめそうだ。
そして、なにより日本庭園の基礎を形成したきっかけは禅宗の導入であろう。
今でも数多くの禅宗寺院に厳かな雰囲気の庭園が存在する。
苔生して、樹々が覆い、薄暗く物静かな雰囲気がある禅宗寺院であるが、築庭当初の雰囲気までは分からない。
案外明るく、通気性の良いものなのかもしれない。
枯山水も時代により異なることを知った。
桃山時代には華やかな色彩の花により彩られていたというのだ。
“枯”という響きとは異なる雰囲気を桃山時代の枯山水庭園は持っていたようだが、江戸時代には枯れてしまったようだ。
この桃山時代は、日本庭園を語るうえで重要な時代らしい。
幾何学的な刈込みも行われたとのことで、それも日本独自で発生した可能性もあるというのだ。
植樹も行われてようだが、
そして、庭園を観光資源とすることも行われていたようだ。
ただし、寺院庭園の場合、見学が許されるのはその宗派の帰依者のみ。
あくまで、訪問する帰依者に快適な非日常性を感じさせる接遇の装置として捉えていたそうだ。
日本庭園の歴史をざっと追及できるとともに、観光資源たる庭園の出現状況についても知ることができた。
日本庭園そのものというよりその歴史展開を手っ取り早く理解するためには最適な1冊と感じた。
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
ここに参加するようになって、読書の幅が広がったように思います。
それでも、まだ偏り気味。
いろんな人の書評を参考に、もっと幅広い読書を楽しみたい!
- この書評の得票合計:
- 43票
| 読んで楽しい: | 4票 | |
|---|---|---|
| 参考になる: | 39票 |
|
あなたの感想は?
投票するには、ログインしてください。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:吉川弘文館
- ページ数:182
- ISBN:9784642016513
- 発売日:2015年09月29日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。