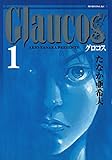shawjinnさん
レビュアー:
▼
暗渠となったかつての川は、大雨のときにだけ、本来の流れを取り戻す。
たとえば、東京都の目黒川をずっと上流にたどっていくと、池尻大橋駅近くの国道246号線と交差するところで唐突に途切れていることがわかる。そこから上流は緑道となっていて地下に水路がある。地上のせせらぎは人工水路だ。
ならば、目黒川の水はどこから来ているのかといえば、新宿区の落合水再生センター(下水処理場)からの高度処理水が導水されている。導水場所は池尻北児童遊園の地下である。更にさかのぼれば、東京都の上水道は利根川、荒川、多摩川から取水しているので、結局のところ、目黒川の主たる水源は利根川、荒川、多摩川の水なのだ。まあ、一回利用されて水再生センター(下水処理場)を経由しているのだけれども。
このような具合に都市部の川は、人工の度合いが高い。蓋をされてしまった川には、幹線下水道管が配備されていることが多い。東京23区の下水道の8割は合流式なので、マンホール等からの雨水と、各建物からの汚水が一緒の下水道管を流れている。もちろん、全ての下水道管は水再生センターにつながっていて、普段はそこで下水処理されている。
たとえば、本書にも紹介されている目黒川の支流である羅漢寺川は、今では全流路が暗渠化されていて、地下には羅漢寺川幹線という幹線下水道管が敷設されている。その羅漢寺川幹線は山手通りの地下にある目黒川幹線に接続されていて、最終的には大田区の森ケ崎水再生センターにつながっている。
ところが大雨のときには、マンホール等で集められた大量の雨水で薄められた下水道管の中の汚水は、普段の流路からこぼれ落ちて、羅漢寺川幹線の別ルートを通って目黒川に直接注がれるようになる。水の流れは下水道設備の構造が生む自然の法則で決まるので、水門では制御していない(分水人孔)。目黒川との合流点は目黒雅叙園アルコタワーの向かいあたりにある。大雨のときに下水を川へ直接流すのは、水再生センターの容量オーバーを防ぐための処置である。川が臭うことがあるのは、汚水混じりなので仕方がない。もちろん、ろ過機が付いている分水人孔もあるのだけれども。
要は、流れる水が大量になると、暗渠から川へと直接注がれる流路ができる。つまり、大雨のときだけ、かつての川は本来の流れを取り戻すのだ。目黒川流域のアスファルトに降った雨は、マンホール等を介して地域の低い場所へ向かう。そこにあるのは、今や基幹下水道管になった暗渠支流だ。そして、暗渠支流の水は目黒川へと注がれる。これは、暗渠支流が自然河川だったときの水の流れと同じである。
なお、目黒川の支流には、空川(そらかわ)、蛇崩川(じゃくずれがわ)、谷戸前川(やとまえがわ)、羅漢寺川(らかんじがわ)、戸越銀座通りに沿って流れていた川、古戸越川(ことごえがわ)などがあり、今では全て暗渠となっている。また、上流部は、北沢川(きたざわがわ)と烏山川(からすやまがわ)の二股になっていて、これらに注がれる支流も含めて全て暗渠となっている。
そんな暗渠にも様々なたたずまいがある。人工水路との二段構造、緑道、普通の道路などなど。秘密基地のような裏路地感のある暗渠道は特にワクワク度が高い。羅漢寺川の暗渠道には、豊富な湧き水が出ている段丘崖があって、かつてその湧き水は陶器の瓶に注がれていた。それが樹脂製のL型パイプと排水口に変わってしまって、ちょっと残念に思ったことがある。でも、ご近所の人は、今の形状の方が良いと思っているのかもしれない。
妙なかたちをしている道路が暗渠だとわかったときの納得感や、地形の凹凸の理由や、自然河川だったときの流域ごとの土地の雰囲気の違いなど、暗渠を巡っていると色々なことに気づいて楽しい。
本書は、暗渠界隈の有名ライターが揃い踏みをしているので、個別の著作で更に深掘りすることも。
ならば、目黒川の水はどこから来ているのかといえば、新宿区の落合水再生センター(下水処理場)からの高度処理水が導水されている。導水場所は池尻北児童遊園の地下である。更にさかのぼれば、東京都の上水道は利根川、荒川、多摩川から取水しているので、結局のところ、目黒川の主たる水源は利根川、荒川、多摩川の水なのだ。まあ、一回利用されて水再生センター(下水処理場)を経由しているのだけれども。
このような具合に都市部の川は、人工の度合いが高い。蓋をされてしまった川には、幹線下水道管が配備されていることが多い。東京23区の下水道の8割は合流式なので、マンホール等からの雨水と、各建物からの汚水が一緒の下水道管を流れている。もちろん、全ての下水道管は水再生センターにつながっていて、普段はそこで下水処理されている。
たとえば、本書にも紹介されている目黒川の支流である羅漢寺川は、今では全流路が暗渠化されていて、地下には羅漢寺川幹線という幹線下水道管が敷設されている。その羅漢寺川幹線は山手通りの地下にある目黒川幹線に接続されていて、最終的には大田区の森ケ崎水再生センターにつながっている。
ところが大雨のときには、マンホール等で集められた大量の雨水で薄められた下水道管の中の汚水は、普段の流路からこぼれ落ちて、羅漢寺川幹線の別ルートを通って目黒川に直接注がれるようになる。水の流れは下水道設備の構造が生む自然の法則で決まるので、水門では制御していない(分水人孔)。目黒川との合流点は目黒雅叙園アルコタワーの向かいあたりにある。大雨のときに下水を川へ直接流すのは、水再生センターの容量オーバーを防ぐための処置である。川が臭うことがあるのは、汚水混じりなので仕方がない。もちろん、ろ過機が付いている分水人孔もあるのだけれども。
要は、流れる水が大量になると、暗渠から川へと直接注がれる流路ができる。つまり、大雨のときだけ、かつての川は本来の流れを取り戻すのだ。目黒川流域のアスファルトに降った雨は、マンホール等を介して地域の低い場所へ向かう。そこにあるのは、今や基幹下水道管になった暗渠支流だ。そして、暗渠支流の水は目黒川へと注がれる。これは、暗渠支流が自然河川だったときの水の流れと同じである。
なお、目黒川の支流には、空川(そらかわ)、蛇崩川(じゃくずれがわ)、谷戸前川(やとまえがわ)、羅漢寺川(らかんじがわ)、戸越銀座通りに沿って流れていた川、古戸越川(ことごえがわ)などがあり、今では全て暗渠となっている。また、上流部は、北沢川(きたざわがわ)と烏山川(からすやまがわ)の二股になっていて、これらに注がれる支流も含めて全て暗渠となっている。
そんな暗渠にも様々なたたずまいがある。人工水路との二段構造、緑道、普通の道路などなど。秘密基地のような裏路地感のある暗渠道は特にワクワク度が高い。羅漢寺川の暗渠道には、豊富な湧き水が出ている段丘崖があって、かつてその湧き水は陶器の瓶に注がれていた。それが樹脂製のL型パイプと排水口に変わってしまって、ちょっと残念に思ったことがある。でも、ご近所の人は、今の形状の方が良いと思っているのかもしれない。
妙なかたちをしている道路が暗渠だとわかったときの納得感や、地形の凹凸の理由や、自然河川だったときの流域ごとの土地の雰囲気の違いなど、暗渠を巡っていると色々なことに気づいて楽しい。
本書は、暗渠界隈の有名ライターが揃い踏みをしているので、個別の著作で更に深掘りすることも。
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
読んでいて面白い~と思った本の読書記録です。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:筑摩書房
- ページ数:256
- ISBN:9784480434814
- 発売日:2017年11月09日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。
『はじめての暗渠散歩: 水のない水辺をあるく』のカテゴリ
登録されているカテゴリはありません。