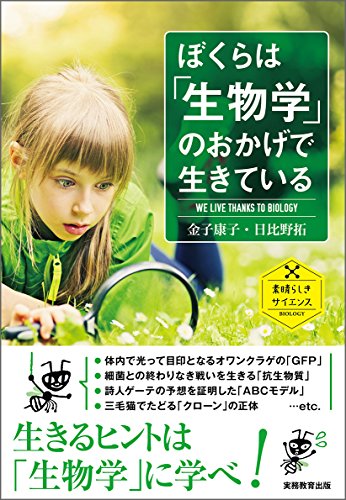▼
生物学が教えてくれること
「生物学」は何の役に立つか、と問われたら、実のところ、それほど直接目に見える形で役に立っている部分は多くはないだろう。生物の生態を知り、進化について学び、体の仕組みを調べても、即刻、暮らしが豊かになるわけではないし、逆にそれを知らなければ死んでしまうというわけでもない。
しかし、長い目で見ていったときに、生物が作り出すものや働きを人が利用している例は多い。生命全般に共通する仕組みを知ることが、例えば医薬品の開発に役立つことがある場合もあるし、人と他の動物の違いを見ていくことで、意外な気づきがあることもある。体の中に同居する生物が、実は私たちを助けてくれていることもわかってきている。
本書では、あまり広くは知られていないけれど、人の暮らしと案外関連する、そんな事象や研究エピソードをあれこれ紹介する。
著者の金子氏は植物細胞生物学、日比野氏は発生生物学・比較免疫学が専門の研究者。著者らの専門分野が中心の、幅広い話題を拾っている。1つのトピックが数ページであり、挿絵や顕微鏡写真などの図版も多いため、比較的気軽に読み進められる一方、科学的にしっかりした記述で安心して読める。
いくつか紹介してみる。
2008年のノーベル化学賞受賞で話題になったクラゲの緑色蛍光タンパク質(GFP)。これはクラゲの発光では、むしろ脇役のタンパク質で、主役であるイクオリンが発する青い光を黄緑色に変化させるタンパク質だ。なぜ主役でなく脇役が注目されたかといえば、クラゲの発光における価値というよりも、応用研究に役立った点が評価されたためだ。
イクオリンはカルシウムイオン濃度の変化に反応して発光するが、GFPは光を当てるだけで発光する。毒性がほぼないため、生きた細胞内で使うことも可能となる。そのため、例えば、がん細胞にGFPで目印を付ければ、増殖や転移の仕方が観察できることになる。さらには個々のタンパク質にGFPをくっつけて、そのタンパク質がいつどこで発現されるか確認するようなことも可能である。
クラゲの中では、光の色を変えるという、いささか地味な仕事をしていたタンパク質が、幅広くその後の研究に大きな可能性を拓いたことになる。
オス・メスをめぐる話もおもしろい。
生物では、オスがメスよりも大きい一夫多妻制を採る種がある。強いオスがハーレムを作り、子孫を残す形だ。これとは逆に、オスが小さい種もある。クモやカマキリが代表例だ。さらに、オスが極端に小さい「矮雄」と呼ばれるものもある。アンコウの仲間である。アンコウは食材として出回るのはほとんどメスだという。ある種などは、メスが2mという巨大サイズなのに、オスは15cm。深海では生殖相手に滅多に出会えないため、一度出会うとオスはメスの皮膚に噛みついて離れないようにする。その後、何と、皮膚も血管も融合してしまい、目や心臓もなくしてしまう。残るのは、精巣の機能だけ。
愛の究極形といえば聞こえはよいが、生きる厳しさ・すさまじさも感じるようなエピソードである。
将来的に広がっていきそうなのが「DNAナノテクノロジー」の話。DNAは生物のいわば設計図で、生物はそれぞれ、種に特有のDNAを持ち、これに基づいてタンパク質が合成されて体が作られていく。
DNA(デオキシリボ核酸)は、塩基A、C、G、Tが異なる4種の構成単位で作られる長い鎖である。AはT、CはGとフックのように対を作る。鎖は2本で1セット、向かい合って二重らせんを形成する。一方の鎖がATCGGTであれば反対の鎖はTAGCCAと並ぶことになる。
熱を加えればらせんはほどけるが、温度を下げると元の二重らせん構造に戻る。二本鎖の方が安定なためである。
DNAの性質を利用して、データ記憶媒体とすることが出来れば、現在のコンピュータの0、1の2進法でなく、A、C、G、Tの4進法が使えることになり、同じデータ量を少ない媒体で記憶することが可能になる。
また、二本鎖を作りやすい性質を利用すれば、適切に設計したDNAが自然に立体構造を作ることも可能である。こうした発想は「DNAオリガミ」と呼ばれる。人体に無害なので、例えば病気の細胞に接触した場合だけ蓋が開くようにしておけば、薬を運ぶ「箱」として使うことも出来る。
マメ科植物と根粒菌の話もおもしろい。
マメ科の植物は往々にして、他の植物が生育不能であるような痩せた土地にも生えられる。強い味方=根粒菌が共生しているためである。根粒菌は空気中の窒素を固定して、マメ科植物に利用しやすい形に変換して提供する。窒素はアミノ酸の材料で、植物には必須であるが、植物が空気中のものを直接利用するのは簡単ではない。肥料として与えるのはそのためだ。
マメ科植物は窒素の見返りに、根粒菌に栄養分の糖を分け与え、菌を包み込む膜を作って住処を提供する。
こうしてマメ科植物は、養分の少ない土地にも茂り、植物+菌のダブルパワーで、ときには駆除に困るほどはびこってしまうわけである。
その他、ABO式血液型、三毛猫クローン、植物の開花の仕組み、両生類の心臓・循環系など、意外に身近で知られていない、興味深い話が満載である。
明日からすぐに日々の暮らしに役立つわけではないが、ちょっと奥深い世界を覗ける、楽しい驚きが詰まった1冊。
しかし、長い目で見ていったときに、生物が作り出すものや働きを人が利用している例は多い。生命全般に共通する仕組みを知ることが、例えば医薬品の開発に役立つことがある場合もあるし、人と他の動物の違いを見ていくことで、意外な気づきがあることもある。体の中に同居する生物が、実は私たちを助けてくれていることもわかってきている。
本書では、あまり広くは知られていないけれど、人の暮らしと案外関連する、そんな事象や研究エピソードをあれこれ紹介する。
著者の金子氏は植物細胞生物学、日比野氏は発生生物学・比較免疫学が専門の研究者。著者らの専門分野が中心の、幅広い話題を拾っている。1つのトピックが数ページであり、挿絵や顕微鏡写真などの図版も多いため、比較的気軽に読み進められる一方、科学的にしっかりした記述で安心して読める。
いくつか紹介してみる。
2008年のノーベル化学賞受賞で話題になったクラゲの緑色蛍光タンパク質(GFP)。これはクラゲの発光では、むしろ脇役のタンパク質で、主役であるイクオリンが発する青い光を黄緑色に変化させるタンパク質だ。なぜ主役でなく脇役が注目されたかといえば、クラゲの発光における価値というよりも、応用研究に役立った点が評価されたためだ。
イクオリンはカルシウムイオン濃度の変化に反応して発光するが、GFPは光を当てるだけで発光する。毒性がほぼないため、生きた細胞内で使うことも可能となる。そのため、例えば、がん細胞にGFPで目印を付ければ、増殖や転移の仕方が観察できることになる。さらには個々のタンパク質にGFPをくっつけて、そのタンパク質がいつどこで発現されるか確認するようなことも可能である。
クラゲの中では、光の色を変えるという、いささか地味な仕事をしていたタンパク質が、幅広くその後の研究に大きな可能性を拓いたことになる。
オス・メスをめぐる話もおもしろい。
生物では、オスがメスよりも大きい一夫多妻制を採る種がある。強いオスがハーレムを作り、子孫を残す形だ。これとは逆に、オスが小さい種もある。クモやカマキリが代表例だ。さらに、オスが極端に小さい「矮雄」と呼ばれるものもある。アンコウの仲間である。アンコウは食材として出回るのはほとんどメスだという。ある種などは、メスが2mという巨大サイズなのに、オスは15cm。深海では生殖相手に滅多に出会えないため、一度出会うとオスはメスの皮膚に噛みついて離れないようにする。その後、何と、皮膚も血管も融合してしまい、目や心臓もなくしてしまう。残るのは、精巣の機能だけ。
愛の究極形といえば聞こえはよいが、生きる厳しさ・すさまじさも感じるようなエピソードである。
将来的に広がっていきそうなのが「DNAナノテクノロジー」の話。DNAは生物のいわば設計図で、生物はそれぞれ、種に特有のDNAを持ち、これに基づいてタンパク質が合成されて体が作られていく。
DNA(デオキシリボ核酸)は、塩基A、C、G、Tが異なる4種の構成単位で作られる長い鎖である。AはT、CはGとフックのように対を作る。鎖は2本で1セット、向かい合って二重らせんを形成する。一方の鎖がATCGGTであれば反対の鎖はTAGCCAと並ぶことになる。
熱を加えればらせんはほどけるが、温度を下げると元の二重らせん構造に戻る。二本鎖の方が安定なためである。
DNAの性質を利用して、データ記憶媒体とすることが出来れば、現在のコンピュータの0、1の2進法でなく、A、C、G、Tの4進法が使えることになり、同じデータ量を少ない媒体で記憶することが可能になる。
また、二本鎖を作りやすい性質を利用すれば、適切に設計したDNAが自然に立体構造を作ることも可能である。こうした発想は「DNAオリガミ」と呼ばれる。人体に無害なので、例えば病気の細胞に接触した場合だけ蓋が開くようにしておけば、薬を運ぶ「箱」として使うことも出来る。
マメ科植物と根粒菌の話もおもしろい。
マメ科の植物は往々にして、他の植物が生育不能であるような痩せた土地にも生えられる。強い味方=根粒菌が共生しているためである。根粒菌は空気中の窒素を固定して、マメ科植物に利用しやすい形に変換して提供する。窒素はアミノ酸の材料で、植物には必須であるが、植物が空気中のものを直接利用するのは簡単ではない。肥料として与えるのはそのためだ。
マメ科植物は窒素の見返りに、根粒菌に栄養分の糖を分け与え、菌を包み込む膜を作って住処を提供する。
こうしてマメ科植物は、養分の少ない土地にも茂り、植物+菌のダブルパワーで、ときには駆除に困るほどはびこってしまうわけである。
その他、ABO式血液型、三毛猫クローン、植物の開花の仕組み、両生類の心臓・循環系など、意外に身近で知られていない、興味深い話が満載である。
明日からすぐに日々の暮らしに役立つわけではないが、ちょっと奥深い世界を覗ける、楽しい驚きが詰まった1冊。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。現在、中雛、多分♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント
- ぽんきち2016-01-08 22:01
薄荷さん
そうそう、モテる(?)アンコウはいくつもぶらぶら付けているらしいですねw
もしかしたらオスが増えてもまったく感知していない可能性もあるようです。「あらー、何かコブが増えたわ」程度にしか思っていないのかもしれません(^^;)。
アン肝も当然メスのが食用なんでしょうし、これがほんとの肝っ玉かあちゃん・・・?
> 『ハッピーハッピー♪アンコウ親子~♪』
や、これは知りませんでした。ちょっとぐぐったら家電店のCMなんですね(しかし、CMソング自体の音源には行き当たらず(^^;))。家電でも、石○電気とか、オ△デンなんかはうちの地方でも流れていたんですがwクリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:実務教育出版
- ページ数:232
- ISBN:9784788911703
- 発売日:2015年12月22日
- 価格:1512円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。