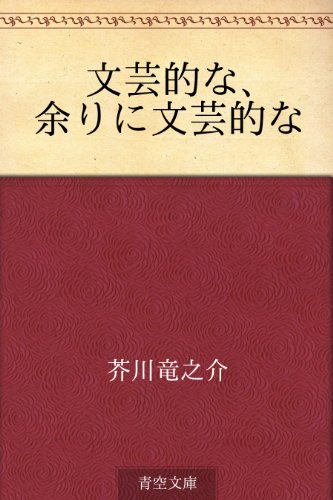はるほんさん
レビュアー:
▼
♪かっぱっぱー るんぱっぱーかーっ芥川 かっぱっぱー
本日は芥川龍之介の命日「河童忌」だ。
太宰の桜桃忌、梶井の檸檬忌、藤沢周平の寒梅忌という文学忌の中、
河童忌というのは思い切ったネーミングである。(笑)
なら「河童」でも読みなおそうかと思ったのだが、やめた。
自分は芥川作品が好きだが正直なところ、後期の作品は読み辛い。
と言っても死の直前、1~2年くらいの間の作品のことなのだが
聡明な文章とたがの外れた話筋が不協和音を奏でているようで、苦しい。
一説には統合失調症であったと言われ、命を絶った遠因とされる。
芥川は「物語が書けない」とよく言われる。
確かに古典のような原作を改編したものが多く、
短編を多く生み出しているが、長編作品は残されていない。
実際、自分のような芥川スキーが読んでも
中編以上の作品はなにかキレの悪さを感じる。
本作品は、芥川・谷崎潤一郎との論争文と言われる。
「話筋の無い小説はありやなしや」とでも言う内容で
谷崎が話筋があってこそ小説だと主張したらしいのに、
芥川はそうとは限らないと主張する。
が、論争文にしては随分と話があちこちに飛んでいる。
というより、芥川自身が己の道を模索していたように思う。
そもそも話筋の無い小説とは何か。
芥川の説明では散文や詩のようなものが近いと言っているが
彼は詩人になりたいわけではないのだ。
例えに美術などを用いているので余計に分かりにくいのだが
自分の解釈では芥川は「魂に訴えるもの」に惹かれているように思う。
詩歌は確かに、話筋では無く言葉で読者を惹きつける。
彼はそれを小説で表現できないだろうかと言っている。ように思う。
まるで絵画のように、一目ではっと何かを与えるような。
文字を読んで目が覚めるような小説、とはいったい何だろう?
これも全く、自分の解釈である。
例えば「吾輩は猫である。名前はまだない。」
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」のような冒頭文は
それに近いものがあるのではないかと思う。
が当然、印象の強い文章だけで小説は進められない。
あとはやはり「話筋」で紡がれていくのが小説だ。
なら芥川はいったい、何処へ行きたかったのだろう?
「リアル」という意味が近いかもしれない。
話筋と言う調律ではなく、心のヒダに直接入り込んでいくもの。
芥川の古典改編はどれも、元ネタから行間を読み
キャラの心情に迫ろうとしたものが多い印象がある。
「書かれていないものを描きたい」
だが小説である以上は、文字という制約に縛られる。
現代ならひょっとして芥川の目的地は、
アニメーターか映画監督にでも相当するのかもしれない、と思ったりする。
だが芥川は、それを文字で表現したかったのだ。
本作品には、続編がある。
「続・文芸的な、余りに文芸的な」はもう少し短い。
そこにはこんな叫びが書かれている。
本当に「物語」が書けなかったのかどうかは結局のトコロ分からないが、
文豪であるが故の葛藤があったのは確かだと思う。
今や彼の代名詞となった「芥川賞」は、確かに今もその懊悩を引き継ぎ、
多様な世界観に焦点があてられるのではないかと思う。
まだ誰も見たことが無い、絵画のように鮮烈な作品が生まれるようにと。
故に、賛否両論あってこそのあの賞だと思う。
「ほら、僕が言おうとしていたのはこういう作品なんですよ」
と芥川が微笑めるように、無名・新人小説家たちは毎年そこを目指す。
そう考えると、今まであまり興味のなかった受賞作品というのも、
ちゃんと意味があるのかもしれないと思えるようになった。
自分は文庫派なので、どちらにしろ旬の時期には読めないが。(笑)
本屋の売り上げが落ちる時期に
イベントとして芥川・直木賞が作られたとも聞くが
河童忌の前に受賞作品が発表になるというのも、
考えようによってはコニクイ演出である。
──今年の受賞作品を、芥川は彼岸で目にしたのだろうか。
芥川「芸人が小説書くとか、現代はすげーなー」
太宰「芸人路線ならオレが最初なのに…」
とか何とか言ってるかもしんない。
太宰の桜桃忌、梶井の檸檬忌、藤沢周平の寒梅忌という文学忌の中、
河童忌というのは思い切ったネーミングである。(笑)
なら「河童」でも読みなおそうかと思ったのだが、やめた。
自分は芥川作品が好きだが正直なところ、後期の作品は読み辛い。
と言っても死の直前、1~2年くらいの間の作品のことなのだが
聡明な文章とたがの外れた話筋が不協和音を奏でているようで、苦しい。
一説には統合失調症であったと言われ、命を絶った遠因とされる。
芥川は「物語が書けない」とよく言われる。
確かに古典のような原作を改編したものが多く、
短編を多く生み出しているが、長編作品は残されていない。
実際、自分のような芥川スキーが読んでも
中編以上の作品はなにかキレの悪さを感じる。
本作品は、芥川・谷崎潤一郎との論争文と言われる。
「話筋の無い小説はありやなしや」とでも言う内容で
谷崎が話筋があってこそ小説だと主張したらしいのに、
芥川はそうとは限らないと主張する。
が、論争文にしては随分と話があちこちに飛んでいる。
というより、芥川自身が己の道を模索していたように思う。
そもそも話筋の無い小説とは何か。
芥川の説明では散文や詩のようなものが近いと言っているが
彼は詩人になりたいわけではないのだ。
例えに美術などを用いているので余計に分かりにくいのだが
自分の解釈では芥川は「魂に訴えるもの」に惹かれているように思う。
詩歌は確かに、話筋では無く言葉で読者を惹きつける。
彼はそれを小説で表現できないだろうかと言っている。ように思う。
まるで絵画のように、一目ではっと何かを与えるような。
文字を読んで目が覚めるような小説、とはいったい何だろう?
これも全く、自分の解釈である。
例えば「吾輩は猫である。名前はまだない。」
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」のような冒頭文は
それに近いものがあるのではないかと思う。
が当然、印象の強い文章だけで小説は進められない。
あとはやはり「話筋」で紡がれていくのが小説だ。
なら芥川はいったい、何処へ行きたかったのだろう?
「リアル」という意味が近いかもしれない。
話筋と言う調律ではなく、心のヒダに直接入り込んでいくもの。
芥川の古典改編はどれも、元ネタから行間を読み
キャラの心情に迫ろうとしたものが多い印象がある。
「書かれていないものを描きたい」
だが小説である以上は、文字という制約に縛られる。
現代ならひょっとして芥川の目的地は、
アニメーターか映画監督にでも相当するのかもしれない、と思ったりする。
だが芥川は、それを文字で表現したかったのだ。
本作品には、続編がある。
「続・文芸的な、余りに文芸的な」はもう少し短い。
そこにはこんな叫びが書かれている。
僕は時々かう考へてゐる。
――僕の書いた文章はたとひ僕が生まれなかつたにしても、
誰かきつと書いたに違ひない。
本当に「物語」が書けなかったのかどうかは結局のトコロ分からないが、
文豪であるが故の葛藤があったのは確かだと思う。
今や彼の代名詞となった「芥川賞」は、確かに今もその懊悩を引き継ぎ、
多様な世界観に焦点があてられるのではないかと思う。
まだ誰も見たことが無い、絵画のように鮮烈な作品が生まれるようにと。
故に、賛否両論あってこそのあの賞だと思う。
「ほら、僕が言おうとしていたのはこういう作品なんですよ」
と芥川が微笑めるように、無名・新人小説家たちは毎年そこを目指す。
そう考えると、今まであまり興味のなかった受賞作品というのも、
ちゃんと意味があるのかもしれないと思えるようになった。
自分は文庫派なので、どちらにしろ旬の時期には読めないが。(笑)
本屋の売り上げが落ちる時期に
イベントとして芥川・直木賞が作られたとも聞くが
河童忌の前に受賞作品が発表になるというのも、
考えようによってはコニクイ演出である。
──今年の受賞作品を、芥川は彼岸で目にしたのだろうか。
芥川「芸人が小説書くとか、現代はすげーなー」
太宰「芸人路線ならオレが最初なのに…」
とか何とか言ってるかもしんない。
投票する
投票するには、ログインしてください。
歴史・時代物・文学に傾きがちな読書層。
読んだ本を掘り下げている内に妙な場所に着地する評が多いですが
おおむね本人は真面目に書いてマス。
年中歴史・文豪・宗教ブーム。滋賀偏愛。
現在クマー、谷崎、怨霊、老人もブーム中
徳川家茂・平安時代・暗号・辞書編纂物語・電車旅行記等の本も探し中。
秋口に無職になる予定で、就活中。
なかなかこちらに来る時間が取れないっす…。
2018.8.21
この書評へのコメント
- クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:
- ページ数:50
- ISBN:B009IWNIEQ
- 発売日:2012年09月27日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。