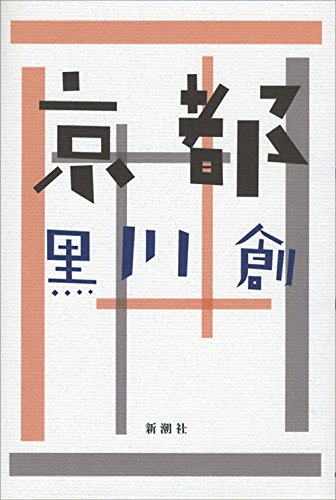ぽんきちさん
レビュアー:
▼
厚い白粉を落とした、「素顔」の京都の蔭り
ストレートなタイトルだが、ステレオタイプな京都本ではない(いや、ステレオタイプって何、となるといささかややこしいのだが)。
観光客向けの京都ではないし、古き佳き日本の香りの京都ではないし、かといって暗い露地の奥に魔が潜む京都でもない。
余所行きの仮面を外した京都。住人があまり口にしないけれど知っている、そんな京都の蔭を帯びた「横顔」である。
京都の地名を入れた4編を収める。
「深草稲荷御前町」は伏見稲荷の門前町にある喫茶店を営む男の話。好きになった女性と結婚するが、自らの出自も絡み、結婚生活には波風が立つ。自分でもどうしようもないもどかしさを抱えつつ、素直になりきれない。幼少時の暮らしぶり、幼なじみの過去と今を織り交ぜ、男の心象風景が語られる。
「吉田泉殿町の蓮池」。京都大学近くの鞠小路と呼ばれる通りにあった米屋。主人公はそこに住んでいた。人々が暮らす場所にはいろいろな小規模商店があり、子供もおおぜい走り回っていた。そんな街の賑わいや京都の地理の歴史に加え、街中の被差別地区の話も混じる。人々の暮らし方が劇的に変わる時代、主人公の家族もまた、伝統的な形を保つことは出来なくなる。
「吉祥院、久世橋付近」。ちんぴら生活から抜けきれない男と、夫の浮気で離婚した女。2人の人生がふとしたことで交錯する。底辺の生活でもあるようだが、不思議と悲愴感はない。吉祥院というのは西京極九条付近、京の街の南西部にあたる。低湿地で桂川が溢れることも多かったという。
「旧柳原町ドンツキ前」。バスに乗り、河原町を駅に向かってずっと下ると、最後に塩小路で、かくっと曲がる。このあたりに「ドンツキ」という靴鞄店の大看板があったという。今でもここに履物屋さんが確か複数あるはずで、引っ越してきた当初は何だか印象が強かった。その昔、市電が通っていたこのあたりには靴屋や革製品屋が多かったのだという。革製品といえば、そう、穢多・非人である。その地域に幼少時の思い出を持つ、主人公の物語である。
現代も描かれるが、著者の定点はいささかセピア色の昭和にある。
著者の私小説的な色合いも帯び、庶民の近代史も織り込まれ、ノンフィクション風のところもある。
登場人物たちの話し言葉は生粋の京言葉だ。舞妓さんの言葉でも時代劇風でもない、庶民の言葉である(ああ、これがなかなか喋れるようにならないんだよな・・・)。
この地に住んで10年にしかならないが、「そうそう、これはある」と思える描写がある。長く住む人は余計「わかる」部分があるだろう。一方で、旅行で何度か来たという人だと、「こんな京都もあるのか」とまったく違った印象を受けるかもしれない。
京都はきちんとしているようで、どこかどちらでもよいことには寛容なところがある。例えば地名。音だったり訓だったり、結構適当だったりする。音便のように訛ることもある。合理的と言えば合理的だが、どうしても「緩い」という印象が先立つ。「まぁよろしおすやろ」と言われそうでもある(でもこれも似非京言葉と冷笑されそうでもある)。
別の地域で「不良」とか「乱暴」とか言われそうな行動が「やんちゃ」と言われる。何だか途端にかわいげのあるもののように思えてしまう。京言葉の柔らかさからくるマジックのようだが、「京」というよりも、どこかお調子者で柔らかさのある「上方」の気風なのかもしれない。
そして被差別地区。転入して、引っ越し先を探す際、子供の保育所を探す際、学校の「人権月間」参観で。折々に耳にした。新参者がよく事情もわからず触れるには難しすぎた。本書を読むと少し見えてくるものがある。住み続けている人には肌身でわかる感覚なのかもしれない。
平成の京都の向こう側に透けて見える、昭和の京都、大正の京都、明治の京都。
さらに深い平安時代の京都。そんなことを思わせるものが本書にはある。
そう、この街は続いている。
千年の都といったいささか陳腐な呼び名で呼ばれる前からあり、おそらくはブームが去ってもあり続ける街。
著者は登場人物の心の揺れを丁寧に綴る。
普遍的にどこでもありそうなこともある。
しかし一方、この街でなければならないこともある。
そんな「核」が、目立たぬように、あちこちにしたたかに眠っているのが京の街というものかもしれない。
ちょっとディープな「京都」である。
観光客向けの京都ではないし、古き佳き日本の香りの京都ではないし、かといって暗い露地の奥に魔が潜む京都でもない。
余所行きの仮面を外した京都。住人があまり口にしないけれど知っている、そんな京都の蔭を帯びた「横顔」である。
京都の地名を入れた4編を収める。
「深草稲荷御前町」は伏見稲荷の門前町にある喫茶店を営む男の話。好きになった女性と結婚するが、自らの出自も絡み、結婚生活には波風が立つ。自分でもどうしようもないもどかしさを抱えつつ、素直になりきれない。幼少時の暮らしぶり、幼なじみの過去と今を織り交ぜ、男の心象風景が語られる。
「吉田泉殿町の蓮池」。京都大学近くの鞠小路と呼ばれる通りにあった米屋。主人公はそこに住んでいた。人々が暮らす場所にはいろいろな小規模商店があり、子供もおおぜい走り回っていた。そんな街の賑わいや京都の地理の歴史に加え、街中の被差別地区の話も混じる。人々の暮らし方が劇的に変わる時代、主人公の家族もまた、伝統的な形を保つことは出来なくなる。
「吉祥院、久世橋付近」。ちんぴら生活から抜けきれない男と、夫の浮気で離婚した女。2人の人生がふとしたことで交錯する。底辺の生活でもあるようだが、不思議と悲愴感はない。吉祥院というのは西京極九条付近、京の街の南西部にあたる。低湿地で桂川が溢れることも多かったという。
「旧柳原町ドンツキ前」。バスに乗り、河原町を駅に向かってずっと下ると、最後に塩小路で、かくっと曲がる。このあたりに「ドンツキ」という靴鞄店の大看板があったという。今でもここに履物屋さんが確か複数あるはずで、引っ越してきた当初は何だか印象が強かった。その昔、市電が通っていたこのあたりには靴屋や革製品屋が多かったのだという。革製品といえば、そう、穢多・非人である。その地域に幼少時の思い出を持つ、主人公の物語である。
現代も描かれるが、著者の定点はいささかセピア色の昭和にある。
著者の私小説的な色合いも帯び、庶民の近代史も織り込まれ、ノンフィクション風のところもある。
登場人物たちの話し言葉は生粋の京言葉だ。舞妓さんの言葉でも時代劇風でもない、庶民の言葉である(ああ、これがなかなか喋れるようにならないんだよな・・・)。
この地に住んで10年にしかならないが、「そうそう、これはある」と思える描写がある。長く住む人は余計「わかる」部分があるだろう。一方で、旅行で何度か来たという人だと、「こんな京都もあるのか」とまったく違った印象を受けるかもしれない。
京都はきちんとしているようで、どこかどちらでもよいことには寛容なところがある。例えば地名。音だったり訓だったり、結構適当だったりする。音便のように訛ることもある。合理的と言えば合理的だが、どうしても「緩い」という印象が先立つ。「まぁよろしおすやろ」と言われそうでもある(でもこれも似非京言葉と冷笑されそうでもある)。
別の地域で「不良」とか「乱暴」とか言われそうな行動が「やんちゃ」と言われる。何だか途端にかわいげのあるもののように思えてしまう。京言葉の柔らかさからくるマジックのようだが、「京」というよりも、どこかお調子者で柔らかさのある「上方」の気風なのかもしれない。
そして被差別地区。転入して、引っ越し先を探す際、子供の保育所を探す際、学校の「人権月間」参観で。折々に耳にした。新参者がよく事情もわからず触れるには難しすぎた。本書を読むと少し見えてくるものがある。住み続けている人には肌身でわかる感覚なのかもしれない。
平成の京都の向こう側に透けて見える、昭和の京都、大正の京都、明治の京都。
さらに深い平安時代の京都。そんなことを思わせるものが本書にはある。
そう、この街は続いている。
千年の都といったいささか陳腐な呼び名で呼ばれる前からあり、おそらくはブームが去ってもあり続ける街。
著者は登場人物の心の揺れを丁寧に綴る。
普遍的にどこでもありそうなこともある。
しかし一方、この街でなければならないこともある。
そんな「核」が、目立たぬように、あちこちにしたたかに眠っているのが京の街というものかもしれない。
ちょっとディープな「京都」である。
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:新潮社
- ページ数:251
- ISBN:9784104444076
- 発売日:2014年10月31日
- 価格:1944円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。