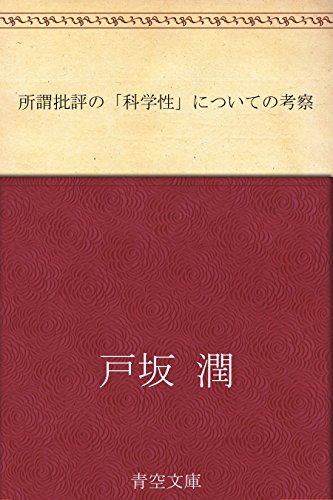本書は次のような文章で始まります。
「単に文芸批評だけではない。総ての評論風の批評は直接感受した印象の追跡を建前とする。ただその印象が芸術的な印象ではなくて、理論的印象や科学的印象である時、普通これを印象とは呼ばないまでで、この場合、印象の持っている印象らしい特色には別に変りがない」
批評には「印象批評」と呼ばれるものとそうじゃないものがあるよね、と。
「印象批評」と言うのは簡単に言えば感想文的な、理論的な根拠を持たないものです。いわゆる批評家ではない作家の書評などもこれに含まれます。
「印象批評」とはそういう意味で、アカデミックな立場からは揶揄する言葉として使われることが多いのですね。
小林秀雄などは「印象批評」の代表のようなものとして、そういう批判によくさらされています。
ただ、この著者は言うのです。「でも、評論風の文章と言うものが語っているその対象は、結局印象なんだよね」と。
「印象批評」であろうとなかろうと、批評する対象そのものは印象でしかなく、批評という行為はそれを追跡することなのだ、と。
「心ある読者は、単に読むという活動自身に於て、印象追跡者である。批評家である。批評家とは、そういう最も普通な、併し誰でも可能だという意味に於ける誠実さをもった、読者の代表者である」
だから別に「印象批評」だっていいじゃん、と思うわけですが、ただ印象について理論的根拠をもたないでそのまま語ってしまうと、説得力に欠けてしまうわけです。
なぜかというと、それはとても「主観的」なものだからです。
「俺が面白いっつってんだからそれでいいじゃん!」と言われれば、言われた方はもう「うん、そうだよね。ごめんね」と謝るしかないわけですが、「批評」というものを学問的に、論理的に、科学的に考えようとするならそれでは困る、ということなんでですね。
印象そのものは確かに主観的なものなのだけれど、
「主観的な偶然性を消去するために、印象を繰り返し、つつきまわし、比較し、実験し、等々して見るのである。之によって自分の自分らしい個性ある印象が、次第に明白になって来る。印象の明白感と自明感によって心内的実験が確立される」
と。
きっとその印象はただの思い込みかもしれないのだから、いろんな立場の人から見てもそうだ、と言えるかどうか、自分の中で確認してみよう、と、そういうことだと思うのですね。それが「客観性」だと。
その「客観性」というのは「常識」とか「みんなそう言ってるから」とかそういうのではなく、もっと有無を言わさず従わざるを得ないようなものを言うのですね。
それが論理だったり科学だったりするのです。
「俺は酸素の存在なんて信じない!」と僕が言うのは勝手だし、仮に「おう、俺もそう思うぜ!」という仲間がたくさんいたところで、それは「客観的」ではない。そんな程度では「客観的な俺v」という称号は得られないのですね。
そういうことでデカルトという人は頭がおかしくなるまで何もかもを疑い続け、晴れて「合理主義の父」と呼ばれることができたのです。それが良かったのか悪かったのかは知りませんが(彼自身にとって)。
でも現在は「科学」という素晴らしいものがあるから、僕たちは別に気が狂うまで何かを疑う必要はないのですね(ありがとうデカルト!)。
星新一のショートショートで、宇宙からUFOに乗ってやってきた宇宙人に地球人がそのUFOの作り方などを聞こうとしたら、宇宙人が答えられなくてがっかりした、というものがあります。
そりゃそうなんですよね、僕たちだって別にエンジンの仕組みがわかっていなくても自動車の運転免許はとれますから。
1+1が本当に2であるかどうかを考えるんじゃなくて、1+1はとりあえず2ということにしとこうよ、そこに文句つけんなよ、大丈夫だって! 車運転するときにいちいちエンジンの事なんて考えないだろ! というのが科学的態度なわけです。多分。
というわけで著者は「印象批評」に対してこう批判するのです。
「どの場合でも変らぬ点は、印象からの距離と印象からの抽象というのが如何に批評にとって重大かということへの、関心の不足である」
と。
そして著者はこう言うのです。
「思うに批評が科学的であることの、もっとも手近な特色は(そして恐らく最も形式的な特色でもある)、それが組織的で体系的だということにあるだろう」
「自然科学」というものはそれこそ数字という究極に論理的なところまで落とし込んで「法則」を発見する。「法則」が発見されれば、宇宙人にとってのUFOのように、別にそのことについて深いことを知っていなくてもそれを利用することができる。ここに「自然科学」の有無を言わさずだれもを従わせる「論理性」「客観性」があるのでしょう。
一方文学のような「人文科学(なんていうと理系の人は鼻で嗤うかもしれないけれど)」というのは「印象」を数字には落とし込めない分野ですが、それでも一応「科学」と名乗れるのは、それが文学であれ社会学であれ民俗学であれ、「知の集積」だからなんですね。
人文科学ではないけれど、茂木健一郎さんがよく言う「脳科学的に言うと…」という言葉の裏には、科学的法則という「客観性」と、それらを証明してきた古今東西の脳科学者たちという「応援団=知の集積」が背後についているから妙な説得力を持つのです。
でも、そう考えると、やっぱり小林秀雄という人はすごかったのだなあと思います。
彼はきっと、「批評」という客観性の世界にこれと言った後ろ盾をもたずに乗り込んでいったのだから。
彼の批評は「科学的」でも「論理的」でもなかった。でも、多くの人がそれに魅了されてしまった。
そして今でも、やはり彼のような「印象批評」は決して廃れることなく続いている。本書の表現を引用すれば、印象批評は
ヒドラのように不屈なのです。
その答えはきっと、僕たちは誰もが「科学者」としての自分とそうじゃない自分を心の中にあわせもっているから。
「印象批評」は確かに科学的でも、論理的でもないかもしれない。
それはもしかしたら、マジックのように、種も仕掛けもあるけれど、結局はただのまやかしなのかもしれない。
でも小林秀雄なら、きっとこう言うのではないかと思うのです。
科学に対して文学的感想を述べることが野暮であるように、文学について科学的感想を述べることもまた、野暮なものかもしれないよ、と。文学や芸術そのものがまやかしでしかないのかもしれないのだから。
自然現象の究明は楽しいけれど、マジックの種明かしは興ざめにしかならないかもしれない。
ただ、文学や芸術がたとえただのまやかしであったとしても、それによって誰かを楽しませることができるように、科学に対する文学的感想も、文学に対する科学的感想も、ある種のマジックとして誰かを楽しませることができるとしたら。
と、ここまで似非教師ぶって「批評」や「科学」について延々と述べてきた僕に向かって、生徒である僕の本心はこう言うのです。
「先生、僕はいろいろ考えているうちに、自分が人を納得させたいのか、それとも人を笑わせたいのか、分からなくなってしまいました(泣)」
「知らねーよ(怒)」
twitterで自分の個人的な思いを呟いてたら見つかってメッセージが来て気持ち悪いのでもうここからは退散します。きっとそのメッセージをした人はほくそ笑んでいることでしょう。おめでとう。
今までお世話になった方々ありがとうございました。
この書評へのコメント
- 三太郎2015-03-06 21:40
>素通堂さんへ
関係あるかどうか微妙ですが、小林秀雄は哲学者の三木清との対談「実験的精神」の中で、「論証するには論理でよいが、実証するには文章が要る。哲学というものを創るという技術は、建築家が建築するように、言葉というものを尽くす必要がある」と言っています。ここは、哲学を批評と置き換えてもよいのかも。
つまり、(実験等により)実証されない理論は、科学では無意味ですが、批評での実証とは、言葉という「物」を創ることだ、言い換えれば言葉を尽くすことだと。
小林はきっとただ印象を述べているつもりはなかっただろうと思います。また、人を納得させる(論証する)目的であれこれ言葉を連ねたつもりもなかったと思います。
それは批評なのか?という意見はあるとは思いますが。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - 素通堂2015-03-07 00:52
三太郎さん、コメントありがとうございます。
文章を書くのは難しいものだなと思います。
僕はご紹介いただいた「実験的精神」は読んでおりませんが、小林秀雄の言葉が大好きな一人です。
僕自身、小林秀雄が「ただ印象を述べていた」とは思っていません。
ただ、この本の著者のように、より「科学的な批評」を是とする人たちが彼の文章を「印象批評にすぎない」と批判する気持ちも、分からないではないのです。
小林秀雄は「様々な意匠」で
「だが、古来如何なる芸術家が普遍性などという怪物を狙ったか? 彼等は例外なく個体を狙ったのである。あらゆる世にあらゆる場所に通ずる真実を語ろうと希ったのではない、ただ個々の真実を出来るだけ誠実に出来るだけ完全に語ろうと希っただけである」
と述べています。
僕はこの言葉は、彼が批評する対象を語っただけでなく、彼自身の批評もまた、そのようなものだと語ったのではないかと思っています。
続くクリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - 素通堂2015-03-07 00:52
批評する対象そのものに普遍性がないとしたら、それを語る批評自体もまた普遍性をもちえません。
普遍性をもちえない「科学」などあるでしょうか。そのような「論理」というものは。
「人を納得させたいのか笑わせたいのか分からない」というのは、半分ジョークで半分本音です。
科学を愛する人たちが普遍性を求める気持ちもわかります。ただ一方で、小林秀雄が言うように普遍性などは存在しない、というのも分かる気がするのです。
小林秀雄は人を納得させるために書いていたのではない、という三太郎さんのお言葉に、僕もまったく同感です。
でも人を納得させる批評=普遍性のある批評というのも、あり得るだろうと思います。
そうしないと、批評というのは小林秀雄のような天才にだけしかできないものになってしまいますから。
うーん、でも、繰り返しになりますが、結局のところ自分でもよく分からないです。
長々と書きながらこんなしめくくりですみません(泣)クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - 三太郎2015-03-07 09:11
>素通堂さん
議論をしかけたつもりはないんです。小林秀雄に対しては僕もアンビバレントな気持ちを抱いています(^^;
「実証する」とは、自然科学なら繰り返し実験により確かめる、考えうる反証を否定してみせるということでしょう。ファーブルみたいに。
でもそうやって実証された「理論」もたぶん物理学以外では、理論で予想された結果が100%保障されるわけでもないですよね。自然界には常に例外が見つかるわけで・・・
これが文学や芸術となったら、どうやって「理論」を実証できるのでしょうか。統計的な数字の処理ができたとしても、それは理論ではないでしょうから。
僕はむしろ、「個々の真実を出来るだけ誠実に出来るだけ完全に語る」ことが「あらゆる世にあらゆる場所に通ずる真実を語る」ことに繋がるんじゃないかと信じたいんですよ。
まあ正直なところ僕としては、完全ではなくても、個々の真実を出来るだけ誠実に語りたいとは思っているのです。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - 素通堂2015-03-07 11:45
三太郎さん
ごめんなさい。しつこいなと思われるかもしれませんが、僕の気持ちを書かせてください。
三太郎さんのコメントを読んで、思わず三太郎さんの「ファーブル昆虫記http://www.honzuki.jp/book/206064/review/134230/」のレビューを読み返してしまいました。
ファーブルが進化論に抱いた嫌悪感は、それが持つ「普遍性の仮面」だったのでしょうか。実証や観察を差し置いて、まるで理論だけですべてが説明可能であるかのように振る舞うような。
それは文学や芸術にとっても同じで、だからこそ『個々の真実を出来るだけ誠実に出来るだけ完全に語る」ことが「あらゆる世にあらゆる場所に通ずる真実を語る」ことに繋がるんじゃないか』と。
おだてるわけじゃないですが、ファーブルの姿勢も三太郎さんの姿勢もかっこよすぎます! ファーブル昆虫記、読みたくなったじゃありませんか!!…でも十巻読破は無理(泣クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。
- 三太郎2015-03-07 17:17
>素通堂さんへ
>ファーブルが進化論に抱いた嫌悪感は、それが持つ「普遍性の仮面」だったのでしょうか。
素通堂さんの言いたいことは何となく分かります。進化論は実験で検証できませんからね。
進化論は、物理学における量子力学のように、実験により完全には検証することができない理論かもしれませんね。
それでも生命の本質をついているように思えます。DNAも知られていない時代に進化論を考え抜いたダーウィンも、実験する替わりに、まずは事実を出来るだけ正確に記述したのでしたね。
19世紀の二人の偉大な科学者がまったく違うアプローチで生命の神秘に挑んだと思うと、いろいろ考えさせられます。ダーウィンも読んでみたくなりました。
(ファーブルも是非どうぞ!私は岩波版が好きですが・・・言葉使いがちょっと古いかも)クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - 素通堂2015-03-07 19:17
mothra-flightさん、コメントありがとうございます!
戸坂潤は「文芸評論の方法について」というエッセイで、
「しばらく前までの小林秀雄は何等か体系に近いものを吾々に感じさせた。私は夫を「物質を恐れる」体系だと云ったこともある。だが実は之も、本当は方法でもシステムでもなかったのだ。単に風格の誇張されたものに過ぎなかったと云わねばならぬようだ。(中略)処が彼の最近の変化、平俗化と政論化とは、以前のシステム(?)とはまるで無関係なのだ。だから、以前のはシステムではなくて単にスタイルであったに過ぎない」
と述べていました。おっしゃる通り、隔たった位置にいるわけではないけれど、向いている方向が正反対というか、「好きだけど嫌い! でも好き!」みたいな。
と言っても、戸坂潤や小林秀雄について僕自身まだまだちゃんと理解できてない部分が多いと思います。もっとちゃんと読み込まないとだめだ…orzクリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - mothra-flight2015-03-07 20:39
向きが逆ってのは言い得て妙ですねえ。ただし突き詰めると同じようなところを向いているような気もします。
ふたりの特質を考えるうえで大事なのは、ふたりとも「文学」っていうのを、何らかの「認識」であると捉えているところじゃないかなあと思います。
小林の場合、文学において「認識」されるものは「私」であり、戸坂だと「社会」に生きるこの私が抱える一身上の問題=道徳・モラルだと。
そして、文学において「認識」されたものを見出す作業が、「批評」であると。
問題は、小林の見出そうとする「私」なるものが、いわゆる「社会化した私」(『私小説論』)という問題だったとして、その認識はいかに可能であるか、つまり「個人性と社会性との各々に相対的な量の変換式の如きものの新しい発見」(同上)だとか、戸坂の核である「自分=科学的認識=文学」という発想により、果たして「私」を書き記すことは可能であるのか、ということでしょうね。
つづくクリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - mothra-flight2015-03-07 20:40
戸坂は、今ここにいて他の誰とも交換不可能なこの私のことを「自分」と呼び、個人と厳密に区分しました。
そして文学とはそのような「自分」を表現することであり、そのために必要とされるのは「科学的認識」だとしてます。
重要なのは戸坂が考える「自分」という概念で、彼は次のように書いています。
「反映・模写という言葉は、こうした非因果的な直接関係を云い表わす範疇なのである。だから実は意識があって存在を反映するのではない(意識は元来なかった)、却って反映という存在の随伴現象が意識ということだ。夫が『自分』ということなのだ」。
ここで彼がいっているのは、「自分」というのは「反映」の効果であるということです。
逆に言えば「反映」という「存在の随伴現象」=「意識」を正しく捉えることができれば、「自分」を捉えることも可能だと考えているわけです。ここに戸坂の批評の可能性への期待があります。
つまり戸坂は「私」を捉えることについて楽観的なところがあると思います。
つづくクリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - mothra-flight2015-03-07 20:35
一方、小林はそれについて懐疑的なように思えます。
彼はベルグソン論の冒頭で、大きな蛍を見つけて、それを数日前に死んだ母だと思ったという回想をしているのですが、続けて以下のように書いています。
「困ったことがある。実を言えば、私は事実を少しも正確に書いていないのである。(中略)私は、後になって、幾度か反省してみたが、その時の私には、反省的な心の動きは少しもなかった。おっかさんが蛍になったとさえ考えはしなかった。何も彼も当たり前であった」
この「何も彼もが当たり前であった」ことそのものが、問われるべき「私」なわけです。
つまり「反映」という「存在の随伴現象」が「何も彼もが当たり前であった」ということなのであり、これを表現するのは、いかなる仕方で可能なのかと小林は問うていたと思います。それを突き詰めることが批評なんだと。
したがって戸坂と方向性を同じくしながらも、小林のほうが一枚上手といえるかもしれません。
…調子にのってしまいました。横から入って、長っ尻でごめんなさい(´・ω・`)
このあたりに興味があったら、橋川文三を読むといいかもしれません。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - 素通堂2015-03-07 20:55
うわあ、mothra-flightさん、ありがとうございます☆ これはこんなコメント欄に書くなんてもったいないですよ。コメント欄に「素晴らしい洞察」ボタン、ないじゃないですか!
正直難しすぎて僕にはよく分からないのですが、小林のように「存在の随伴現象(意識)」を「当たり前」だと言われてしまうと、批評の方法論として困るじゃないか、というのか戸坂の立場なのでしょうか。ちゃんと説明しろ、と。
でも小林からすれば、そんなものを説明しろと言う方が無茶だ、と。「自分=科学的認識=文学」の真ん中の科学的認識なんて本当にあるのかよ、ということでしょうか。
少なくとも戸坂の方は小林の批評に惹かれながら、でもそれを認めてしまうと「やっぱ天才はすごいね」って話で終わってしまう、そんなの科学じゃないよね、ということなのかなあ、と思いました。
分かってないくせに強引にまとめてしまってすみません(泣)
ありがとうございました!!クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
- 出版社:
- ページ数:11
- ISBN:B00SB0YD68
- 発売日:2015年01月10日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。