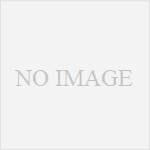ぽんきちさん
レビュアー:
▼
動かせぬ運命に向かい、降りられぬ列車に乗って進む。
北條民雄は昭和初期の作家である。ハンセン病を発症し、多磨全生園に入所。闘病生活の傍ら、こつこつと小説を書く。川端康成を師と仰ぎ、川端も北條の才を認めて交流している。23歳で夭折。死後は川端が北條の全集を刊行した。
ハンセン病(作中では「癩病」)に対する差別の目が非常に厳しい時代である。日本の隔離政策が始まったのが1931年。著者本人は1934年に全生病院に入院している。結核の薬であったプロミンがハンセン病にも効くことが発見されるのが1941年。しかし、著者はそれ以前、1937年に命を落としている。
「いのちの初夜」は北條の代表作である。
本書には、このほか、「望郷歌」、「吹雪の産声」を収める。
「いのちの初夜」では、幾度となく自殺を思い、試み、しかし成功しないまま、隔離病院にやってきた主人公の姿が描かれる。周囲の重症癩患者の姿に戦き、そしてそれが将来の自分の姿であることに怯える。内から見る目と外から見る目が交互に現れ、そして訪れるのは絶望である。終盤で、主人公と、患者でもあり付添でもある男が、議論を戦わせる。これはいずれも著者の分身だろう。その中で出てくる付添の男のひと言が、本作の主題である。
「望郷歌」は、ハンセン病とわかった子供たちとその教師役の患者青年が描かれる。孫にひどい仕打ちをした(あるいはせざるをえなかった)祖父の姿が悲しい。
「吹雪の産声」では、自らも患者である主人公が、患者である妊婦の出産と、死に瀕した親友を見つめる一夜を描く。
本書は、差別的に遇される死病を得た人の物語である。
死に至る病気は残酷だ。抗えぬ運命の中で、体は朽ちながら、心は怯えながら、それでも生き続ける。
しかし、ふと思うのだ。その絶望は、ハンセン病患者に限ったものではないはずだ。
人間として滅んでゆくことがわかっていながら、なお「いのち」は羽ばたけるのか。
特殊な状況の中で発せられたその問いが、普遍性を持つからこそ、本作は残ってきているのではないか。
*1月最終日曜が世界ハンセン病の日だった関係で、twitterで北條民雄に関するツイートが流れてきたり、「雪国」(復活!課題図書倶楽部・2015課題図書)で川端を思い出したり、で、そう言えばこれ、読んでなかったなぁと改めて読んでみました。もう1ヶ月近く経っていますが。
*結核とハンセン病の病原体はいずれもマイコバクテリア属で、結核菌(Mycobacterium tuberculosis)が主に肺への親和性が高く、感染力が高いのに比較して、らい菌(Mycobacterium leprae)は神経への親和性が高く、感染力はさほど高くありません。感染力が高くないのは患者に近く接している人にはわかるのではないかと思うのですが、にもかかわらず、ハンセン病に対する差別が(結核に比しても)非常に大きいものになったのは、外貌に症状が現れてしまうためだったのか。あるいは逆に遺伝病だと誤解されてすらいたことに起因するのか(遺伝病なら隔離することにまったく意味はないはずですが)。このあたり、差別全般につながるような気もしますが、問題が重いだけにあまり軽はずみな結論は出せず。機会があれば、追々別の本で考えてみたいと思います。その前に、感染症一般の歴史について、何か1冊読むかなぁ・・・。
*北條の死因はしかし、ハンセン病ではなく結核であったようです。直接の関係はないですが、「夏の花」の原民喜の妻が結核に糖尿病を併発していたのを思い出しました。この時代、栄養状態もさほどよくはなかったでしょうし、ひとたび何か発症してしまうと、多重感染や合併症も多かったのかも知れません。これも軽はずみな結論は出せないですが。
*川端は堀辰雄とも親交が厚かったのですね。「雪国」は今ひとつぴんとこなかったのですが、近いうちに別の作品を読んでみたいと思っています。何か、作品も交友関係も幅広すぎて、門外漢がちょっと囓ってもどうこうなるのかまったくわからないですけど。
ハンセン病(作中では「癩病」)に対する差別の目が非常に厳しい時代である。日本の隔離政策が始まったのが1931年。著者本人は1934年に全生病院に入院している。結核の薬であったプロミンがハンセン病にも効くことが発見されるのが1941年。しかし、著者はそれ以前、1937年に命を落としている。
「いのちの初夜」は北條の代表作である。
本書には、このほか、「望郷歌」、「吹雪の産声」を収める。
「いのちの初夜」では、幾度となく自殺を思い、試み、しかし成功しないまま、隔離病院にやってきた主人公の姿が描かれる。周囲の重症癩患者の姿に戦き、そしてそれが将来の自分の姿であることに怯える。内から見る目と外から見る目が交互に現れ、そして訪れるのは絶望である。終盤で、主人公と、患者でもあり付添でもある男が、議論を戦わせる。これはいずれも著者の分身だろう。その中で出てくる付添の男のひと言が、本作の主題である。
「望郷歌」は、ハンセン病とわかった子供たちとその教師役の患者青年が描かれる。孫にひどい仕打ちをした(あるいはせざるをえなかった)祖父の姿が悲しい。
「吹雪の産声」では、自らも患者である主人公が、患者である妊婦の出産と、死に瀕した親友を見つめる一夜を描く。
本書は、差別的に遇される死病を得た人の物語である。
死に至る病気は残酷だ。抗えぬ運命の中で、体は朽ちながら、心は怯えながら、それでも生き続ける。
しかし、ふと思うのだ。その絶望は、ハンセン病患者に限ったものではないはずだ。
人間として滅んでゆくことがわかっていながら、なお「いのち」は羽ばたけるのか。
特殊な状況の中で発せられたその問いが、普遍性を持つからこそ、本作は残ってきているのではないか。
*1月最終日曜が世界ハンセン病の日だった関係で、twitterで北條民雄に関するツイートが流れてきたり、「雪国」(復活!課題図書倶楽部・2015課題図書)で川端を思い出したり、で、そう言えばこれ、読んでなかったなぁと改めて読んでみました。もう1ヶ月近く経っていますが。
*結核とハンセン病の病原体はいずれもマイコバクテリア属で、結核菌(Mycobacterium tuberculosis)が主に肺への親和性が高く、感染力が高いのに比較して、らい菌(Mycobacterium leprae)は神経への親和性が高く、感染力はさほど高くありません。感染力が高くないのは患者に近く接している人にはわかるのではないかと思うのですが、にもかかわらず、ハンセン病に対する差別が(結核に比しても)非常に大きいものになったのは、外貌に症状が現れてしまうためだったのか。あるいは逆に遺伝病だと誤解されてすらいたことに起因するのか(遺伝病なら隔離することにまったく意味はないはずですが)。このあたり、差別全般につながるような気もしますが、問題が重いだけにあまり軽はずみな結論は出せず。機会があれば、追々別の本で考えてみたいと思います。その前に、感染症一般の歴史について、何か1冊読むかなぁ・・・。
*北條の死因はしかし、ハンセン病ではなく結核であったようです。直接の関係はないですが、「夏の花」の原民喜の妻が結核に糖尿病を併発していたのを思い出しました。この時代、栄養状態もさほどよくはなかったでしょうし、ひとたび何か発症してしまうと、多重感染や合併症も多かったのかも知れません。これも軽はずみな結論は出せないですが。
*川端は堀辰雄とも親交が厚かったのですね。「雪国」は今ひとつぴんとこなかったのですが、近いうちに別の作品を読んでみたいと思っています。何か、作品も交友関係も幅広すぎて、門外漢がちょっと囓ってもどうこうなるのかまったくわからないですけど。
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:勉誠出版
- ページ数:144
- ISBN:9784585012436
- 発売日:2010年02月01日
- 価格:1080円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。