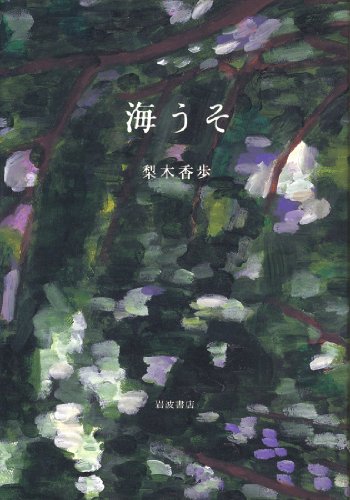素通堂さん
レビュアー:
▼
何に対しての「防塁」であったのか。寄せては返す波のように、侵食してくる「時間」に対してか。忘れ去られようとする「記憶」を、守ろうとしてか。
時は昭和の初め。南九州にある「遅島」に、人文地理学者の秋野は調査に訪れます。
そこで出会った島の人々は、昔ながらの生活を続けていました。
「遅島」には、かつて修験道の別格本山であった「紫雲山」があり、西の高野山とも言われていました。しかし明治初年の神仏分離令(廃仏毀釈)により、蔵王院をはじめとしたすべての寺院が破壊されたのです。
それが、秋野がこの島に惹きつけられた理由なのでした。
秋野は村の若者梶井君と一緒に島を散策します。そして村に伝わる恵仁岩の伝説や良信の防塁、島にかつて存在したモノミミのことなどを調べ始めます。
しかし調査の結果分かったことはいくつかの仮説だけ…。
学問というのは、そういうものなのかもしれません。特に考古学や文化人類学のような「過去」を知ろうとすることは。
それらがすでに「失われたもの」であるがゆえに、真実ではなく仮説しか示しようがない。逆に言えば、だからこそロマンがあるのでしょう。
梶野は廃墟となった蔵王院の印象を山根氏に語ります。
山根氏はそれに応えてこう言うのでした。
この物語は、日本という国が明治維新という近代化の結果「喪失したもの」を、人文地理学者の視点を通して描こうとしています。
しかしその行く先は、先に引用した「色即是空」なのでした。
「色即是空」について、少し長くなりますが岩波文庫の「般若心経・金剛般若経」より現代語訳を引用しましょう。
つまり、悟りの境地に達した立場からすれば、失うものそのものが「ない」以上、「失う」ということも「ない」のだ、と。
この物語において、島の「喪失」の原因に「廃仏毀釈」が取り上げられています。
ではなぜ「廃仏毀釈」をする必要があったのか、と言えば、本書でも述べられている通り、それは日本という国の近代化のためなのでした。
何かを失ったとすれば、その背景には獲得した何かがあるのです。
その逆もまた同じ。
つまり、何も犠牲にすることなく、何かを手に入れるということはできない、ということ。
では、近代化とは何でしょうか。日本が近代化することによって何かを失ったとするのなら、逆にそのことによって獲得したものとは。
たとえば「文学」や「芸術」、学者である主人公秋野のアイデンティティの支えである「学問」や「歴史」という概念もまた、近代化によって海外からもたらされたものです。そして「国家」という概念すらも。
秋野が島で世話になった老夫婦に「モノミミ」について尋ねたとき、老夫婦は言葉を濁します。なぜなら、秋野自身が「近代人」であり、昔ながらの生活をしている老夫婦でさえ、「近代人」なのですから。
僕たちはつい、片方のものだけを見てしまいます。「色」か、「空」か、そのどちらかだけを。
だから「失われたもの」だけを見て嘆いたり、あるいは「得られるもの」だけを見て希望を膨らませたりするのです。
でも実際には「色即是空」、何かを獲得すれば必ず何かを失うもの。
「国」も、「島」も、「人」も、みな確固とした何かであり続けるわけではなく、何かを獲得したり、何かを失ったりしながら変化し続けていきます。
この世界は「色」だけではありません。もはや知りようのない、正に「失われる」ものは本当にたくさんあるでしょう。
でも一方で、この世界は「空」だけでもないのです。僕たちは誰もが、「近代」や、「現代」の恩恵を受けて生きているのですから。
ほんとうの理由なんてわからない、その「わからない」ということがこの世界の有り様なのかもしれません。
だけど僕たちはそんな「世界」に、そんな「国」に、そんな「時代」に生きているのです。
「空」の中に「色」を求め、「色」の中に「空」を求めるようにして。
この「世界」も、この「国」も、この「時代」も、なによりも僕たち「自身」が「色即是空」であり「空即是色」なのだとしたら……。
それはきっと、こういうものだと思うのです。
「ある」ように感じても本当は「ない」もの。
「ない」ように感じても、本当はちゃんと「ある」もの。
まるで、海辺に浮かんだ海うそ=蜃気楼のように。
そこで出会った島の人々は、昔ながらの生活を続けていました。
「遅島」には、かつて修験道の別格本山であった「紫雲山」があり、西の高野山とも言われていました。しかし明治初年の神仏分離令(廃仏毀釈)により、蔵王院をはじめとしたすべての寺院が破壊されたのです。
「何百年も続いてきたものが、ほとんど一瞬のように滅んでしまう。そのことを、どうとらえていいのか……」
それが、秋野がこの島に惹きつけられた理由なのでした。
秋野は村の若者梶井君と一緒に島を散策します。そして村に伝わる恵仁岩の伝説や良信の防塁、島にかつて存在したモノミミのことなどを調べ始めます。
しかし調査の結果分かったことはいくつかの仮説だけ…。
学問というのは、そういうものなのかもしれません。特に考古学や文化人類学のような「過去」を知ろうとすることは。
それらがすでに「失われたもの」であるがゆえに、真実ではなく仮説しか示しようがない。逆に言えば、だからこそロマンがあるのでしょう。
梶野は廃墟となった蔵王院の印象を山根氏に語ります。
「何か、確かに、以前あったもの、というものがある。その気配は十分漂っているのに、それ自体は、根こそぎなくなっている。それは、私がここに来る前から「応えて」いたものの、続きなのかもしれないが……。諸行無常、というのでは、何かとらえきれないもの」
山根氏はそれに応えてこう言うのでした。
「色即是空、ということかな」
この物語は、日本という国が明治維新という近代化の結果「喪失したもの」を、人文地理学者の視点を通して描こうとしています。
しかしその行く先は、先に引用した「色即是空」なのでした。
「色即是空」について、少し長くなりますが岩波文庫の「般若心経・金剛般若経」より現代語訳を引用しましょう。
「この世においては、すべての存在するものには実態がないという特性がある。
生じたということもなく、滅したということもなく、汚れたものでもなく、汚れを離れたものでもなく、減るということもなく、増すということもない。
それゆえに、シャーリプトラよ。
実体がない、という立場においては、物理的現象もなく、感覚もなく、表象もなく、意志もなく、知識もない。眼もなく、耳もなく、鼻もなく、舌もなく、身体もなく、心もなく、かたちもなく、声もなく、香りもなく、味もなく、触れられる対象もなく、心の対象もない。眼の領域から意識の領域にいたるまでことごとくないのである。」
つまり、悟りの境地に達した立場からすれば、失うものそのものが「ない」以上、「失う」ということも「ない」のだ、と。
この物語において、島の「喪失」の原因に「廃仏毀釈」が取り上げられています。
ではなぜ「廃仏毀釈」をする必要があったのか、と言えば、本書でも述べられている通り、それは日本という国の近代化のためなのでした。
何かを失ったとすれば、その背景には獲得した何かがあるのです。
その逆もまた同じ。
つまり、何も犠牲にすることなく、何かを手に入れるということはできない、ということ。
では、近代化とは何でしょうか。日本が近代化することによって何かを失ったとするのなら、逆にそのことによって獲得したものとは。
たとえば「文学」や「芸術」、学者である主人公秋野のアイデンティティの支えである「学問」や「歴史」という概念もまた、近代化によって海外からもたらされたものです。そして「国家」という概念すらも。
秋野が島で世話になった老夫婦に「モノミミ」について尋ねたとき、老夫婦は言葉を濁します。なぜなら、秋野自身が「近代人」であり、昔ながらの生活をしている老夫婦でさえ、「近代人」なのですから。
僕たちはつい、片方のものだけを見てしまいます。「色」か、「空」か、そのどちらかだけを。
だから「失われたもの」だけを見て嘆いたり、あるいは「得られるもの」だけを見て希望を膨らませたりするのです。
でも実際には「色即是空」、何かを獲得すれば必ず何かを失うもの。
「国」も、「島」も、「人」も、みな確固とした何かであり続けるわけではなく、何かを獲得したり、何かを失ったりしながら変化し続けていきます。
この世界は「色」だけではありません。もはや知りようのない、正に「失われる」ものは本当にたくさんあるでしょう。
でも一方で、この世界は「空」だけでもないのです。僕たちは誰もが、「近代」や、「現代」の恩恵を受けて生きているのですから。
「何に対しての「防塁」であったのか。寄せては返す波のように、侵食してくる「時間」に対してか。忘れ去られようとする「記憶」を、守ろうとしてか。
それもほんとうはだれにもわからない。良信本人にもわからなかったのかもしれない。いや、きっとわからなかったに違いない。ひとがそれほどの力をもちいて何かを断行するときの、ほんとうの理由など、きっとだれにもわからないのだ」
ほんとうの理由なんてわからない、その「わからない」ということがこの世界の有り様なのかもしれません。
だけど僕たちはそんな「世界」に、そんな「国」に、そんな「時代」に生きているのです。
「空」の中に「色」を求め、「色」の中に「空」を求めるようにして。
この「世界」も、この「国」も、この「時代」も、なによりも僕たち「自身」が「色即是空」であり「空即是色」なのだとしたら……。
それはきっと、こういうものだと思うのです。
「ある」ように感じても本当は「ない」もの。
「ない」ように感じても、本当はちゃんと「ある」もの。
まるで、海辺に浮かんだ海うそ=蜃気楼のように。
投票する
投票するには、ログインしてください。
twitterで自分の個人的な思いを呟いてたら見つかってメッセージが来て気持ち悪いのでもうここからは退散します。きっとそのメッセージをした人はほくそ笑んでいることでしょう。おめでとう。
今までお世話になった方々ありがとうございました。
- この書評の得票合計:
- 35票
| 読んで楽しい: | 3票 |
|
|---|---|---|
| 素晴らしい洞察: | 7票 | |
| 参考になる: | 23票 | |
| 共感した: | 2票 |
あなたの感想は?
投票するには、ログインしてください。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:岩波書店
- ページ数:200
- ISBN:9784000222273
- 発売日:2014年04月10日
- 価格:1620円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。